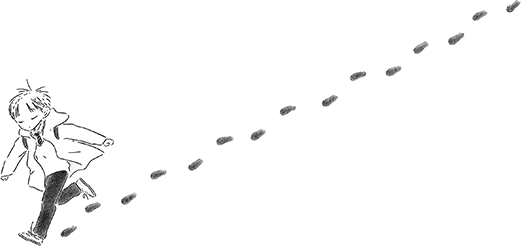書評
普遍へと開かれた窓
三浦しをん
何度も笑い、何度もこみあげる涙をこらえつつ読み進めた。
ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、英国の「元底辺中学校」に通う息子さんの日々を記したエッセイだ。「じゃあ、子育てエッセイなのかな」と思われるかもしれないが、まったくちがう。
元底辺中学校に通っているのは、白人の労働者階級の子たちが大半だ。そのなかには貧困層の子もいる。移民の子も少数ながらいるが、やはり大半は白人だ。「白人」と一言で言っても、家庭環境や生活レベルには当然ながらグラデーションがあるし、そこへさらに「移民か否か」「白人か非白人か」といった分類項も加わってくるから、校内はものすごく複雑かつ繊細な様相を呈している。
著者の息子さんは英国で生まれ育ったが、お父さんはアイルランド人、お母さんである著者は日本人なので、この学校では「少数派」と言える。もちろん、こういった「分類」はすべてアホらしいものなのだが、実際にその街で暮らし、学校に通っていれば、さまざまな軋轢や差別に直面することもあるし、相手の立場やルーツを慮らねばならない局面も多い。
現に息子さんは、実によく考え、感じ、相手を思いやった行動を選び取るひとなのである。友人たちとのかかわりや、周囲の大人たちの振る舞いを通し、息子さんは思考と感情を豊かに育んでいる。著者もまた、そういう息子さんと楽しく真摯に会話したり、次々に起きる騒動にさりげなく一緒に向きあったりすることで、英国のみならず、日本も含めた世界中が直面している複雑さについて、誠実に考察を深めていく。
本書は個人的な「子育てエッセイ」ではない。学校や地域といった、一見すると狭いように感じられる「地べた」から、確実に「普遍」を見晴るかす眼差しを宿している。世界と時代と人間を活写した本書を読めば、これが「異国に暮らすひとたちの話」ではなく、「私たち一人一人の話」だとおわかりいただけるはずだ。私は自身の来し方を振り返り、「なぜあのとき、息子さんのような言動を取れなかったのか」と自らの思考と良心の強度を問わずにはいられなかった。
とはいえ、決して四角四面ではなく、読者になにか(たとえば善行)を強いてくることがないのがまた、本書のすごいところだ。むしろ、キャラ立ちが濃くて、いい意味でいいかげんなひとばかりが登場する。
いじめられっこのティム(息子さんのお友だち)の危機に駆けつけた上級生が、呼吸するたびに「ファッキン」を連発するジェイソン・ステイサム(似の少年)だった瞬間、「漫画か!」と私は爆笑した。著者のお父さん(福岡県在住・幼児だった孫に泳ぎを教えるため、いきなり玄界灘に投げこむ)は「ベスト・キッド」のミヤギさん似らしいし、著者の配偶者は重要な場面で「知らね」とケツをまくって新聞読んでるし。肝心の息子さんも相当おもしろくて、オアシス風の曲を作ったものの、まだ恋を知らぬお年ごろゆえ、やむをえず「祖父の盆栽」への思いをつづった詞を載せて切々とギターをかき鳴らす。どんな歌だよ! むっちゃ聴きたいよ!
とにかく、出てくるひとみんなに会ってみたくてたまらなくなる。実際に会ったら問答無用でボコられるのでは、という荒くれものもなかにはいるのだが(なにしろジェイソン・ステイサムだ)、著者のユーモアたっぷりかつ冷静な筆致を味わううちに、かれらの事情や思いが垣間見えてきて、「私はなぜ、ジェイソン・ステイサム(似の少年)を猛獣のように思ってしまっていたんだろう」とハッとする。
無知による勝手な先入観や偏見や差別意識から完全に自由になるのはむずかしいのかもしれない。けれど本書を読み終えたいま、私の胸のうちに息子さんの言葉がこだましている。
「友だちだから。君は僕の友だちだからだよ」
ほんとにほんとに、そのとおりだ。ちがいやわかりあえない部分があってもなお、相手を知ろうとし、思いを馳せることはできる。どうして人間に知性と想像力が備わっているのかといえば、自分とは異なるひとと「友だち」になるためではないのか。閉めきっていた部屋の窓が開き、思わずあふれた涙のうえを新鮮な風が吹き抜けていったような、そんな気持ちになった。
(みうら・しをん 小説家)
波 2019年7月号より
単行本刊行時掲載