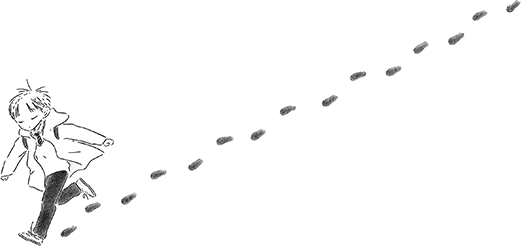書評
未来は彼らの手の中に
高橋源一郎
90年代の10年間、4月から10月までほぼ毎月、ぼくはイギリスに通っていた。競馬を見るためにだ。この本の著者、ブレイディみかこさんが住むブライトンにも行った。海がきれいな街だった。そして、映画「さらば青春の光」の舞台だってことは知っていたけれど、その街で、こんな素晴らしい物語が生れたことを、ぼくは知らなかった。それは、ブレイディみかこさんの10歳の息子が中学生になってからの1年半を描いた素敵な(でも、深く考えさせられる)お話だ。
日本人で保育士で(その他もろもろの)「わたし」とアイルランド人で元銀行員で現大型ダンプの運転手である配偶者との間に生まれた「息子」は、幼児の頃は「底辺託児所」に、小学校の頃は公立で名門のカトリックの小学校に通い「バブルに包まれたような平和な」学校生活をおくる。やがて中学へ。「息子」が選んだのは「緑に包まれたピーター・ラビットが出てきそうな上品なミドルクラスの学校ではなく、殺伐とした英国社会を反映するリアルな学校」、「元底辺中学校」だった。そこは、どんな学校、いや、どんな世界だったんだろうか。
ぼくはこの本を読んでいる間ずっと、自分の子どもたちのことを考えずにはいられなかった。1学年違いの兄弟である彼らは、幼児の頃からいろんな託児所に預けられた。中には連れて来る親はぼく以外全員風俗嬢(みんな、いいママ友だった)という無認可で24時間保育してくれるところもあった。「底辺託児所」だったんだ。小学校は最初、公立で豊かな家庭の子が多い「名門」に通った。けれども、ぼくは悩んだ。いろいろな理由で。そして、彼らが2・3年生になった時、ちょっと変わった学校に転校させた。試験も成績表もクラスもない、規則は全部自分たちで決める、ついでにいうと「先生」も「生徒」もいない学校だ(そこは全員、名前もしくはニックネームで呼び合うので)。いま中学2年・3年になった彼らは、この前、自分たちで育てた豚で作ったソーセージを食べさせてくれた。美味しかったな、すごく。
子どもたちが「ふつう」の学校に行かなかったので、逆に、ぼくは、「ふつう」よりもずっと、子どもたちと社会の関わりについて考えなきゃならなかった。きっと彼らもそうだったろう。この本の中の「息子」や「わたし」のようにだ。
ぼくたちは、「息子」や「わたし」の前に次々と現れる、強烈で印象的なエピソードたちにびっくりさせられる。そして、思わず考えこむ。あるいは、胸をうたれる。そして、最後に、自分たちの子どもや社会について考えざるをえなくなる。入学前の見学会で制服の中学生たちが演奏してくれるノリノリの音楽。廊下に飾ってあるセックス・ピストルズのアルバムジャケット。入学翌日にはもうミュージカルのオーディション。なんだか楽しそう? 表面はね。でも、学校の中にあったのは、過酷なイギリス社会の現実を反映した世界だった。自分だって移民なのに人種差別をし、他の移民にヘイトをぶつける子がいる。貧しくていつも腹を空かしている子がいる。クリスマス・コンサートでハードな現実をそのままラップにして歌う子(「万国の万引きたちよ、団結せよ」だぜ。最高だね)がいる。目の前にある、貧困。差別。格差。分断。憎しみ。「息子」と「わたし」は目を背けず、ユーモアを失わず、その中に入りこむ。それこそが、最高の教育なのかもしれないのだった。
ぼくの好きなエピソードの一つが、「12歳のセクシュアリティ」と題されたところ。「息子」と、つい差別的な言動をしてしまう移民の友人は、「託児所」時代の知人である、子どもが2人いるレズビアンのカップルと出会い、その友人は驚く。いや、驚くのはまだ早い。学校では、セクシュアリティについてLGBTQに関する授業も行われているのだ。そして、「わたし」は、息子たちが「親のセクシュアリティがどうとか家族の形がどうとかいうより、自分自身のセクシュアリティについて考える年ごろになっていたのだと気づ」くのである。そして、「わたし」はこう考える。いや、ぼくも、また。
「さんざん手垢のついた言葉かもしれないが、未来は彼らの手の中にある。世の中が退行しているとか、世界はひどい方向にむかっているとか言うのは、たぶん彼らを見くびりすぎている」
(たかはし・げんいちろう 小説家)
波 2019年7月号より
単行本刊行時掲載