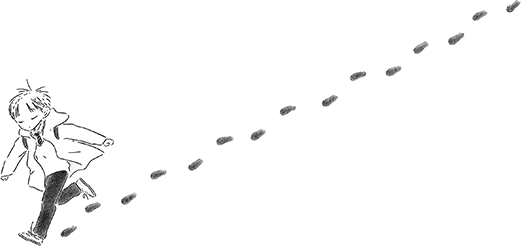インタビュー
元・底辺中学校で出会うリアルな「世界」
ブレイディみかこ
「これは全書店員がどうやったら多くの人に読んでもらえるか考えるべき1冊だ」全国の書店員さんが心を揺さぶられた等身大ノンフィクションの舞台裏。
――書店員さんの感想、すごいです。
ブレイディ ほんとうにありがたいです。全国の書店員さんたちが「ゲラを読んでください」の呼びかけに手を挙げてくださり、忙しい業務の合間に熱い感想を書き送ってくださったからこそ、著者を含む関係者がその気になった本ですので(笑)。
書店員さんたちからいただいた感想を綴じ込んだファイルと、新潮社の宣伝部の方がそれぞれの感想をその人が働く書店用にカスタマイズしてくれた狂気のPOP(笑)の分厚い束が、わたしの仕事部屋にあります。これを見ていると、不覚にもまた視界が滲んで……。
この本は、12歳の息子と彼が通っている中学校、個性豊かな彼の友だちや先生たちとの日常について書いたものです。わたしの住む英国では、ありふれた日常を描いた作品のことを「キッチン・シンク」と呼びます。日本語にすれば「台所の流し」で、人目を引くものや珍しいものを探して描くのではなく、そこらへんに転がっているものを題材にして作品を作るという意味でもあります。
あまりに自分に近いところにある出来事を書いているので手探りでしたが、感想にとても励まされました。
――ユニークなタイトルです。
ブレイディ これ、息子の落書きの言葉なんです。ある日、彼の部屋を掃除していたら、国語のノートが開かれたままになっていました。「ブルー」という単語はどういう感情を意味するかという問いに「怒り」と答えて、赤ペンで直されていました。と、右上にこの落書きが目にはいったんです。青い色のペンで、ノートの端に小さく体をすぼめて息を潜めているような筆跡でした。
わたしは日本人で、配偶者は白人のアイルランド人です。息子は何かこんなことを書きたくなるような経験をしたんだろうか。この落書きを書いたとき、彼はブルーの正しい意味を知っていたのか。それとも知る前だったのか。そう思うと、そのことを無性に知りたくなりました。そして、落書きの言葉をそのままタイトルに使ってしまったんです。
――どんな中学校なんですか。
ブレイディ 荒れていたことで有名だった「元・底辺中学校」です。公立ですが、音楽や演劇、ストリートダンスといった授業に力を入れてから子どもたちの素行も成績も良くなった。なんだかドラマの「glee/グリー」みたいだな、と思いました。落ちこぼれそうな生徒がいたら教室のすぐ外で“個別授業”をやるところとかも、日本の高校で落ちこぼれたわたしには好感度が高かった。
――次から次に事件が起こります。
ブレイディ なにしろ、自分が固まりきらないプレ思春期ですからね。息子が学校であったことを話してくれるので、わたしはそれを書き留めているだけです。息子とはいえ、自分ではない人のことは案外わからないもの。だから、わたしの解釈はなるべく書きません。あとは読者が考えてくれればいいと思っているんです。
――子どもたちの解決方法がすごい。
ブレイディ そうなんです! たとえば、こんなことがありました。わたしはボランティアで制服の古着を繕うリサイクル活動をしているんですが、息子から「一着買って友だちにあげたいんだけど……」と相談を受けました。彼の家は本当に貧しくて制服はお兄ちゃんのおさがり。いや、制服どころではなく食費にも事欠いていて、学食の万引きの常習犯です。
わたし自身も貧しくて定期代もアルバイトで稼ぐような子どもでした。だから、彼に制服をあげたい。でも、切り出し方が難しい。どう言えば相手が傷つかないか、考えを巡らせたんですが、なかなか考えつきません。すると、わたしに構わず、息子は友だちに制服を渡してしまいました。
「どうして僕にくれるの?」
案の定というべきか、大きな緑色の目で見つめながらそう聞く彼に、息子は言いました。
「君は僕の友だちだからだよ」
こんなシンプルなことが大人のわたしには言えなかった。毎日、子どもたちに教えてもらうことばかりです。
――続きが楽しみです。
ブレイディ これからどうなるのか……息子にもわからないでしょう(笑)。
彼はいま、iPhoneでの作曲に夢中です。ダンスミュージック風の曲をつくって、それを流しながら踊ったりしていますね。カントリーとラップを融合させたLil Nas Xの「Old Town Road」が今のお気に入りみたいです。わたしもふりだしは音楽ライターでしたから、血は争えないというか。でも、彼の興味も、アイデンティティーも、これからどんどん変わっていくはず。できるかぎり、書き留めていきたいと思っています。
(ぶれいでぃ・みかこ 小説家)
波 2019年8月号より
単行本刊行時掲載