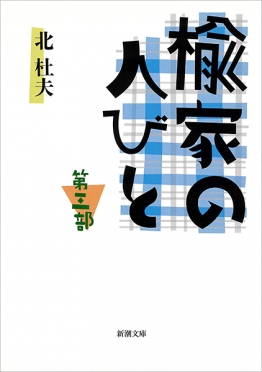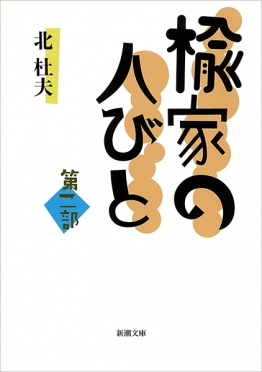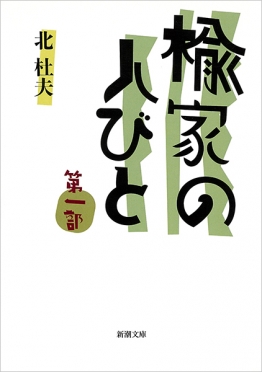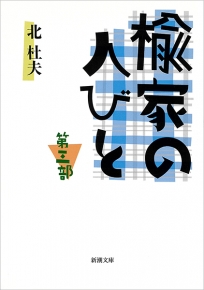
楡家の人びと 第三部
781円(税込)
発売日:2011/07/05
- 文庫
- 電子書籍あり
戦禍、天災、疾病、事故、重なる不幸が一族を襲う。それでも残った者は明日をめざす。昭和を代表する名作長編の素晴らしきフィナーレ。
遂に太平洋戦争が勃発。開戦時の昂揚も束の間、苛酷さを増す戦況が一族の絆を断ち切り、大空襲は病院を壊滅させる。敗戦に続く荒廃の季節、残された者には、どんな明日が待っているのか――。人間のささやかな毎日の営み、夢と希望、苦悩と悲嘆、そのすべてが時の流れという波濤に呑みこまれ、「運命」へと変貌してゆくさまを、明治から昭和への時代変遷を背景に描きあげた一大叙事詩。
書誌情報
| 読み仮名 | ニレケノヒトビト3 |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 384ページ |
| ISBN | 978-4-10-113159-7 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | き-4-59 |
| ジャンル | 文学賞受賞作家 |
| 定価 | 781円 |
| 電子書籍 価格 | 781円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2013/09/06 |
書評
「荷風の昭和」のあとに読みたくなる三冊
「波」8月号で2018年から連載をはじめた「荷風の昭和」をなんとか無事に終えることが出来た。軍国主義が強まってゆき、日中戦争を経て太平洋戦争に至り、その破局による戦後の混乱期を老作家はどう生きたか。その生を辿ることは今年八十歳になった人間には興味深いものがあった。
書籍の刊行は来年の5月の予定だが、来年令和7年(2025)は、昭和が続いていれば昭和100年になる区切りの年だ。改めてさまざまな形で昭和が語られることだろう。
昭和19年、サイパン島が落ち、日本本土への空襲が始まってゆく時代に生まれた人間にとって、昭和とはまず何よりも戦争があった時代である。
永井荷風の『ぼく東綺譚』は昭和11年に脱稿し、翌年4月から、東京・大阪の「朝日新聞」の夕刊に連載された。最終回は昭和12年6月15日。翌7月に日中戦争が勃発し、それが太平洋・アジア戦争へと続いてゆくことを考えれば、若き日に荷風に惹かれた大正9年生まれの作家、安岡章太郎が『私のぼく東綺譚』(新潮社、1999年)で書いているように「わがくにに辛うじて戦前の平和が残されていたギリギリの時期に発表された」、消えゆく時代への哀歌である。
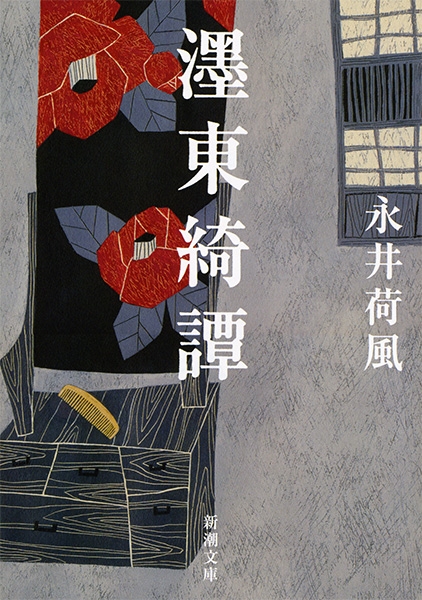
荷風自身を思わせる老作家の「わたくし」が隅田川の向こうにある私娼の町、玉の井を歩き、そこで出会った私娼お雪のなかに「ミューズ」を見る。ここでは、東京の三流の遊び場だった玉の井が、軍国主義の厭うべき現実から離れた美しい隠れ里として描かれている。もっとも汚れた町のなかにこそ、もっとも美しい世界を見る。戦争へと向かう世に背を向けた荷風の詩的抵抗といっていいだろう。いま何度読み返しても心に沁み入る。
北杜夫の『楡家の人びと』は、作者自身の一家をモデルにした楡家三代の物語。トーマス・マンの『ブッデンブローク家の人びと』の日本版といえようか。
一代で東京の青山に壮大な脳病院を建て、衆議院議員となった当主、五人の子どもたち、さらにその子どもたち。この一族が体験する大正、昭和が語られてゆく現代史にもなっている。関東大震災、二・二六事件、戦争、東京空襲が市井の家族の視点から描かれる。
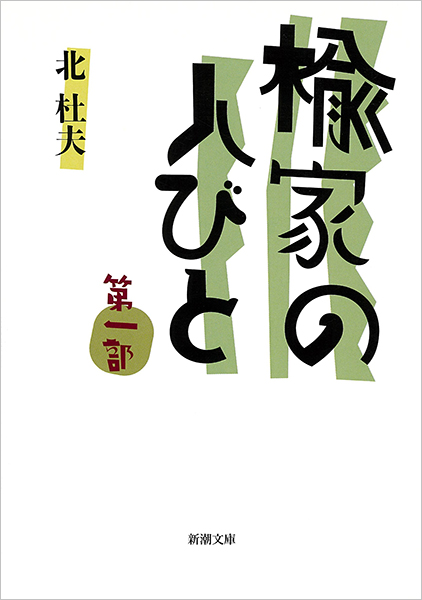
純文学というと閉鎖的な作家の特殊な私生活を描く作品が多かったなか、普通の市民生活を描き、実に新鮮。
昭和39年に新潮社から単行本が出版された。函入り。二段組、五百ページを超える大著だが、文章は平明端正で読みやすい。これまで何度も読んだ。
函には三島由紀夫の推薦文があり「戦後に書かれたもっとも重要な小説の一つである」「これほど巨大で、しかも不健全な観念性をみごとに脱却した小説を、今までわれわれは夢想することもできなかった」と絶讃している。
大正13年生まれの吉行淳之介も荷風を敬愛した。「抒情詩人の扼殺」という秀れた追悼文もある。
『原色の街』(昭和31年)は『ぼく東綺譚』の戦後版の趣きがある。玉の井の町が東京大空襲によって焼失し、業者が向島に新たに作った私娼街、鳩の街を舞台にしている。
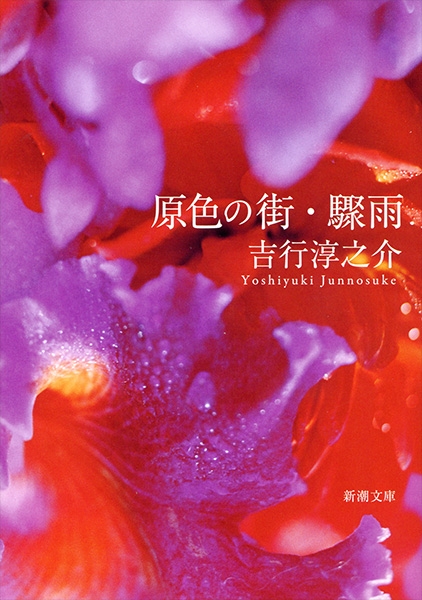
そこには戦前の玉の井がかろうじて持っていた江戸の残り香はもうなくなっている。けばけばしい化粧や衣裳の女性たち。いっときの快楽を買う客たち。欲望がむきだしになっている。まさにぎらついた原色の街。
主人公の船会社に勤める会社員の元木英夫はそんな街であけみという私娼に会う。彼女は欲望のどぎつい色に染まっていない。彼女に比べれば、英夫の婚約者の瑠璃子のほうがお嬢様なのに娼婦のようなところがある。
吉行淳之介もまた荷風のように汚れのなかにこそ美しさを見ようとしている。
鳩の街は売春防止法によって昭和33年の4月に消えた。この小説も昭和の一側面への美しい挽歌になっている。
(かわもと・さぶろう 評論家)
著者プロフィール
北杜夫
キタ・モリオ
(1927-2011)本名・斎藤宗吉。東京青山生れ。旧制松本高等学校を経て、東北大学医学部を卒業。神経科専攻。1960年、半年間の船医としての体験をもとに『どくとるマンボウ航海記』を刊行。同年、『夜と霧の隅で』で芥川賞を受賞。その後、『楡家の人びと』(毎日出版文化賞)、『輝ける碧き空の下で』(日本文学大賞)などの小説、歌集『寂光』を発表する一方、「マンボウ・シリーズ」や『あくびノオト』などユーモアあふれるエッセイでも活躍した。父、斎藤茂吉の生涯をつづった「茂吉四部作」により大佛次郎賞受賞。