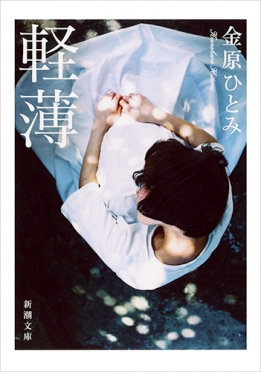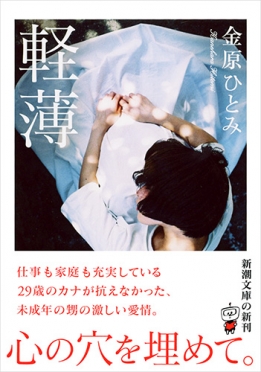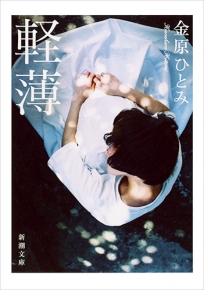
軽薄
649円(税込)
発売日:2018/08/29
- 文庫
- 電子書籍あり
家庭を持つカナと、未成年の甥。二人を繋いだ、それぞれの罪と罰。究極の恋愛小説。
18歳の頃、カナは元恋人に刺されるも一命を取り留めた。29歳の今、仕事も夫と幼い息子との家庭も充実しているが、空虚な傷跡は残ったままだ。その頃、米国から姉一家が帰国しカナは甥の弘斗と再会。19歳になった彼に激しい愛情を寄せられ、一線を越えてしまう。カナに妄執する弘斗は危うげで、そしてある過去を隠していた――。二人を繋いでしまった、それぞれの罪と罰。喪失と再生の純愛小説。
書誌情報
| 読み仮名 | ケイハク |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 岩倉しおり/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 304ページ |
| ISBN | 978-4-10-131334-4 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | か-54-4 |
| ジャンル | 文学賞受賞作家 |
| 定価 | 649円 |
| 電子書籍 価格 | 649円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2021/07/02 |
書評

暗い熱水の底
天からは陽光が降り注ぎ地面からは清水が湧き、そのように神が仕組んだとおりに、緑が生い茂り生命が溢れる地表。けれど、神が用意した穏やかな世界には棲めなくて、酸素も乏しい深海の、暗い熱水の底でしか生きられない生きものもいる。そのような存在もまた神の創造だろうか。
金原ひとみさんの作品を読むたび、誰よりも光を求めながら、けれど性の引力と愛の欠落感ゆえ、暗い熱水の底に落ちていき、そこでようやく呼吸が出来る人たちに出会う。自分が安住することのできない平穏な地表世界を、呪うのでも憎むのでもなく、ひたすら凝視する作者の眼差しを、溜息とともに怖いとも美しいとも思う。
血の繋がった男女の性愛は、背徳というより禁忌である。けれど背徳も禁忌も、地表世界のモラルに照らした言葉。背かねばならぬ徳が存在し、それゆえ忌み禁じられる領域も在る世界のはなし。
海底の別世界には別のモラルがある。男女にとって何がもっとも必要か、生きて行くための最後の希望とは何か。
どうやら万死あるだけの熱水と酸欠の場でしか、命を燃やすことが出来ず、そこでしか生の実感を得られない男女も居るのだと、作者は切実に、傲慢に、素直な高揚をぶつけて書いている。
主人公は三〇歳の女性で、一五歳年上の経済力ある夫との間に、男の子を成している。仕事にも恵まれている。高級マンションに住み、ベビーシッターを雇って育児と仕事を両立させている。子供はかわいいし、これ以上望めない暮らし。
けれど骨身に届く何かが欠けていた。
エロスに導かれる幸福な悲劇が進行する根底には、過去において異常な執着に縛られた、骨身に届く痛みや恐怖の記憶がある。高校時代に同棲していた男は、彼女を束縛し束縛もされたあげく、離反に耐えきれずストーカーとなり、ついに彼女の背中に刃物を突き立てた。
忘れたい記憶は、しかし彼女の身体にひそかに毒を埋め込んでいたらしく、その毒の作用か、平穏な暮らしの中に舞い込んできた、一見柔和な一九歳の大学生の、強引な性愛にのめり込んで行く。一〇歳年下のこの青年も、実は同じような執着性向を隠しもっていて、アメリカで女性教師を殺しかけた過去があり、逃げるように帰国したのだった。しかも彼は歳の離れた姉の一人息子で、血の繋がった甥である。生まれたばかりの赤ん坊の甥を一〇歳の自分が見た記憶があり、この記憶は、自分が産んだ息子への気持ちにも重ねられている。息子であっても異性として認識するタブーを、作者はあっさりと乗り越えている。
その実態を説明する場面は、軽やかで衝撃的だ。彼女の誕生パーティに集まってきた姉夫婦とその息子、自分たち夫婦と幼い息子、つまり二家族六人を見て彼女は気づく。
「私がこの中の二人の男とセックスをした事があり、一人を膣から生み出した……そして姉と私は同じ膣を通って生まれてきた……」
いつもながら作者は、インモラルの臨界点を超えてくる。臨界点を超えたところにも、破壊的な命の燃焼が可能なのだと、訴えてくる。
そのような燃焼熱でしか生きる実感が得られないという、轟々たる哀しみを伝えてくるのだが、その動力は性だ。性の快楽は、インモラルの臨界点を超えるだけの力があるかどうか。それが勝負になる。だから作者は、全精力を傾注して、快楽の深さを描く。性交を通じて、人の奥深いところに眠る本性に手を伸ばす。
しかし快楽を深めれば深めるほど、愛からは遠ざかる。彼女はストーカーとなった男にも、夫にも、そして性愛にふける甥に対しても、愛を感じていない。自分は誰も愛していない、と思っている。寒々とした自己憐憫は、彼女をさらに性愛へと駆り立てる。
「愛」とは何か。それを追い求める小説でもある。さて、見つかるだろうか。
彼女は夫を捨てて、甥とともに地表の恵まれた世界から逃げ出すことを考える。世間から見れば異常でしかない、深くて暗い熱水の底で、これが「愛」だと思えるものを掴めるのだろうか。
小説のエッジぎりぎりを疾駆する作者が、転げ落ちそうで落ちないのは、鋭敏な身体感覚でもって、我々地表世界と繋がっているからなのだ。
(たかぎ・のぶこ 作家)
波 2016年3月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
飽和状態を迎えた世界で
――昨年、長篇小説『持たざる者』を刊行なさったあと、間をおかず『軽薄』を発表なさいましたね。
金原 『持たざる者』を書いている間中、震災をテーマにしたこともあり、どこかノンフィクション小説を書いているような、重々しい世界でもがいているような歯がゆさがありました。これを書き上げたら、より個人的なテーマで小説を書きたい、という思いがあり、『持たざる者』の完成とほぼ同時に書き始めたのが『軽薄』でした。
ですが『軽薄』を書き上げた時、この二作のつながりを感じました。『持たざる者』は四人の視点人物が登場し、それぞれ自分が信じていた世界を喪失する物語です。『軽薄』の主人公、カナもまた、十代の頃ストーカーに殺されかけ、それまで信じていた世界を喪失し、それから十年後が舞台になっています。『軽薄』は『持たざる者』で描かれた世界の喪失のその後、に繋がるところで描かれたのだと思います。
――「軽薄」という言葉を、主人公は何度も自分自身に対して用いますが、読んでいると、なにが軽薄でなにが軽薄でないのか、人間が生きるとき、そもそも軽薄を免れることができるのだろうか、と思わされます。
金原 例えば震災と原発事故は、平和な世界で現実と乖離的な関わり方をしていた人々からその距離感を剥ぎ取り、それぞれが身を沈めていた軽薄さからも引き離し、強烈に目の前のものと向き合う体験となったはずですが、これは主人公のカナが直面したストーカーによる殺人未遂事件とも重なります。
自身を「軽薄さ」から強引に引き離す事件と遭遇したカナは、彼女なりに真摯にその後の自分の人生と向き合いますが、甥と軽薄な関係を結ぶようになり、自分自身の築き上げてきた世界もまた、ある種の軽薄さの上に成り立っていたのだと気づきます。ある時は呪いのように、ある時は生きる術として人生の隙間に容易に侵入してくるもの、軽薄とはそういうものなのかもしれません。
――主人公である29歳のカナは、アメリカから帰国した未成年の甥と関係を持ちます。そのふるまいを、倫理からとらえるのではない描き方をなさっていますね。
金原 この小説に描かれているのは、タブーを犯す快楽ではなく、タブーを犯しても快楽を抱けなくなった人の生き様です。カナは家族や血縁というものにほとんど価値を見出していない人間であり、だからこそ彼女にとって甥と不倫をすることはタブーではなく、単なる瑣末な問題を抱えた関係に過ぎません。作中でも、人が大切と思うことと自分が大切と思うことの間に差がありすぎる、と彼女は感じています。あらゆる共同幻想に耽溺できない人間として生きていくしかないと諦めた女性、と私は捉えています。しかしこれは、ある種の飽和状態を迎えた世界で、人が自然に行き着くところなのではないかとも思います。
――「完璧な人生」と自認していた充たされた暮らしを後にしようとしている主人公には、ある種の明るさ、一筋の希望のようなものがあると感じたのですが。
金原 結婚式で皆から祝福されることや、自分の葬式で皆が泣くことを罰ゲームのようにしか感じられない彼女が、「完璧な人生」と銘打たれるような生活に疑問を抱くのは当然で、また彼女は、かつてストーカーと歩んでいたような破滅的な人生にももはや魅力を感じていません。彼女がこれからどんな世界を築いていくのかは描かれていませんが、もはや信じていないけれども何となく続けていた宗教から脱退したように、彼女が自身の人生に責任を持ち正直になったような、そんな清々しさを私も感じました。
現代では、意味は感じていないけれど何となく続けられている習慣、信じていないけれど惰性で採用されている価値観が横行しているように感じます。そういうものに縛られ、より本質的なものを見失ってしまわないよう、それぞれ個人が自身の生き方を定めていく力が求められる時代になったのではないでしょうか。
――人間の存在の根幹に迫る作品だと思います。どうもありがとうございました。
(このインタビューはメールで行なわれました)
(かねはら・ひとみ 作家)
波 2016年3月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
金原ひとみ
カネハラ・ヒトミ
1983(昭和58)年、東京生れ。2003(平成15)年、『蛇にピアス』ですばる文学賞。翌年、同作で芥川賞を受賞。2010年、『TRIP TRAP』で織田作之助賞、2012年、『マザーズ』でドゥマゴ文学賞、2020(令和2)年『アタラクシア』で渡辺淳一文学賞、2021年『アンソーシャル ディスタンス』で谷崎潤一郎賞、2022年『ミーツ・ザ・ワールド』で柴田錬三郎賞を受賞。著書に『アッシュベイビー』『AMEBIC』『ハイドラ』『持たざる者』『マリアージュ・マリアージュ』『軽薄』『fishy』『デクリネゾン』『腹を空かせた勇者ども』、エッセイに『パリの砂漠、東京の蜃気楼』などがある。