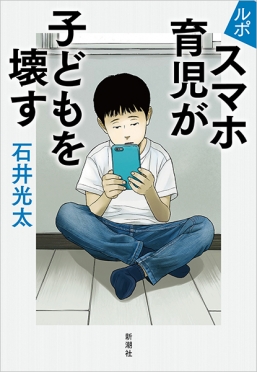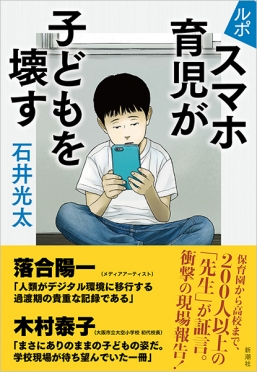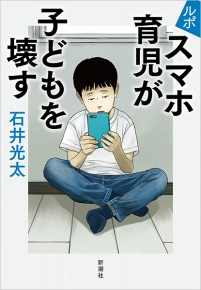
ルポ スマホ育児が子どもを壊す
1,870円(税込)
発売日:2024/07/18
- 書籍
- 電子書籍あり
保育園から高校まで、200人以上の教師に取材を重ねた衝撃の現場報告。
スマホ登場以来16年、教室にいるのはもはや私たちが知る「子ども」ではなくなっていた。ハイハイも体育座りもできない保育園児。教室の「圧」に怯える小学生。クラスメイトの姓すら知らない中学生。会ったその日にベッドインする高校生――児童に関する問題を丹念に追ってきた著者がデジタルネイティブの育ち方を徹底レポート。
【参考文献】
書誌情報
| 読み仮名 | ルポスマホイクジガコドモヲコワス |
|---|---|
| 装幀 | 鈴木マサカズ/装画、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 週刊新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 272ページ |
| ISBN | 978-4-10-305459-7 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | 評論・文学研究、ノンフィクション |
| 定価 | 1,870円 |
| 電子書籍 価格 | 1,870円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2024/07/18 |
書評
人類がデジタル環境に移行する過渡期の貴重な記録
2050年を生きる感覚でものを考える。
このフィルターでものを見て、考えると、それまでと違う側面を浮き彫りにできる。だから、2050年に読み返したら面白いだろう。と、そんなふうに本書を読んだ。
保育園・幼稚園から小・中、高校まで、現場の「先生」たち200人以上の証言を集めたというこのルポは、生徒がひしめく教室で日々働く「先生」という立場の人たちから、幅広く言葉を集めた証言集だ。ノンフィクション作家の石井光太さんによるもので、先生たちの気持ちや戸惑いまで率直に伝わってくる。これを50年、いや100年後に読んだらどうか。まずはいつもの2050年の観点で読んでみたら、これがめっぽう面白くて、ハマった。
ラジオで言えば、日本で放送が始まったのは1925年、関東大震災が理由というが、当時どう日本で受け止められたのか。「うちの子はラジオばっかり聴いてバカになる」と言っていた人がいるのか。「ラジオ育児」(なんていうものがあるなら)の当時の証言集を読んだと思えばよいかもしれない。その社会の価値観や不安の要因が見えてくる。
つまり、石井さんが、環境の大きな変化の一つとしてデジタルやスマホを挙げ、先生たちの多くがそこに理由を見つけようとしている、というその主観が興味深いのだ。
とはいえ、平易に読むと、ここ最近の子どもの環境の変化をまとめている一冊なのだが、タイトルのように「スマホ育児」に全てを負わせるには無理がある。毎年10億台も売られるスマホ時代の今現在だからと言って、なんでもスマホのせいにはできはしない。ラジオ放送の増加と比例して殺人件数が増えたとしても、そこに相関関係があるかは、別の測定と検証が必要だ。
象徴としてスマホを挙げたとは書かれているが、スマホでもITでも、機器や技術に状況の全責任を負わせるのは、どんな場合でも無理があるのは言わずもがな、不満と言えばそこだろうか。
ただし、スマホを媒介とするインターネット、そしてメディアの影響は大きい。テレビしか情報源がなかった世代とは、情報の取り方が明らかに違う。テレビゲームを買うのにコストがかかった世代とスマホゲームをすぐに手に入れられる世代では、ゲームへの距離も変わる。何しろ、スマホというゲーム機が毎年10億台以上出荷されていると思えば、環境は激変していると言える。ファミコンのある子の家に遊びに行く必要は、もはやない。
大学という教育現場にいる僕の立場では、スマホよりもマイナス面を感じるのがコロナだ。「エピローグ」にもあるが、石井さんもそこからこの本を書き始めたようだ。
たとえば、大学でぼくが最近驚いたのは、コロナ禍でずっと家にいて初めて大学に来た3年生の、コミュニケーション下手だ。この春には、その世代が会社に新入社員として入ってきているはずだ。全員が同じ状況なので、不登校ともまた違う。小中高はいわずもがな、大学でほんとうのコロナ禍の影響が出てくるのはこれからだろう。
子どもに何がいいかなんて、今を生き終わってみないと良し悪しは言えないと思う。ただ、学生たちを見ていて思うのは、大人は心配するけれど子どもは今を生きているということ。子どもでいられる時間はすごく短い。僕自身は、四十七都道府県の県庁所在地をまわったり、おじいちゃんにパソコンを買ってもらってハマったり、空手をやったり、身体的に動き回ってあれこれしていたらあっという間だった。
ルポにある中2の子も、5年後には大学生だ。いじめられていると、本人にとっては毎日つらいだろうけれど環境を変えてなんとかするしかない。もちろんそれは簡単ではないだろうが、この子たちが大人になるまでの時間はそんなに長くないのだ。
大学では毎日「自分がおもしろいと思わないところに進んでもダメだよ」「時間を忘れるような方向に進め」と学生に話す。面白いと思ったことをロジックで味付けしていくのが科学的なアプローチだ。それを感情で味付けするひとはアーティストで、それを音楽にする人がいてもいいし、今回のルポのように、証言を集めて文化人類学者のようにまとめたっていい。教育者ができるのは、この環境変化を踏まえた上で、行きたい道へと案内することだけだ。
令和の時代の記録では、学校の現場ではこんなことが起こっている。この本はそれでいいんだと思う。というより、その点において、けっこう絶妙なのである。
(おちあい・よういち メディアアーティスト)
波 2024年8月号より
単行本刊行時掲載
イベント/書店情報
著者プロフィール
石井光太
イシイ・コウタ
1977(昭和52)年、東京生れ。日本大学芸術学部文芸学科卒業。国内外の文化、歴史、医療などをテーマに取材、執筆活動を行っている。2021(令和3)年『こどもホスピスの奇跡』で新潮ドキュメント賞を受賞。主な著書に『絶対貧困』『遺体』『「鬼畜」の家─わが子を殺す親たち』『43回の殺意─川崎中1男子生徒殺害事件の深層』『近親殺人─家族が家族を殺すとき』『ルポ スマホ育児が子どもを壊す』などがある。