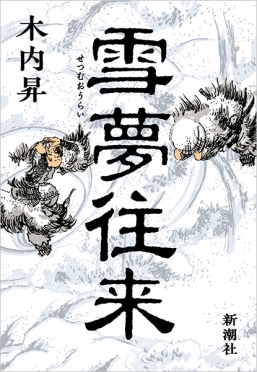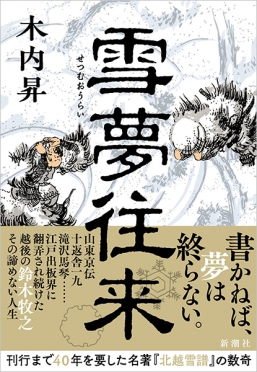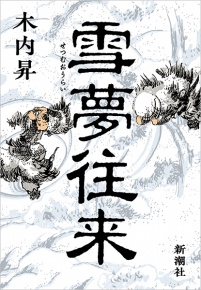
雪夢往来
2,200円(税込)
発売日:2024/12/16
- 書籍
- 電子書籍あり
書かねば、夢は終らない。名著『北越雪譜』、刊行に至る四十年の数奇な道。
江戸の人々に雪国の風物や綺談を教えたい。越後塩沢の縮仲買商・鈴木牧之が綴った雪話はほどなく山東京伝の目に留まり、出板に動き始めるも、板元や仲介者の事情に翻弄され続け――のちのベストセラー『北越雪譜』誕生までの長すぎる道のりを、京伝、弟・京山、馬琴の視点からも描き、書くことの本質を問う本格時代長篇。
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
書誌情報
| 読み仮名 | セツムオウライ |
|---|---|
| 装幀 | 鈴木牧之編撰・京山人百樹増修・京水百鶴画図『北越雪譜』図版より/装画、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 400ページ |
| ISBN | 978-4-10-350957-8 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文芸作品 |
| 定価 | 2,200円 |
| 電子書籍 価格 | 2,200円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2024/12/16 |
書評
作家の「まこと」、物語の「まこと」とは何か
新聞記者になって三十余年。その間、本当にたくさんの方に話を聞かせていただいた。政治家、役人、スポーツ選手、学者、俳優……そして数多の市井の人々。合わせれば、一万人を超えているだろうか。喜びの声を聞く取材も、悲しみの声を拾うインタビューもあったが、その都度、できるだけ相手の心に近づき、寄り添えるよう努めてきたつもりだ。時に共に笑い、怒り、うなだれながら。
けれど、そうして出会った人の中で、うまく捉え切れない人たちがいた。作家――。東京本社社会部から文化部へ異動した2000年以降、多くの作家に新刊インタビューをしてきたが、彼らが紡いだ小説を挟んでのやり取りでは、その人にきちんと迫れたか、自信を持てないことが度々あった。そもそも小説は虚構であり、そこから書き手の内面を汲み取ることは容易ではないし、登場人物の思いや行動から著者の本音を探ろうとしても、彼らは「書いているうちにキャラクターたちが勝手に動き出すんです」などと口にする。
作家とは何者か。物語を紡ぐ人間の「まこと」はどこにあるのか。木内昇さんの『雪夢往来』は、本好きなら誰もが抱く疑問に、一つのヒントをくれるように思う。四人の作家、それも実在した人物の心の裡を見事に浮き上がらせているからである。
四人とは、江戸時代後期の戯作者である山東京伝と、その弟で後に戯作者となる京山、『南総里見八犬伝』の著者として知られる曲亭馬琴に、越後の商人で、地元の風俗や綺談を本にして江戸に伝えたいと願う鈴木牧之(本名・儀三治)。今作は、二十代後半の儀三治が本を出すことを夢見てから、『北越雪譜』として板行され、ベストセラーとなるまでの四十年という歳月を描く。儀三治の原稿は京伝や馬琴らの手に渡り、彼らの仲介で幾度も板行が試みられるが、なかなか実現しない。木内さんは、儀三治の煩悶や焦り、さらには京伝、京山、馬琴の戯作者としての思いや、板行を巡る板元とのやり取りなどを詳らかにしていく。
そこに描かれた戯作者の立場や心情は、現代の作家たちのそれに通じるものに違いない。板元と京伝の、こんなやり取りからも見て取れる。〈力の籠もった稿となれば、よい書物にはなるかもしれません。しかし、よい書物が売れる書物になるか、というと、どうも勝手が違うようでしてね〉〈馬鹿を言うな。いい書物を、うまく宣伝して売るのが手前らの仕事だろう〉
馬琴の言葉からは、職業作家の多くが感じているであろうジレンマもうかがえる。〈戯作というのは水ものじゃ。こうして日々真面目に努めておっても、必ず相応の見返りがあるというものでもあるまい〉〈戯作が読まれるのは、世が太平なときに限ってのことなのじゃ。飢饉だの天災だの疫病だのがあれば、誰も戯作になぞ目もくれぬ〉
ああ、そうだった。東日本大震災が起きた時も、少なくない数の作家が己の物語の力を疑って肩を落とし、中には「小説家は虚業だ」と語る人もいた。
だが、本当にそうだろうか、とも思う。そうであるならば、どうして彼らは作家であり続け、物語を書き続けるのか。読者はなぜ、新たな物語を待ち続け、読み続けるのか。この作品はそんな問い、言い換えれば、人を惹きつけてやまぬ物語の力とは何か、物語の「虚」と「まこと」の間には何があるのか、というところにまで切り込もうとする。
作中、印象的な一文がある。〈京伝は、話が甚だしい虚構だったとしても、その奥に人の普遍な業や想いがしかと息づいておれば、それこそがまことになると信じている。ゆえに、一貫した善人も悪人も出さぬ〉。先述の通り、作家の考えが必ずしも登場人物に反映されるわけではないが、これはおそらく、木内さん自身の思いなのだろう。
木内さんはこれまで、「虚」である小説の中にごく自然に「まこと」や「普遍」を入れ込んできた。異なる時代、立場の人間の物語であっても、深い人物造形と精緻な描写で、今を生きる私たちに「これは自分たちの話だ」と実感させてきた。今作も二百年ほど前を生きた「書き手」たちの物語ではあるが、本を手にした「読み手」はその耳元で、彼らの息づかいまでを聞くことになる。板行の行方に一喜一憂する儀三治。戯れるように物語を生み出す京伝。そんな兄の才能の前に打ちひしがれる京山。一方、馬琴は他のすべてを犠牲にして戯作に挑んでいる。「書き手」だけではない。木内さんの筆は、その周囲にいる人物の姿も鮮明に立ち上がらせる。何にも気付いていないようでいて、多くを悟っている儀三治の妻、兄の背を追う京山を〈追わなくたってよござんす。旦那様には、旦那様にしか行けない道が、きっとある〉と励ます妻……。本から目を上げ周囲を見やれば、そう遠くない場所に彼らと似た人はいる。
ただ、戯作者たちの晩年の姿にだけは、「自分たちとは違う」と感じるかもしれない。彼らは物語に取り憑かれ、呑み込まれて苦しんでいるのに、どういうわけか、その厄介さを受け入れ、面白がってさえいる。これが作家か。ならば、やはり彼らの存在は謎のままである。
(むらた・まさゆき 読売新聞東京本社編集委員)
波 2025年1月号より
単行本刊行時掲載
担当編集者のひとこと
『北越雪譜』をご存じですか。越後・塩沢の縮仲買商・鈴木牧之が豪雪地の生活や風習、伝承などを豊富な挿絵入りで著した江戸のベストセラーです。今も読み継がれ、手元にある岩波文庫版の奥付を見れば、なんと74刷。著者の木内昇さんは、長年『北越雪譜』を愛読していましたが、近年になって、この本が初稿完成から刊行まで40年もかかっていたこと、その背景には誰もが知る著名戯作者たちと江戸出版界の思惑が絡んでいたことを知り、小説に書きたいと思い立ちました。
最初に原稿を預かり出版を提案した山東京伝。京伝の死後、原稿を引き取ったものの長年死蔵した滝沢馬琴。兄・京伝の果たせなかった約束を叶え刊行を実現した山東京山。そして、夢断ちがたく越後でその時を待ち続けた牧之。書き手としての姿勢も書く内容も異なる4人の視点から「なぜ書くのか」を問うた本作は、創作と出版に関わる人々の熱を見事に描き出す作品になりました。
今や東京から越後湯沢までは新幹線で1時間強。しかし、かつては険しい山と雪に隔てられ、往来は困難でした。その距離を超え、40年の時も超えて想いが繋がる瞬間にぜひ立ち会ってください。(出版部・KY)
2025/05/27
著者プロフィール
木内昇
キウチ・ノボリ
1967年生まれ。出版社勤務を経て独立し、インタビュー誌「Spotting」を創刊。編集者・ライターとして活躍する一方、2004年『新選組 幕末の青嵐』で小説家デビュー。2008年に刊行した『茗荷谷の猫』が話題となり、早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。2011年に『漂砂のうたう』で直木賞を受賞。2013年に刊行した『櫛挽道守』は中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞を受賞した。他の作品に『よこまち余話』『光炎の人』『球道恋々』『火影に咲く』『化物蝋燭』『万波を翔る』『占』『剛心』『かたばみ』『惣十郎浮世始末』など多数。