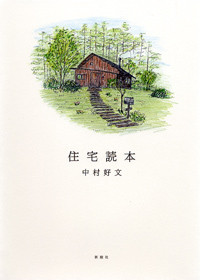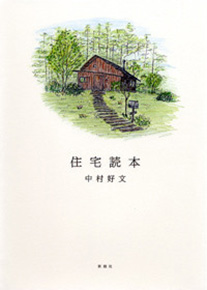
住宅読本
4,400円(税込)
発売日:2004/06/20
- 書籍
いい住宅ってなんだろう? “住宅名人”の建築家が考えた十二の条件。
書評
波 2004年7月号より 建築家の目、生活者の目 中村好文『住宅読本』
中村好文さんの『住宅巡礼』が、長いこと行方不明だと案じていたら、兄の家にいっていたらしい。
「もう、なめるようにして読んだわ!」と兄嫁が返しにきた。
「なめるように読む」……、そう、好文さんの本には、その言葉がふさわしい。イラストを楽しみ、写真を楽しみ、文字を楽しみ、そして、文章を楽しむ。なんべんもなんべんも楽しむ。
『住宅読本』も、まさしくそういう本である。
テーマはズバリ、「いい住宅ってなんだろう?」。
『住宅巡礼』で、好文さんとともに見知らぬ土地を歩いた私たちが、今回旅するのは、心の中。懐かしい風景、子供のころに見つけた居心地のいい場所……。
中村好文さんの文章の魅力は、町を歩いていても、映画を観ても、本を読んでも、いつも建築家の目がそこにあって、キラリ(決してギラリではない)と輝いたその目に映ったものを、読み手に伝えてくれるところではないかと思う。
しかし、『住宅読本』を読んでいくと、好文さんには建築家の目だけではなく、もうひとつの目があることに気づかされる。暮らす人、生活者としての確かな目である。
たとえば、「隅々まで磨きたてられ、整然と整理整頓され過ぎている」台所には、ヒンヤリとしたものしか感じないとおっしゃる。「美しく散乱する台所、あるいは多少の散乱ぐらいでへこたれない大らかな台所」が、この建築家の理想で、そうした「散乱対応型の台所」へと読者を案内する。ご自身のアトリエの台所である。好文さんのアトリエでは、所長、スタッフの区別なく、くじ引きで、買い出し、料理、皿洗いの役割が決められ、毎日昼食をともにしているという。その昼ご飯のおいしそうなこと。
「いい住宅ってなんだろう?」
それは、風景の中にしっくりとおさまっていて、居心地とさわり心地がいいものと、好文さんは条件に並べる。マクロで考え、ミクロで感じる。前者が建築家だとしたら、後者は生活者だろうか。その両方の目をきっちりとお持ちなのだ。
今年のはじめ、私は、『父の縁側、私の書斎』という本を上梓した。家にまつわる思い出を綴ったものである。
「建築家の美学と生活者の感性は違う」
と、拙著をお読みになって、好文さんはおっしゃった。
「ふみさんが一貫して住み手の立場から、正直で、正確で、ときに手厳しい感想を綴っていることが、本書をあまり類のない、優れた住宅論にしている」
望外のお言葉をいただいて、私は面映くてしかたなかった。住宅論など、書いたつもりもないのに。だいいち書きたくったって、私に書けるわけがない。
だが、『住宅読本』を読んで思った。私も、「こういうこと」を書いていたのではないか。いや、書けはしなかったけれど、書きたかったのは、じつは「こういうこと」だったのだ。
私の本を「住宅論」とおっしゃったのは、好文さんが建築家の目で、書いた本人も気づいていないような部分を、すくい取ってくださっていたからだと思う。
そうそう、そう!『住宅読本』をめくりながら、何度も頷いている私がいた。「床の間」的な空間の必要性、「住み継ぐ」ことと「使い継ぐ」ことの大切さ、「明かり」と「灯り」の違い。
「なるほどねぇ」と、感心したこともたびたびである。テーブルとセットの椅子をいっぺんに揃えるのではなく、モダンデザインの名作といわれる椅子の数々を、長い時間をかけてひとつひとつ増やしていった、中村好文さんご自身の体験談。また、家と同時に、子供たちのための小さな遊び小屋と、それぞれの思い出の品をしまっておけるような、しっかりした宝箱をデザインしてほしいと、依頼してきたご夫婦の話。
私は身もだえした。ああ、この本を抱えて、我が家を建て替えた二十代のあの日に戻りたい。私の人生も、きっと違ったものになっていただろうに。
また一方で思う。何度やり直しても同じかもしれない。二十代には二十代の価値観しかない。中村好文さんが長い時間をかけて、「いい住宅」のイメージをつかんだように、私も幾多の失敗とため息を通して、そのイメージを理解できるようになったのだ。
でも、これから家を建てたい、またはリフォームしたいと思っているかた、ぜひ目を通してください。これは、読めばかならず「徳」がある、『住宅徳本』です。建てたばかりにして早くも後悔していらっしゃるかたは、近づかないほうがお身のためかもしれません。きっと、『住宅毒本』となってしまうでしょうから。
「もう、なめるようにして読んだわ!」と兄嫁が返しにきた。
「なめるように読む」……、そう、好文さんの本には、その言葉がふさわしい。イラストを楽しみ、写真を楽しみ、文字を楽しみ、そして、文章を楽しむ。なんべんもなんべんも楽しむ。
『住宅読本』も、まさしくそういう本である。
テーマはズバリ、「いい住宅ってなんだろう?」。
『住宅巡礼』で、好文さんとともに見知らぬ土地を歩いた私たちが、今回旅するのは、心の中。懐かしい風景、子供のころに見つけた居心地のいい場所……。
中村好文さんの文章の魅力は、町を歩いていても、映画を観ても、本を読んでも、いつも建築家の目がそこにあって、キラリ(決してギラリではない)と輝いたその目に映ったものを、読み手に伝えてくれるところではないかと思う。
しかし、『住宅読本』を読んでいくと、好文さんには建築家の目だけではなく、もうひとつの目があることに気づかされる。暮らす人、生活者としての確かな目である。
たとえば、「隅々まで磨きたてられ、整然と整理整頓され過ぎている」台所には、ヒンヤリとしたものしか感じないとおっしゃる。「美しく散乱する台所、あるいは多少の散乱ぐらいでへこたれない大らかな台所」が、この建築家の理想で、そうした「散乱対応型の台所」へと読者を案内する。ご自身のアトリエの台所である。好文さんのアトリエでは、所長、スタッフの区別なく、くじ引きで、買い出し、料理、皿洗いの役割が決められ、毎日昼食をともにしているという。その昼ご飯のおいしそうなこと。
「いい住宅ってなんだろう?」
それは、風景の中にしっくりとおさまっていて、居心地とさわり心地がいいものと、好文さんは条件に並べる。マクロで考え、ミクロで感じる。前者が建築家だとしたら、後者は生活者だろうか。その両方の目をきっちりとお持ちなのだ。
今年のはじめ、私は、『父の縁側、私の書斎』という本を上梓した。家にまつわる思い出を綴ったものである。
「建築家の美学と生活者の感性は違う」
と、拙著をお読みになって、好文さんはおっしゃった。
「ふみさんが一貫して住み手の立場から、正直で、正確で、ときに手厳しい感想を綴っていることが、本書をあまり類のない、優れた住宅論にしている」
望外のお言葉をいただいて、私は面映くてしかたなかった。住宅論など、書いたつもりもないのに。だいいち書きたくったって、私に書けるわけがない。
だが、『住宅読本』を読んで思った。私も、「こういうこと」を書いていたのではないか。いや、書けはしなかったけれど、書きたかったのは、じつは「こういうこと」だったのだ。
私の本を「住宅論」とおっしゃったのは、好文さんが建築家の目で、書いた本人も気づいていないような部分を、すくい取ってくださっていたからだと思う。
そうそう、そう!『住宅読本』をめくりながら、何度も頷いている私がいた。「床の間」的な空間の必要性、「住み継ぐ」ことと「使い継ぐ」ことの大切さ、「明かり」と「灯り」の違い。
「なるほどねぇ」と、感心したこともたびたびである。テーブルとセットの椅子をいっぺんに揃えるのではなく、モダンデザインの名作といわれる椅子の数々を、長い時間をかけてひとつひとつ増やしていった、中村好文さんご自身の体験談。また、家と同時に、子供たちのための小さな遊び小屋と、それぞれの思い出の品をしまっておけるような、しっかりした宝箱をデザインしてほしいと、依頼してきたご夫婦の話。
私は身もだえした。ああ、この本を抱えて、我が家を建て替えた二十代のあの日に戻りたい。私の人生も、きっと違ったものになっていただろうに。
また一方で思う。何度やり直しても同じかもしれない。二十代には二十代の価値観しかない。中村好文さんが長い時間をかけて、「いい住宅」のイメージをつかんだように、私も幾多の失敗とため息を通して、そのイメージを理解できるようになったのだ。
でも、これから家を建てたい、またはリフォームしたいと思っているかた、ぜひ目を通してください。これは、読めばかならず「徳」がある、『住宅徳本』です。建てたばかりにして早くも後悔していらっしゃるかたは、近づかないほうがお身のためかもしれません。きっと、『住宅毒本』となってしまうでしょうから。
(だん・ふみ 女優)
著者プロフィール
中村好文
ナカムラ・ヨシフミ
建築家。1948年千葉県生まれ。1972年武蔵野美術大学建築学科卒業。宍道建築設計事務所勤務の後、都立品川職業訓練校木工科で学ぶ。1976年から1980年まで吉村順三設計事務所に勤務。1981年レミングハウスを設立。1987年「三谷さんの家」で第1回吉岡賞受賞。1993年「一連の住宅作品」で第18回吉田五十八賞特別賞を受賞。現在、日本大学生産工学部居住空間デザインコース教授。著作は『住宅巡礼』『住宅読本』(ともに新潮社)、『普段着の住宅術』(王国社)、柏木博氏との共著に『普請の顛末』(岩波書店)などがある。
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る