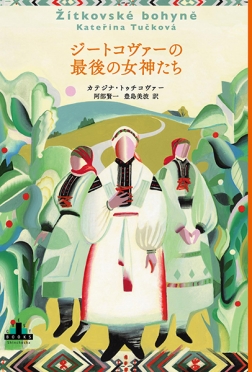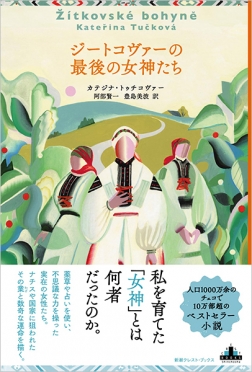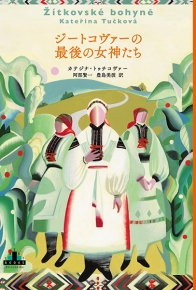
ジートコヴァーの最後の女神たち
3,080円(税込)
発売日:2025/09/25
- 書籍
私は「女神」に育てられた。知られざる驚異を描いたチェコのベストセラー。
チェコのとある辺境の寒村には、不思議な能力で人々を助ける「女神」と呼ばれる女性たちが生きていた。天候をも左右したというその術に戦争中はナチスが注目し、共産主義時代には弾圧されたことも。チェコに実在した彼女たちの数奇な運命を、その血を受け継ぐ民族誌学者の女性が探っていく。歴史のベールをはぎ取る物語。
プロローグ
第I部
スルメナ
ドラ・イデソヴァー
文書館──一日目
白い蛇
パルドゥビツェ夜想曲
カテジナ・スハーニェルカ
文書館──二日目
共通の遺産
夜の眩暈
文書館──三日目
ヤコウベク
文書館──四日目
事案「女神」
第II部
児童養護施設
イレナ・イデソヴァー
オシュチェプカさんの古本屋
ヨゼフ・ホフェル
嵐を静める
アルジュビェタ・バグラーロヴァー
イルマ・ガブルヘロヴァー
父
手紙
ヨゼフィーナ・マフダロヴァー
マグダレーナ・ムルクヴァ
第III部
青いフォルダー
魔女のアーカイブ
魔女的存在=スルメノヴァーのファイル
魔女的存在=マフダル家のファイル
特殊部隊の研究者
フリードリヒ・フェルディナント・ノルフォルク
第IV部
コプルヴァジ
ユスティーナ・ルハールカ
赤い腕飾り
ヴィエンツェスラフ・ロズマザル
インゲボルク・ピチーノヴァー
ポトチナー
ヤニゲナ
第V部
インジフ・シュヴァンツ
ベドヴァー
エピローグ
著者あとがき
訳者あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | ジートコヴァーノサイゴノメガミタチ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |
| 装幀 | Hitomi Itoh/Illustration、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 448ページ |
| ISBN | 978-4-10-590203-2 |
| C-CODE | 0397 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 3,080円 |
書評
「女神」という名の「呪い」
かつて私自身の子ども部屋に貼られた地図にあったのは、チェコスロヴァキアという国だった。けれどその後学校で教材として使っていた地図帳で、その国はいつの間にかチェコとスロヴァキアというふたつの国になっていた。
この物語の舞台となるチェコ共和国は、ふたつの世界大戦の以前からその在り様を変え続けてきた。第一次大戦後にオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊して成ったチェコスロヴァキア共和国は、その後ナチス・ドイツによって一度地図から姿を消す。戦後は社会主義国となり、プラハの春を経てその反動から警察国家へ、そして1990年代に二つの国へと分離していった。
チェコのジートコヴァーという地域にかつて「女神」と呼ばれる特殊な役割を持つ女性たちがいた。女性の血筋によって継承されている女神たちは、薬草を使って病を治し、ときに天候をコントロールし、呪いを行って、医療行為や地域のトラブル等の相談を受けていた。しかし今世紀頭に、最後の女神が亡くなったことでその文化は途絶える。この物語はインターネットだけで情報のやり取りが難しい程度の、つまり現代よりも少し前の時代、ドラという女性研究者の視点で語られる。
女神の文化は実在するけれど、この物語のすべてが事実かというと、そういうわけではない。それはまさに女神の存在が事実で、実際に遺族がまだ社会に生きているからだ。戯曲家で美術史家、かつ人権活動家でもある作者のトゥチコヴァーは、主人公のドラのように綿密な取材をし、それをもとに物語の形でこれをあらわした。
女神たちの文化について研究をしているドラは、自身も女神の役割を担ってきた血筋に生まれた。母親が父親に殺された後、彼女は障害を持つ弟と共に伯母の女神スルメナに育てられ、彼女の女神としての仕事を手伝っていた。やがて民族学の研究をするようになったドラは、女神についての資料を集めてそれを追ううち、自身の幼いころの記憶が呼び起こされていくようになる。
膨大なアーカイブの中から伯母スルメナの痕跡を探し続け、役所や図書館、文書館などに散らばる資料を集める中で、ドラは自身の記憶と向き合い続ける。資料は魔女裁判の記録や病院のカルテ、警察の秘密調査結果、新聞記事、個人的な書簡など多様だった。資料を読み、書き写し、地域の人たちと対話する中でドラの記憶が鮮明になっていく物語は、アーカイブ・サスペンスともいうべきダイナミズムにあふれている。
体制が移り変わり続ける国の中で、女神たちは一貫して疎まれてきた。キリスト教社会の敵、社会主義国家の敵、先端医科学の敵。聖職者や医者、科学と相容れない風習を持つ女神は、反社会的とされ、その時代ごとの社会で拷問や治療を受ける。
調査のなかでドラは「親衛隊(SS)魔女特殊部隊」という存在があったことを知る。ナチス・ドイツは、この地域に古くからある魔術的な民間信仰の風習にひかれ、彼女たちのことを研究していた。女神たちの神秘性、オカルト性はアーリア人の民族意識と結びつけられ、増幅され、女神は民族意識高揚のシンボルと考えられた。彼女たちは、母や妻である上に巫女の役割まで押し付けられた。
またドラは、別の女神によって自分の血筋にかけられた呪いの話を聞き、かつてスルメナがどのようにその呪いにあらがって戦っていたかを知ることになる。学者として呪いの存在を疑う一方、それを支えているのが自分の生きる社会に根付き、浸透しきっている精神性であることに、ドラは愕然とする。
資料はいくつもの言語によって書かれていたが女神自身によるものはほとんどなく、第三者が残したものばかりだ。ドラは、かつてスルメナに届いた手紙を自身が代わりに読んであげていたことを思い出す。つまり女神たちの多くは文字の読み書きができなかった。女神たちのドキュメントを辿ること、しかし女神たち自身はそれを残せなかったこと。文字と資料についてのこのふたつの事実は、本作中においてとても重要になる。物語というものはそれ自体魔術的で、過去の記述や資料を読み解く行為もまた、世間において魔術的なものとして扱われることがある。この物語の作者は、これをきわめて示唆的に、自覚的に描いている。
ドラに待ち受ける運命とともに、呪いとアーカイブの入れ子構造の物語は閉じられる。この物語がいま、この国で読まれることは、多くの人が思う以上にとても大きな意味がある。
(たかやま・はねこ 作家)
波 2025年10月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

「女神」たちは本当に生きていた
歴史に埋もれながらも生き続けた「女神」たちの存在を描いた小説がチェコでベストセラーになったカテジナ・トゥチコヴァー。不思議な力で人々に影響を及ぼし続けた彼女たちを追いかけた日々を語る。
聞き手 マルツェラ・ペハーチコヴァー
翻訳 阿部賢一
(『ジートコヴァーの最後の女神たち』の出版を記念し、小説の舞台となったチェコ東部のジートコヴァーで2012年6月に開催された朗読会後にインタビューが行われた)
――朗読会に参加した地元の人々はあなたの本を読んでいましたか?
そう思います。地元の人たちにとって、女神は大きなテーマです。ジートコヴァーの人口は百八十人ですが、今回の朗読会には百四十人が来てくれました。みんな、シュテフィナ(訳注:「最後の女神」とされ、作中にも登場するイルマ・ガブルヘロヴァーの娘)の葬儀に参列し、その流れで来てくれたのです。
――生前のシュテフィナと話をしたことはありましたか?
連絡を取ろうとしましたが、彼女は乗り気ではありませんでした。シュテフィナは八十歳を越えており、最後は不幸な死に方でした。「神の術」を頼りにやってきた男性に殴り殺されたんです。しかもその葬儀の最中、突然停電になりました。「女神」はそうやすやすと墓に入らないってことが証明されたのです。それまで彼女のことを疑っていた地元の人たちも、その時ばかりはあれは女神の仕業だねって頷いていました。シュテフィナが神の術を使うようになったのはビロード革命(訳注:1989年、チェコスロヴァキアで共産主義体制が崩壊した)以後のことだったので、あれは女神じゃない、単なる金儲けでやってるだけだって疑う人が多かったんです。
――この土地で女神の魔法が再び使われるようになるでしょうか?
わかりません。ある女性はカード占いをしており、別の女性は蠟をつかって将来を占っていますが、二人の母親は、薬草の効能について知識がありませんし、呪文を唱えられるような女神でもありませんでしたから。
――女神には、なにがしかの力があると信じていますか?
うーん……半分ぐらいかな。私が調査をしていた時、「女神たち」と特別な体験をしました。病気にかかって、なかなか回復しなかったことがありました。当時は女神の生活を科学的に調べていて、彼女たちの力をあまり信じていなかった。でもいろいろな人に尋ねると、女神の影響をどれだけ受けたか、暗示的にですが話してくれました。女神の力を彼らが信じていたからで、裏を返せば、自分たちを信じるように女神たちが彼らに接していたからです。もしかしたら、それがあの人たちの最大の技なのかもしれません。つまり、生き方の何かを変えて持病の治療に専念すること、あるいは誰かとの関係を改善するように促すことです。
私の小説でも、実名を出して実際のことを書きたいという気持ちに駆られました……。ですが、もしそうしていたら、女神たちに恨まれたでしょう。それに、当時は病気に罹り、熱が下がらず、どうしたらいいかとしばらく思い悩んでいましたから。結局、実名は出さず、出自も他人には分からないようにして書こうと決心するやいなや、病気から回復しました。それで落ち着きました。
――女神のことを最初は誰から聞きましたか?
友人の歴史家で民俗学者のダヴィッド・コヴァジークです。情報が尽きることがない泉のような人です。都市部に暮らすようになる前、両親が離婚した幼少期に暮らしていた農村の環境に舞い戻る必要があると、三年ほど前に彼に話しました。それに、興味深い運命をたどった女性について調べたいということも。すると彼はすぐにぴんと来て、ジートコヴァーの女神のことを教えてくれたのです。
――それで興味に火がついた?
そう、すぐに。でも、その話が現実なのか、はじめは確信がありませんでした。ナチス・ドイツの親衛隊、共産主義者との関係、語り手の伯母で「女神」だったスルメナ、こういったことすべてを一つずつ確認し、調査し、そのうえでフィクションの要素を足す必要がありました。
――ジートコヴァーの女神について書こうと決心したのですね。
……でも、物語がどこに向かうかまだわかりませんでした。手始めに、論文、書籍、民族誌の年報などを読み、それから、女神について何か書きたいと思い、このテーマについて何か教えてもらえるものはないかとモラフスケー・コパニツェ(訳注:ジートコヴァー一帯の呼称)に出かけました。そこで一軒ずつ訪ねて、ある時、一人の女性教師に遭遇しました。その人が、女神やその子どもたちの家々へと私を案内してくれたんです。
――あなたの小説は、どの程度事実に基づいていますか?
具体的に言うのは難しいですが、あえていえば七割以上は実際の資料に基づいています。
――読者や批評家の評判はどうですか?
『ジートコヴァーの女神たち』は好意的に受け止められています。本を読んだという人からメールが毎日のように届いて、うちの家族にも似たようなことがあったなどと教えてくれるのです。この小説は、普通とは異なる生き方をしていた多くの人に何かを訴えたようです。まさか、女神たちの運命がここまで反響があるものとは思ってもみませんでした。
出典:リドヴェー・ノヴィニ紙(金曜版)、2012年8月3日(Lidové noviny, 3. 8. 2012, č. 31, pátek)(抜粋)
(カテジナ・トゥチコヴァー)
波 2025年9月号より
単行本刊行時掲載
短評
- ▼Takayama Haneko 高山羽根子
-
民族誌学研究者ドラは、生まれ育った集落の「女神」と呼ばれる女性たちについて資料を集め、自分のルーツを故郷の記憶と共に辿っていく。時代の流れの中、国家のしくみが変わっても絶えず敵とされてきた「女神」。キリスト教の、社会主義国家の、医学の敵。物語は、チェコに実在した「女神」という存在に関する警察の捜査報告や魔女裁判の記録、精神病院でのカルテ、論文や書簡などの資料を横断しつつ、真実のある地点へ向かっていく。このスリルに満ちたアーカイブ・サスペンスがいまの日本で読める、これは実のところ、とても重要なことだ。
- ▼Týdeník Rozhlas ロズフラス誌
-
巧妙に構成された物語は複数の文体が絡み合い、徐々に巨大な絵となっていく。ありふれた環境にも、偉大な物語が潜んでいると教えてくれる。著者は、歴史・民俗にわたる広範な資料を、注目に値する小説へと見事に昇華させた。
- ▼Lidové noviny リドヴェー・ノヴィニ紙
-
著者は本作において、感服するしかない語りの才能を示した。独創的なテーマを選んだだけでなく、緊張感と現実味のある手法でフィクションと現実を巧みに結びつけ、豊かな人物を描き出し、脱線しながらも交錯し合う物語を作り出した。
トークイベント動画
著者プロフィール
カテジナ・トゥチコヴァー
Tuckova,Katerina
1980年生まれ。美術史家・評論家・劇作家でもある。カレル大学で博士号を取得。2006年に小説家としてデビュー。2012年に刊行された『ジートコヴァーの最後の女神たち』でヨゼフ・シュクヴォレツキー賞、マグネジア・リテラ読者賞、「チェコの本」読者大賞などを受賞。チェコでベストセラーとなり、約20の言語に翻訳されている。他の作品に『Vyhnani Gerty Schnirch』『Bila Voda』など。
阿部賢一
アベ・ケンイチ
東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は中東欧文学、比較文学。著書に『複数形のプラハ』『翻訳とパラテクスト ユングマン、アイスネル、クンデラ』(読売文学賞受賞)など。訳書にカレル・チャペック『白い病』、パトリク・オウジェドニーク『エウロペアナ 二〇世紀史概説』(共訳、日本翻訳大賞受賞)など。
豊島美波
トヨシマ・ミナミ
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程在籍。『チェコを知るための60章』(分担執筆)、ヴァーツラフ・ハヴェル『通達/謁見』(阿部氏との共訳)など。