
宇宙に果てはあるか
1,210円(税込)
発売日:2007/01/25
- 書籍
ビッグバン以前、ブラックホール以後。宇宙はどこまでわかったのか?
始まりは? 重力は? 大きさは? アインシュタインからハッブル、ホーキングまで――宇宙をめぐる12の謎に挑んだ科学者たちの、創意と誤まりと発見のよろこびにみちた思考のプロセスを、深くて平易な語り口で解き明かす待望の一書。わたしたちはいま、宇宙のどこにいて、どこへ向かって生きているのだろう。
シャプレーの大銀河説/カーチスの島宇宙説
渦巻星雲の新星/われわれはどこにいるのか
境界条件の問題/果てのある宇宙モデル
果てのない宇宙モデル/「生涯最大のヘマ」
宇宙に果てはあるか
フリードマン模型――閉じた宇宙の場合/アインシュタインの批判
フリードマン模型――開いた宇宙の場合/ソビエトの状況
動的宇宙論の受容/宇宙は変化しているのか
セファイド――宇宙の距離標識/銀河までの距離の測定
ドップラー効果による視線速度の測定/距離-速度関係の発見
ハッブルの法則と宇宙の膨張/データの修正
宇宙はどれほど大きいか
宇宙の熱核反応/宇宙の火の玉
αβγ理論/ささやかな誤り
宇宙はどのように始まったか
ビッグバンと背景放射/背景放射の理論
定常宇宙論の敗北/ビッグバンは本当にあったのか
恒星内部での核反応/ppチェーンとCNOサイクル
恒星における元素合成/星はなぜ輝くのか
大質量星の安定性/恒星の末路/持続的な重力崩壊
その後の研究成果/ブラックホールとは何か
標準理論の構築/太陽系形成の標準理論/ジーンズ不安定性
ボトムアップ説とトップダウン説/世界はいかに形づくられたか
惑星が存在する確率/生命に適した惑星の個数/生命発生の確率
知的生物に進化する確率/技術文明を発展させる確率
技術文明の継続期間/われわれはひとりぼっちか
場の凝縮と真空のエネルギー/宇宙のインフレーション
地平線問題の解決/インフレーション理論の受容
ビッグバンの前に何があったか
始まりの秩序/ブラックホールのエントロピー
ホーキング放射/宇宙のエントロピー
われわれはどこへ向かっているのか
科学者リスト
本文中で紹介した論文
索引
書誌情報
| 読み仮名 | ウチュウニハテハアルカ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮選書 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-603576-0 |
| C-CODE | 0344 |
| ジャンル | 宇宙学・天文学 |
| 定価 | 1,210円 |
書評
一筋縄でなかった宇宙論の歩み
現代宇宙論は、さまざまな観測的事実と整合的なビッグバン理論が大勢を制し、今や実証科学の道を歩んでいる。アインシュタインが一般相対性理論に基づく宇宙モデルを発表して九〇年、ガモフがビッグバン理論を提唱して六〇年の歳月を経て、信頼に足る科学的宇宙像が確立しつつあるのだ。
その間には、さまざまな論争があり、思い違いや事実の誤認があり、時代に制約された常識の壁もあった。本書は、そのような宇宙論がたどったジグザグの歴史を、一二の設問に分けて詳しく跡付けしたものである。類書と異なる特色は、すべての設問について、まず原論文から入って問題の所在を明らかにし、続いてどのように議論され修正されてきたかを振り返っていることだ。
例えば、銀河系の大きさに関わるシャプレーとカーチスの「大論争」(第一章)では、アンドロメダ星雲までの距離決定に問題があった。アインシュタインは宇宙は静止していると信じたために宇宙を有限とせざるを得なかったが(第二章)、運動する宇宙に転換すれば無限宇宙が普通になった。ハッブルは宇宙年齢を小さく見積もりすぎ(第四章)、ガモフはすべての元素が初期宇宙で形成されるという楽観論から出発した(第五章)。それらは後の研究によって糺され、あるいは偶然の発見によって新たな道が切り拓かれて、徐々に明確な宇宙像へと焦点を結んできたのだ。
さらに、ガモフの理論を「ビッグバン」として嘲笑したホイルの思惑(第六章)、ブラックホールを毛嫌いしてそれを否定したアインシュタインの失敗(第八章)など、「あらまほしい」宇宙と「あるべき」宇宙のせめぎ合いという人間臭い歴史もあった。宇宙論は一筋縄で発展したわけではないのである。
科学の発展にとって重要なことは、間違いがあっても要所を突いた問題を提起することだ。そこからさまざまな所論が誘起され百家争鳴を経る中で、やがて誰もが納得する理論へと落ち着いていく。宇宙論もこのような科学の正道を歩んできた。アインシュタインは(ここに二例を書いたように)何度も「生涯最大の失敗」を繰り返したが、彼の間違った論文ほど生産的であったことはない。これも宇宙論の貴重な歴史なのである。
(いけうち・さとる 宇宙物理学者)
波 2007年2月号より
立ち読み
はじめに
科学とは「誤りを修正できる学問だ」という言い方がある。
科学の最先端では、その人に伺いを立てれば、たちどころに真実を教えてくれるような賢者は存在しない。多くの科学者たちは、誰も正解を知らないまま、手探り状態のなかで研究を続けているのである。このため、最初は思いつきに近い不完全な仮説を提出し、反対陣営からさまざまな批判を浴びせかけられながら、部分的な修正や抜本的な見直しを繰り返していくしかない。著名な科学者が提唱したにもかかわらず、ものにならずに捨て去られる仮説も少なくない。定説として生き残るのは、批判に耐えられるように手直しされ、対抗仮説との争いにうち勝ち、実験や観測にもとづく客観的なデータによって検証された、ほんのひと握りの学説にすぎない。
科学とは、あまたの誤りを犯しながら、それに対する自己修正を積み重ねていく学問である。こうしたプロセスがあるからこそ、科学は信頼に値するのだ。
本書では、「宇宙論」と呼ばれる分野で、科学者たちが、さまざまな間違いや誤解を重ねつつも、試行錯誤の末に新たな知識を獲得するにいたる過程を見ていきたい。
かつて畏怖と崇敬の対象だった宇宙は、ここ100年ほどの間に、ようやくその姿をおぼろげながら見せ始めた。宇宙がビッグバンに始まり、現在なお急激に膨張を続けていること、宇宙に銀河系と同じような銀河が無数に存在していることは、さほど科学に関心のない人でも聞きかじったことがあるはずだ。こうした知識を、科学者たちはどのようにして獲得してきたのだろうか。
宇宙論の歴史をたどる書物の多くは、新しい知見が、天才的な科学者の洞察によっていきなり獲得されたかのような書き方をしている。しかし、現実に起きたことは、それほど単純ではない。基礎理論の未熟さや観測データの不足が原因で、天才的な科学者といえども、すぐには正当な洞察に到達できなかった。それでも、何とか前に進もうと苦闘を続けた結果、ようやく宇宙の全貌を捉えられるようになったのである。
こうした科学研究の実態を幾分なりとも伝えるために、本人はあまり広言してほしくないであろうミスも含めて、できるだけ原論文に忠実な形で紹介するようにつとめた。一般向けの書物では、話の筋道が見えにくくなることもあって、オリジナルな学説ではなく、のちの科学者が修正をほどこしたものを解説している場合が多い。だが、自己修正しながら発展するのが科学の本質だとすれば、優秀な科学者たちが犯した誤りを知ることも、科学に対する理解を深める上で役に立つはずである。
本書で取りあげるのは、大銀河説と島宇宙説の間の“大論争”に始まり、アインシュタインの宇宙モデル、ハッブルの法則、背景放射の発見から、インフレーション宇宙論やブラックホールのエントロピーにいたる全部で12の話題である。
最新の量子宇宙論にはほとんど触れていないが、それには理由がある。ちまたには、超弦理論やその発展形であるM理論などにもとづいた宇宙論を紹介する書物が、何冊も出版されている。確かに、こうした理論は、ブラックホールの性質などに関して無視できない成果をあげてはいる。しかし、いまだに実験や観測によって検証されておらず、理論として練りあげられているわけではない。いうなれば、シャドーボクシングはやたらと威勢がよいが、一度も実戦に出場していないボクサーのようなもので、殿堂入りした名チャンピオンたちと同列に論じるわけにはいかないのである。
科学研究とは、さまざまな仮説を出しあって、検討の末に最良と思われるものを選びだす作業である。世にいう「最先端学説」とは、あくまで検討中の仮説のことであり、その正当性には疑問符がついている――はっきりいえば、大半は間違っている――と心得ておいていただきたい。
科学者たちの努力にもかかわらず、宇宙には、まだ多くの謎が残されている。いつか人間がすべてを明らかにできるとも思われない。しかし、これまでに解明された部分だけでも、科学が世界についての認識を着実に深化させてきたことの証である。そこに、宇宙に比べてあまりにはかないわれわれ人間の存在意義を見いだせないだろうか。
第1章 われわれはどこにいるのか 大銀河説と島宇宙説
銀河系の概念は、最新の観測機器が明らかにした天文学的知見と整合するように拡張されるべきである。太陽系は、もはやその中心としての地位を保つことができない。
シャプレー「宇宙の大きさ 第1部」1921年
外なる銀河である渦巻星雲は、従来よりはるかに広大な宇宙の姿を我々に示す。1000万光年から1億光年に及ぶその領域に、我々は探求の歩を進めることになるだろう。
カーチス「宇宙の大きさ 第2部」1921年
宇宙のなかの人間
宇宙について知れば知るほど明らかになってくること――それは、広大無辺な宇宙空間のなかで、人間が置かれているのが、世界の中心といった特権的な地位ではなく、どこにでもありそうな平凡な立場だという事実である。
人間がこうした認識を獲得するまでには、いくつかのステップが必要だった。まず、地動説によって、地球が不動の中心ではなく、太陽の周りを回る惑星の1つにすぎないという世界観の転換が図られた。地動説の提唱者の一人コペルニクスは、『天球の回転について』(1543年)のなかで、水星・金星・地球・火星・木星・土星の6惑星が、中心にある太陽の周りを円運動するという「太陽系」のモデルを提出している。
こうして宇宙の中心に据えられた太陽も、次のステップで、その地位を剥奪される。コペルニクスの太陽系モデルで、夜空に輝く無数の恒星は、太陽を中心とする巨大な天球(透明な球殻)の上に並んだ“明かり”だとされていた。だが、コペルニクスの死後に生まれたケプラーやガリレオのような新時代の天文学者は、恒星が宇宙空間に浮かんだ輝く天体であることを正しく理解した。近代科学の礎を築いたニュートンは、『プリンキピア』(1687年)の末尾ちかくで、恒星を太陽と同じ種類の天体と見なし、その周りに惑星が存在する可能性について言及している。
夜空に輝く恒星が太陽と同種の天体である――裏を返せば、太陽は無数に存在する恒星の1つにすぎない――という見方は、18世紀には、天文学者の間で広く受けいれられる。「宇宙における人間の地位」を知るために必要な次のステップは、多くの恒星がどのような分布をしており、そのなかで太陽がいかなる位置を占めるかを明らかにすることである。
太陽を含む多くの恒星が1つの巨大なシステムを構成しているという説は、1780年代にイギリスの天文学者ハーシェルによって提唱された。当時の技術では、恒星までの距離を直接測定することは難しかった(測定が可能になるのは1838年以降である)。彼は、天空を多くの区画に分けて恒星数を丹念にカウントし、恒星が密に見える領域は奥行き方向に拡がりがあると仮定することによって、恒星が「太陽を中心とするいびつなレンズ状の集団」を形づくっているという描像を得た。ハーシェル自身は、晩年にいたって自分のアイデアに懐疑的になるものの、膨大な数の恒星がレンズないし円盤状の「銀河系」を構成しているという見方は、19世紀の終わりまでに、多くの観測を通じて実証される(図1)。
「宇宙に存在するすべての恒星がレンズ状に集まっており、その中心に太陽が位置する」というハーシェルが示した銀河系の姿は、額面通りに受け取るならば、太陽中心の宇宙観を復活させるようにも思える。人間は、やはり宇宙の中心にいるのだろうか? この問題をめぐって、20世紀初頭の天文学界は紛糾した。
人間が宇宙の中心にいないという議論は、皮肉なことに、相対立する2つのグループによって、別々に展開される。一方は「太陽は銀河系の中心にない――しかし、銀河系は宇宙で唯一の天体集団だ」と主張し、他方は「宇宙には銀河系に匹敵する島宇宙が数多く存在する――しかし、太陽は銀河系の中心にある」と論じた。まさに、宇宙における人間の地位を問うこの議論は、アメリカを代表する二人の天文学者、シャプレーとカーチスの“大論争”をもって、頂点に達する。
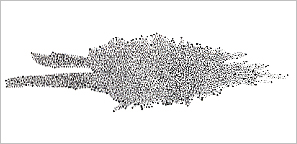
担当編集者のひとこと
科学者たちは謎をどう解いた? 20世紀最大の知的遺産、それが宇宙論だ。
吉田伸夫さんが書き下ろしたこの本は、20世紀に驚異的な成果をあげた宇宙論の進展をていねいに跡づけたもの。宇宙論史上に名高いシャプレーとカーチスの「大論争」をはじめ、アインシュタインからホーキングにいたる科学者たちが宇宙の謎に挑んだ画期的な思考のプロセスを、深くそして平易に説き明かしています。
銀河はひとつか複数か、宇宙に果てはあるか、ビッグバン以前にはいったい何が起こり、またブラックホールはこれからどのようにして蒸発するのか。本書は12の謎を掲げ、それを見事に解明した科学者たちの原論文にさかのぼりながら、彼らのいかにも人間くさい先入観や、公表してほしくないかもしれないケアレスミスまで含めて、そのスリリングな科学的思考法を浮彫にしていきます。
著者は1956年生れ。東海大学などで非常勤講師をつとめながら、科学史や科学哲学をはじめ、幅ひろい分野で研究を行なっています。実際にお会いすると、珈琲にスプーンで二杯お砂糖をいれる物静かな紳士。この本はむしろ文科系の読者にこそ読んでいただきたい、とおっしゃっていました。ちなみにこの本、内容は高度なのに、数式は四つしか登場しません。
2007/01/25
キーワード
著者プロフィール
吉田伸夫
ヨシダ・ノブオ
1956年、三重県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業、同大学院博士課程修了。理学博士。専攻は素粒子論(量子色力学)。東海大学、明海大学で非常勤講師をつとめながら、科学哲学や科学史をはじめ幅ひろい分野で研究を行なっている(ホームページ「科学と技術の諸相」参照)。著書に『宇宙に果てはあるか』『光の場、電子の海』(いずれも新潮選書)、『日本人とナノエレクトロニクス』(技術評論社)などがある。
































