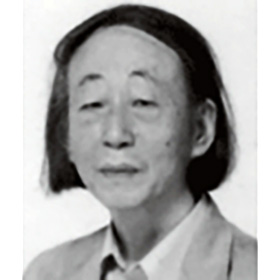誤読された万葉集
748円(税込)
発売日:2004/06/18
- 新書
- 電子書籍あり
古典一新。あの人麻呂の、憶良の、旅人の歌は、そういう歌だったのか!
万葉集は誤って理解されてきた――。庶民の素朴な生活感情を素直に表現した国民歌集などではない。山上憶良は家族思いで大伴旅人は大酒飲みというイメージには問題がある。性の歌もある。都市生活が営まれ、郊外も誕生していた。平安文学とのあいだに断絶はない。……従来の万葉観を大胆にくつがえし、最古の古典に新たな輝きを与える。
目次
はじめに
1 人麻呂は妻の死に泣いたのか
2 額田王と天武天皇は不倫の関係か
3 山上憶良は家族思いだったか
4 大伴旅人は大酒飲みか
5 逢引の夜には月が出ている
6 妹が妻や恋人の意となるわけは
7 枕詞にも意味がある
8 序詞の不思議を解く
9 挽歌は異常死の死者を悼む歌である
10 旅の歌には美意識がある
11 斎藤茂吉の解釈にも問題はある
12 方言はなぜ東歌と防人歌にかぎられるのか
13 性の笑いもある
14 日本には古代から郊外があった
15 万葉集から平安文学へ
2 額田王と天武天皇は不倫の関係か
3 山上憶良は家族思いだったか
4 大伴旅人は大酒飲みか
5 逢引の夜には月が出ている
6 妹が妻や恋人の意となるわけは
7 枕詞にも意味がある
8 序詞の不思議を解く
9 挽歌は異常死の死者を悼む歌である
10 旅の歌には美意識がある
11 斎藤茂吉の解釈にも問題はある
12 方言はなぜ東歌と防人歌にかぎられるのか
13 性の笑いもある
14 日本には古代から郊外があった
15 万葉集から平安文学へ
あとがき
参考文献
参考文献
書誌情報
| 読み仮名 | ゴドクサレタマンヨウシュウ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-610073-4 |
| C-CODE | 0292 |
| 整理番号 | 73 |
| ジャンル | 古典 |
| 定価 | 748円 |
| 電子書籍 価格 | 660円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2012/01/27 |
インタビュー/対談/エッセイ
波 2004年7月号より 万葉集は多様な世界である 古橋信孝『誤読された万葉集』
『万葉集』は庶民の素朴な生活感情を率直に表現した歌集である。今でもそう考えている人が多いのではないだろうか。しかし、これは近世に始まる見方に過ぎない。背景には国家意識の芽生えがあった。日本の最古の古典なのだから、という思いがまず先にある。心の共同性を象徴するものとして『万葉集』を位置づけたのである。近代に入ると、ナショナリズムの高まりとともに、この見方はいっそう強調されることになった。その影響は現在もまだ根強く残っている。
しかし、時代に縛られた固定観念からはそろそろ解放されてもいいのではないか。つぶさに読めばすぐにわかることだが、『万葉集』には多様な世界が表現されており、単純に「庶民の素朴な生活感情を率直に表現した歌集」などと言うことはできない。他の歌集に比べ、意外なほどにさまざまな歌が集められているし、解釈によっては、まったく新しい歌として甦ってくるものも数多い。
例えば、酒飲みが酔っ払って作ったような歌がある。
「あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見れば猿にかも似る」(巻三・三四四)
大伴旅人の歌である。ああ醜い、りこうぶって酒飲まぬ人をよく見ると、猿に似ている、と言っているわけで、酔っ払いの歌と読めなくもない。旅人には大酒飲みというイメージもある。しかし、歌の背景に中国文学の影響を考えないと読み誤る。当時の中国の新しい表現法や小説類の影響をもろに受けた歌だからである。
驚いたことには、性の歌もある。
「わが背子が犢鼻にする円石の吉野の山に氷魚そさがれる」(巻十六・三八三九)
犢鼻は褌、氷魚は鮎の幼魚だが、全体の意味はよくわからない。というより、もともと無意味な歌として作られたもので、たぶん男のモノを「小さいね」とからかっているのである。
「銀も金も玉も何せむに勝れる宝子に及かめやも」(巻五・八○三)
山上憶良のよく知られた歌である。訳せば、銀も金も宝石も何の意味があるだろう、子に勝る宝はない、となる。なるほど憶良は家族想いの歌人であったと考えてもおかしくはない。しかし、当時の憶良は政治家(筑前守)でもあった。また時代は都市化によってそれまでの家族が崩壊しつつあった。そういう点を押さえると、違った解釈が可能になってくるのではないか。
詳しい解釈は私の『誤読された万葉集』にゆずるが、どの歌も、庶民の素朴な生活感情とも日本人固有の表現とも言えないだろう。全二十巻に収められているのは、柿本人麻呂のような正統的な歌だけでもなく、防人歌のような庶民の歌だけでもない。むしろ、こうした多様性こそが特徴と言えるかもしれないのだ。そのあたりに『万葉集』の面白さがあるのである。
しかし、時代に縛られた固定観念からはそろそろ解放されてもいいのではないか。つぶさに読めばすぐにわかることだが、『万葉集』には多様な世界が表現されており、単純に「庶民の素朴な生活感情を率直に表現した歌集」などと言うことはできない。他の歌集に比べ、意外なほどにさまざまな歌が集められているし、解釈によっては、まったく新しい歌として甦ってくるものも数多い。
例えば、酒飲みが酔っ払って作ったような歌がある。
「あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見れば猿にかも似る」(巻三・三四四)
大伴旅人の歌である。ああ醜い、りこうぶって酒飲まぬ人をよく見ると、猿に似ている、と言っているわけで、酔っ払いの歌と読めなくもない。旅人には大酒飲みというイメージもある。しかし、歌の背景に中国文学の影響を考えないと読み誤る。当時の中国の新しい表現法や小説類の影響をもろに受けた歌だからである。
驚いたことには、性の歌もある。
「わが背子が犢鼻にする円石の吉野の山に氷魚そさがれる」(巻十六・三八三九)
犢鼻は褌、氷魚は鮎の幼魚だが、全体の意味はよくわからない。というより、もともと無意味な歌として作られたもので、たぶん男のモノを「小さいね」とからかっているのである。
「銀も金も玉も何せむに勝れる宝子に及かめやも」(巻五・八○三)
山上憶良のよく知られた歌である。訳せば、銀も金も宝石も何の意味があるだろう、子に勝る宝はない、となる。なるほど憶良は家族想いの歌人であったと考えてもおかしくはない。しかし、当時の憶良は政治家(筑前守)でもあった。また時代は都市化によってそれまでの家族が崩壊しつつあった。そういう点を押さえると、違った解釈が可能になってくるのではないか。
詳しい解釈は私の『誤読された万葉集』にゆずるが、どの歌も、庶民の素朴な生活感情とも日本人固有の表現とも言えないだろう。全二十巻に収められているのは、柿本人麻呂のような正統的な歌だけでもなく、防人歌のような庶民の歌だけでもない。むしろ、こうした多様性こそが特徴と言えるかもしれないのだ。そのあたりに『万葉集』の面白さがあるのである。
(ふるはし・のぶよし 武蔵大学教授)
蘊蓄倉庫
「マンヨウシュウ」か「マンニョウシュウ」か
万葉集。さて、これをどう読んだらいいか。おそらく、「マンヨウシュウ」に決まっているじゃないか、という声が即座に返ってくるだろう。しかし、正しくは「マンニョウシュウ」である、と主張される方も一部にはおられるはずである。
江戸時代には「マンニョウシュウ」が定説化していたし、近代に入ってからもそう読む人が少なくなかった。たしかに、一語一語発音すれば、「man-eu-syuu」となり、それが「man-n-eu」と変化し、「mannyou」となったと考えられなくもない。
しかし、奈良時代の音韻の研究によれば、むずかしい議論はひとまずおくとして、そういう変化をしなかったようである。その結果、今では専門家も含めて「マンヨウシュウ」と読まれるようになっているのである。
万葉集。さて、これをどう読んだらいいか。おそらく、「マンヨウシュウ」に決まっているじゃないか、という声が即座に返ってくるだろう。しかし、正しくは「マンニョウシュウ」である、と主張される方も一部にはおられるはずである。
江戸時代には「マンニョウシュウ」が定説化していたし、近代に入ってからもそう読む人が少なくなかった。たしかに、一語一語発音すれば、「man-eu-syuu」となり、それが「man-n-eu」と変化し、「mannyou」となったと考えられなくもない。
しかし、奈良時代の音韻の研究によれば、むずかしい議論はひとまずおくとして、そういう変化をしなかったようである。その結果、今では専門家も含めて「マンヨウシュウ」と読まれるようになっているのである。
掲載:2004年6月25日
著者プロフィール
古橋信孝
フルハシ・ノブヨシ
1943(昭和18)年東京生まれ。国文学者。武蔵大学教授。東京大学文学部国文科卒業。著書に『古代の恋愛生活』『吉本ばななと俵万智』『万葉歌の成立』『古代都市の文芸生活』『雨夜の逢引』『平安京の都市生活と郊外』『和文学の成立』など。
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る