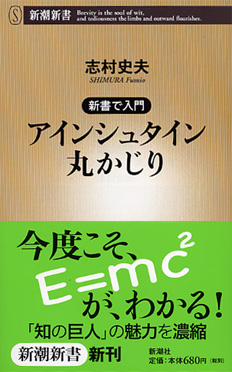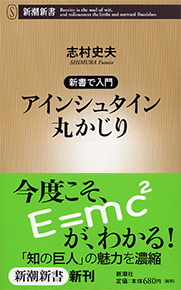
新書で入門 アインシュタイン丸かじり
748円(税込)
発売日:2007/03/20
- 新書
- 電子書籍あり
今度こそ、E=mc2が、わかる! 「知の巨人」の魅力を濃縮。
偉い。凄い。深い。しかも面白い。アインシュタインについて知ることは、二十世紀最高の知性に触れることである。「時空が歪む」という空前絶後の発想はどこから生まれたのか。無名の役人はいかにしてノーベル賞科学者となったのか。波乱万丈の人生と業績を辿り、数々の味わい深い名言からその哲学を知る。「熱狂的ファン」を自任する物理学者が、知の巨人の魅力を濃縮。ついに、今度こそ相対性理論がわかる!
主要参考文献
書誌情報
| 読み仮名 | シンショデニュウモンアインシュタインマルカジリ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-610207-3 |
| C-CODE | 0242 |
| 整理番号 | 207 |
| ジャンル | 物理学 |
| 定価 | 748円 |
| 電子書籍 価格 | 660円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2012/02/24 |
蘊蓄倉庫
天才の名言
アインシュタインには名言が数多くあります。『新書で入門 アインシュタイン丸かじり』で紹介している、「想像力は知識よりも重要です。知識には限界がありますが、想像力は世界を包み込むことさえできるからです」「好奇心というものは、それ自体に存在理由があるのです」等の名言は、実にかっこよく、どこかで使ってみたいものです。
掲載:2007年3月23日
立ち読み
第1章 アインシュタインは偉い
「奇跡の年」から一〇〇年
いきなり私事で恐縮であるが、私は「三人の人物」の熱狂的ファンである。一人は夏目漱石、もう一人は「フーテンの寅さん」。そして、残る一人が、アルバート・アインシュタイン(一八七九―一九五五)なのである。
本書は本来、二〇〇五年に刊行するつもりであった。その年がアインシュタインの「奇跡の年」と呼ばれる一九〇五年から一〇〇年という、きりのいい年だったからである。しかし、それが少々遅れた。その理由は本書で説明する「時空の歪み」とはまったく関係がなく、あくまでも出版社や著者の都合である。とはいえ、そもそもアインシュタインの素晴しさというものは、「○年目」期間限定のものではない。いつであっても、その偉業を何ら損なうものではないことはいうまでもない。
いつであろうが、アインシュタインについて知っていただきたい。その偉さ、すごさ、面白さ、新しさ、すべてについて知っていただきたい。それが本書の狙いである。
そんなことをいきなりいわれても困る、相対性理論については何度か入門書を読んだがわからなかった、とおっしゃるかも知れない。しかし、それでも知っていただきたい。
まず、いきなり理論の説明をするのではなく、いかにアインシュタインがすごかったか、その点について本章では述べておきたい。それを理解していただければ、なぜ知っておく必要があるのかも自ずとおわかりいただけるはずである。
さて、二〇〇五年は「奇跡の年」から一〇〇年ということで、ユネスコが「世界物理年」と制定し、日本を含む世界各地で「物理学」に関するさまざまなイベントが催された。
私はいま、理工系の大学で「物理学入門」を含む物理系の科目を教えており、毎年、新入生に「物理はやさしい、面白いと思っている人、手を挙げて」と聞くのだが、手を挙げる学生は皆無か、極めて稀である。逆に「難しいと思っている人、手を挙げて」と聞くと、大半の学生が手を挙げる。実際、高校で物理を勉強して来る学生は年々減っている。――断っておくが、これは「理工系大学」での話である。
また、私は時々、「生涯学習」「市民大学講座」のような場で一般社会人に話をするのであるが、一般社会人の「物理」に対する感想は、いま述べた学生のものとほぼ同じである。
ちなみに、「物理学」を辞書的に定義すれば「自然科学の一部門で、自然現象を支配する法則を発見し、それらを体系化し、究極的には自然現象を“理解”し、文明の利器などへの応用の道を開こうとする学問分野」ということになる。
確かに、いま私自身が記した「物理学とは……」を読んだり、学校で教わる(教わった)物理のことを思い起こしたりすれば、「物理は難しい、面白くない」と思っている人が世の中に少なくないのもよくわかる。
しかし、こうした事態は「学校で教わる物理」、もっとはっきりいえば「試験のための物理」が面白くなく、その結果、「物理は難しい」と多くの人に思わせてしまったためであり、物理そのもののせいではないのである。私は、まず、このことをはっきりと申し上げておきたい。
「試験のための物理」(何も物理に限ったことではないが)に要求される最も重要なことは、事項や公式を理屈抜きに暗記し、「問題」の「答」(それは必ず用意されている!)を機械的に、そして効率よく見つけることである。
しかし、これは、物理を含む自然科学を学ぶ(そして、究極的には、楽しむ)上で、「最も不要なこと」であるばかりでなく、「最も避けなければならないこと」なのである。
「自然科学を学ぶ」第一歩は「自然に接すること」だが、その時、最も重要なことは、まず理屈抜きに感動すること、そして「なぜだろう?」と不思議に思うことであり、事項や公式の暗記などとはまったく無縁のことなのだ。
そして、次に、自然科学の楽しみは「理屈を考えること」にある。人間の智恵と比べれば自然は極めて雄大、不可思議であり、「答が機械的に見つかる」ようなシロモノでは決してないのである。
第2章で述べるつもりであるが、アインシュタインは、自然科学を学び、楽しむ上で、まさに極上の、理想的な資質を持っていたといえる。
閑話休題。
この「奇跡の年」というのは、二〇〇五年の一〇〇年前、つまり一九〇五年のことであるが、それは、それまで、物理学者としてはまったく無名であった二六歳の青年アインシュタインが「ノーベル賞級」の五篇の論文を立て続けに発表した年なのである。その五篇の論文のうちの三篇はいずれも革命的な「超ノーベル賞級」といってよい。
長年、物理学の分野で仕事をして来た私には、この“奇跡ぶり”、そしてアインシュタインの並外れた“天才ぶり”がよく理解でき、「まさに奇跡!」としかいいようがないのであるが、物理学にあまり縁がない読者には、この“奇跡ぶり”が実感できないかも知れない。
例えば、まったく無名の若者がいきなり野球のメジャーリーグで首位打者、打点王、ホームラン王、盗塁王、最多勝利のタイトルを独占したようなものである。ここで、獲得したタイトルのすごさと共に、打者、走者、投手としてのタイトルが混在していることにも注目していただきたい。
担当編集者のひとこと
「アインシュタイン愛」
「ジャイアンツ愛」というフレーズを唱えたのは原辰徳監督でした。この言い方に倣えば、『新書で入門 アインシュタイン丸かじり』の著者、志村史夫さんは、熱烈な「アインシュタイン愛」の持ち主です。原監督の巨人論が面白いかどうかは知らないのですが、志村さんのアインシュタインの解説は、熱烈なファンだからこその熱さがあって大変面白いものになっています。
本を作るための打ち合わせでのお話にも実に熱が入っていました。本書の最終章で紹介しているアインシュタインの数々の名言を引きながら、
「いやあ、本当にいいよね。この言葉。なんていいんだろう」
と嬉しそうにお話をされます。
その様子は「相対性理論」なんて難しいものの生みの親について語っているようには傍目にはとても見えないでしょう。
しかし、この愛があるからこそ、志村さんのアインシュタインへの賛辞は、他の追随を許さないのです。アインシュタインがノーベル賞級の論文を1年間に5本発表した「奇跡の年」の“奇跡ぶり”について、志村さんはこんなふうに表現しています。
「例えば、まったく無名の若者がいきなり野球のメジャーリーグで首位打者、打点王、ホームラン王、盗塁王、最多勝利のタイトルを独占したようなものである。ここで、獲得したタイトルのすごさと共に、打者、走者、投手としてのタイトルが混在していることにも注目していただきたい」
「アインシュタイン愛」の強さが何となく伝わったでしょうか。この愛の強さに引っ張られているうちに、何となく「相対性理論」もわかったような気になれる。そんな入門書になっています。
2007/03/23
キーワード
著者プロフィール
志村史夫
シムラ・フミオ
1948(昭和23)年東京・駒込生まれ。名古屋工業大学大学院修士課程修了。名古屋大学工学博士(応用物理)。2007年現在、静岡理工科大学教授、ノースカロライナ州立大学併任教授。『こわくない物理学』など著書多数。2002(平成14)年、日本工学教育協会賞・著作賞受賞。