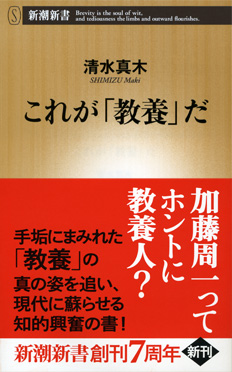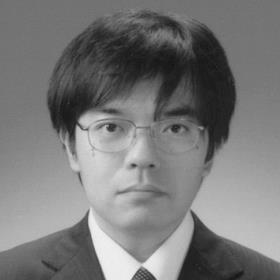これが「教養」だ
792円(税込)
発売日:2010/04/16
- 新書
- 電子書籍あり
加藤周一ってホントに教養人? 手垢にまみれた「教養」の真の姿を追い、現代に蘇らせる知的興奮の書!
「教養」の歴史は意外なほど浅い。もともとは、一八世紀西欧の片隅でひっそりと生まれた小さな概念で、「公の立場と私の立場に引き裂かれた人間が、それを統合するために必要な能力」という極めて限定的な意味しか持たなかった。その教養がなぜ、「古典」「読書」「該博な知識」などと結びつき変質してしまったのか──。新進気鋭の哲学者が、探偵のごとく「真の教養の姿」を追い求め、現代に蘇らせる知的興奮の書。
目次
第1章 手垢にまみれた教養の本当の姿
「教養とは何か」という危険な問題/一八世紀生れの新しい考え方/小さな断片をゴミから掘り出す/まずは「あかの他人」を引き離そう/教養の定義/公共性の構造転換/話し合いによって問題を解決する社会/協会と団体/市民社会は「面倒な社会」/仕事と家庭はどっちが大事?/三つに分裂した生活/「丸ごとの人間」を受け入れる社会/ギリシア人はどう考えたか/「交通整理」の必要性/完全に打算的な人間は「教養ある人間」である/教養、迷走を始める/「自分らしさ」が「人間性」にすり替えられた
第2章 「教養」という日本語の考古学
大正時代から使われ出した言葉/諸橋『大漢和辞典』には載っているが……/幕末までほとんど知られていなかった/明治初期の「教養」は「教育」の意味/後付けの説明には要注意/最初の「哲学」者、西周/『哲学字彙』の役割/ローマ文化は世界最初の翻訳文化/「カルチャー」は「修錬」と訳されていた/言文一致と言文不一致/和語と漢語/「ビルドゥング」の訳語としての「教養」/修養団、一燈園、講談社/新渡戸稲造のどこが偉いのか/教育者としての感化力/新渡戸は「教養」と言っていなかった/「修養」と「教養」はどこまで置き換え可能か/教養する? 教養の目的? 教養になる?/修養は、直接の目標にはなれない/問われ続けていた「修養とは何か」/加藤咄堂の『修養論』/修養と教養をつないだ新渡戸/教養は「輸入の缶詰」
第3章 「輸入の缶詰」を開けてみる
加藤周一と俗物/「俗物」の試金石/教養主義から逃れていると信じた加藤/教養の通俗的な理解/幅広い知識は教養とは関係ない/「教養教育」って何?/二極化する大学/プロイセンの教育改革/学校が「教養の装置」に/「哲学部」の下剋上/「リベラルアーツ=教養」の勘違い/缶詰の中身を調べる必要性/一八世紀のドイツ人も覚えた違和感/群盲象を撫でる/立花隆の東大講義/「教養書」とは何ぞや/教養か実用か/「学歴はないけれど、教養がある」
第4章 教養を生れたままの姿で掘り出そう
『山椒魚』は高級で『日刊ゲンダイ』は低級?/古典と教養は何の関係もなかった/「古典」はいつ生れたか/クイズの答/古典とは、新しいものを正当化するために現れた古いもの/紀元前一世紀の「過去との断絶」/古典は「文章のお手本」だった/ホメロス作品も「マニュアル本」だった!/一九世紀に変わった「古典」の意味/古典の正典化/ロマン主義と独創性信仰/ナポレオンが作った学校/社会の要求を無視したドイツの教育改革/再生産としての読書/ポリフォニーとしての文学/「末端消費者」になった読者/三位一体の成立/教養は必要か/名人芸としての教養
あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | コレガキョウヨウダ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-610361-2 |
| C-CODE | 0210 |
| 整理番号 | 361 |
| ジャンル | 哲学・思想、思想・社会 |
| 定価 | 792円 |
| 電子書籍 価格 | 660円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2012/05/25 |
蘊蓄倉庫
新渡戸稲造は「教養」という言葉を使っていなかった
英語で発表した『武士道』の著者で、旧制一高の校長を務めた新渡戸稲造は、大正時代を代表する「教養人」の一人として知られています。しかし、生前の彼は「教養」という言葉を使っていませんでした。その代わりに使っていたのが「修養」です。そのものずばりの『修養』という書物も出しています。「教養」という言葉を使わなかった新渡戸が、後世、「教養主義」の代表的人物として取り上げられるようになったのは、偉大な教育者であった彼の言葉に感化された人々──旧制一高の生徒たち──が、彼の言葉を「教養をめぐる発言」として「翻訳」したため、と考えられます。
英語で発表した『武士道』の著者で、旧制一高の校長を務めた新渡戸稲造は、大正時代を代表する「教養人」の一人として知られています。しかし、生前の彼は「教養」という言葉を使っていませんでした。その代わりに使っていたのが「修養」です。そのものずばりの『修養』という書物も出しています。「教養」という言葉を使わなかった新渡戸が、後世、「教養主義」の代表的人物として取り上げられるようになったのは、偉大な教育者であった彼の言葉に感化された人々──旧制一高の生徒たち──が、彼の言葉を「教養をめぐる発言」として「翻訳」したため、と考えられます。
掲載:2010年4月23日
著者プロフィール
清水真木
シミズ・マキ
1968(昭和43)年東京生まれ。明治大学商学部教授。東京大学大学院博士課程修了。博士(文学)。哲学、哲学史専攻。広島大学総合科学部講師、助教授等を経て現職。著書に『友情を疑う―親しさという牢獄―』『知の教科書 ニーチェ』などがある。
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る