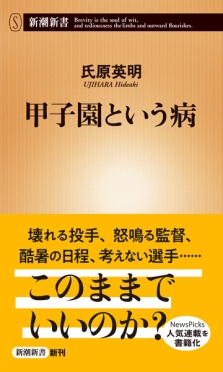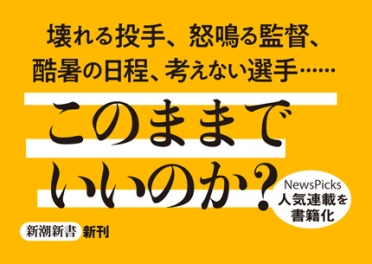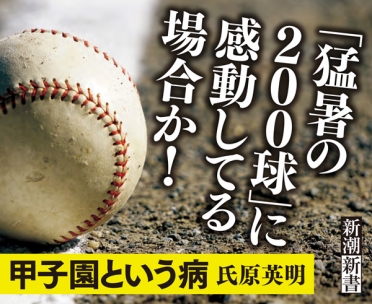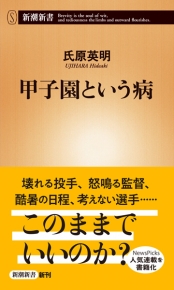
甲子園という病
792円(税込)
発売日:2018/08/09
- 新書
- 電子書籍あり
壊れる投手、怒鳴る監督、酷暑の日程、考えない選手……このままでいいのか?
NewsPicks人気連載を書籍化。
甲子園はいつもドラマに事欠かないが、背後の「不都合な真実」に光が当たることは少ない。本来高校野球は「部活」であり「教育の一環」である。勝利至上主義の指導者が、絶対服従を要求して「考えない選手」を量産したり、肩や肘を壊してもエースに投げさせたりするシステムは根本的に間違っている。監督・選手に徹底取材。甲子園の魅力と魔力を知り尽くしたジャーナリストによる「甲子園改革」の提言。
書誌情報
| 読み仮名 | コウシエントイウヤマイ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 192ページ |
| ISBN | 978-4-10-610779-5 |
| C-CODE | 0275 |
| 整理番号 | 779 |
| ジャンル | スポーツ・アウトドア |
| 定価 | 792円 |
| 電子書籍 価格 | 792円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2018/08/24 |
インタビュー/対談/エッセイ
「甲子園という病」への処方箋
悲願と言ってしまったら自分のライター人生が終わってしまう気がするので言わないが、これは私自身が書きたいと思い続けていた書籍である。
と言っても、甲子園の批判を書きたかったという意味ではない。私はただただ正しい報道姿勢を貫きたいと思っただけだ。
今年夏の甲子園で取材をしていると、同業者たちから「氏原さんにしか書けない作品」と言われる。書籍のタイトルの印象が与えてしまっているのかもしれないが「氏原は批判を率先して書く人物」と思われているのは心外だ。はっきり言わせてもらうと、私のことをそう見る人たちにはジャーナリスト精神もなければ問題意識もない。
私が甲子園の取材をするようになったのは2003年の夏からだ。当時の甲子園にはダルビッシュ有(現シカゴ・カブス)というアイドルのようなスター選手がいたが、いわゆる将来のスターと騒がれる選手の取材をする日々にワクワクしたものだった。当時の私は熱投を称賛していたクチで、朝日新聞を中心とした高校野球礼賛に、かなり加担していた。
そんな私のマインドが変わるようになったのは指導者たちの言葉に疑問を持つようになったからだ。多くの高校に取材で出入りしていた私に、指導者たちがこんなことを言ってきた。
「氏原君、今年は素材のいい一年生が入部してきたから、また取材に来てよ」と。実際に足を運んでみると、本当にいい選手だった。ところが一年経つと、同じ人がまた同じことを言う。「いい一年生が入った」と。そして、前年の一年生の話題にはならないのだ。こういうケースは度々あった。
つまり、高校野球の指導者の何人かは育てるのが下手なのではないかと思うようになった。そして、その遠因が甲子園にあるということに気づいたのだ。長時間練習、上意下達的な指導、試合での登板過多など、「甲子園」は本当に高校球児のためになっているのか、と。
そうした視点で見ていくと、「こんなにいるのか」と驚くほどケガを抱えている選手が多いことに気づいた。また、監督の都合で干されたり、イップスになったりしている選手もたくさんいた。
しかし、そうした問題に多くのメディアが気づいていなかった。いや、気づいていないのではなく見て見ぬふりをしているのかもしれない。登板過多が「熱投」に変わって美談になるこの世界は、本当に「クレイジー」だと思う。
当初の書籍タイトルは「甲子園中毒」をイメージしていた。高校野球に関わる人は「甲子園」にとらわれた中毒症状で、それならいつかは解毒するはずだと信じたい自分がいたからだ。最終的には「甲子園という病」になったが、病には処方箋が必要だ。この本がそうなってくれればと願う。
(うじはら・ひであき スポーツジャーナリスト)
波 2018年9月号より
蘊蓄倉庫
松坂大輔と黒田博樹
ほぼ同じ時期にメジャーで活躍した投手、松坂大輔と黒田博樹は、対称的な高校時代を過ごしています。松坂はご存じの通り、高校三年生の時に甲子園で春夏連覇を成し遂げ、日本のプロ野球でも大活躍しました。しかし、30歳になったメジャー移籍3年目のシーズン以降はまともに活躍できていません。一方、33歳からメジャーで7年投げ、松坂を遙かにしのぐ活躍を見せた黒田は高校時代は3番手投手。この活躍の差の理由に「高校時代の投球数」を指摘する声は少なくありません。
余計なお世話ですが、甲子園で投げまくってチームを優勝に導き、プロ野球でもメジャーでも活躍しているものの、今年30歳になるヤンキースの田中将大投手が松坂と同じ道を歩まないか気がかりです。
掲載:2018年8月24日
担当編集者のひとこと
「勝利至上主義」という病
2018年の夏の甲子園大会は、記念すべき100回大会となりました。
この100年の間に、数々の感動のドラマがあったことは確かですが、今の甲子園に全く問題がない、と考える人はあまりいないでしょう。感動のドラマの裏側では、いまや無視できないほど多くの問題が積み上がっています。
一番の問題は、「一発勝負のトーナメント方式」を採用しているために、高校野球全体が「勝利至上主義」の色に染まってしまっていることです。
今年の100回大会でも、プロ注目の金足農業のエース・吉田輝星投手が、県大会から甲子園本大会まで一人で投げきり、甲子園の決勝戦で滅多打ちにされて五回終了後に自ら降板するという「玉砕」ドラマを演じましたが、実力エースが無理をして潰れるのは吉田投手に限りません。本来、高校野球も「部活」であり「教育の一環」のはずですが、一発勝負のトーナメント方式を採用しているため、「選手の能力を信じて成長を待つ」ということがやりにくい環境が出来上がってしまっているのです。
また、勝利至上主義ゆえに監督が無駄にカリスマ化したり、「考えない選手」が大量に生まれてしまう、という問題もあります。選手から勝負の喜びを奪う敬遠策やバントが多用されるのも同じ理由で、その果てには「松井秀喜の5敬遠」のような、とても選手のことを第一に考えているとは言えないような策も生まれてしまうわけです。
選手の育成という点で、日本の野球が中南米に大きく劣っている原因は、間違いなく「甲子園」の存在にあります。
そういう事情を充分に意識しつつ、著者は徹底的に現場を歩き、「甲子園という病」にやられた関係者や、新たな試みを続ける学校・指導者・選手たちを丹念に取材していきます。
現実は一筋縄ではいきません。確かに甲子園に問題はありますが、同時に「やはりこれは人生の一時をかけるに値する舞台なのだ」と思わせてくれるエピソードも多く、感動的な物語も尽きません。
ただ、本書の「感動」は、甲子園礼賛メディアの報じる「酷暑で200球投げ抜いたエースはすごい!」式の、制度の不備と児童虐待にも等しい過酷さを糊塗するための「感動」ではなくて、選手の成長とスポーツの楽しみを追求する施策の成功によってもたらされているものです。
著者はもともと地方紙の記者でしたが、独立して以来のこの15年、夏の甲子園大会をほぼ全試合観戦しており、後にプロ入りした有名選手たちは軒並み取材しています。100回大会で優勝した大阪桐蔭も継続取材の対象校。今回の原稿は「甲子園メディア」に忖度せずに積年の思いを綴った著者渾身の力作です。どうぞご一読下さい。
2018/08/24
著者プロフィール
氏原英明
ウジハラ・ヒデアキ
1977(昭和52)年ブラジル・サンパウロ生まれ。スポーツジャーナリスト。奈良新聞勤務を経て2003年に独立。2003年の夏以降、甲子園大会はすべて現場で取材している。著書に『甲子園という病』、執筆協力に菊池雄星著『メジャーをかなえた雄星ノート』がある。