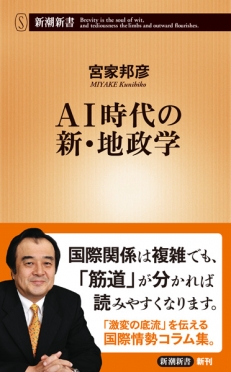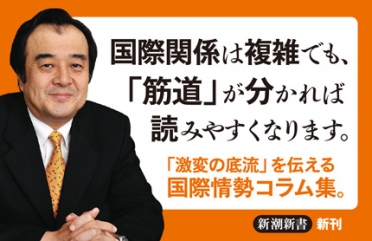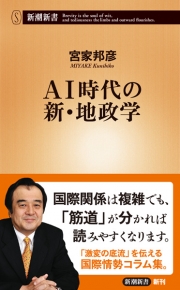
AI時代の新・地政学
858円(税込)
発売日:2018/09/14
- 新書
- 電子書籍あり
国際関係は複雑でも、「筋道」が分かれば読みやすくなります。「激変の底流」を伝える国際情勢コラム集。
AI時代を迎え、従来の地政学の常識は大きく書き換えられていく。戦略兵器となった「AI兵器」が核にとって代わり、熱い戦争ではなく「水面下の刺し合い」が主戦場となる可能性すらある。大事なのは、技術の革新を認識しつつ、変わらぬ人間の本質と冷徹な現実を見据え、世界の行く末をクールに考え抜く姿勢だ。戦略的思考に定評のある元外交官が、縦横無尽・自由自在・ユーモアたっぷりに未来を読み解く。
AIが作る芸術に創造性はあるのか
AI革命はダークサイドを変えるか
AI革命と米中の地政学
AI革命と米露の地政学
AIと日韓、日朝、日中の地政学
AI革命は戦争をどう変えるのか
AI革命で変わる国家戦略論
AIを悪魔にするのは人間である
AI革命時代に日本がすべきこと
歴史の大局を左右する「ドライバー」とは
「力の真空」理論と北朝鮮情勢
中国人とアラブ人の5つの共通点
中国人と中東人はここが違う
ユダヤ陰謀論に陥るな
ユダヤ・ロビーとイスラエル・ロビー
周辺国としての日本、ロシア、トルコ
トランプを生んだダークサイド
ダークサイドを支える民衆
国際政治版「メジャーリーガー」は米中露
米露関係の悪化
厳冬のモスクワで見たロシア帝国の黄昏
インドは頼もしい対中同盟国となるか
イランの地政学「米国による制裁」はどうなる
対北朝鮮「宥和政策」は機能するのか
周辺の大国に翻弄される「朝鮮」外交
半島「力の真空」ゲームを各国は如何に戦うか
韓国という隣人との付き合い方
EU離脱:UKの末路の始まり
ハンガリーの地政学:スラブとゲルマンの狭間で
ポーランドの地政学:最悪の隣人を持つ悲劇の民族
スウェーデンの地政学:高福祉平和中立国家の真実
エストニアの地政学:陸軍3800人の国がロシアに勝つ方法
トランプ当選をなぜ予測できなかったのか
アメリカ南北戦争パート3
トランプ不規則発言の規則性
トランプ国連演説の報じられない部分
対中外交の失われた四半世紀
「社会主義市場経済」はマーケットなのか
現代中国の「満州事変」と「リットン報告書」
アメリカと中国の変化する関係性
拝啓 文在寅大統領閣下
拝啓 習近平国家主席閣下
拝啓 孫政才元重慶市党委員会書記閣下
拝啓 国家安全保障担当補佐官閣下
沖縄をこよなく愛した外交官の物語
伊勢志摩サミットとオバマ広島訪問
伊勢志摩サミット:議長国の特権と責任
息子のバンドを追っかけ上海へ?
ジェームズ・ボンドのいない日本
当世日本「シンクタンク」事情
大衆迎合政治「日本よ、お前もか!」
ポピュリズムの嵐、日本にも?
日本型ポピュリズムの特徴は?
良くわからん! 戦闘と武力衝突の違い
前川前次官は官僚王国ニッポンの黄昏
書誌情報
| 読み仮名 | エイアイジダイノシンチセイガク |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 週刊新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 240ページ |
| ISBN | 978-4-10-610781-8 |
| C-CODE | 0231 |
| 整理番号 | 781 |
| ジャンル | 政治・社会 |
| 定価 | 858円 |
| 電子書籍 価格 | 858円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2018/09/21 |
蘊蓄倉庫
中東と中国の共通点と違い
元外交官でイラクと中国で勤務した経験を持つ宮家邦彦さんは、中東と中国について、面白い指摘をしています。日本が苦手とするこの両者には5つの共通点があって、それは自己中心、部外者不信、面子重視、援助不感謝、陰謀論好きとのこと。ただ、これは開発途上国の国民が共通して持つ「劣等感」の裏返しであり、中東や中国に限ったことではないそうです。
では違いの方は何か。宮家さんが編み出した方程式をご紹介しておきます。
【中国】-【酒】-【豚】-【小姐(お姉さん)】+【石油】=【中東】
掲載:2018年9月25日
担当編集者のひとこと
知的な誠実さ
本書は、2015年の年末から2018年の4月まで著者が「週刊新潮」で連載していたコラムを抜粋し、加筆、修正、再編集を施したものです。
この期間はトランプ、ブレグジット、シリア情勢とイスラム国、北朝鮮の核開発、ロシアのクリミア侵攻などニュースに事欠かない時期でしたが、著者はそうした事象の中から、その後の国際情勢を動かす「ドライバー」を見つけようと努めています。「駆動させるもの」と「筋道」を見つければ、複雑な国際情勢の展開も読み解きやすくなるからです。
なかでも、著者が注目しているのが「AI」。AIと言えば、日本では専ら経済活動への影響が取り沙汰されていますが、軍事面での人間の関与を低下させ、国家間の地理的距離を変質させるという意味で、AIは地政学上の「ゲームチェンジャー」ともなりうる存在です。
近い将来、AI兵器が核兵器にとって代わり「戦略兵器」となる可能性や、AI兵器が一発の弾も放たずに敵国の「大量破壊」を成し遂げる、などという事態も考えられるのです。現状、そこまでの変化は起きていませんが、「いまは非常識に思えてもありうべき未来の姿を考える」ところが、戦略的思考に長けた著者の真骨頂と言えます。
ただ、元はコラムですから、堅い話ばかりが続くわけではありません。著者は外務省時代の研修言語がアラビア語で、かつ中国への赴任経験もあります。いわば、日本にとって「付き合いづらい相手」の両横綱の専門家ですが、その中国人とアラブ人の共通点と相違点をめぐる考察などは、元外交官の著者ならではの面白さです。
編集をしていて感じたのですが、宮家さんのある種の「知的誠実さ」。自分が分からないことは「分からない」と記しますし、判断が間違っていたなら「間違っていた」と記します(トランプ当選は予測できなかったそうです)。元官僚ですから、意に沿わぬ仕事を任されることもあったでしょうが、それでもスジを通そう、物事の道理を突き詰めて考えようという姿勢が貫かれています。
宮家さんは神奈川の栄光学園のご出身だそうですが、同じく栄光出身の隈研吾さんや養老孟司さんと知的構えに似たようなものを感じます。まあ、勝手な思い込みですが。
入り口は取っつきやすいですが、読んでいるうちに思考を遠くまで連れて行ってくれる本です。
2018/09/25
著者プロフィール
宮家邦彦
ミヤケ・クニヒコ
1953(昭和28)年神奈川県生まれ。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。元外交官。東京大学法学部を卒業後、外務省に入省。在中国大使館公使、在イラク大使館公使などを経て2005年に退官。『「力の大真空」が世界史を変える』など著書多数。