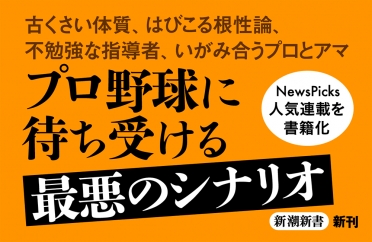野球消滅
836円(税込)
発売日:2019/08/09
- 新書
- 電子書籍あり
古くさい体質、はびこる根性論、不勉強な指導者、いがみ合うプロとアマ。プロ野球に待ち受ける最悪のシナリオ。NewsPicks人気連載を書籍化。
いま、全国で急速に「野球少年」が消えている。理由は少子化だけではない。プロとアマが啀(いが)み合い、統一した意思の存在しない野球界の「構造問題」が、もはや無視できないほど大きくなってしまったからだ。このままいけば、三十年後にはプロ野球興行の存続すら危ぶまれるのだ。プロ野球から学童野球まで、ひたすら現場を歩き続けるノンフィクション作家が描いた日本野球界の「不都合な真実」。
書誌情報
| 読み仮名 | ヤキュウショウメツ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-610825-9 |
| C-CODE | 0275 |
| 整理番号 | 825 |
| ジャンル | スポーツ・アウトドア |
| 定価 | 836円 |
| 電子書籍 価格 | 836円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/08/23 |
インタビュー/対談/エッセイ
野球界をアップデートしたい
「少年野球人口減少など、大した問題ではない」
2016年末のプロ野球(NPB)オーナー会議である球団トップがそう語ったという情報は、プロアマの野球関係者たちを落胆させた。
近年、確かにプロ野球の観客動員数はうなぎのぼりだ。だが少年野球人口減少を「対岸の火事」と捉えるのは利己的かつ近視眼的で、無知にもほどがある。一人のプロ野球選手は、多くのアマチュア指導者たちのおかげで誕生しているのだ。
ただしアマの指導者たちが手塩にかけた選手がプロになり、いくらプロ球団が儲けても、その利益はアマに還元されない。学生野球憲章は選手やチームを商業的に利用しないことを規定しており、プロからお金を受け取ることはできないからだ。また、プロ、社会人、大学、高校、中学校、学童と各世代の組織はバラバラに誕生して各自で運営されてきた歴史があり、手を取り合って明るい未来を目指すという発想が極端に薄い。甘い蜜はすべてプロが吸い上げる構図になっている。
学童野球という球界の底辺を支える全日本軟式野球連盟の宗像豊巳専務理事は、こう嘆いた。
「我々には興行もなければ、何もない。チームの登録料でメシを食っている団体です。日本高野連、日本野球連盟(社会人野球の組織)、NPBみたいに興行を持っているところは羨ましい」
少年野球人口減少の一因に「野球はお金がかかる」というものがある。ひとり親家庭や低所得者層が増えるなか、グローブやバット、遠征代など親の負担が重い野球をやらせたくない――そうした要因に対処するには、プロ野球が助成するという方法もある。親と子どもを野球の世界に引き込めれば、マーケティングにもつながるはずだ。
しかし、そうした動きは一向にない。団体間に壁があるからだ。NPBが12球団をまとめるような行動もない。ある球団の職員は、普及振興活動をしたら、「収益を生む仕事をしろ」と上司に嫌味を言われたという。目先の利益に囚われ、このまま野球少年減少を抑止できないと、遠くない将来に野球市場が縮小し、自分たちのビジネスが成り立たなくなるにもかかわらず。
競技者が減り続けている以上、野球界は育成モデルを変化させることが不可欠だ。これまでは大人数からふるいにかける方式でプロ選手を選抜してきたが、今後は限られた者を確実に引き上げることが求められる。だが世代別で組織が異なる野球界では、育成は短期的視点に陥りやすい。指導者は、勝利至上主義で目の前の結果ばかりを求めるような仕組みになっている。
根深い構造問題を抱える野球界は、足元を揺るがす危機に対処できるか。野球を愛する者たちと一緒に、何とか知恵をひねり出したいと思って、この本を書いた。
(なかじま・だいすけ スポーツ・ノンフィクション作家)
波 2019年9月号より
蘊蓄倉庫
高校野球の「韓国化」
日本では「する」スポーツにして、「見る」スポーツでもあった野球ですが、いま急速に「する」スポーツとしての地位を下げつつあります。2016年時点で日本の高校には野球部員が男子生徒全体の1割以上はいたことになっていますが、各種の指標は、野球を「する」少年の数が劇的に減りつつあることを告げています。
ちなみに野球が「する」スポーツではなく、超エリートスポーツマンの「する」スポーツである韓国では、同じ2016年時点で野球部員は男子高校生のわずか0.3%。いま日本の高校野球界で進んでいるのは、野球が選抜された一部エリートの競技と化していく「韓国化」とも言うべき現象なのです。
掲載:2019年8月26日
担当編集者のひとこと
野球少年が消えている
高校野球もプロ野球も隆盛を極める一方で、日本の風景から急速に「野球少年」が消えていっています。「日本は少子化なんだから当たり前だろ」と思われるかも知れませんが、野球少年の減少ペースは少子化のペースを遙かに上回っており、そこに野球固有の「構造問題」があることは否定できません。
日本の野球界では、長年プロとアマがいがみ合う関係にあり、球界としての「統一した意思」が存在しません。これは、Jリーグを頂点にして、ジュニア世代から育成の観点を強く持っているサッカー界とはまったく異なった点です。小中学校で投げ続け、肩や肘を痛めながら「甲子園を目指して燃え尽きる」野球少年はいまでも少なくない。しかも、それを是とする「安定の昭和コメント製造機」張本勲のような人が、球界では全く珍しくないのです。
少年野球の世界には、「地元の新聞を取らないと事実上大会に出られない」といった、不思議な慣行も残っています。共働きやひとり親世帯は増え続けていますが、少年野球の世界では「お茶当番」などの保護者負担が当然視されている。野球界の仕組みと意識が時代と合っていないのです。野球は「やる」スポーツから「見る」スポーツへと急速に変化しており、かつては普通だった「中学から野球部に入る」という慣行が消えつつあります。長い目で見るとプロ野球興行の基盤すら侵食しかねないほどの変化が、水面下で生じつつあるのです。
著者の中島さんは、長年スポーツの取材に携わっており、中南米野球を現地で深く取材した経験から、日本の野球界の構造問題を指摘するだけでなく、改善のための提言も続けています。甲子園の「投げすぎ」問題は毎年繰り返されていますが、その背後には野球界の古くさい体質や指導者の根性主義、科学的知見に対する無知、勝利至上主義などの問題が絡み合っており、一筋縄ではいきません。
本書では、著者の考える野球界に必要な「アップデート」についても語られていますので、興味を覚えた方は、ぜひ手にとって頂ければ幸いです。ついでに言えば、去年の8月に出た『甲子園という病』と一緒に読むと、より理解が深まると思います(笑)。
2019/08/26
著者プロフィール
中島大輔
ナカジマ・ダイスケ
1979年埼玉県生まれ。上智大学卒。スポーツ・ノンフィクション作家。著書『中南米野球はなぜ強いのか』で第二十八回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。他の著書に『野球消滅』『プロ野球 FA宣言の闇』など。プロからアマチュアまで野球界を広く取材している。