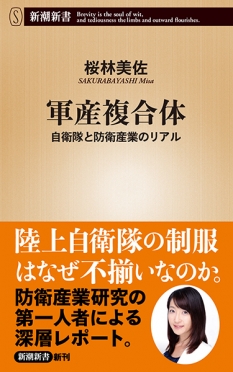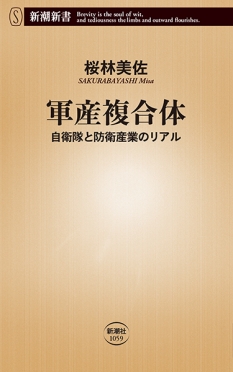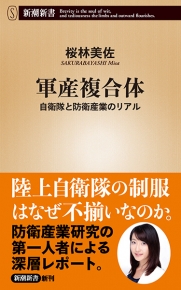
軍産複合体―自衛隊と防衛産業のリアル―
990円(税込)
発売日:2024/09/19
- 新書
- 電子書籍あり
陸上自衛隊の制服はなぜ不揃いなのか。防衛産業研究の第一人者による深層レポート。
台湾有事が現実的な懸念となる今、自衛隊の安定的な運用のためにも防衛産業の再興が欠かせない。しかし、日本の防衛産業には何重もの「足かせ」がある。顧客は自衛隊だけ、大企業の弱小部門に過ぎない存在感の低さ、筋違いの「死の商人」批判などから、「本当はやめたい」会社も少なくないのだ。一貫して自衛隊と防衛産業の取材を続けている専門家が語る、「軍産複合体」のリアルな姿。
書誌情報
| 読み仮名 | グンサンフクゴウタイジエイタイトボウエイサンギョウノリアル |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-611059-7 |
| C-CODE | 0231 |
| 整理番号 | 1059 |
| ジャンル | 政治・社会 |
| 定価 | 990円 |
| 電子書籍 価格 | 990円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2024/09/19 |
インタビュー/対談/エッセイ
戦争を避けるための儲からない仕事
タイトルからは、戦争で儲けようとしている人たちの話のようにイメージされると思うが、本書でリポートしているのは戦争を避けるため儲からない仕事をしている人たちの姿である。
日本の「防衛産業」とは一体どういうものなのか、まだほとんど知られていない。それは当然で、正確に言えば日本には「防衛産業」は存在しないからだ。防衛事業だけで成り立っている企業はなく、「一部門」でしかない。その防衛需要依存度は平均で4%程度と言われ、会社によっては1%以下という場合もあるため、「防衛? ウチにそんな事業ありましたっけ」と、社員ですら存在をよく知らないこともある。
「防衛産業」にとって最も近い人たちは自衛官である。ユーザーは自衛隊しかいないからだ。では自衛官が防衛産業のことをよく知っているかといえば全くそんなことはなく、接点のない自衛官のほうがはるかに多い。
つまるところ、わが国の防衛産業の人たちは、自分たちの属する会社にも、唯一のお客さんである自衛隊にも、その存在意義がしっかり理解されていない存在なのだ。
その「防衛産業」に今、世の中が注目している。輸出を推進し、世界で勝負できるようにさせようとか、そんなことをすれば死の商人になるとか議論百出であるが、これらはあくまでも想像(妄想)の世界でしかない。全く門外漢の日本人がオハイオ州の製造業をいかに立て直すか、などと論じたりはしないように、本来であれば自分たちがよく知らない日本の防衛産業について議論そのものができないにもかかわらず、居酒屋談義のみならず国会でも話題になっているのが現在の状況だ。
私自身、思いがけずこの問題に取り組むことになり十数年、知り得た課題を様々な形で発信してみたものの、大きな改善も見られず、また誤解ばかりが広まっているため無力感の中にあった。
そんな時「軍産複合体」が日本を救うというコンセプトで執筆の機会を頂くことになり、装備行政に一石を投じたいなどという身の程知らずな野望は捨て去り、半ばやけっぱちな態度で、とにかくこれまで見聞きしたことを旅行記のように書き綴ってみたのが本書である。
また、防衛産業を語るには自衛隊を知る必要があり、両者を切り離して議論しても全く意味がない。そこで今回は自衛隊にまつわる話題も多く盛り込んでいる。考えてみると、従来の拙著では、自衛隊の本には自衛隊のこと、防衛産業の本には防衛産業のことを書くものだと思い込んでいた。その縛りを取り払って頂いたことが画期的だった。
誤解の多い「武器輸出」論議も含め、わが国にある技術を日本の防衛や世界の安定に活かす議論を正しく行うための一助になればありがたい。
(さくらばやし・みさ 防衛問題研究家)
蘊蓄倉庫
「第二の人生」に不安を残す自衛官
自衛隊では定員割れが常態化してしまっていますが、その理由の一つが自衛官の定年です。「精強性の維持」を理由として、自衛官の定年は2曹、3曹が54歳、1曹から2佐までが56歳、1佐が57歳となっています。つまり、将官クラスにまでたどり着けないと、60歳まで働けないわけです。
2024年10月からは、階級に応じてさらに定年を延長することになっていますが、自衛官という職業に就くと「第二の人生」に不安を残すという状態が続くなら、なかなか定員充足には至らないでしょう。
掲載:2024年9月25日
担当編集者のひとこと
ジャン・バルジャンとイノベーション
台湾有事の現実的な可能性が意識され、日本でも防衛論議が活発になされるようになってきました。岸田政権は防衛費をNATO諸国並みのGDP比2%にするべく、2023年度からの5カ年で総額43兆円にする方針を打ち出しました。昨年には「防衛生産基盤強化法」も成立し、防衛産業の基盤を整備しようとの気運も高まってきています。
しかし、日本の防衛産業の現場を見ると、本当に「足かせ」だらけです。顧客は事実上自衛隊だけ。量産効果が働かず低い利益率。大企業の弱小部門に過ぎないので低い存在感。筋違いの「死の商人」批判。こうした理由から、「本当はやめたい」と考えている会社も少なくありません。実際に機関銃製造の住友重工、装甲車生産のコマツなど、防衛事業から撤退している会社が近年相次いでおり、業界には少なからず衝撃が走っています。
そんな現状に対し、「輸出によって防衛産業を振興する」とか「デュアルユース技術によるイノベーションを」といった意見も見られますが、日本の防衛産業の現実はなかなかそうした「経済原理」が浸透するような状況にありません。むしろ、「義理と人情と浪花節」の側面の方が強いのですが、そうなったのには「武器輸出三原則」とか「専守防衛」といった、特殊日本的な事情がありました。
実際、武器輸出三原則がなくなって「輸出によって防衛産業を振興」といったところで、本当に武器を必要としている国は、近年まで武器を禁輸していて、売る側の国のくせに買う側にいろいろ条件をつけてくるようなところから買いたいとは思わないでしょう。
また、自衛隊の現場はコンプライアンスでがんじがらめ。隊での糧食をちょっと多めにとっただけで処分された「自衛隊のジャン・バルジャン」があちこちで生まれているような状況にあります。そんな組織に「官民の交流で現場のニーズを汲み上げてイノベーションを」などといっても、無理筋の議論に思えてきます。
著者は、「防衛産業も安全保障政策の一環として位置づけ、その振興も安全保障政策の一環として考えるべき」との立場です。武器輸出を産業政策としてバンバン行っているような韓国や欧州諸国とは、良くも悪くも日本は状況が違うようです。そうした「泥臭い現実」に、著者は丁寧に解説してくれます。
少し裏事情を話すと、実はこの企画、「はじめにタイトルありき」で考えていました。私は近年、安全保障関連の企画をずいぶんと手掛けてきたのですが、そうした中で、「安保関係の分野で一番デカい穴は防衛産業だな」という印象を強く持つようになっていました。「これはテーマとして何とか形にしないと」と思っていたのですが、「防衛産業」というテーマはなかなか読者を集めにくい。
そこで、「軍産複合体」というキーワードを使ってみるのはどうだろうか、と考えました。この言葉はもともと、アイゼンハワー大統領が退任演説の際に、その影響力に対して警鐘を鳴らす意味で使った言葉ですが、日本の安保環境を考えると、むしろ肯定的な意味で使えるのではないか、と思ったのです。
最初は、当事者とか関係者とかを集めた座談会形式がいいのかな、などとも考えていましたが、いろいろと調べていると、防衛産業の現状と問題点について、圧倒的に「分かっている」人が一人いることに気付きました。それが、本書の著者である桜林美佐さんです。
桜林さんに「軍産複合体」という打ち出しで書いて貰えれば、それがいちばん。そこで、恐る恐るオファーを出したところ、受け入れて頂き、このたびようやく刊行にこぎ着けることができました。
忙しい桜林さんに書き下ろしをお願いするのは心苦しかったのですが、二人で相談して苦し紛れに出したやり方が、「毎月、月初に原稿を貰う」というやり方でした。実は、書き手というのは締め切りを守らない人の方が多いので(笑)、そんなやり方が機能するのか半信半疑だったのですが、桜林さんはなんと、こちらからせっつかなくても毎月原稿をご自分から送って下さるという優秀な書き手だったのです!
どうしてそんなにきっちりしているのか。聞けば、「私はもともとテレビ業界にいたので、『締め切りまでに、決められた時間の尺を埋める』ということが染み込んでいる」とのことでした。テレビ業界での修業の賜だったんですね。恐れ入りました。
本書では、自衛隊と防衛産業のリアルな現実を描写しつつ、現時点で望みうる最善手をいろいろと提案しています。最近、川重の潜水艦をめぐるスキャンダルなどもありましたが、そうしたスキャンダルが生まれる背景の事情などにも踏み込んで記されています。
自衛隊と防衛産業の現状について、キッチリと理解するのには最適な本。出来るだけ多くの方に読んで頂きたいと思います。
2024/09/25
著者プロフィール
桜林美佐
サクラバヤシ・ミサ
1970(昭和45)年東京都生まれ。防衛問題研究家。日本大学芸術学部を卒業後、アナウンサーやディレクターとしてテレビ業界で活躍。一貫して自衛隊関連の取材を続けている。著書に『危機迫る日本の防衛産業』『誰も語らなかったニッポンの防衛産業』など。