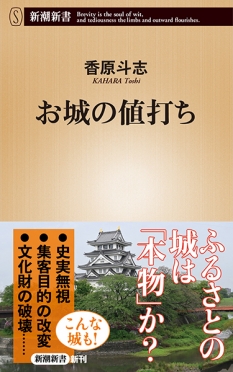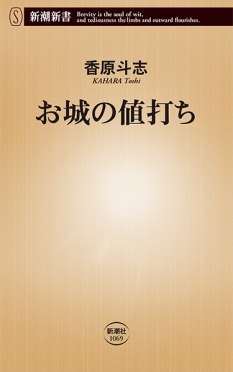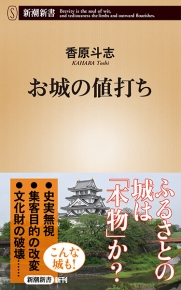
お城の値打ち
990円(税込)
発売日:2024/12/18
- 新書
- 電子書籍あり
ふるさとの城は「本物」か? 【こんな城も!】●史実無視 ●集客目的の改変 ●文化財の破壊……。
「本物の城」は12しかない!? 近年の「城ブーム」のおかげで、全国各地で名所・史跡として人気を集める城の数々。だが、中には史実とはおよそ異なる姿がまかり通っている例もある。そもそも、かつて数万あったという日本の城郭はなぜ激減してしまったのか。「現存天守」「復元天守」「復興天守」「模擬天守」の違いとは――文化財、史跡としての城の値打ちと、その歴史と未来を問う。
はじめに
社会をあぶり出す鏡/「城郭用語」について
第一章 なぜ多数の城が消えたのか
一 太平洋戦争による甚大な被害
近世城郭と天守について/数百棟の天守が十二棟に/失われた七棟/標的になった大城郭
二 築城ラッシュと幕府の規制
慶長の築城ラッシュ/城の九割以上が消えた/焼失した天守
三 城の価値を否定した明治政府
藩の財政難と戊辰戦争/価値は軍用財産として/二束三文での払い下げ/粗雑にあつかわれた「存城」
第二章 生き残った城たち
一 城の消滅を惜しむ声
保存意識の芽生え/姫路城を救った偶然の連鎖
二 民間の有志と篤志家の存在
博覧会が守った松本城/松江城天守百万円也/旧藩士の悲願――明石城三重櫓/搬出しにくかった備中松山城
第三章 天守再建ブームの光と影
一 戦争で失われた天守再建の実態
戦後復興のシンボル/先陣は原爆で倒壊した広島城/窓を大きく、豪華にした大垣城/石垣を崩して出入口を新設――岡山城
二 町おこしと天守復興ラッシュ
熊本城と会津若松城は優秀だが/行政が台無しにした小田原城/観光のための愚行/史実無視の岸和田城や浜松城/最大の個性を否定した今治城/史実と異なる「大阪城」の事情
三 天守がなかった城に建った天守たち
存在しなかった天守がシンボルに/ふるさと創生基金とエセ天守
第四章 平成、令和の復元事情
一 平成にはじまった天守の木造復元
木造復元ブームの火つけ役――白河小峰城/幕末にはなかった掛川城天守/建築基準法をクリアした白石城/最大の木造復元――大洲城/美観の再現――新発田城
二 改善される鉄筋コンクリート造天守
より史実に近い内外観に/戦前の姿に近づいてきた例
三 名古屋城と江戸城の問題点
名古屋城天守とバリアフリー/名古屋城天守の価値/天守建築の最高傑作――江戸城/江戸城復元が困難な理由/なんのための復元か
第五章 日本の城が進むべき道
一 広範囲にわたる復元への流れ
盛んな御殿、櫓、門の復元/金沢城の復元手法/熊本城と巨大地震/百年先への視野
二 城と周辺の環境との関係
赤穂城整備の限界/海が遠ざかった海城/日本に欠けている視点
おわりに
主要参考文献
書誌情報
| 読み仮名 | オシロノネウチ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-611069-6 |
| C-CODE | 0220 |
| 整理番号 | 1069 |
| ジャンル | 歴史読み物、歴史・地理・旅行記 |
| 定価 | 990円 |
| 電子書籍 価格 | 990円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2024/12/18 |
インタビュー/対談/エッセイ
城は奥行きが深い鏡
明治維新を迎えたとき、全国に70棟程度の天守が建っていた。その後多くが失われ、12しか現存していないが、いま日本中の天守を数えると、70どころか90にも達するようだ。その多くは鉄筋コンクリート造だが、外観だけでも正確に復元されているなら、それをとおして往時の景観を偲ぶことができる。だが、そうはなっていない。
可能なかぎり史実に近づける努力が重ねられたものもあるが、大半は「模擬天守」と呼ばれ、史実を反映していない。かつての姿と異なるだけでなく、天守が建った記録がない城に建つ天守もある。その場合、城を訪れた人は歴史散歩をしているつもりで、歴史への誤解を膨らませてしまう。
なぜこんなことになったか。それは城という存在の政治的、文化的立ち位置と関係している。
元来が軍事施設である城は、織田信長が安土城を築いて以降、権力と権威の拠り所となり、権力者が最先端の技術を導入して文化を発信する場になった。ところが、明治政府は城を旧体制の遺物とみなして価値を認めず、保存するという発想をもたなかった。このため明治初期に、大半の城は破壊された。軍用に供する城はそれなりに残されたが、陸軍が使いやすいように改変された挙句、太平洋戦争の空襲の標的となった。
だが、政府はどうであれ、城は住民にとっては地域のシンボルだったから、戦後復興の過程で、各地に雨後の筍よろしく天守が出現することとなった。なかには復元の水準に高得点をあたえられるものもあるが、悪影響を考えると0点どころか、マイナスの点数をつけるほかないものもある。
空前の城ブームといわれる昨今だが、よほどの城好きでないと、真贋を見極めるのは難しかろう。そう思ったことが本書の執筆につながった。
ただし、元号が平成になるころから状況は変わり、各地で温度差こそあれ、史実に忠実な整備が基本になってきた。天守という「点」に終わらず、城域という「面」で整備する動きも盛んである。それはうれしいことだが、景観や建物の高さなどの規制がない周囲との齟齬が生じている場合も少なくない。城の整備が進むほど、広域にわたる歴史的景観への問題意識も台頭せざるをえない。
このように城は歴史だけでなく、歴史にどう向き合ってきたのか、今日どう向き合っているか、という日本人の歴史意識の歩みと現状から、歴史的環境にとどまらず広く都市全体の整備のあり方まで、多くを映し出す奥行きが深い鏡である。
入口は天守でいい。この天守はどんな経緯で建ったのか、史実を反映しているのか、どの部分がどういう理由で史実と異なっているのか。そんなことを意識し、頭の片隅に入れてから城と向き合うと、良くも悪くも風景が異なって見えてくる。本書はそのための一助になりたいのである。
(かはら・とし 歴史評論家)
蘊蓄倉庫
日本に城は3万あった!
日本に存在した城の総数は3万を数えるそうです。一説には4万から5万もの城があったとも。大半は空堀を掘って掘り出した土で土塁を構築するなどした「土の城」。われわれが「城」と聞いて思い浮かべる天守を備えたものは、織田信長が建てた安土城(安土城の場合は「天主」と呼ぶそうですが)以降、近世に急速に広まったそうで、全体の割合で言えば数%程度。それでも、天守のない城を含めて3000程度の城が安土桃山時代までは残っていたそうですが、江戸期に入って幕府の「一国一城令」でその数は激減、幕末に残っていた天守のある城は全国に70数棟だったと考えられています。さて、現在の日本に残る天守はそこからさらに数を減らし、たったの12。ではいかなる成り行きでここまで減ってしまったのか……それはぜひ本書をお読みください。
掲載:2024年12月25日
担当編集者のひとこと
日本に「本物の城」が12しかないって?!
きっかけはプレジデント・オンラインの「日本に『本物の城』は12しかない……城めぐりを楽しむ人たちに伝えたい姫路城と小田原城の決定的違い」(https://president.jp/articles/-/62060)という記事でした。
城巡りは好きでも、詳しくはない私は「え? そうなの?」という事実の連続で、同じように思った人も多かったのでしょう、その記事は同誌の「2022下半期BEST5」にも選ばれました。それと同時に私は、音楽評論家としても知られている香原斗志さんがお城についても新書一冊書ける知識と経験をお持ちの方だなと気づかされたのでした。
そうして出来上がったのが本書、『お城の値打ち』です。
なぜ「本物の城」が12しか残っていないのか? どうして史実と異なる城がまかり通っているのか? 「現存天守」「復元天守」「復興天守」「模擬天守」の違いとは?
文化財としての城のあり方を問う、香原さんの「城愛」が詰まった一冊です。ぜひご一読ください。
2024/12/25
著者プロフィール
香原斗志
カハラ・トシ
神奈川県横浜市出身。歴史評論家、音楽評論家。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本古代史から近世史まで、幅広く執筆活動を行う。音楽評論家としてはオペラを中心にクラシック音楽全般について評論活動を続ける。主な著書に『教養としての日本の城』など。