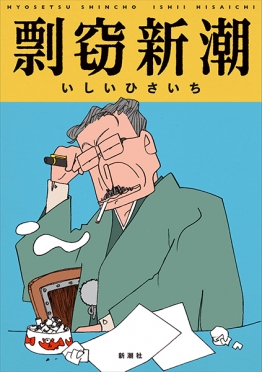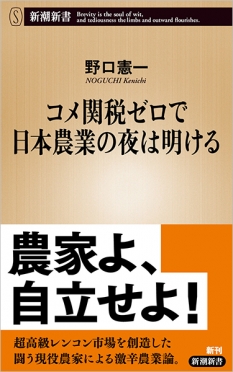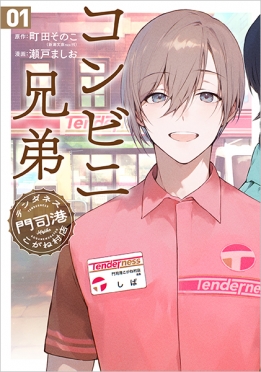お知らせ
作家・漫画家7名が書籍スキャン事業者を提訴へ
12月20日、7名の作家・漫画家が、書籍スキャン事業者2社に対して行為差止めを求める訴えを東京地方裁判所に提起されました。
詳細は以下のプレスリリースをご覧ください。
【プレスリリース】書籍スキャン事業者への提訴のご報告
2011年12月20日
本日、下記のスキャン事業者2社に対して行為差止めを求める訴えを東京地方裁判所に提起しましたので、ご報告いたします。
1.訴えの概要
原告:浅田次郎/大沢在昌/永井豪/林真理子/東野圭吾/弘兼憲史/武論尊
(五十音順)
被告:有限会社愛宕(神奈川県川崎市幸区所在) 事業名「スキャンボックス」
スキャン×BANK株式会社(東京都新宿区所在)事業名「スキャン×BANK」
請求の趣旨(要旨)
被告は、第三者から委託を受けて別紙作品目録記載の作品が印刷された書籍を電子的方法により複製してはならない。
(損害賠償の請求は行っていません。)
法的根拠:
被告各社は、不特定多数の利用者から注文を受け、不特定多数の書籍をスキャンして電子ファイルを作成し、利用者に納品する事業を行っているものです。このような行為をその書籍の著作権者の許諾なく行うことは、著作権法21条の複製権侵害です。
本年9月、原告らは、スキャン事業者に宛て、自己の作品の書籍をスキャンして電子ファイルを作成することを許諾しない旨を明確に伝えるとともに質問書を送りましたが、被告各社は、「今後も引き続き、原告らの作品について注文があった場合は、スキャン及び電子ファイル化を行う」旨を回答しております。
従って、被告各社は、今後も、原告らの著作権を侵害するおそれがあるので、著作権法112条1項に基づいて、その差止めの請求をしたものです。
(なお、ユーザー自身が個人的な目的で書籍をスキャンする、いわゆる「自炊」は、著作権法上の「私的複製」として認められていますが(著作権法30条1項)、業者が(まして大規模に)ユーザーの発注を募ってスキャンをおこなう事業は私的複製には到底該当せず、複製権の侵害となります。)
2.本件の経緯
スキャン事業者は、昨年初頭には数社にすぎなかったものが、本年9月には約100社になるほど、爆発的に増加しました。現状の同事業には、後記のような数々の問題があり、これに強い危惧をもった作家122名及び出版社7社は、連名で、本年9月5日、事業者に対してスキャン(複製)を許諾しない旨を明確に通知するとともに、今後、差出人作家の作品をスキャン事業の対象にするかどうか等の質問を致しました。
質問の結果、事業者の多くからは「差出人作家の作品について、今後スキャン事業を行わない」との回答がなされ、あるいはその後事業停止などが確認されましたが、被告2社を含む一部事業者は、なお対象作品のスキャン継続の姿勢を示しています。
3.スキャン事業による権利侵害の重大性
スキャン事業者により大量に作成される電子ファイルは通常、複製防止処置等(いわゆるDRM)が施されておらず、誰もが自由に複製することが可能です。そのため、電子ファイルは、友人らに転々と複製され拡散されたり、違法なインターネット上へのアップロードやファイル交換ソフト等により一気に拡散する危険性があります。海賊版被害が深刻化する中、このようなファイルが、本来の私的複製では到底困難な規模で不特定多数の依頼者に提供される事態を、著作権者は到底看過できません。(なお、スキャン事業者は、スキャン依頼者の電子ファイルの現実の用途を確認する実効的な措置を何らとっていません。)
電子書籍市場はまさに成長途上にあります。原告らの作品も、その承諾の下に、既刊本も含めて多くが電子書籍として販売されており、また、今後、さらに多くの作品が電子書籍化されることが想定されております。電子書籍のラインナップが急速に充実しつつある現在、書籍の電子ファイルが無許諾の事業者によりこのように無秩序に、そして大量に作成されることは、電子書籍の市場の形成を大きく阻害しかねません。
現在、インターネット上で裁断本を買取・販売している事業者が多く存在し、またYahoo!オークションで「裁断済」等のキーワードで検索すると同時期に1338件もの出品があるなど(1件で数十冊なども多数)、裁断本が広く転々流通している状況があります。流通の用途はスキャンの繰り返し以外には考えづらく、現実に、裁断本をまとめて落札し、短期間で再度オークションに出品する例も確認されています。現状は、「1冊の本が1つの電子ファイルに変わっただけ」とは到底いえません。
スキャン事業には、1年ほどの短期間で膨大な数の事業者が参入するに至りました。作品を生み出した関係者のあずかり知らないところで、創意と工夫の結実である書籍等のスキャンにより相当額の収益を上げていると考えられます。このまま事態を放置すれば、無秩序な事業者の参入が進み、作家・出版社が書籍の収益から更なる新たな創作をおこなっていくという「創造のサイクル」が大きく害されてしまいます。速やかな対応が必要な状況にあると考えられたところです。
このような経緯から、法的に現行のスキャン事業が著作権侵害にあたるものであることを裁判を通じて明らかにする必要があると考え、まずは特に悪質と考えられた2業者について訴えを提起するに至ったものです。本訴を通じて、あるべき電子書籍の流通とルールの姿について、議論と理解が進むことを願っています。
以上