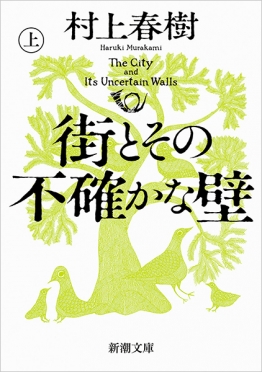橋の上の人はまばらで、夜の光が目を冷やした。
鴨川の水の黒い上に、車の光が次々さしこみ、目の前を通る車なのに、遠い祇園あたりから飛んでくる光とも見える。疲労に沈んだ顔の人びとにまじって、一井(いちい)の影も水にとけた。
橋の下から、帽子をかぶった女が、河原に出てきた。ぬかるみに足をとられながら、泥を跳ねあげて、歩いていた。一井は欄干に体を預けて、おおい、と呼んだ。女は答えず、北へ向かって歩いていった。
一井は衿を立て、首もとを覆った。
橋を抜けた先、往来をぬって、鞘町通の路地裏では、黒い夜空が淡く黄ばみ、街灯の光に浸かっていた。はよ、雪でも降らんか、と思いながら、彼はアパートの四階までのぼった。
台所に入ると、炊飯器から立つ蒸気が、壁を伝って天井までのぼっている。一井はジャケットのままで、うしろから扶実(ふみ)に触った。扶実はあっ、といって、しゃもじを持つ指に米粒がついた。湯気の中でも、白い頬だった。
机の上の一升瓶を示し、
「ほんまにこれはうまいですよ、って、ゆうてはったわ。」
一井が、買うてきて、と朝に頼んでいた銘柄だった。
扶実が鍋のふたを取ると、さっと味噌の香りが立った。つやつやした葱や人参の合い間に、鮭の切り身があざやかである。
ガラスの猪口に酒を注ぎながら、澄明な液を少し揺らすと、吟醸らしい香りが立った。舌の上に転がしていると、酸味と旨味がとけあってきた。
扶実はくっと飲み、目をつぶって、息をついた。目を閉じていると、髪の流れに囲まれた顔全体は、白く、硬く、まるでつくりものに見えた。目を開けて、一井と目が合うと、もやもやとぼかした眉をそらせ、
「どうしたん。」
一井はうなずいた。
「ええもんやな。」
「さっきまで忘れとって、こんな時間、酒屋さん行ってもあかんかと思うたけど、行ってみたら、今閉めよう思ってましたって、入れてくれて。これでよかったな。」
一井は椀を両手でつつみ、相当熱いのを吹いて、冷ましながら飲んだ。
「こんど、飛竜頭入れて。」
扶実は笑って、
「好きやな、吉貴(よしき)。」
そのまま、立ってゆき、これね、と、彼に封筒を渡した。一井はびっくりした。
「えらいたくさんやなあ。」
「豊作で、人手足りんかったくらい。」
扶実の実家は、福知山の近くの農家である。生活の足しに、と、毎月送ってくる。
一井がしまおうとすると、ちゃんと見て、といって聞かない。彼はざっと見て、机に投げた。
「行ったほうがいいかな。」
扶実は答えず、食器をかたづけはじめた。
「まだ、ええよ。」
食器を盆にのせて、立ちあがった扶実の喉もとのくぼみに、斑な色合いがいざなわれ、なだらかに沈んだ。
週明け、新しく積み上がっている書類を消化しながら、一井は充実感を得た。
病院の建物は、気温の変化を忠実になぞって、昼休みになるとちょうどいい頃合にぬくくなった。机の横は、カーテンの隙間からさしいった西日が弱々しく、ほの明るい。
同僚の、八木の机のそばを通ると、彼はめがねをみがいていた。一井を見あげ、
「もう、老眼ですよ。」
待合を通りかかると、水色のソファに体をもたせた人々が、うっとりと魅入られたように、目を閉じている。
ふとった看護師が、杖をついた老婆を抱きかかえて、
「オオノさん。わかりました。こんどから、女の先生に、診てもらおうな。」
場ちがいなくらい、溌剌と声をはりあげる。
女の先生な?、と、くりかえす相手に、そう、女の、やさしい先生、とってもやさしい、女の先生、水曜日に来られるさかい、ほんでええやろ、と、ひとくちひとくち、いって聞かせていた。
玄関の外で、リュックを背負ってうろうろしていた男が、一井を見つめて、聞いた。
「すいません。第五、第五病棟、どこですか。」
一井は先に立って、案内した。病棟の前まで行って、別れようとすると、男は、すいません、四一六です、すいません、とくりかえし、一井に身ぶりで、いっしょに来て、と頼んだ。病棟は、昼どきの食べものの臭いが、むっと立ちこめている。
西向きの二人部屋は、手前のベッドのカーテンが開けはなしになっていた。男の医師が、中学生くらいの少年の足もとにひざまずき、採血している。少年は血色の悪い顔で、針を見ていた。
窓ぎわの布団の上に、老人の短く刈りあげた頭が見えた。枕に首をもたせかけ、窓を向いている。
男が離れているので、一井が、佐古田さん、面会ですよ、と呼びながら、ベッドをまわっていくと、丸い目に会った。目と口のまわりの黄ばんだ皮膚に、細かいしわがどっと折りこまれた。息だけの声が出た。
「行かんと、あかん。」
すかさず、見舞いの男が答えた。
「いいんやで、気にせんで。」
男に場所をゆずり、病室を出ると、一井はひき戻される気がした。老人の、今のいいぶりには、確固とした形があった。あんな老人、どこ行くとこあるんか、と思いながら、一井は病院の中庭を歩いた。光の中で、若い楓の紅葉の輝きをまぶたに吸わせていると、行かんとあかん、とは、自分の母のよくいってたことだと気づいた。
もう死んで五年になり、墓も長く行っていなかった。
母の病気がわかったとき、彼は高校生だった。母は、一年くらいは教会に通ったりして、ふつうに暮らしていたが、さいごの二ヶ月は、病院で過ごしていた。
母は、外の景色もあまり見なかった。気にすることといえば、主日の礼拝やのに、こんなとこでぼけっとして、と、それが苦痛らしかった。彼が日曜に見舞いに行くと、行かんとあかんのに、と繰り言がつづいた。
年末に、一井と姉と父とで見舞いに行くと、また、行かんとあかん、と口にした。すると、父がいきなり通帳を取りだした。
「なんや、この二十万。」
母は、ふつりと目を閉じた。
父はにがにがしく笑い、カーテンをひいて出た。一井がついていくと、父は彼を見て、
「ありゃ、貢いどるんや。」
あほやった、と父はくりかえした。貢いどったんや、とくりかえしながら、どんどん現実離れした想像へ傾いてゆくようだった。
一井が病室に戻ると、母は枕元に置いた聖書を指して、第二コリントの四章、といった。子どもの前で聖書のことを口にしたのは、あとにも先にも、そのときだけだった。
一井が読みだすと、母は首をふった。一井は、懐疑的な気分が、はっきりと声にでていた。そこで、代わって一井の姉が数節読んだ。
「たとえわたしたちの『外なる人』は衰えていくとしても、わたしたちの『内なる人』は日々新たにされていきます。……わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。」
五年たった今も、自分が一度聞いた聖句を覚えてることに、一井は驚いた。
病院を出ると、日が落ちた。彼は、川の方へ向かった。母が通っていたカトリック教会は、病院からまっすぐ東に歩いて、川の手前だった。鞘町通のうちからはおおよそ北に当たった。優美な曲線の屋根で、ガラス扉越しに、青いステンドグラスが見えた。
一井が扉の前で立っていると、事務員が出てきた。
「神父さん、今日はご用事で、ミサ終わって、出はりました。お伝えしとけることなら、お伺いしますけど。」
一井は、いいです、といって帰った。
玄関に宅配の箱が置いてあった。箱を開けると、新聞紙を敷いて、大ぶりの柿をならべた上に、一筆箋がはさんであった。忙しいと思うけど、いつでも顔見せに来てください、と、扶実の母親の字である。
(続きは本誌でお楽しみください。)