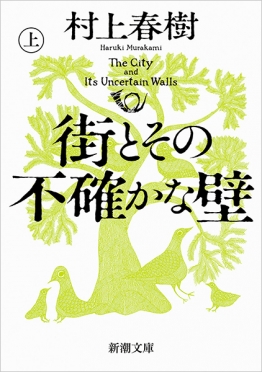第一章
獣は、そそり立つ岩の向う側にゐた。獲物を狙ふ跳躍に備へて、全身に力を漲らせ、真黒な剛毛を逆立てて蹲まつてゐる。雨蝕によつて作られた峡谷を貫く急流に裾を洗はれる岩。高さは二階建の家ほどもあらうか。天辺が横一直線に削がれたやうに平らであつた。私が育つた村の外れを流れる河が淵を成したあたりにも、同じやうな形の巨岩があつて、徴兵前の若者たちは、天辺から淵に飛び込む度胸を競つたが、臆病な私は、たうとうその仲間に入れなかつた。
私が迫撃砲弾の破片に右膝をやられて、同年兵二人に担がれ、この岩蔭に横たへられたのが十八時半。既に薄暮であつた。トラックで迎へに来てやるぞ。私の身体と平行に小銃を置き、煙草を二本差し出して、桜井が言つた。のんびり眠つて待つとればいい。私は頷いて笑はうとしたが、顔の神経は動かなかつた。八路軍の兵士に発見されたら、小銃なんぞ物の役には立たず、たやすく捕虜になるだらう。分隊長が近付いて来た。彼は身を起さうとした私を制し、ご苦労、と一と言だけ言つて立ち去つた。これが永の別れか、とぎごちなく挙手の礼をしながら、私は思つた。殆ど間を置かずに、出発、の号令が、離れた場所で聞えた。不意に襲つて来た恐怖に、私は震へた。
東南に十粁離れた村に、八路の小隊が入り込んでゐる、と密偵の通報を受けて、私たちは未明に駐屯地から出撃した。総勢十八名、敵の不意を討つ払暁攻撃は、討伐の常道である。八路軍の諜報網はよく整備されてゐて、攻撃は不発に終る場合が多いのを中隊の全員が知つてゐたが、命令に従はないわけには行かない。
危ぶんだ通り、村は藻抜けの殻であつた。敵兵ばかりか、住民さへすべて姿を消してゐた。私は型通り、三十戸余りの村の捜索を行なつたが、ろくな戦利品は得られず、徒らに疲労が募つた。あいつ等、鶏まで持つて逃げやがつた。土間に鶏の羽根が散乱してゐるのを見て、桜井がいまいましさうに言つた。
敵と接触出来なければ、長く留まるのは危険である。敵兵は逃げ散つたのではなく、村を遠巻きにして、私たちの行動を見張つてゐる可能性があつた。無人の村は鎮まり返つて、その静けさが却つて、遠くから放たれる視線の矢を感じさせた。ほんの一刻の小休止をしただけで、私たちは引揚げにかかつた。帰途の隊列はだれてゐた。徒労感と睡気が兵を苦しめた。行軍中は厳禁の私語が、あちこちで高くなつた。起伏のある荒地が連なる周辺の光景が、夢の中に融け入りさうになる。小銃が重みを増し、こいつを抛り投げたらどんなに気持がいいだらう、と妄想に捉はれる。
荒野の道がだらだらと下りを続けたあげくに尽き、峡谷の入口にさしかかつた所で撃たれた。対岸から撃ち出す小銃弾が、隊列の行く手のごろた石の重なりに当つて弾けた。散開、伏せ、の号令とほぼ同時に、敵は一斉に急射を浴せて来た。私たちも撃ち返した。敵影は見えない。弾が飛んで来たとおぼしいあたりに向けて、闇雲に撃つた。
撃ち合ひは、およそ三十分で熄んだ。また八路のお祭射撃かいや、と同年兵の田丸が呟いた。遠距離から戦を挑み、応戦する日本軍が優勢と見れば深入りをせずに避退し、劣勢と判断すれば嵩にかかつて攻め立てるのが、遊撃戦に長けた八路軍の常套手段なのであつた。しばらく対岸に動く気配がないのを確かめて、私たちは行軍を再開した。小銃に凭れて眠りかける二等兵の腰を、田丸は蹴飛ばした。
その時、空気を切り裂いて爆発が起つた。迫撃砲、と叫ぶ誰かの声とともに、私は膝に衝撃を受け、打ち倒された。頭を石に打つけて、意識を失つた。
私の背中を抱へて、起さうとする手があつた。大丈夫か、立てるか、と耳許で叫ぶ桜井の声がした。大丈夫、と反射的に答へて、私は立たうとした。立たなければ置き去りにされる、と思つた。しかし、動かさうとした右膝を刺す痛みに呻いて、再び地面に転がつた。いかんな、と口の中で言つて、桜井が立ち去る気配があつた。桜井、と呼んだが声にならなかつた。八路兵の遺棄死体が眼に泛んだ。ゴム人形のやうに膨れ上つて、眼を開き、口も一杯に開いて、泥まみれで死んでゐた。あの眼に映る景色があつたか、あの口は最後に何を叫んだか。
私は見棄てられなかつた。さう長くない時間ののちに、また桜井が私の傍に跼んだ。何だ、泣いてやがら、この莫迦野郎。堅くざらついた掌が、私の頬を拭つた。無意識に涙を流してゐたらしかつた。それを恥と思ふ感覚は、私にはなかつた。
傷ついた膝に、桜井が脱いで呉れたシャツを当てがひ、巻脚絆で厳重に縛り上げた。桜井と、もう一人、分隊中で最も膂力のある川島一等兵の肩に縋つて、私は歩かうとしたが、疼き、血の滲み出る脚は動かず、二人に引き摺られる形になつて、私はたちまち隊列から遅れた。三十分と行かぬうちに、田丸が前方から駈け戻つて来た。こんな調子ぢや八路を歓ばせるばかりだ、と顔を引攣らせて、彼は呶鳴つた。そして桜井を道の端に連れて行き、二た言三言、何か囁いた。桜井は頷いた。分隊長も同意だ、と田丸は大きな声を出した。私に聞かせるつもりだつたらう。田丸は私に見向きもせずに走り去り、桜井がゆつくりと私に近付いた。お前をこの谷間の、と言つて彼は少し間を置いた。どこか安全さうな所へ残して行く、安心しろ、置き去りぢやない、四時間か、せいぜい五時間の辛抱だ、必ず救援に来てやる、いいな。厭だなんて言つたら銃殺だな。私は、川島の汗みどろの顔をみつめた。お前だつて、早く引揚げて眠りたいだらう。川島は顔を背けた。私は、とんでもなくあさましい口を利いてしまつたのを悔いたが、間に合はなかつた。
そろそろ日が暮れる、と桜井が、峡谷の向うの、巨大な親指を天に向つて突き出したやうな形の山を見上げた。先刻までその頂上を赤く彩つてゐた西日が、もう翳つてゐた。暮れちまへばどこも安全だ、暗闇をうろつく八路なんてあるわけがねえ。八路は夜襲もお手のものだぞ、と私は秘かに思つた。
川島が私に背を向けて跼み、桜井が私を抱き上げてその背に凭せかけた。川島の軍袴はたちまち私の血に汚れた。済まん、と小さい声で私は言つた。平気であります、と川島が応じた。私は、彼が感情を露はにしないのに、理不尽にも苛立つた。
いつもと変らない、出発の号令とともに分隊はゐなくなつた。その場から蒸発したやうに、跫音を立てずに。空の明るみが褪せ、星が輝き始めた。何度も何度も見た夜空の光景。私はほつと息を吐いた。今は月が昇る季節でない事は知つてゐた。
傷が底深く疼き、丸太ん棒のやうに投げ出された身体が痛んだ。川島が自分の襦袢を丸め、枕代りに首筋の下に突込んで呉れたのが唯一の救ひであつた。汗に湿つた襦袢は、蒸れた枯草に似た臭ひがした。あいつには確か男の子が一人ゐたな、と私は思つた。
頭の位置からほんの十数米離れて、丈の低い柳が二本あつた。私は眼を挙げて、その勢ひなく垂れ下つた葉が、少しづつ闇に溶け入つて、影に変るのをみつめた。あと十時間の辛抱。桜井が言つたほど早く、救援が来る筈はなかつた。十時間の辛抱。さいはひ、風はなかつた。若し夜半に風が吹けば、私の身体はたちまち黄砂に埋もれるだらう。真夏の討伐行の途次、山の中腹の平地に露営した。月が明るく、微かに風が吹き抜けた。眠りこける私の胸のあたりに、重たく触れて来るものがあつた。隣に眠る兵の、半袖の上衣から突き出た毛むくぢやらの腕。私は邪慳に押し返した。私よりかなり年上とおぼしいその兵は、眼を無理に開いてまじまじと私に見入り、やがてにつと笑つた。そしてまるで息を引取るときのやうに顎を落し、また眠つた。甘つたれんぢやねえよ、仕合せな夢なんか見やがつて、と私は秘かに毒づいて、その男の夢の中身を、ざらついた思ひで想像した。
山中露営の夜ばかりではない。占拠した民家の南京虫が群がる土間でも、終夜狼の遠吠えを聞く駐屯地の藁蒲団の中でも、眠りはとりどりの夢に彩られた。その夢を翌日、得々として喋り立てる者があつた。それを煩ささうに顔を背ける者があつた。私はいつも口を鎖ざしてゐたが、夢の残像は記憶に貼り付いて、暮れてもなほ続く行軍のさなか、或いは疲れ果てたあげくの眠りの入り際に、しばしば隈取り鮮やかに蘇つた。
(続きは本誌でお楽しみください。)