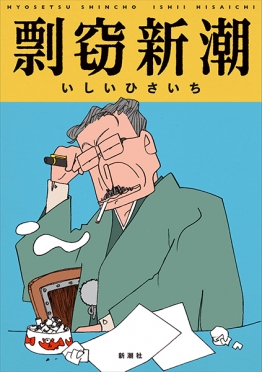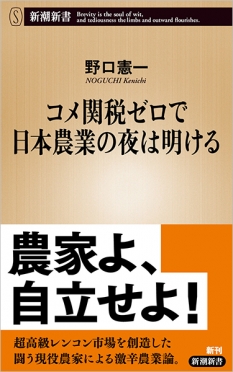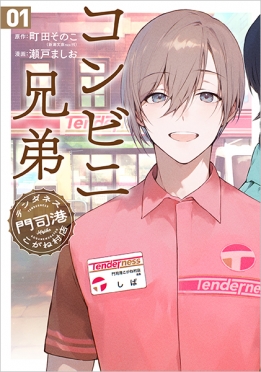序章
けれどどんなことをしても
私の波立つ血が私を離れて
あの陸地、
と呼ぶ所にあがることは出来なかつた。
太陽にあたためられる表皮
つかの間の体温
内部にひろがる暗い部分は
冷えた祖先の血の深み。
もういわない、
私が何であるか
食卓でかみ砕いたのは岩
町で語りかけたのは砂
森で抱きしめたのは風
それだけ。
(「海のながめ」より)
石垣りんはひとりで生き、老いた。
一九二〇(大正九)年に東京・赤坂で薪炭を商う家に生まれ、高等小学校を出た一四歳から定年まで、丸の内の日本興業銀行で働いた。
制服のある職場に通い、家族のいる家に帰って眠る。だが生涯、どこにも、誰にも、所属しなかった。職場も家も、彼女の居場所ではなかった。
りんは四人の母を持った。父が四度結婚したからだ。
四歳で実母と死別し、後妻として家に来た母の妹も病死した。三人目の母は父との間に三人の子を生したが離婚。それから一年たたないうちに、父は四人目の妻を迎えた。すでに銀行で働いていた一七歳のりんは、そのひとの写真を見せられ、思わず「そんなに欲しいの?」と口にする。父は顔色を変えて怒った。
太平洋戦争開戦のとき二一歳。終戦の年の五月、空襲で生家が全財産を失い、失意の父はやがて病を得る。一家の稼ぎ手はりんだけになった。
戦後は品川の路地裏にある一〇坪ほどの家に、祖父、父、義母、同母弟、異母弟と六人で住んだ。五〇歳でひとり暮らしを始めるまで、彼女の生活の場は、二間しかないこの借家だった。
りんの詩には、家と家族が繰り返し登場する。
家にひとつのちいさなきんかくし
その下に匂うものよ
父と義母があんまり仲が良いので
鼻をつまみたくなるのだ
きたなさが身に沁みるのだ
(「きんかくし」より)
血の熱量に耐えられますように
と両手のなかで祈るうち。
私の胴体からは
タコみたいな足が生えて
四本も五本も生えて
八本にもなつて。
さあこれでどうやら支えられると安堵したら
その足を食べにくる
見たような顔をした不思議な人間。
あなたは?
と聞けば
親だという
誰々だという
忘れたの?
という。
(「生えてくる」より)
りんは自分の家族をつくらなかった。生まれた家のメンバーが、生涯で持った家族のすべてだった。
「ずっと続いてきた血の流れが、最後に私のところで乾こうとしているけど、そこまで行かなきゃならないんです」(六三歳のときの言葉)
捨てても捨てても捨てきれない、肉親という名の他者。血の絆は軛にほかならず、外そうともがくほどに息ができなくなる。
自分で選んだわけではない家族という関係性を、りんは何とか生き切ろうとした。そのためには書くことが必要で、だから自分の体を裏返して内臓をさらすようにして、家と家族をうたいつづけた。
(続きは本誌でお楽しみください。)