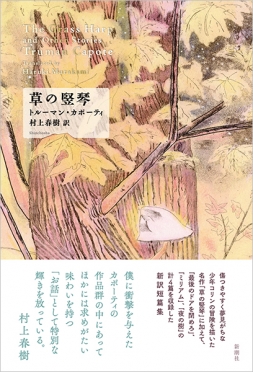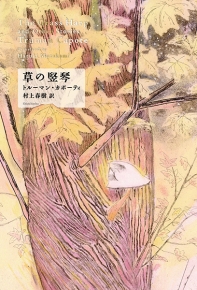
草の竪琴
2,695円(税込)
発売日:2025/06/26
- 書籍
- 電子書籍あり
少年のイノセンスを瑞々しく描いたカポーティの名作を、村上春樹が新訳。
1940年代アラバマ州の田舎町。母を亡くした少年コリンは遠縁にあたるドリーとヴェリーナの老姉妹に引き取られる。ドリーは妹との諍いを機に、コリンとメイドのキャサリンを連れてツリー・ハウスで暮らし始めるのだが……。初期の名作「草の竪琴」のほか、「最後のドアを閉めろ」「ミリアム」「夜の樹」の短篇3作を収録。
草の竪琴
最後のドアを閉めろ
ミリアム
夜の樹
訳者あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | クサノタテゴト |
|---|---|
| 装幀 | 山本容子/装画、新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 272ページ |
| ISBN | 978-4-10-501410-0 |
| C-CODE | 0097 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 2,695円 |
| 電子書籍 価格 | 2,695円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/06/26 |
書評
もうすでに失われてしまったものの儚さ
新訳で読み返してみて、こんなに直喩が多いのかと面食らった。もちろん比喩表現は初期カポーティの代名詞で、そのイメージを持って読み始めたのだけれど、「~のような/~のように」と訳出できるところがこんなに多いのはやっぱり異常だし、真似のできない芸当である。
第一章、語り手の「ぼく」(コリン)が「恋に落ちた」と宣言するドリー・タルボが登場してから五ページ、回想や会話から目立つところを抜き出してみる。「慎ましやかな女羊歯の花弁のようにひっそり身をすぼめた」、「自分を部屋の備品のひとつみたいに、隅っこの影みたいに見せかけることのできる人」、「二人の声の細かい震えが、まるで古い樹木からシロップが浸み出すみたいに聞こえてきて」、「幼い女の子が一人で遊びながら口ずさむような愛らしい響き」、「雪ひらのように崩れやすい顔」、「声はまるで薄葉紙のように薄くさらさらとしていた」、「きらきらと輝く澄んだ目、ミントゼリーのように艶やかな緑色だ」
散らばっているとはいえ、これだけ沢山あったら普通は胃もたれしかねない(しかもこれが全てではない)。比喩まみれというのは悪文の一典型で、クリームがべったり塗られていたり粉砂糖が山を作っていたり、自然にあるべき以上に添加されたものが過剰に主張してくるみたいでよろしくないという人もいる。その真偽はどうあれ、比喩とくに直喩がイメージを添加し、そこにないものでそこを彩るのは確かだ。あなたがまだこの小説を読んだことがないなら、先ほど挙げた比喩が全て、母親を亡くしたコリンが共に暮らすことになった遠縁の親類(ドリー)とそのメイド(キャサリン)という六十代の女性二人に対して付されたイメージであるのを意外に思われるかも知れない。
「草の竪琴」を含む初期作品が幻想的文体であることはカポーティ本人も認めるところだ。家出と町外れのツリー・ハウスでの暮らしと事件という粗筋はそれに適うもののように聞こえるけれど、三人が家出をする理由は同居するドリーの妹ヴェリーナの実業家的な目論見を嫌がってのことだし、樹上の暮らしは暴力的な悪意が迫ってすぐに破綻し、最後には死も訪れる。俗世間の「現実」に、彼らの「幻想」はあっけなく敗北してしまうのだ。
その勝負を読者に拮抗させて見せているのが「ぼく」の幻想的な語り、とりわけ随所にバニラビーンズのように溶けずに交じる直喩だと言える。その偏りが大いに香る場面では、過去を回想するコリンが印象づけたい平穏や愛情というものが痛いほど伝わってくる。「そのあと花占いをし、眠気を誘う話をし、まるで樹上の筏に乗って午後を漂っているような気分になった。ぼくらはそこにすっかり溶け込んでいた。ちょうど陽光に銀色に輝く葉が、そこに含まれているのと同じように。ヨタカたちがそこに住み着いているのと同じように」
この場面に顕著だけれど、村上春樹による新訳は旧訳に比べて直喩の形をかなり強く打ち出している。他の言い回しを用いることもできるはずで、実際そうしているところもあるにせよ、基本的には「~のような/~のように」がまっすぐに用いられる。その繰り返しがもたらすのは、祈りの如き響きだ。そこにないものでそこを彩る直喩は、物語の流れを一瞬止め、もうすでに失われてしまったものの儚さを印象づける。コリンが息を吐くように喩えるたび、あの日々への愛着や哀悼が重ねられていく。
こういう装飾的文体を手懐けている作家は滅多にいない。「私は自分には言葉の束をつかみ、それを空に放り投げると、それがきちんとした順序できれいに並べられて落ちてくるという能力があることがずっとわかっていた」と言ってのけるカポーティならではだが、「ミリアム」が十九歳で書かれたとあっては顰蹙を買いようもない。
「能力」の方は天賦の才だったにしても、ほとんど学校に通えなかった彼は「言葉の束」を独学で得た。両親が離婚し、母親に見捨てられたも同然で親類の家に預けられ、スークという発達障害をもつ祖母ほど年の離れたいとこだけが自分を可愛がってくれた中で培った言葉だ。後年、時代の寵児として荒れた生活を送ったカポーティでも、彼女への愛着だけは生涯忘れなかったという。少年時代への祈りのような「草の竪琴」の献辞は、ドリーのモデルでもあるスークに捧げられている。
(のりしろ・ゆうすけ 小説家)
波 2025年7月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
トルーマン・カポーティ
Capote,Truman
(1924-1984)1924年ニューオーリンズ生まれ。19歳のときに執筆した「ミリアム」でO・ヘンリー賞を受賞。1948年『遠い声、遠い部屋』を刊行し、「早熟の天才」と絶賛を浴びる。著書に『夜の樹』『草の竪琴』『ティファニーで朝食を』『冷血』『叶えられた祈り』など。晩年はアルコールと薬物中毒に苦しみ、1984年に死去。
村上春樹
ムラカミ・ハルキ
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1979年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。2006(平成18)フランツ・カフカ賞、オコナー国際短編賞、2009年エルサレム賞、2011年カタルーニャ国際賞、2016年アンデルセン文学賞、2022(令和4)年チノ・デルドゥカ世界賞を受賞。