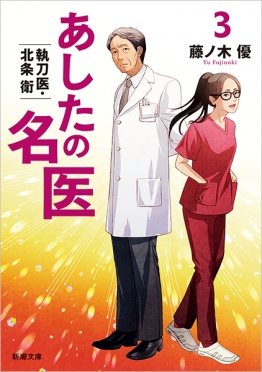12月1日の朝、私は東京ビッグサイトに向かっていた。
大きなイベントがあると交通が混雑することが多いのだが、この日のゆりかもめは空いていたし、会場にも入場待ちの列はまだなかった。
ここで開催される「文学フリマ東京39」に、新潮社の「波」編集部が初めてブースを出すことになり、それを手伝うことになったのだ。
入り口で出店者のチケットを提示すると、代わりに赤いリストバンドを渡される。それを腕に巻きながら中に入る。長机がずらりと並んでいる。
左手の壁際、「の」の列に、「波」編集部のブースがある。隣は「新潮ショップ」で文フリには三度目の出店となる彼らは、てきぱきと『百年の孤独』Tシャツなどを並べている。
一方、初参加の「波」ブースには、楠瀬啓之編集長、長谷川麻由さん、篠田菜々さんが集まり、持ってきた荷物をもたもたと広げていた。
本日のお品書きは以下のとおり。
(1)『新潮社の社員食堂 夏』六十四ページ 千五百円
(2)『あなたはまだ「波」を知らない 新潮社のリトルマガジン徹底案内!』百二十四ページ 千円
(3)南陀楼綾繁『34冊! 新潮文庫の三島由紀夫を全部読む』三十四ページ 五百円
(4)中瀬ゆかりアクリルキーホルダー 千円
(5)校閲判子マスキングテープ 七百円
(1)は雑誌や書籍、テレビ番組にも取り上げられた新潮社の社員食堂のメニュー写真や食堂スタッフのインタビューを掲載したもの。オールカラーで、気合いが入っている。
(2)は「波」創刊五十年にあわせて、私が同誌に書いた「ナミ戦記」五年分と楠瀬編集長の編集後記を収録。(3)も私の短期連載(一気読みシリーズの最初)をまとめたものだ。
(4)は新潮社の出版部担当執行役員にして、テレビやラジオにも出演する中瀬ゆかりさんの写真が麗しいアクキー。(5)は校閲部で使われてきた判子を印刷したマスキングテープ。「要再校」「大至急!」などと生々しい。
これらはすべて、今回の文フリにあわせて制作されたものだ。
他に、「波」の最新号、校閲部を描いたマンガ『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』(こいしゆうか)や新潮文庫のロングセラー『マイブック』なども並べる。
社員三人が長机に商品を並べ、POPを付けていく。開場時間が迫り、各ブースでは準備が佳境に入っている。会場の外には、もう入場待ちの行列ができているようだ。
ブースに戻り、十二時になるとアナウンスがあり、拍手とともに文フリがスタートした。
「波」ってなんですか?
文学フリマは、評論家・編集者の大塚英志さんの呼びかけにより、2002年11月にスタートした。
会場は表参道の〈青山ブックセンター本店〉で、約八十のブースが出店したという。その後、毎年秋に開催する。
私が最初に行ったのは、会場が秋葉原から〈大田区産業プラザ〉に移った2009年だったと思う。この頃には春と秋の二回開催になっている。当時は約三百ブースほどで、一時間もあればぜんぶ見て回れた。
私は1990年代の中頃から、東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット」(コミケ)を見に行くようになり、自分でも何度か出店した。
コミケというとマンガ同人誌とコスプレのイベントという印象が強いが、「評論・情報」というジャンルには、文字中心の同人誌が集まっている。私もここでエッセイをまとめたミニコミを出した。「南陀楼綾繁」という名前を初めて使った場所でもある。
文フリを最初に見たときは、「コミケの文学版」だと思った。しかし、2011年11月に会場が〈東京流通センター〉に移ってからは、さらに規模が拡大し、ジャンルの幅も広がった。以前は〈模索舎〉〈タコシェ〉などの特殊書店やネットの通販で入手していた雑誌や本のつくり手と直接やり取りできるのが新鮮だった。
文学フリマは東京以外にも、札幌、京都、大阪、福岡などでも開催されるようになり、さらに開催地は増えている。そして東京では、2024年5月には入場料が必要となり、今回から会場も東京ビッグサイトに移った。
私は出店者としては、ある出版社に間借りさせてもらった時と、本づくりのワークショップのメンバーと共同で出た時の二回だけで、毎回出店している人たちとは比べ物にならない。
それでも、いちおう経験はあるということで、「波」ブースの手伝いとして参加することになったのだ。
開場してしばらくすると、次々に客がやって来る。
展示してある見本を手に取ってじっくり眺める人もいれば、表紙を指さしてすぐ買っていく人もいる。二冊、三冊とまとめて買ってくれる人もいる。
迷っている人には、簡単に内容を説明するが、聞き流されることも多い。自分が客の立場でも説明をうるさく感じることがあるので、なかなか難しい。
「波」ブースの会計は現金以外に、クレジットカードとPayPayに対応。Suicaも使えるはずだったが、端末にかざしても反応しなかった。ただ、圧倒的に現金で払う人が多かった。
売れた冊数は正の字で記入したが、途中から追いつかなくなって諦めた。
さすがに老舗の出版社だけあって、このブースをめざして来てくれる人が多い。私の知り合いも何人も顔を見せて、買っていってくれた。
その一方で、若い人から「『波』ってなんですか?」と訊かれた。初めて見たと云う。まさに「あなたはまだ「波」を知らない」状態だ。
「出版社のPR誌のなかでは五十年以上続いているもので……」と説明すると、興味を持ってくれる。最新号は早々に売り切れ、「もっと持って来ればよかった」と編集長が悔やむ。
以前は書店で入手していたけど最近見かけないという客は、編集部から持ってきたバックナンバーを詰めた箱(二冊で百円)から、中古レコードを漁るように何冊も選んで買ってくれた。
今回の出店は、「波」という雑誌がどんなものか知ってもらう、いい機会になったと思う。
本日のお買い上げ
十三時頃、中瀬さんが会場に到着。入場待ちの行列ができていて、遅れたという。
ブースに立ち、よく通る声で「新潮社です!」と呼びかけると、遠くからわらわらと人が集まってくる。テレビ・ラジオのファンが多く、なかには「小学生の頃から家族と『5時に夢中!』観てます」という若い女性もいた。
中瀬さんが「これを買うと幸せになりますよ!」とアクリルキーホルダーを振りかざす姿は、まるで車寅次郎が啖呵売をするかのように鮮やかだった。
合計で二千円以上お買い上げの方には中瀬さんのミニ色紙が付く。何十枚か用意していたが、途中で全部なくなっていた。さすが。
強力な売り子がいるので、ブースを離れて、会場を見て回る。
前の会場に比べると広くなったのはたしかだが、列と列の間の通路はかなり狭く、ブースの前に立つ人が多いと通り抜けるのも大変だ。一方、通路が広いところもあるが、そこに出店している知り合いは「立ち寄らずに通り過ぎる人が多いんです」と嘆く。なかなか難しいものだ。
本来は、前知識を入れずに面白そうな本と出会うのが理想だが、これだけ出店者が多いとその余裕はない。事前にウェブカタログやSNSでの告知を見てメモしておいたブースを回るので精いっぱいだ。
近年、文フリで勢いがあるのが短歌や俳句のジャンルで、作者のサインを求めて行列ができるブースもある。それらも横目で通り過ぎる。
今回買ったものを順不同で挙げると、珍説奇説を満載した『UFO手帖』、全国のキリスト看板(「死後さばきにあう」など)を採集する冊子、ATG映画のパンフレットの総目次、11月に閉店した京都の古書店〈アスタルテ書房〉の写真集、雑誌の専門図書館〈大宅壮一文庫〉が発行するテーマ別のリスト、サツマイモなら何でも扱う『イモヅル』など。我ながら節操がない。
文フリには個人やグループが発行する本だけでなく、商業出版社も出店している。山形のスコップ出版、京都の灯光舎など地方の版元と出会える機会でもある。盛岡の本屋〈BOOKNERD〉は、日本在住のアメリカ人が各地の喫茶店を巡った『KISSA BY KISSA』を初売りしていた。文フリに合わせて新刊を出す出版社は、今後増えていくだろう。
一方で、何組か、これまでの常連の姿が見えなかったのは、抽選に落ちたのか、自らの意思で出店しなかったのか。
たまたまだが、新潮社に関する本も見つかった。元新潮社の編集者が設立したpalmbooksは、飴屋法水と岡田利規の往復書簡と対話を、日めくりカレンダーのような造本で出していた。また、三上於菟吉『血闘』(ヒラヤマ探偵文庫)は、大正時代に一世を風靡した作家が新潮社から出した長篇の復刻版だ。
そして、栗山真太朗『新潮新人賞の最終候補になると何が起こるか日記』は、タイトル通り、2023年の新人賞の候補になった著者のエッセイ。編集者とのやり取りが具体的に描かれていて興味深い。
ここまでで二十冊以上、二万円以上買ってしまった。それでも、リストの三分の二しか回れずに時間切れになった。
祭りの後で
「波」ブースに戻ると、「南陀楼さんに会いに何人も来ていたよ」と云われる。これはイベントあるあるで、ブースを離れる時に限って来客が多いのだ。楠瀬編集長は「オレに『南陀楼さんですよね?』って訊かれたよ」と不満そうだった。
十五時を過ぎても、人の波は途切れない。
文フリ初体験の中瀬さんは、「すごく熱気があって、ただただ圧倒されますね。文芸好きがこんなにもいるなんて、一編集者としても最高に心強い」と話す。「買ってくれた方々全員をハグしたい!」と云いながら、恒例の競馬に向かう予定をキャンセルして、終わり近くまでブースに立っていた。
そして、十七時。拍手とともに、文フリ東京39は終了した。
この日の来場者は約一万五千人。出店者を除いても約一万一千人が来場した。もちろん過去最高の動員だ。
「波」ブースの商品はいずれもよく売れたが、特に三島由紀夫本の売れ行きが良かったのは、著者として嬉しい。五百円という買いやすさがあったのか。
時間のないなかで三冊の新刊をつくったことについて、長谷川さんは「通常業務との両立が大変でした」と笑う。
終了後、SNSでは「大手出版社が文フリに出ること」に否定的な意見が目に付いた。
初期からの出店者がそう思うのは、もっともだという気がする。しかし、少なくとも「波」編集部は、ただ会社の既刊を持って来るのではなく、文フリに合わせた新刊をつくり、新参者としておずおずと参加しているのだ。
今回初めて文フリを見たという、某社の編集者は「ここに来ると出版不況というのが信じられなくなりますね」と話した。
この二十五年以上、産業としての出版業界は縮小し続けている。その一方で、文フリや出版社・書店が直接販売するイベントは盛んに行なわれている。また、独立系と呼ばれる小規模な出版社や書店も増えている。出版という行為は読者に求められているのだ。
だから、文フリはむしろ、既存の出版社がこれまでの出店者から新たなヒントを得る場なのだと思う。
楠瀬編集長は「出版社の編集者にとって、マニアックなもの、尖ったもの、小回りのきくものをつくり、読者の顔を直接見る経験はこれからますます大事になっていくと思います」と話す。
ほとんどの出店者が帰り、机や椅子が片付けられた会場には「祭りの後」の風情が漂っていた。
次回の文フリ東京は、2025年5月11日に開催。もちろん、「波」編集部はエントリー済みです。読者のみなさん、会場でお会いしましょう!
(なんだろう・あやしげ)
波 2025年1月号より