 |
ワイルド・シーン Wild Scenes

ミュージシャンの個性が、彼が生計を立てている気まぐれな世界と結びついたとき、しばしばミュージシャン仲間で「ワイルド・シーン」と称される騒ぎがもたらされることになる。
英国人のバンドリーダーであるレイ・ノーブルの依頼を受けて、グレン・ミラーがニューヨークの「レインボウ・ルーム」で演奏するバンドを編成したとき、彼は何人かのジャズ・ミュージシャンを入れた。トランペットにチャーリー・スピヴァクとピー・ウィー・アーウィン、サックスにバド・フリーマンとジョニー・ミンス、ギターにジョージ・ヴァン・エプス、ウィル・ブラッドリーとミラー自身がトロンボーン、クロード・ソーンヒルがピアノだ。
ノーブルはいくつかの曲に二通りのエンディングを用意していたが、彼はどちらのエンディングでいくのかを、しばしば言い忘れた。ジョージ・ヴァン・エプスが語る。
<レイがやってきて、我々に「甲のエンディングでいくぞ」と告げる頃には、バンドの半分はもう乙のエンディングにとりかかっていた。だからいつもいつも混乱のうちに終わることになった。ある夜のことだが、曲はもうそろそろ終わりに近づいているというのに、御大の姿はどこにもない。クロードのピアノだけはたしかだったが、レイの方は出たり入ったりで、踊っている客の中に紛れ込んで、十二小節ごとにふらっと戻ってくるという調子だった。クロードはウェイターの手からテーブル・クロスをもぎとった。そして頭の上からそれをかぶり、言った、「マダム・ズッカのお告げですぞな。エンディングは乙でいきますぞ」。場内爆笑だったね>
レインボウ・ルームでそのバンドが大晦日に引き起こしたワイルド・シーンを、ピー・ウィー・アーウィンが回想する。
<大晦日の演奏だから、バンドはかなり酒が入っていたと言っていいと思う。それはもちろん客の方だって同じことだろう。ことの発端はなんでもないことだったんだ。バンドが演奏していて、歌手のアル・バウリーが前に出て歌っていた。たぶん踊っていた誰かがたまたまステージの近くに寄りすぎて、レイ・ノーブルのピアノの前にあったマイクロフォンに足を引っかけたかなにかしたんだと思う。マイクロフォンは下のダンスフロアまで飛んでいった。踊っていた客がそのマイクロフォンを足で蹴飛ばして、それがアル・バウリーにたまたま当たってしまったんだ。アルは何が起こったのか、さっぱりわからなかった。それで彼はそのとき手に持っていたタムタムか何かを、客に向かって投げつけた。その客はテーブルに戻って、ロールパンをふたつ手に取り、それをバンドに向かって投げつけた。バンドはそれを拾って、投げ返した。
気がついたら、あの取り澄ましたレインボウ・ルームの空中を、ありとあらゆるものがびゅんびゅん飛び交っていた。中にはアイスクリームのカップを投げている客もいたし、バンドはそれを投げ返していた。まさに狂乱状態、喜劇映画に出てくるパイ投げそのままだ。トロンボーン奏者の一人は真ん中に穴のあいたプランジャー・ミュートを使っていた。レイ・ノーブルはブラス・セクションに逃げ込んで、楽器を手に取り、プランジャーを逆向きにマウスピースにつっこみ、それをかざして顔を防御した。彼の顔は見えなかった。見えるのはプランジャーだけだ。しばらくして騒ぎは収まった。翌日の新聞で、俺たちはずいぶん手痛い批評をうけたよ>
大晦日のパーティーにはほかにもワイルド・シーンの例がある。それは一九六八年にコロラド州アスペンの「サニーズ・ランデヴー・クラブ」で起こった。そのクラブはピアニストのラルフ・サットンと奥さんのサニーによって経営されていた。ラルフのトリオのメンバーはジャック・レズバーグとジェイク・ハナだった。サニーはレズバーグを脇に呼んで、ラルフになんとか「蛍の光」を演奏させてねと頼んだ。レズバーグはいいですよと言って、ラルフの説得にあたった。
<僕はラルフに言ったんだ。お客のためにやっぱり何はともあれ「蛍の光」はやるべきだよって。すると彼は言った、「客なんかクソ食らえだ。俺はそういう意味のないならわしが大きらいなんだ」。僕は言った、今日は大晦日でみんな楽しみに来ているんだよ。そのためにお金だって払っている。それくらいはサービスしたっていいんじゃないのかい。とうとう彼も同意した。「よし、わかった。やろうじゃないか」
真夜中のちょっと前に、僕は言った、「そろそろだよ、ラルフ」。そうしたらなんということか、ラルフは「星条旗よ永遠なれ」をやりだしたんだ。ジェイクはドラムの後ろで直立して敬礼し、あらんかぎりの声で「ファック・コミュニズム! ファック・コミュニズム!」って怒鳴った。ずっこけたね。とにかく店中が腹を抱えて笑ったよ。たしかに「蛍の光」をやるよりはみんな喜んだと思うな。とにかくなんでもいいからシャンパンを飲んで、みんなでにぎやかに新年を祝えばそれでいいんだよな>
ベニー・カーターは、昔のコニーズ・イン・ホテルの場所にあった「クラブ・ハーレム」で、自分のバンドを率いて演奏していた。そのクラブは経営不振のために閉店することになっていた。金持ちの遊び人として有名なジョージ・リッチがベニーに言った、「そいつはひどい話だ。君のバンドが演奏する場所がなくなっちゃうじゃないか。今晩の仕事が終わったら、うちに来てくれないか」
ベニーは言われたとおりそこに行った。それについてひととおり話をしたあとで、リッチは言った、「じゃあ、私があのクラブを買い取ることにしよう」。そしてソファのクッションのうしろから札束をごそごそと取り出してきた。彼はそこにお金をつっこんでいたのだ。それからクラブのオーナーに電話をかけた。カーターは語る。
<彼は九千ドルくらいで話をまとめた。そしてクラブの新しいオーナーになった。彼はたまにクラブに顔を見せて、酒を飲み、テーブルをあちこちまわっていた。私は言った、「ねえジョージ、何々のことはどうしたらいいのかな?」。彼はそのたびに言った、「そんなこと私は知らない。これは君のクラブだ」。彼がそのクラブを買った理由はただひとつ、私のバンドを解散させないためだったんだ。あの人のことは死ぬまで忘れられない>
|
|
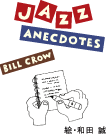

発売:2005/07/01
|
|