
ぼく東綺譚
473円(税込)
発売日:1951/12/27
- 文庫
愛の枯れる街で出会った、作家と娼婦、ふたり。私娼街・玉の井を舞台に描く、社会諷刺に満ちた荷風の最高傑作。
小説「失踪」の構想をねりつつ私娼街玉の井へ調査を兼ねて通っていた大江匡は、娼婦お雪となじむ。彼女の姿に江戸の名残りを感じながら。――二人の交情と別離を随筆風に展開し、その中に滅びゆく東京の風俗への愛着と四季の推移とを、詩人としての資質を十分に発揮して描いた作品。日華事変勃発直前の重苦しい世相への批判や辛辣な諷刺も卓抜で、荷風の復活を決定づけた名作。
書誌情報
| 読み仮名 | ボクトウキタン |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 発行形態 | 文庫 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 144ページ |
| ISBN | 978-4-10-106906-7 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | な-4-3 |
| ジャンル | 文芸作品 |
| 定価 | 473円 |
書評
「荷風の昭和」のあとに読みたくなる三冊
「波」8月号で2018年から連載をはじめた「荷風の昭和」をなんとか無事に終えることが出来た。軍国主義が強まってゆき、日中戦争を経て太平洋戦争に至り、その破局による戦後の混乱期を老作家はどう生きたか。その生を辿ることは今年八十歳になった人間には興味深いものがあった。
書籍の刊行は来年の5月の予定だが、来年令和7年(2025)は、昭和が続いていれば昭和100年になる区切りの年だ。改めてさまざまな形で昭和が語られることだろう。
昭和19年、サイパン島が落ち、日本本土への空襲が始まってゆく時代に生まれた人間にとって、昭和とはまず何よりも戦争があった時代である。
永井荷風の『ぼく東綺譚』は昭和11年に脱稿し、翌年4月から、東京・大阪の「朝日新聞」の夕刊に連載された。最終回は昭和12年6月15日。翌7月に日中戦争が勃発し、それが太平洋・アジア戦争へと続いてゆくことを考えれば、若き日に荷風に惹かれた大正9年生まれの作家、安岡章太郎が『私のぼく東綺譚』(新潮社、1999年)で書いているように「わがくにに辛うじて戦前の平和が残されていたギリギリの時期に発表された」、消えゆく時代への哀歌である。

荷風自身を思わせる老作家の「わたくし」が隅田川の向こうにある私娼の町、玉の井を歩き、そこで出会った私娼お雪のなかに「ミューズ」を見る。ここでは、東京の三流の遊び場だった玉の井が、軍国主義の厭うべき現実から離れた美しい隠れ里として描かれている。もっとも汚れた町のなかにこそ、もっとも美しい世界を見る。戦争へと向かう世に背を向けた荷風の詩的抵抗といっていいだろう。いま何度読み返しても心に沁み入る。
北杜夫の『楡家の人びと』は、作者自身の一家をモデルにした楡家三代の物語。トーマス・マンの『ブッデンブローク家の人びと』の日本版といえようか。
一代で東京の青山に壮大な脳病院を建て、衆議院議員となった当主、五人の子どもたち、さらにその子どもたち。この一族が体験する大正、昭和が語られてゆく現代史にもなっている。関東大震災、二・二六事件、戦争、東京空襲が市井の家族の視点から描かれる。
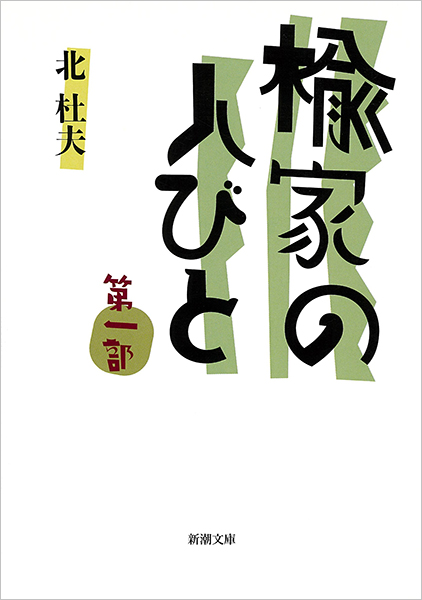
純文学というと閉鎖的な作家の特殊な私生活を描く作品が多かったなか、普通の市民生活を描き、実に新鮮。
昭和39年に新潮社から単行本が出版された。函入り。二段組、五百ページを超える大著だが、文章は平明端正で読みやすい。これまで何度も読んだ。
函には三島由紀夫の推薦文があり「戦後に書かれたもっとも重要な小説の一つである」「これほど巨大で、しかも不健全な観念性をみごとに脱却した小説を、今までわれわれは夢想することもできなかった」と絶讃している。
大正13年生まれの吉行淳之介も荷風を敬愛した。「抒情詩人の扼殺」という秀れた追悼文もある。
『原色の街』(昭和31年)は『ぼく東綺譚』の戦後版の趣きがある。玉の井の町が東京大空襲によって焼失し、業者が向島に新たに作った私娼街、鳩の街を舞台にしている。

そこには戦前の玉の井がかろうじて持っていた江戸の残り香はもうなくなっている。けばけばしい化粧や衣裳の女性たち。いっときの快楽を買う客たち。欲望がむきだしになっている。まさにぎらついた原色の街。
主人公の船会社に勤める会社員の元木英夫はそんな街であけみという私娼に会う。彼女は欲望のどぎつい色に染まっていない。彼女に比べれば、英夫の婚約者の瑠璃子のほうがお嬢様なのに娼婦のようなところがある。
吉行淳之介もまた荷風のように汚れのなかにこそ美しさを見ようとしている。
鳩の街は売春防止法によって昭和33年の4月に消えた。この小説も昭和の一側面への美しい挽歌になっている。
(かわもと・さぶろう 評論家)
担当編集者のひとこと
「波」巻末を飾る名物連載、川本三郎さんの「荷風の昭和」がいよいよ昭和十一年に突入しました。つまり二・二六事件が起き、永井荷風が『ぼく東綺譚』を執筆した年です(東京・大阪朝日新聞での連載は翌十二年)。
ひさびさに新潮文庫でこの名作を読むと、年齢のせいか、身にしみました。六月末から九月の終わり頃まで、わずか三か月ほどの「わたくし」(大江匡。数えで五八歳の作家)と玉の井の娼婦(お雪。二六歳)との交情の物語ですが、何よりこたえられないのは、移りゆく季節感(および時の流れ)の嫋々たる描き方。滅多にそんなことは思わないのですが、ここには人生がある、という気になります。
とりわけ、へええと唸ったのは、あとがきのような「作後贅言」でした。『ぼく東綺譚』本文は、男の身勝手な思いからお雪から離れることになり、「ここに筆を擱くべきであろう」と書いてから、お雪とのありうべき再会を空想したり、稲妻に照らされた横顔を思い出したりしながら、詩のようなものを書きつけて終わります。尻切れトンボを風情にしたような終わり方。
そのあとに「作後贅言」が来る。ここでの「わたくし」はもう大江匡ではなく、荷風そのままですが、しかしこれも『ぼく東綺譚』の一部だと言いたくなるような詩情と面白さがあります。『ぼく東綺譚』は大江が「失踪」という〈小説内小説〉を構想するところから始まりましたが、「作後贅言」まで至ると、『ぼく東綺譚』自体が〈随筆内小説〉になるような、不思議な読後感がやってきます。
お雪との仲が深まるのは、ちょうど今の季節。ひさびさにいかがですか?(出版部・K)
2020/08/27
著者プロフィール
永井荷風
ナガイ・カフウ
(1879-1959)東京生れ。高等商業学校附属外国語学校清語科中退。広津柳浪・福地源一郎に弟子入りし、ゾラに心酔して『地獄の花』などを著す。1903(明治36)年より1908年まで外遊。帰国して『あめりか物語』『ふらんす物語』(発禁)を発表し、文名を高める。1910年、慶応義塾大学教授となり「三田文学」を創刊。その一方、花柳界に入りびたって『腕くらべ』『つゆのあとさき』『ぼく東綺譚』などを著す。1952(昭和27)年、文化勲章受章。1917(大正6)年から没年までの日記『断腸亭日乗』がある。

































