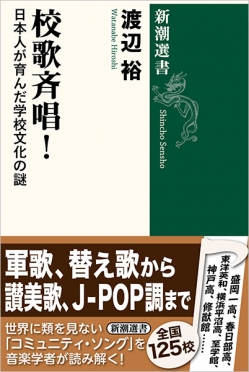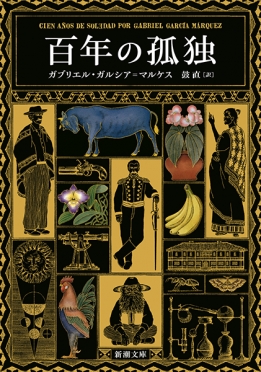砂の女
781円(税込)
発売日:1981/02/27
- 文庫
- 電子書籍あり
来る日も来る日も砂・砂・砂……。
砂丘へ昆虫採集に出かけた男が、砂穴の底に埋もれていく一軒家に閉じ込められる。考えつく限りの方法で脱出を試みる男。家を守るために、男を穴の中にひきとめておこうとする女。そして、穴の上から男の逃亡を妨害し、二人の生活を眺める村の人々。ドキュメンタルな手法、サスペンスあふれる展開のうちに、人間存在の極限の姿を追求した長編。20数ヶ国語に翻訳されている。読売文学賞受賞作。
書誌情報
| 読み仮名 | スナノオンナ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 288ページ |
| ISBN | 978-4-10-112115-4 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | あ-4-15 |
| ジャンル | 文芸作品、文学賞受賞作家 |
| 定価 | 781円 |
| 電子書籍 価格 | 781円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2024/03/07 |
書評

安部公房生誕100年記念 安部公房と私
ジャンルの壁を越え、今なお影響を与え続ける偉大な作家。俳優、作家、文学紹介者、ゲームクリエイターの4名がその愛を語り尽くす。
箱男
浅野忠信
仕事場で自分の存在をスタッフに忘れられることがたまにある。
例えば雪崩のシーンを撮るために雪の中に埋められ、じっと待っていて他の人からは雪の一部にしか見えていない時とか、アクションシーンのためワイヤーでビルの3階ぐらいの高さに吊るされスタッフの目線に自分がいない時とか、一人全裸で温泉街で待機しカメラやスタッフは遠くにいる時など。
しかしそういう時は大声で自分の存在をアピールして私のことを忘れないでくれ! と訴えるのだが、このまま黙っていてもいいかも! と思ったのが撮影で段ボール箱に入り、小さな覗き穴からみんなを見ている時だった。
真夏の撮影で物凄く暑いので私は段ボールの中にほぼ裸でいた。明らかに自分が箱の中にいることを忘れられているなと悟った時、冷静に人々の癖や独特な動きなどを観察して、でも自分はだらしなくパンツいっちょでボケーッとしていられる、しかもみんなのど真ん中で、自分の存在は大きくそこにあるのに誰にも相手にされずに済む。こんなに矛盾した心地いいことは滅多にないから余計に黙っていたくなった。
これが箱男の快感の一部なのか!? と笑ってしまった。
安部公房さんがはたしてどんな気持ちでこの小説を書いたのかわからないが、少なくともこの作品を知っていて尚且つそれを実際に経験したのは佐藤浩市さん、永瀬正敏さんと私ぐらいだと思う。ヤドカリが宿に隠れ、あたかもただの貝殻のふりをするように、なんでもない場所で“物”として世界を見ると、とてつもなく自由な気持ちになれるし、何かがリセットされ続けている感覚になった。
ただそれと同時に、そこにもう一つ同じ箱男の存在があった時に物凄く邪魔された気持ちになり、普段よりも自分が見られている気持ちになるのも確かだったと思う。勿論仕事なので佐藤さんや永瀬さんが邪魔だとは一切思わなかったが、同じように箱に入っている時に箱の中の世界や居心地、独特な時間の流れが深く理解できるので、目の前に自分ではない別の箱男がいると逆に恥ずかしくなったりもした。
この撮影がコロナ後で良かったと思う。なぜならみんながマスクをして自分の口を隠す生活を経験したから。あれこそ一種の箱男的感覚を試せる時間だったと思う。自分の口を隠し表情を読み取られず、時には声に出さず想いを口にすることができるのは時になんとも言えない自由のようなものを得た感覚になったのを覚えている。コロナ禍が明けてからもマスクをしたいと思う時が自分にもあったのだが、撮影を終えた時にやはり、もっと箱に入っていたかったと思ったこともあったので、映画を見たり小説を読む人によっては共感できる気持ちがそこにあるかもしれないと思う。
真夏のエアコンのない現場で箱に入り中腰で歩いたり、喋り続けたり、時には転がったり、アクションをしたり、忘れられたり、みんなの素の状態を凝視したりと、この異様な体験をできたことを安部公房さんに感謝したい。そしてできれば安部さんに伝えたかった。
この映画を見た方や小説を読んだ方がひょっとしたら箱に入り町のどこかで佇むことを試しているかもと思うと笑ってしまうが、その時はほっといてあげようと思う。
映画『箱男』は2024年公開
(あさの・ただのぶ 俳優)
夢の通い路
一穂ミチ
忘れられない「怖い夢」がある。七歳か八歳の頃で、夢の中のわたしは、団地のような場所にひとり佇んでいた。当時住んでいたマンションでも友達の家でもなく、全く見覚えのない建物だった。夕暮れ時で、目の前の公園にある奇妙な形の遊具が、無人にもかかわらずぎーこぎーこと水平運動を繰り返していた。
ただそれだけの内容なのに、強烈に恐ろしく、目が覚めた時には泣いていた。でもこうして書いてみても、幼い自分が感じた恐怖の一割も伝わらないだろう。夢の手触りは残っているのに、何がそんなに怖かったのか、うまく説明できない。だから人に話す時は「安部公房の小説に迷い込んだみたいな感じだった」と言う。非現実であるはずなのに、薄皮のように肌に張り付く現実感があまりに生々しかった。
昆虫採集に出かけた男が、蟻地獄のような砂中の一軒家に閉じ込められる『砂の女』、ラジオ番組の脚本家のもとへ突然訪れた自称火星人と応酬を繰り広げるうちに精神の均衡が崩れていく『人間そっくり』、自殺を図ろうとしていた男が生きながら「死体」としてロボットに改造される『R62号の発明』など、いずれも主人公は悪事を働いたわけでもなく、何らかの禁忌を犯したわけでもないのに、あまりにもなめらかに、白昼に現れた黒点のような展開に呑み込まれていく。その唐突さに却ってリアリティを感じてしまうのは、現実世界のままならなさ、残酷さに多少なりとも触れてきたせいだろうか。
たとえば、電車でひと駅乗り過ごす。いつもと違う道を通って帰ってみる。そんな日常の予期せぬトラブル、ささやかな逸脱の一歩先に、安部公房的な異界が何の境界線もなく待ち受けているように思えてひやりとする。安部公房を一度読んだら、以前の自分にはもう戻れない。この世には底なしの砂穴がいくつもひそんでいて、避けることも逃げることもできない、とわたしはもう「知って」しまった。
安部公房自身は、「ここ数年来、ぼくは枕元にテープ・レコーダーを常備して待つことにした。見た夢をその場で生け捕りにするためである」と綴っている(『笑う月』)。活きの良すぎる夢の断片たちが、本人の死後もぴちぴちと跳ね、読む者の現実に侵食を繰り返している。わたしも、あなただって、彼の夢を読んでいるのではなく、彼の夢の中で存在しているのかもしれない。ずっと。だから、生きていて何が起こったって不思議ということはない、と自分に言い聞かせている。
(いちほ・みち 作家)
「あ」だから出会えた
頭木弘樹
中学生のとき図書館で友達と待ち合わせをした。私は本を読まないほうだったので、図書館に行ったのはそのときが初めてだった。友達は遅れた。退屈した私は、日本文学の「あ」のところを見てみた。安部公房という作家がいた。海外で翻訳された本が何冊も並んでいたので、ほう、海外でも評価されている人なんだ、と目にとまった。海外の本に「Kobo Abe」と書いてあった。「公房」は「こうぼう」と読むのか。「工房」みたいで面白いと思った。
『砂の女』『箱男』。女は砂で、男は箱なのか。どんな小説なんだろう? と『箱男』を手にとってみた。最初のところを見ると、「ダンボール空箱 一個/ビニール生地(半透明) 五十センチ角/ガムテープ(耐水性) 約八メートル」などと、箱男になるための箱の製法が書いてある。なんだこれは? 学校の国語の教科書の小説とはぜんぜんちがう。私は音楽のほうでは、たまたま現代音楽を知って、聴いていた。クラシックに対する現代音楽のように、現代文学もずいぶんすごいところまで進んでいるんだなあと驚いた。知らない国を初めて訪れたように、一行ごとに新鮮だった。
いつの間にか、夢中になって読んでいた。周囲の雑音がまったく聞こえなくなっていた。なにか透明なカプセルにでも包まれているような感じだった。友達がやってきて、何度も声をかけたそうだが、気づかなかった。肩をたたかれて、はっとしたときには、水の中から顔を出して息をつくような感じがした。こういう特別な読書体験は、その後も数回しかない。
大学で関東に出たとき、安部公房の家の前まで行ってみたことがある。しかし、すごく尊敬していたので、とてもチャイムを押せなかった。その後、私は難病になって外出が難しくなり、1993年、安部公房が亡くなったというニュースを見たときには、ベッドの上で号泣した。もうご当人に取材はできないが、妻の真知さんに取材して、安部公房論を書きたいと思った。電話でお願いして承知していただけた。しかし、お会いするはずの日の少し前に、真知さんも亡くなってしまった。けっきょく、私が初めて安部公房邸に入ったのは、真知さんのご葬儀に参列させていただいたときだった。
会いたい人には会っておいたほうがいいと強く思うようになった私は、桂米朝に会って落語の本を出し、山田太一に会ってシナリオ集の編者となった。すべて安部公房が始まりだった。
(かしらぎ・ひろき 文学紹介者)
少年、穴に墜ちる
小島秀夫
父も母も兄も読書家で、家には本が溢れていた。けれど僕は、父たちが読んでいる本を面白がれない子供だった。小学校の高学年頃からミステリやSFに嵌ったが、いわゆる文学を読んでも楽しくなかった。学校で書かされる感想文が、それに拍車をかけた。「感動しました」、「主人公の生き方に学びたいと思います」。そんな紋切り型の作文は書きたくなかったし、書けなかった。それでも授業なので逃れられない。仕方がなく、父の本棚にあった文学全集の一冊を手に取った。それが安部公房の巻だった。SFも書いている作家、という予備知識があったせいもある。こうして中一の時、初めて読んだのが『他人の顔』である。衝撃だった。感想文には、感動したとも教訓を得たとも書かなかった。ものすごく面白かったことは間違いない。だからその理由を解説した。それが現代国語の先生に絶賛され、クラスの皆の前で朗読された。お約束を無視した感想文が褒められる。もしかしたら、僕の作文そのものではなく、安部公房の作品を選んだ視点を褒められているのでは? 文章や表現ではなく、視点が肝なのでは? それが感想文嫌いを克服するきっかけになった。同時に僕は『砂の女』の男のように、安部公房という底なしの“穴”に嵌った。高校生の時には短編「なわ」の感想文を書き、コンクールで3位に入賞した。1位は「感動しました」系の学校推薦的な感想文。僕にとっての安部公房は特別な存在なのだ。それは、誰もが挙げる1位ではなく、僕だけが嵌る3位という特別な“穴”なのだ。だから、この3位入賞は、嬉しかった。
『第四間氷期』や『水中都市』なども「SFの顔」をしているが、ただのSFではない。当時の小松左京に代表されるSFは、科学技術をベースに、思索や物語を展開していくが、安部公房は違う。理系の論理と文系の感性が融合した独自の世界が構築されている。もともと理系志向だった僕の資質とも相性がよかったのか、『砂の女』、『燃えつきた地図』、『箱男』など、どんどん“穴”に嵌っていくことになる。彼を知れば知るほど、“穴”の内側は深くどこまでも広がり、抜けられなくなる。それは、文学でもSFでもない安部公房という不思議な居心地のいい“穴”なのだ。
僕の作品は、ただのゲームでもなく映画でもなく、ジャンルで括れない、と評されることが多い。十代の頃、“穴”に落ちなければ、今の僕はなかったかもしれない。その“穴”から、今日も作品の構想を練る。「逃げるてだては、またその翌日にでも考えればいいことである」(『砂の女』より)。
(こじま・ひでお ゲームクリエイター)
*
本文中で言及されている小島さんが高校時代に書かれた「なわ」(『無関係な死・時の崖』に収録)の感想文を、下記に特別掲載いたします。
【感想文】第3席
「なわ」(安部公房)を読んで
2年9組 小島秀夫
この小説の冒頭は、リュウマチに蝕まれた六十二才の男が壁の穴から覗いた世界、屑鉄(スクラップ)の死体置場からはじまる。
異様な雰囲気の中での残酷とも言える子供たちの悪行。続いて、ロープを引きずって現われるずぶ濡れ姿の奇怪な二人の姉妹。そして彼女たちに死を誘い、一家心中を強制する少女たちの父親―。
何もかもが狂気に満ち、寓話的である。そして、全体を貫くのは、陰湿な空気と残忍さ。色彩で表わすなら、澱んだ茶色と言えよう。しかも、けだるさが漂い、やりきれない絶望感がある。これだけでも、えたいの知れぬ圧力に堪えがたいほどだ。だが、これに幻覚めいた恐怖が加わる。
正直言って、この小説「なわ」の奥深く隠されたテーマを探り出すには難解であった。未だはっきりと掴めていないほどだ。
しかし、唯一、この小説を解く鍵となるものは最後の四行であろう。このたった4行こそが、テーマの濃縮に違いないとそう確信した。
ここには『なわ』に対する作者の定義がなされている。
「『なわ』は『棒』とならんでもっとも古い人間の道具の一つだった。」
まさに、この通りであり、『なわ』も『棒』も人類(ホモ・サピエンス)の歴史のうち最も初期に考え出された道具、いや、文明である。現在でも、『なわ』や『棒』はあらゆる方面へ進入し、全ての道具や思考の原点となっている。いわばこれらの発明そのものが今の近代文明を生み出したとも言える。そして、これらが単純であればこそ『なわ』や『棒』が最も人間というものを表現し、反映しているのである。
二者とも単純かつ利用範囲が広く、共通点は多いが、よく掘り下げて考えてみると全く正反対の位置にあるのがわかる。これについて、作者は二者を次のように分類している。
「『棒』は悪い空間を遠ざけるために、『なわ』は善い空間を引き寄せるために人類が発明した最初の友だちだった。」
このように、明らかに両者は全く違う用途のために作られたというのがわかる。この「悪い空間を遠ざける」というのは、『棒』を武器として使う事で、敵から身を守るというのが当てはまり、「善い空間を引き寄せる」というのは『なわ』によって何か価値ある物をつなぎ止めたり、あるいは、それによって、価値あるものにするというのが当てはまるだろう。
では、この二人の少女たちは、『なわ』をどのように使ったか?
彼女たちは、『なわ』を武器として父親の首を締めて殺した。言ってみれば、自分たちの生命を守るために『棒』の定義である「悪い空間を遠ざけるため」を使ったのであった。だが、この場合は『棒』ではなく『なわ』をであった。この裏面には『なわ』本来の定義「善い空間を引き寄せるため」というのが、秘められている。つまり、少女たちは父親の存在しない世界、彼女らの死の心配のない世界が善い空間だと判断したのではないだろうか。
すなわち、彼女たちは「善い空間を引き寄せるため」(なわの定義)に「悪い空間を遠ざける」(棒の定義)をしたのだ。いうなれば、『なわ』的根拠で『なわ』を『棒』として利用したわけである。
ただ、ここで少し見方を変えれば、恐ろしい答が出る事になる。僕は、あまり、こちらを好まない。やりきれなくなるからである。
それは、彼女らが父親を締め殺した動機にある。前に述べたように自分たちの命の危険を感じて殺したのなら、さっきのもので問題はないはずだ。しかし、彼女らの動機はあの古靴と交換した百円玉にあるかも知れないのだ。もし、これが的を得ているなら少女たちは父親と一度交換した百円玉を取り返したいがために、罪を犯した事になる。全く、何と恐ろしく、虚しいことだろう。
この小説を読む限りでは、この方が強い感じはしないでもない。しかし、まともな人間としては、何としても前者にしたいのだ。
あの『なわ』によって、引き寄せられたのは彼女たちの生命か、それとも、百円玉か? この差は、はかりしれないほど大きく、そしてこの決定をくだすには、まだまだ、人間という生物を分析し、真の人間性を追求しなければならないだろう。
どういう本?
タイトロジー(タイトルを読む)
女は、素裸だったのだ。
涙でにごった視界のなかに、女は影のように浮んで見えた。畳の上に、じかに仰向けになり、顔以外の全身をむきだしにして、くびれた張りのある下腹のあたりに、軽く左手をのせている。ふだん人が隠している部分は、そんなふうにむきだしにしているのに、逆に、誰もが露出をはばからない、顔の部分だけを、手拭で隠しているのだ。むろん、眼と呼吸器を砂から守るためだろうが、そのコントラストが、裸体の意味を、いっそうきわ立たせているようだった。
しかも、その表面が、きめの細かい砂の被膜で、一面におおわれているのだ。砂は細部をかくし、女らしい曲線を誇張して、まるで砂で鍍金(めっき)された、彫像のように見えた。ふいに、舌の裏側から、ねばりけのある唾液が、ふきだしてくる。(本書51〜52ぺージ)
著者プロフィール
安部公房
アベ・コウボウ
(1924-1993)東京生れ。東京大学医学部卒。1951(昭和26)年「壁」で芥川賞を受賞。1962年に発表した『砂の女』は読売文学賞を受賞したほか、フランスでは最優秀外国文学賞を受賞。その他、戯曲「友達」で谷崎潤一郎賞、『緑色のストッキング』で読売文学賞を受賞するなど、受賞多数。1973年より演劇集団「安部公房スタジオ」を結成、独自の演劇活動でも知られる。海外での評価も極めて高く、1992(平成4)年にはアメリカ芸術科学アカデミー名誉会員に。1993年急性心不全で急逝。2012年、読売新聞の取材により、ノーベル文学賞受賞寸前だったことが明らかにされた。