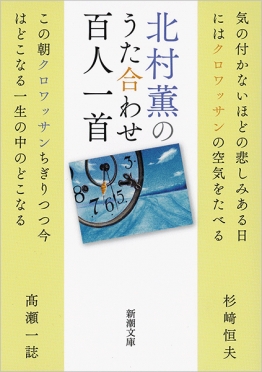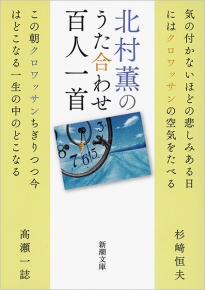
北村薫のうた合わせ百人一首
605円(税込)
発売日:2019/09/28
- 文庫
短歌は美しく妖しく織られた謎――現代短歌550首で短歌の魅力と魔力を味わい尽くす。
五・七・五・七・七の三十一文字で、美しくも壮大な世界を綴り出す短歌。向かい合い、背を向け、あるときは遠く離れながらも響き合う二つの短歌の断ち切り難い言葉の糸を独自の審美眼で結び合わせた50組100首に、塚本邦雄・石川美南から三井ゆき・佐佐木幸綱まで、総数550首を収録。現代短歌の魅力を味わい尽くす、前代未聞のスリリングな随想。『うた合わせ 北村薫の百人一首』改題。
二 季節の色 若山牧水 秋谷まゆみ
三 皀莢とすずらん 梅津ふみ子 篠弘
四 ついにつげえず 小川太郎 藤井常世
五 白い安息 雨宮雅子 田谷鋭
六 窓のうち外 穂村弘 松平盟子
七 夢の男と、女 道浦母都子 吉川宏志
八 牛の声 北原白秋 前川佐美雄
九 少女のねむり 藤原龍一郎 桑原正紀
十 近江 あふみ 河野裕子 永田和宏
十一 はつなつの 横山未来子 谺佳久
十二 その人びと 神山裕一 児玉武彦
十三 夏の記憶 佐伯裕子 苑翠子
十四 遠い母 東直子 尾崎翠
十五 その秋 吉岡生夫 水原紫苑
十六 仰ぐ空 青井史 黒崎善四郎
十七 雨 安永蕗子 穂積生萩
十八 詩人の家 小池純代 萩原朔太郎
十九 崩壊の調べ 仙波龍英 香川ヒサ
二十 かなしみがよぎる 永井陽子 村木道彦
二十一 朝のクロワッサン 杉崎恒夫 高瀬一誌
二十二 死と生と書店 天草季紅 荻原裕幸
二十三 本と人 金坂吉晃 宮柊二
二十四 生きていると疲れる 小原起久子 大松達知
二十五 思ひ出づる女人 樋口覚 高野公彦
二十六 ことば 今野寿美 西村美佐子
二十七 童子 小林幸子 富小路禎子
二十八 まぼろし 林和清 松平修文
二十九 ふと、よぎる思い 佐藤弓生 佐藤晶
三十 父 小池光 馬場あき子
三十一 かぐはしきかな 寺山修司 辺見じゅん
三十二 夢の中の死 杜澤光一郎 高尾文子
三十三 初心 俵万智 佐藤通雅
三十四 昭和 武市房子 竹村公作
三十五 夕暮れに歩く 木下龍也 天野慶
三十六 剃刀研人 斎藤茂吉 渡英子
三十七 その時 河野愛子 大西民子
三十八 王子と母 岡井隆 森岡貞香
三十九 猫と かくこう 梶原さい子 宮沢賢治
四十 祈り 斉藤斎藤 葛原妙子
四十一 絵の中の人 中津昌子 浜田康敬
四十二 非在の言語 大森益雄 石川啄木
四十三 ひとり 小中英之 石田比呂志
四十四 時代の空気 大野誠夫 加藤治郎
四十五 男の出番 小高賢 中地俊夫
四十六 天 花山多佳子 栗木京子
四十七 父逝きて 池田はるみ 山崎方代
四十八 立ちあらはるる 大田美和 江田浩司
四十九 旅路 山中智恵子 釈迢空
五十 そして、眠れよ 三井ゆき 佐佐木幸綱
結びに
歌人と語る「うた合わせ」北村薫・藤原龍一郎・穂村弘
解説 三浦しをん
書誌情報
| 読み仮名 | キタムラカオルノウタアワセヒャクニンイッシュ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 謡口早苗/カバー装画、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 336ページ |
| ISBN | 978-4-10-137334-8 |
| C-CODE | 0192 |
| 整理番号 | き-17-14 |
| ジャンル | 文学賞受賞作家 |
| 定価 | 605円 |
書評
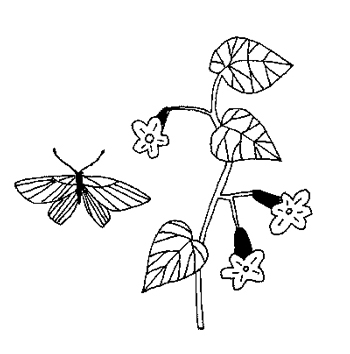
百首を這いめぐる触手
はっとする鑑賞に出会った。吉川宏志の「夢に棲む女が夢で生みし子を見せに来たりぬ歯がはえたと言いて」に関わる箇所だ。結句のしんとした怖さをどう読み取るか。フローベールの『ジュリアン聖者』(岩波文庫)の一行、山田九朗訳が引用される。「――一度も泣かずに歯が生えた」。生き物を殺戮することに取り憑かれる幼児の描写だ。かつて、この一行に「慄えた」と著者は書く。
だが、山田訳の一行は、原文の意味を一瞬のうちに誤読させるもののようだった。「歯もはえそろったが、そのために泣いたことは一度もない」(桑原武夫訳)など、忠実な訳が紹介されていく。だが、理に適って見えるどの訳も、著者を戦慄させてはくれなかった。「夢という非現実から、その小さいが白々とした《歯》が現実に食い入って来そうになる」という結句の解釈。翻訳の一行に導かれた鑑賞が、吉川の一首をさらに怖いものにしている。
心動かされた初発の印象を、安易に「正しさ」に譲りわたさないのは、創作者としての心意気だ。どの鑑賞にも息づくその姿勢は、歌人の藤原龍一郎、穂村弘との巻末の鼎談でも露出する。木下龍也の「つむじ風、ここにあります 菓子パンの袋がそっと教えてくれる」などの解釈にまつわるやりとりだ。「店先に並ぶ菓子パンの袋がそっと囁く」とする、直観的で一途な解釈にたじろぐ二人。著者の抑えがたい想像力が浮き彫りにされる場面である。
韻律に関わる箇所も印象深い。仙波龍英の「ひら仮名は凄じきかなはははははははははははは母死んだ」、香川ヒサの「ひとひらの雲が塔からはなれゆき世界がばらば らになり始む」の二首の組だ。本来は「母母母母母母」となるところが、短歌の場合、平仮名だと「ははははは・ははははははは」と五句七句に別けて読まれてしまう。すると、読後に「哄笑」が響きわたる。この一首から、韻律の怖さと同時に、仙波の韻律への憎悪を読み取っているのである。香川の歌も、一字空けの効果を、「短歌の調べが世界を引き裂く」もの、と鋭く指摘する。
何しろ「――一度も泣かずに歯が生えた」という一行に、瞬時に共振する感性だ。たった一行が放つ衝撃を、今度は一首の短歌に読み取ろうとする。読後の瞬時の戦慄をもとに書かれているのだが、その視線は、百首の歌を這いめぐる触手のようにも思えてくる。
「かくのごと綴られてゆくよろこびのこゑいかばかりわたしが言葉ならば」はどうだろう。詞書「吉行淳之介『目玉』読後」を添える西村美佐子の一首だ。艶のある文章を読む悦びが全身でうたわれている。この官能的な歌を鑑賞するのに、著者自身が言葉になって、一首を這いめぐるのである。書くことの愉悦、読むことの愉悦を知る者の、最良の選歌といっていい。
読んでいて嬉しいのは、選ばれた歌がユニークだったり、これまで気づかなかった秀歌だったりすることだ。それも、どちらかといえば、仄暗い深淵を湛える歌が多いように思われる。例えば、三井ゆきの、夫を焼き場に送った一首、「覚えてもゐぬことを思ひ出さむとす君を包みし火の色などを」。ああ、こんなに凄まじい挽歌があったのかと、しばらく感じ入ったのだった。
戦慄する「歯」のイメージを呼び起し、「世界を引き裂く」調べの怖さを指摘し、そうして「言葉と同化する」法悦へと読者を誘っていく。そのような鑑賞のうちに、著者自身が見ている風景の仄暗さ、もの悲しさに浸されてしまうのである。
誤読を恐れず、初発の感動を手放さない鑑賞に、わたしは自由な広がりを感じた。小説家である著者には、一首のめぐりに、重層的なイメージやドラマが見えていたにちがいない。短歌は、好んで読み承いでくれる人によって、豊かに太っていく詩型なのだ。
(さえき・ゆうこ 歌人)
波 2016年5月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

短歌というミステリーの謎とき
北村 「短歌俳句は作る人でなければ、本当に味わうことはできない」といわれます。私は短歌を作らないんです。「歌人には、どう読まれるのだろうか」と、恐る恐る(笑)、お聞きいたします。
穂村 韻文のパワーって、いわゆる正しさみたいなものからずれたところで成立することがやっぱりあって、そういうことを、書き手の感受性がつきとめているっていうのかな。でも、それは韻文をやる人はみんな直感的に知ってるんだけど、北村さんは直感的に知っていることを、散文的にもう一回、検証されている。韻文の魅力は正しさだけにはないっていうことを重々知っていながら、同時に散文的な執念みたいなものも持っていて、そこに、謎を解いていくミステリーのセンスを感じるんです。
僕はミステリーをそんなに読み込んでいるわけじゃないけど、自分が好きなミステリーって再読できる。それは散文的な謎が解けても、その奥には命とか存在とか人生とか、そういう根本的な謎があって、それがむしろ強化される。謎が解けたことによって、事件は解消されるが、残った一人一人の人間の命や人生はより混沌として異様な感じになって、世界はなんて恐ろしいんだっていうふうに思えるものこそが、すごくかっこいいって思うんだけど、それは、韻文的な深さと散文的な誠実さの両方がないと成立させることのできないジャンルだって思うんですよね。北村さんも、普段ミステリーを書くときに、そういう書き方をしていると思うのですが、短歌を読むときにも、その両輪をすごく回してるっていう感じがするんです。韻文だからわからなくていいとか、そういう読み方ではなくて、ある種の正しさ、散文的な明快さを突き詰めようとする。でも、それがどこかで破綻すると、声を上げて喜ぶみたいなところがあって。とても楽しそうなんです。それを楽しいって感じる感受性がすごくあるんだな、と。だから、この本はとてもスリリングなんですよ。
短歌っていうのは、誰でも一人では味わい切れないジャンルっていう感じがするんです。こういう名手がその味わいかたを教えてくれる――しかも自分が普通とは違う読みをしたっていうことも堂々と書いてくれているから、そこが、やっぱりすごく面白いんです。
藤原 これは北村薫っていう人の目で短歌を読みこんだもので、単なる現代短歌の鑑賞の本ではないですよね。それは歴然とわかります。穂村さんがおっしゃったことは、まったくそうなんです。そして全部読んでいくと、「うた合わせ」として短歌が二首並んで選び出されているけど、結局はその章の中にほぼ九割九分まで一首目のことしか書いてなくて、最後にちょっとだけもう一首のことが触れられているというような章もある、ただの鑑賞の本ではありえない書き方です。
やっぱり覗いてる窓が違うんですよね。歌人からは、こういう読みって出ないと思うんですよ。
北村 そのお言葉は、すごくありがたいですね。ほかの人が書かない、書けないだろうって本を書くことが、書く者の務めですからね。
穂村 それに、とにかく楽しそうですよね。小説を書くときより楽しんでいるんじゃないかって思うぐらい、文章にも、その感じがにじみ出ています。ずっと短歌を書いてると、短歌って面白いのかな? ――みたいな感じになって、わからなくなってくる。最初の何か月かはすごく面白いって確信していたのに。だから、改めて「あ、短歌ってやっぱり面白いんだ」って、思いました。文体そのものも喜びに満ちています。非常に貴重なカンフル剤となってくれる感じがします。
藤原 この本は普通の短歌の読み方を教える本ではないんです。歌人向けでもない。短歌だけでなく文学全般に興味がある人が、読者として想定されている本だと思います。こういう形で現代短歌を読み解いた本はなかった。こういう形の読みに、現代短歌は直面して来なかったんです。どうしても二十年、三十年と短歌を創っていると、ほとんどの歌人の看板を知っているような気になってしまうので、一切のしがらみがない立場で、作品として読んでいるというところがとても貴重だと思います。たくさんの人に読んで欲しいですね。
(きたむら・かおる 作家)
(ふじわら・りゅういちろう 歌人)
(ほむら・ひろし 歌人)
波 2016年5月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
北村薫
キタムラ・カオル
1949年埼玉県生まれ。早稲田大学ではミステリクラブに所属。1989年、「覆面作家」として『空飛ぶ馬』でデビュー。1991年『夜の蝉』で日本推理作家協会賞を受賞。小説に『秋の花』『六の宮の姫君』『朝霧』『太宰治の辞書』『スキップ』『ターン』『リセット』『盤上の敵』『ニッポン硬貨の謎』(本格ミステリ大賞評論・研究部門受賞)『月の砂漠をさばさばと』『ひとがた流し』『鷺と雪』(直木三十五賞受賞)『語り女たち』『1950年のバックトス』『ヴェネツィア便り』『いとま申して』三部作『飲めば都』『八月の六日間』『中野のお父さん』『遠い唇』『雪月花』『水 本の小説』(泉鏡花文学賞受賞))『不思議な時計 本の小説』などがある。読書家として知られ、『謎物語』『ミステリは万華鏡』『読まずにはいられない 北村薫のエッセイ』『神様のお父さん――ユーカリの木の蔭で2』など評論やエッセイ、『名短篇、ここにあり』(宮部みゆきさんとともに選)などのアンソロジー、新潮選書『北村薫の創作表現講義』新潮新書『自分だけの一冊――北村薫のアンソロジー教室』など創作や編集についての著書もある。2016年日本ミステリー文学大賞受賞、2019年に作家生活三十周年記念愛蔵本『本と幸せ』(自作朗読CDつき)を刊行。近著に『中野のお父さんと五つの謎』。