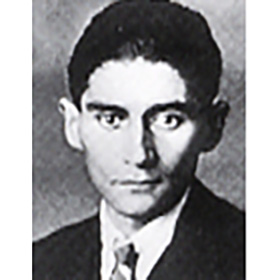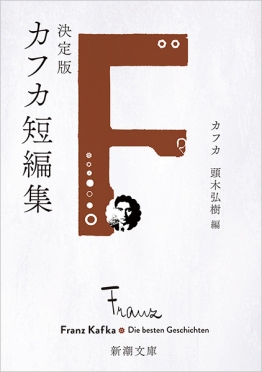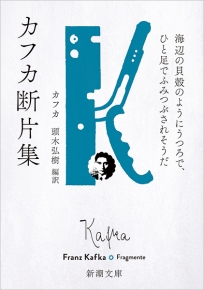
カフカ断片集―海辺の貝殻のようにうつろで、ひと足でふみつぶされそうだ―
693円(税込)
発売日:2024/05/29
- 文庫
- 電子書籍あり
断片こそカフカ! カフカの神髄ともいえる短く未完成な小説のかけらが完全新訳で登場。
カフカは完成した作品の他に、手記やノート等に多くの断片を残した。その短く、未完成な小説のかけらは人々を魅了し、断片こそがカフカだという評価もあるほど。そこに記された胸をつかれる絶望的な感情、思わず笑ってしまうほどネガティブな嘆き、不条理で不可解な物語、そして息をのむほど美しい言葉。誰よりも弱くて繊細で、人間らしく生きたカフカが贈る極上の断片集。完全新訳で登場。
書誌情報
| 読み仮名 | カフカダンペンシュウウミベノカイガラノヨウニウツロデヒトアシデフミツブサレソウダ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 緒方修一/カバー装幀 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-207107-6 |
| C-CODE | 0197 |
| 整理番号 | カ-1-5 |
| ジャンル | 文芸作品 |
| 定価 | 693円 |
| 電子書籍 価格 | 693円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2024/05/29 |
インタビュー/対談/エッセイ
「わからない」がわからせてくれること
『カフカ断片集―海辺の貝殻のようにうつろで、ひと足でふみつぶされそうだ―』(新潮文庫)からさらに厳選した13の断片。絶望的過ぎて思わず笑ってしまう言葉は疲れた心にぴったり。
●カフカについて語り合う、マルケスと安部公房
今年は、フランツ・カフカ没後100年で、安部公房生誕100年で、ガルシア=マルケスの没後10年だ。たまたま数字がきれいに並んだというだけではない。この3人の作家にはじつは深いつながりがある。
カフカが40歳で亡くなった1924年、安部公房が生まれた。そして、日本で最初のカフカの単行本『審判』(本野亨一訳 白水社)が1940年10月に刊行された。定価1円50銭。残念ながら、あまりにも早すぎる出版で、6、7冊しか売れなかったそうだ。しかし、当時高校生だった安部公房がこの本を読んでいた。本人が対談で「高校のとき読んでいるらしい」と語っている(「カフカの生命」『安部公房全集 27 1980.1-1984.11』新潮社)。
戦後になって、中田耕治があらためて安部公房に『審判』を手渡し、そこからカフカを好きになったという。その後、安部公房は1951年に『壁―S・カルマ氏の犯罪』を書いて芥川賞を受賞する。この作品はカフカの影響があると評された。
一方、マルケスは大学生のときにカフカの小説と出合う。「ボゴタ大学に在籍していたガルシア=マルケスは、ある日、友人から借りた『変身』を下宿に持ち帰ると、そのままベッドに横たわり、さっそくページをめくりはじめた。書き出しの一行を目にしたときの驚きを、ガルシア=マルケスは『ベッドから転げ落ちそうになるほどの衝撃』と振り返っている」(大西亮「解説」『落葉 他12篇』新潮社)
他にもインタビューでは、「『変身』を読んだ時に、自分はいずれ作家になるだろうと思ったんだ」「こんなことができるとは知らなかった」「それまでは学校の教科書に出てくるわかりきったお決まりの物語しか知らなかった。でも、文学にはそれとはまったく別の可能性があると気づいたんだ」(『グアバの香り――ガルシア=マルケスとの対話』木村榮一訳 岩波書店)などと語っている。
安部公房もマルケスも、カフカに強い影響を受けている。でも、3者のつながりはそれだけではない。
マルケスの『百年の孤独』(鼓直訳 新潮社)が1972年に日本で初めて出版されたとき、最初はあまり反響がなかったそうだ。それをいち早く高く評価した作家が、安部公房だった。
初めて読んだときのことをこう振り返っている。「読んで仰天してしまった。これほどの作品を、なぜ知らずにすませてしまったのだろう。もしかするとこれは一世紀に一人、二人というレベルの作家じゃないか」(「地球儀に住むガルシア・マルケス」『死に急ぐ鯨たち・もぐら日記』新潮文庫)
また「永遠のカフカ」と題された1980年の新潮社文化講演会で、「あれは絶対読んだほうがいい」と絶賛し、「カフカとは対照的な世界を書いてるけれども」「カフカの影響というものを潜在的に受けていないということは考えられないんですよ」と指摘した(『安部公房全集 27』)。
1990年、初めて来日したマルケスと会ったときのことを、安部公房は大江健三郎との対談でこう語っている。「マルケスもカフカから来ていると思う。彼にそういったら喜んでいた。『審判』かなにか読んだら、翌朝目覚めて、私は小説家になっていたって」(「対談」『安部公房全集 29 1990.1-1993.1』新潮社)
●カフカの「断片」とは?
さて、そのカフカには短編小説もあれば長編小説もある。そしてじつはその他に、膨大な断片がある。
断片とは、短い、未完成な、小説のかけらだ。
普通、未完成なものより完成したもののほうがいい。かけらより、全体のほうがいい。未完成の飛行機に乗りたい人はいない。花瓶が割れてかけらになったらがっかりだ。
しかし、カフカの場合、未完はむしろ魅力となる。「未完であるということは、カフカの作品にとってきわめて特徴的である、と言うよりもむしろその本質的な性格である」と『決定版カフカ全集』(新潮社)第2巻の訳者解題で前田敬作も書いている。『アメリカ(失踪者)』『審判(訴訟)』『城』という3つの長編も、すべて未完だ。
「永久の未完成これ完成である」(『【新】校本宮澤賢治全集』第13巻上「覚書・手帳 本文篇」筑摩書房)という宮沢賢治の言葉が、カフカにもあてはまる。
「最後まで書くことがカフカにとって至上命令ではなかったから、読者は書き手が陥る『この小説を完成させねばならない』『この小説を完成させるためには(途中で前に進めなくならないようにするためには)ここではこうはしないでおいて、こういう風にしておこう』という義務的作業に基づく計算につき合わされることがない」(保坂和志『言葉の外へ』河出文庫)
そして、小さなかけらであることも、また魅力となる。俳句や短歌がそうであるように、小さいからこそ大きな世界を内包できることもある。葉っぱの上の小さな水滴が、世界を映し込むように。松尾芭蕉は俳句について「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中にいひとむべし」という言葉を残している(土芳『三冊子』『新編日本古典文学全集88』小学館)。「現実をとらえることができたとき、そのイメージのひらめきが消えないうちに、書きとめろ」というような意味だろう。カフカも、なるべく中断なしに、一気に書こうとした。頭のなかにあるイメージを、いますぐ、なるべく早く書く。短さには、一気に書けるというよさもある。
もちろん、断片の中には、たんなるメモとか、うまく書けなくてそのままになったものもあるだろう。しかし、その多くは、“もともと断片というかたちでしか書けなかったもの”だと思う。起承転結などの型には収まらず、言葉数を増やせばかえってぼやけてしまう、純粋な結晶のような作品たち。
カフカ自身も、ある自作について、こう書いている。
「これは断片であり、またいつまでも断片のままということになるでしょう、こうした未来形が、この章に最大の完結性を与えるのです」(クルト・ヴォルフへの手紙 1913年4月4日『決定版カフカ全集9』吉田仙太郎訳 新潮社)
これまで断片だけを集めた本が、全集以外にはなかった。それはとてももったいないことだと思い、文庫という手にとりやすいかたちでまとめてみたのが、『カフカ断片集』だ。カフカを初めて読む人にも、短編や長編は読んだことがある人にも、新しいカフカの魅力と出合ってもらえたらと願っている。
●絶望と笑い
そんな『カフカ断片集』の中から、いくつかの言葉をご紹介したいと思う。
カフカの特徴と言える“絶望”と“笑い”を感じさせるものを選んでみた。
カフカは日記でも手紙でもほとんどいつも絶望している。何か大きな出来事があったからではない。カフカはカナリアのような人なのだ。炭坑で有毒ガスが出ているとまずカナリアが苦しみ出すように、他の人がまだ平気で生きている日常でも、カフカは絶望を感じる。それだけ敏感なのだ。過敏と言ってもいいだろう。
絶望があんまり突き抜けていて、笑えてしまうこともある。といっても、カフカが笑わせようとしてコミカルに書いているということではない。カフカの文章はつねに真剣で切実だ。だからこそ笑えるのだ。チャップリンが子どもの頃、近所の食肉加工場からヒツジが逃げ出したことがあり、それを捕まえようとして追いかける人が転んだり、ヒツジがはねまわったりするのを見て、大笑いしたそうだ。でも、ついにヒツジがつかまって食肉加工場に連れて行かれるとき、今度は悲しくなって、家に駆けこんで、母親の膝で泣いた。ヒツジは必死だった。だから笑えて泣けたのだ。
カフカの言葉も同じだ。笑えるときもあれば、別のときには胸にしみて涙が出ることもある。カフカは深刻なのか笑えるのかと議論になることがあるが、どちらかに限定する必要がどこにあるだろう。真剣で切実なことは、つねに滑稽でもある。
たとえば、こんな言葉だ。
家庭生活、友人関係、結婚、仕事、文学など、あらゆることに、わたしは失敗する。
いや、失敗することさえできない。
「何をやってもうまくいかない」とぼやきたくなることは誰にでもあるだろう。しかし、カフカはさらに「失敗することさえできない」とまで言う。そこまで言うかと笑ってしまいそうになる。しかし、カフカにとってはたんなる言葉遊びではなく、真剣で切実な思いだ。失敗するのは、挑戦したからだ。挑戦しなければ、失敗することもできない。カフカは挑戦しない。たとえば、結婚するかしないか迷って、生涯に3回婚約し、3回婚約破棄をする。思い切って結婚しないし、思い切って独身でいる決心もしない。だから、まさに「失敗することさえできない」のだ。
夜への怖れ。夜でないことへの怖れ。
それじゃ、いつも怖いじゃないか、と言いたくなるが、よく考えてみると、わからないでもない。夜は怖い。闇に包まれるのだから。でも昼は本当に安心だろうか。昼は昼で怖くないだろうか?
たとえば、テーブルの上のひとつの林檎。
それを見るために、せいいっぱい背伸びしなければならない小さな子どもと、
それを手でつかんで、食卓にいる人たちに自由にさしだせる主人とでは、
同じ林檎でも見え方がちがう。
たとえば林檎に「健康」をあてはめてみる。健康を失った人にとっては、健康はまぶしく輝く宝だ。しかし、健康な人にとっては、健康なだけで大喜びするのは無理だ。同じものでも、手が届くかどうかで、ぜんぜんちがう。「健康」以外にも、さまざまなものが林檎にあてはまるだろう。
すぐとなりにいる人までの道のりが、わたしにとっては、とても長い。
「すぐとなり」なのに「道のり」が「とても長い」というのは、おかしな言い方だ。しかしこれは「わかる!」という人も多いだろう。人間関係が苦手な人にとっては、相手はとても遠く感じられる。
わたしはいつでも道に迷う。
森の中だが、ちゃんと道がある。
うっそうとした暗い森だが、道の上にはわずかな空も見える。
それでもわたしは、果てしなく、絶望的に、道に迷う。
しかもわたしは、一歩、道から外れると、たちまち千歩も森に入りこんでしまう。
よるべなくひとりだ。
このまま倒れて、ずっと倒れたままでいたい……
道があるのに迷うのはおかしいと思う人もいるだろう。まして、一歩、道から外れただけで、どうして「たちまち千歩も森に入りこんでしまう」のか。大げさで笑ってしまいそうになる。しかし、現実にこういうことはあるのでは? 人生にはさまざまな道が用意されている。たとえば、学校に行って、会社に入って、結婚してというような。しかし、迷ってしまわないだろうか。そして、ちょっと外れただけなのに、たちまち……ということはないだろうか。孤独を感じ、このまま倒れていたいと思ったことはないだろうか。
正しい道筋を永遠に失ってしまった。
そのことを、人々はなんとも深く確信している。
そして、なんとも無関心でいる。
道筋を失ったのに無関心でいるというのは、おかしなことのようだが、でも、今の世界が、日本が、自分が、正しい道筋を失っていなくて、無関心でもない、と言える人がいるだろうか? 正しい道筋を見失ったことを確信しながら、でも目をそらし、無関心でいることで、なんとか日々を送ってはいないだろうか。
だれ? 川岸の並木の下を行くのはだれ?
すっかり見捨てられているのはだれ?
もうどうしようもないのはだれ?
草が生えているのはだれのお墓?
川をさかのぼって、はしごで川岸をのぼって、夢がやってきた。
立ちどまって、夢たちと言葉を交わす。夢はいろんなことを知っている。でも、自分たちがどこから来たかは知らない。
秋の夕暮れはとてもおだやかだ。
夢が川のほうを向き、両腕を上げる。
両腕を上げたのに、なぜわたしたちを抱きしめてくれないのだろう?
どういう意味なのか、よくわからない。だけど、なんとなくひきつけられないだろうか? カフカの言葉にはよく意味のわからないものも多い。今の世の中はわかりやすいものが人気だが、「なんだかわからないけどイイ!」と感じることができるのも、また楽しいものだ。カフカの“わからなさの魅力”もぜひ味わってほしい。
安部公房もこう言っている。「解釈はほとんど無数にある。一つのカフカ論にはどうしても収まりきらない。そしてカフカが人を惹きつけるのは、その多様性なんだ。どんなふうにでも解釈できる、存在としての自律性だね」(「『方舟さくら丸』を書いた安部公房氏に聞く」『安部公房全集 28 1984.11-1989.12』新潮社)
ここで私が書いている解説も、だからそんな解釈のひとつにすぎない。ぜんぜんちがう読み方も、いくらだってできるはずだ。
でも、雨のしずくが頭に落ちてくるのは、我慢ができない。ささいなことのようだが、まさにそのささいなことが我慢できないんだ。いや、もしかすると我慢できるのかもしれないが、ささいなことを避けられないのが我慢ならないんだ。実際、自分の身を守るすべがないんだ。帽子をかぶっても、傘をさしても、頭の上に板をのせてみても、なんの助けにもならない。雨はなんでも通り抜けてしまうから。通り抜けているんじゃないとしたら、帽子、傘、板の下で、同じ激しさの雨が新たに降りだしているんだ。
断片の、さらに一部分だけを引用してみた。帽子、傘、板の下で雨が降るというのは、なんだかシュールなイメージだが、でも、全体的にはわかる気のする人も多いだろう。ささいな不快がつづいて、どうにも我慢できないことはあるものだ。我慢できないほどのことではないはずと思ってみるが、やっぱりきつい。それは「ささいなことを避けられないのが我慢ならない」からなのかもしれない。
だれかがつくった贋の風景のなかで生きている。
照明が明るくなれば朝で、すぐに暗くなればもう夜。
単純なごまかしだ。しかし、舞台にいるあいだは、従わなければならない。
ただ、もし逃げ出せるだけの力があるなら、そうしてもかまわないのだ。背景に向かっていって、スクリーンを切り裂き、そこに描かれた空がきれぎれの布となって舞うなかを通り抜け、そこらに置いてある小道具をとび越えて、現実のほうへ、せまくて暗くて湿っぽい路地へと。
その路地は、劇場に近いので昔から劇場通りと呼ばれてはいるが、本物の路地だし、本物が持つすべての深みをそなえている。
映画「トゥルーマン・ショー」(1998年)を思い出す人もいるだろう。今の現実はまやかしで、みんな演技をしていて、じつは本当の現実が別にあるのではないか。そんな思いにとらわれたことのある人なら、共感できるはずだ。周囲の現実に「本物が持つすべての深み」を感じることができないのだ。
わたしはいちども木にくっついていたことがなく、秋風に吹かれて舞う木の葉ではあるけれども、どの木の木の葉でもないのだ。
木の葉なのに、「いちども木にくっついていたことがなく」「どの木の木の葉でもない」ということはありえない。わけのわからない文章とも言える。しかし、家庭にも、学校にも、会社にも、地域にも、どこにも属することができないと感じている人は、決して少なくないのでは。自分を他の人たちと同じ人間とは思えなくて、でも人間として生きるしかなく、ただ「秋風に吹かれて舞う」しかないという思い。
いつでも準備はできている。どこにでも引っ越せる。
だから、ずっと故郷にいる。
これは私はすごく身につまされる。変えようと思えば人生をがらっと変えることもできるのではと思いながら、けっきょくそのままでいる。「やればできる」と思いながら、やらないのだ。やってもできないことがこわくて、変化がこわくて、あるいはただ怠惰なために。
彼はいつだって準備不足だ。
それは自分がいけないのだ、と思うことさえ彼にはできない。
というのも、いついかなる時でも準備ができているように責め立てられるこの生活のなかで、準備をする時間がどこにあるだろう。
たとえ時間があったとしても、なにが起きるのかわからないうちから、準備ができるだろうか。人が決めたことならまだしも、自然に起きることを、次々と切り抜けていくことなど、そもそもできるだろうか?
そういうわけで、彼はもうずっと以前から、車輪の下敷きになっている。
おかしなことでもあり、また、なぐさめにもなるのだが、彼はそうなってしまうことへの準備が、他のどんなことへの準備よりもできていなかった。
さっきは「いつでも準備はできている」と言っておきながら、今度は「いつだって準備不足だ」と言っている。これも断片のよさだ。断片どうしが矛盾している。そのときそのときの思いを書いているからだ。体系的なものだったら、矛盾は欠点になるが、断片ではむしろ長所だ。だって、人間は矛盾したものではないだろうか。
この言葉は、仕事にもはてはまるだろうし、人生全体にもあてはまるだろう。歳をとることも、わかっていながら準備できないことのひとつだ。なにしろ、三十代にしても五十代にしても、人はいつもそれを初めて体験するのだから。準備できるはずがない。
本とは、
ぼくらの内の氷結した海を砕く
斧でなければならない。
これは断片作品ではなく、私が『カフカ断片集』の「編訳者解説」の中で引用した、カフカの手紙の中の言葉だ。
カフカが理想の本について書いている一節だが、カフカ自身の言葉が、まさに「ぼくらの内の氷結した海を砕く斧」だと思う。
最後に、先にも引用した「永遠のカフカ」と題された講演会から、安部公房によるカフカのすすめの言葉を。
「読んでない人がいたらね、その人は幸せです、これから読めるんだから。でも、僕も二回目、三回目と読んでも、これは前読んだ話だとならない。発見が繰り返し出てきます。でも、読んでいない人はうらやましいぐらいだよ」
(かしらぎ・ひろき 文学紹介者)
もう死んでいるから、その人らしく開花する
カフカ没後100年だ。1924年6月3日、40歳でカフカは亡くなった(41歳の誕生日のちょうど1カ月前だった)。
生前にカフカはこんなことを書いている。
ある人物に対する、後世の人たちの判断が、同時代の人たちの判断よりも正しいのは、その人物がもう死んでいるからである。
人は、死んだあとにはじめて、ひとりきりになったときにはじめて、その人らしく開花する。
死とは、死者にとって、煙突掃除人の土曜の夜のようなもので、身体から煤を洗い落とすのだ。
(1920年の手記 拙訳『カフカ断片集―海辺の貝殻のようにうつろで、ひと足でふみつぶされそうだ―』新潮文庫)
この言葉にしたがえば、没後100年たった今こそ、カフカは「その人らしく開花する」と言えるのかもしれない。
生前はほとんど無名だったカフカだが、今では世界中で読まれている。まさに「後世の人たちの判断が、同時代の人たちの判断よりも正しい」という状況だ。
そして、SNSなどを見ていると、カフカを初めて読んだ人が「なんだ、これは!」とびっくりしている。その衝撃は今も新鮮で、「当時は斬新な作品でした」などという説明は不要だ。これは驚くべきことではないだろうか。
ガルシア=マルケスの『百年の孤独』が文庫化されることが話題だが、マルケスが作家になろうと思ったのも、カフカがきっかけだ。若いときにカフカの小説を初めて読んで、「ベッドから転げ落ちそうになるほどの衝撃」を受けたそうだ(「解説」大西亮『落葉 他12篇』新潮社)。
「こんなことができるとは知らなかった」「それまでは学校の教科書に出てくるわかりきったお決まりの物語しか知らなかった。でも、文学にはそれとはまったく別の可能性があると気づいたんだ」とインタビューでも語っている(『グアバの香り――ガルシア=マルケスとの対話』木村榮一訳 岩波書店)。
カフカが亡くなった年に生まれた安部公房は、今年が生誕100年だが、「今読んでも全く昔の小説だとは思えない」「そのままの状態でいまだに全然衰えを見せず、もし名前を全然知らない人が今読んだとしたら、これは新しい人が出てきたと思うでしょう」(「永遠のカフカ」)、「時間が経てば経つほどカフカの大きさが分ってくる」(「カフカの生命」)と語っている(『安部公房全集 27 1980.1-1984.11』新潮社)。
ただ、カフカ自身は自分の原稿を焼却するように遺言している。今でも私たちがカフカの作品を読めるのは親友のブロートが遺稿を守ってくれたからだ。ナチス・ドイツがプラハを占領する前夜に、遺稿を詰め込んだトランクを抱えてかろうじて逃げ出したこともあった。
燃やすように言ったとはいえ、カフカ自身にも愛着のある作品はあった。たとえば『判決』という短編について、「この物語はまるで本物の誕生のように脂や粘液で蔽われてぼくのなかから生れてきた」と日記に書いている(1913年2月11日)。その他にも、「ぼくは『火夫』をとてもよくできたと思っていた」(1913年5月24日の日記)、「『田舎医者』のような作品なら、ぼくも一時的な満足を覚えることができる」(1917年9月25日の日記)など、自分でほめている作品も、少ないながらある(『決定版カフカ全集7 日記』谷口茂訳 新潮社)。
そういう作品を集めたのが、『決定版カフカ短編集』だ。
また、この100年のあいだに、多くの読者から愛されてきた作品もある。たとえば、無生物とも生物ともつかない不思議なオドラデクの出てくる『父の気がかり』という作品など。「後世の人たちの判断」は正しいわけで、そういう作品も収録した。
カフカの作品には長編、短編のほかに、じつはたくさんの断片がある。短い、未完成な、小説のかけらだ。私はカフカの作品はすべて好きだが、なかでもとくに断片がたまらなく好きだ。完成品より未完成品が好きというのは、変に思うかもしれないが、ロダンのトルソ(頭や手足の欠けた彫刻)のように、カフカの断片には、完成した作品にはない、独特の魅力がある。たんに完成途中で放棄されたのではなく、“もともと断片というかたちでしか書けなかったもの”もあると思う。
そういう断片を集めたのが、『カフカ断片集』だ。これまで断片だけを集めた本がなかった。全集にはそういう巻もあったが、今は入手困難だ。文庫で断片を読めるようになれば、多くの人に新しいカフカの魅力と出合ってもらえるのではないか。初めてカフカを読む人にも、短編や長編は読んでいる人にも。そういう思いで、この断片集を編訳した。ぜひ手にとってみていただけたらと願っている。
(かしらぎ・ひろき 文学紹介者)
著者プロフィール
フランツ・カフカ
Kafka,Franz
(1883-1924)オーストリア=ハンガリー帝国領のプラハで、ユダヤ人の商家に生れる。プラハ大学で法学を修めた後、肺結核に斃れるまで実直に勤めた労働者傷害保険協会での日々は、官僚機構の冷酷奇怪な幻像を生む土壌となる。生前発表された「変身」、死後注目を集めることになる「審判」「城」等、人間存在の不条理を主題とするシュルレアリスム風の作品群を残している。現代実存主義文学の先駆者。
頭木弘樹
カシラギ・ヒロキ
文学紹介者。筑波大学卒。編訳書に『絶望名人カフカの人生論』『絶望名人カフカ×希望名人ゲーテ』、編著に『決定版カフカ短編集』など。