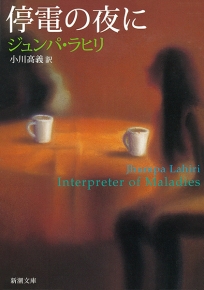
停電の夜に
737円(税込)
発売日:2003/02/28
- 文庫
鮮烈な感動の一撃。なまじのスリラー小説など吹き飛ばすほどサスペンスフル!
毎夜1時間の停電の夜に、ロウソクの灯りのもとで隠し事を打ち明けあう若夫婦──「停電の夜に」。観光で訪れたインドで、なぜか夫への内緒事をタクシー運転手に打ち明ける妻──「病気の通訳」。夫婦、家族など親しい関係の中に存在する亀裂を、みずみずしい感性と端麗な文章で表す9編。ピュリツァー賞など著名な文学賞を総なめにした、インド系新人作家の鮮烈なデビュー短編集。
書誌情報
| 読み仮名 | テイデンノヨルニ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 発行形態 | 文庫 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 336ページ |
| ISBN | 978-4-10-214211-0 |
| C-CODE | 0197 |
| 整理番号 | ラ-16-1 |
| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |
| 定価 | 737円 |
書評
処方箋を出さない観察者
午後八時から九時まで、吹雪でやられた電線の復旧工事のため、一帯が停電になるという。それも、五日間。午後八時といえば夕食の時間だ。このところ顔をつきあわせるのを避けつづけ、食事さえそれぞれの部屋で勝手に済ませてきたふたりも、暗闇のなかでは食卓に留まらざるをえない。弱々しい蝋燭の光を頼りに食事がはじまると、妻が突然、いままで黙っていたことを告白しあいましょうと提案する。停電はどんなに長引いてもいつか復旧する。過去の重石をひとつずつ取り払っていく打ち明け話にも、危機は早晩乗り越えられるというかすかな希望が込められているようで、じっさい闇のなかの対話は新しい習慣を生み出し、ふたりの距離を縮めそうな気配を漂わせもする。だが、心のなかの明かりは本当に灯されるのだろうか。
1967年生まれのインド系アメリカ人、ジュンパ・ラヒリの処女短篇集『停電の夜に』の表題作は、そんな状況のなかで互いの傷をまさぐるように展開していく。彼女の小説に登場するのは、多くの場合、カルカッタ出身のベンガル人を両親に持ち、ロンドンで生まれて幼少時にアメリカへ渡った彼女自身の来歴に近しい、移民とその周辺の人々である。新天地の環境や文化や人間関係を受け入れ、そこに順応しようと試行錯誤を繰り返しながら、けっして容易ではないその道筋のあちこちで登場人物が直面する、いわば存在の根にかかわる身の置きどころのなさを、ラヒリはひとつひとつ丁寧に見つめる――関係のどん詰まりや、癒しがたい孤独を描くばかりでなく、そこからの再生の可能性をも、絶妙のさじ加減でほのめかしながら。
むろん合衆国という、強固なまとまりを見せてはいるものの、一種の仮想現実に等しい多民族国家の、足もとの危うさを摘出するだけならさしたる新味はない。ラヒリの世界が読者に信頼感を抱かせる理由のひとつは、親たちの祖国にも、また生まれ育った米国にも心の底で馴染めず、じぶんの《家》は《ここ》にないとの喪失感が、そうした現実にこれから直面しようとしている世代の無垢と感応し、双方をいち段成長させるところにある。たとえば、独立運動さなかのパキスタンに妻と七人の娘を残したまま不安な日々を過ごしているインド人植物学者との交流の一時期を十歳の少女の目で描く「ピルザダさんが食事に来たころ」や、新鮮な魚を手に入れられないことに大きなフラストレーションを感じているインド人女性が孤独をまぎらわすかのようにベビーシッターをはじめ、やってきた男の子に祖国への抑えがたい郷愁を晒してしまう「セン夫人の家」の二篇には、アメリカでの生活に先立つ時空をいつまでも大事に抱えた人々に対する、子どもならではの直観的な理解と残酷な「見切り」が、ふかく捉えられている。
ラヒリの世界を独創的なものに仕立てているもうひとつの大きな理由は、移民として「はるかに遠い人を思う」ことと、身近な他者である夫や妻への無理解が表裏の関係に置かれている点だ。「ふたり」単位の孤独のなかに、香辛料の効いた料理やサリーといったまぎれもない祖国の痕跡が刻印され、そうした慣習や食生活の持続、あるいは放棄が、かえって「ここ」と「むこう」の遠さを炙りだしている。その手つきの巧みさは、原書の表題作である「病気の通訳」や「神の恵みの家」を一読すれば明白だが、先の「停電の夜に」において、それはいっそう強く感じられるだろう。
予定より一日早く工事が終わったのに、妻の希望で、五日目の晩も彼らは蝋燭を灯して告白ゲームをつづける。だが蝋燭が尽きそうになったところで彼女はそれを吹き消し、今度は電灯をつけて話したいと言って、いきなり別れ話を持ち出す。彼らの関係を狂わせた直接の原因と、妻の言葉に対抗して夫が投げつけた切り札については、ここで触れることができないけれど、いずれにせよ妻は取り乱し、四日ぶりに灯した明かりを自ら消してしまう。少々大袈裟に言えば、停電の闇を拒むことで、彼女は自分自身の闇を選びとったのだ。作者はその闇の可能性に賭け、彼らが「はるかに遠い人を思う」ように互いを見つめ合えるようになるのか、それとも完全に離反してしまうのかを宙づりにしたまま、物語を切りあげる。
ラヒリの主人公たちに巣くっているのは、アメリカを新しい祖国として選んだ移民たちのみならず、現代人の誰もが冒された不安の病だとも言えるだろう。「病気の通訳」とは、だから登場人物の職業というより、作者自身の立場を指し示すものだ。相対する他者の病状を通訳するだけで自ら処方箋は出さない、慎重で冷静で、なおかつ慈悲深い観察者の位置。それが若き才筆の依って立つ、美しい倫理である。
(ほりえ・としゆき フランス文学)
波 2000年9月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
ジュンパ・ラヒリ
Lahiri,Jhumpa
1967年、ロンドン生まれ。両親ともコルカタ出身のベンガル人。2歳で渡米。コロンビア大学、ボストン大学大学院を経て、1999年「病気の通訳」でO・ヘンリー賞、同作収録の『停電の夜に』でピュリツァー賞、PEN/ヘミングウェイ賞、ニューヨーカー新人賞ほか受賞。2003年、長篇小説『その名にちなんで』発表。2008年刊行の『見知らぬ場所』でフランク・オコナー国際短篇賞を受賞。2013年、長篇小説『低地』を発表。家族とともにローマに移住し、イタリア語での創作を開始。2015年、エッセイ『ベつの言葉で』、2018年、長篇小説『わたしのいるところ』を発表。2022年からコロンビア大学で教鞭を執る。
小川高義
オガワ・タカヨシ
1956年横浜生まれ。東大大学院修士課程修了。翻訳家。ホーソーン『緋文字』、ヘミングウェイ『老人と海』、ジェイムズ『ねじの回転』、ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『見知らぬ場所』『低地』、トム・ハンクス『変わったタイプ』、『ここから世界が始まる トルーマン・カポーティ初期短篇集』、エリザベス・ストラウト『ああ、ウィリアム!』など訳書多数。著書に『翻訳の秘密』がある。


































