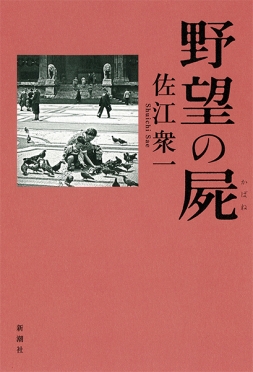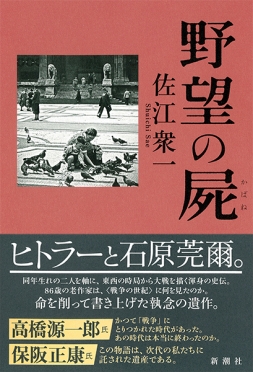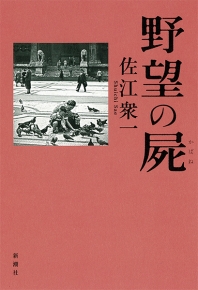
野望の屍
2,200円(税込)
発売日:2021/01/27
- 書籍
- 電子書籍あり
ヒトラーと石原莞爾。同年生れの二人を軸に東西の時局から大戦を描く渾身の史伝。
一九二五年、刊行直後の『我が闘争』を熟読した石原はその野心をたぎらせていた。高まる自国主義のなかで共振する日独、満州の謀略。国家のスローガンに万歳が応え、日常は塗り潰されていく。そして瓦解、夥しい死者。冷静に史実を叙述しながら八六歳の作家は〈戦争の世紀〉に何を見たのか。命を削って書き上げた執念の遺作。
第1章 ヒトラーの“ベルリン進軍”
第2章 ドイツ留学の石原莞爾
第3章 ランツベルク監獄と『
第4章 理想と野心
第5章 関東軍の謀略
第6章 昭和テロリズムと謀略の満州
第7章 ヒトラー首相となる 松岡洋右、国際連盟脱退
第8章 皇太子誕生と二・二六事件
第9章 国民政府を相手とせず
第10章 日独伊三国同盟締結
第11章 対ソ戦か対米戦か。「最初の半年か一年はずいぶんと暴れてご覧に入れます」
第12章 チャーチルとルーズベルトの原爆開発計画
第13章 虚構と真実のノルマンディ上陸作戦
第14章 ヒトラー地下壕で新妻と自殺 マクダの少女たち悲惨
終章 草むす
書誌情報
| 読み仮名 | ヤボウノカバネ |
|---|---|
| 装幀 | Alamy/カバー写真、PPS通信社/カバー写真、新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 288ページ |
| ISBN | 978-4-10-309020-5 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 2,200円 |
| 電子書籍 価格 | 2,200円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2021/01/27 |
書評
あの日、ヒトラーを見た私
昨秋に亡くなった佐江衆一氏の御遺作『野望の屍』をいただいた。
佐江氏には何度か御目にかかったが、取り立てて親しいというほどではない。御著書をいただくのも初めてだった。けれども、表紙を見て思い出した。以前にお会いした時、私がむかし、ドイツにいて、ヒトラーを見たとお話ししたことがある。それを覚えておられて、この御本を送るよう手配して下さっていたのだろうと思った。
さっそく拝読した。たいそうおもしろかった。私はこどものころ、中国各地で暮し、上海では蒋介石の邸の隣に住んでいたから、その点でも興味深かった。
1927(昭和2)年8月に神戸で生れた私は、11月には日本郵船の伏見丸に乗って欧州へ向かった。銀行勤めの父が、ハンブルクへ転勤になったのである。母の話では、1928年の1月1日に、マルセーユへ着いたという。
私がもの心ついたのはハンブルク時代で、庭の広い一戸建てで、隣家のドイツ人のお姉さんが、よく遊んでくれた。その後、父がベルリンへ出張所を開くよう命じられ、ベルリンへ移った。ベルリンでは、マンション住まいだった。女中のケーテがかわいがってくれた。
ヒトラーが台頭したのは、そのころである。
ベルリンで最初に住んだのは、カスタニアーレという通りの五階建てマンションの五階だったそうだが、わずかしか住まず、私は覚えていない。次に移ったのが、アムパーク十五番地のマンションで、ここはよく覚えている。ここも五階建てで、一フロアが一戸になっている。私どもは二階に住んだ。
マンションと云っても、かなり広い。玄関を入るとホール、その奥の客間には、大家さんが残していったものと、私の母のもの、二台のグランド・ピアノがあったが、まだ広々としていた。続いてダーメン・チンマ(婦人用客間)、ヘーアン・チンマ(父の書斎)、寝室、食堂、子供部屋、女中部屋、台所、浴室などがある。
向いのマンションには、当時、人気の映画スター、マルレーネ・ディートリッヒが住んでおり、ときどき見かけた。
私どものマンションの持ち主は、資産家のユダヤ人で、ナチスが勢いを得てきたため、危険を感じ、市外のワンゼー(湖)のほとりの別荘に移り、あとを家具つきで、私どもに貸したという。
一度、招かれて、別荘へ遊びに行ったことがある。両親が食堂で御馳走になっている間、私は退屈して、廊下をぶらぶら歩きまわった。通りかかった部屋のドアを開けると、そこは不要な道具をしまっておくところらしく、雑多な家具の間に、私の背丈より高い白い物が見えた。近寄ってみると、それは白鳥の羽だった。なんだか怖くなって、あわててそこを出たのを覚えている。
別荘には芝生の広い庭があり、湖までななめに続いていた。のちに映画で、これとそっくりの別荘が舞台になっているのを、見たことがある。
日本へ帰ってからも、両親はときどき、大家さんのことを思い出して、話していた。ひどい目に遭っていないだろうか、アメリカへでも逃げていればいいが、と云っていた。
ベルリンでは、私はいつも、ケーテにくっついて歩いていた。日常会話はドイツ語で、親ともドイツ語で話した。日本へ帰ったとき、日本語が話せず、小学校へ上がる直前だったので、親が心配して、当時、住んでいた東京・阿佐ヶ谷の幼稚園に通わせた。私はたちまち日本語で話すようになり、ドイツ語は頭から抜けてしまった。
そのドイツ語だが、家へ来たドイツ人の客に云わせると、田舎訛が強いという。私のドイツ語は、女中のケーテから覚えたもので、ケーテは田舎の出身だったらしい。
ケーテが近所の小間物屋へ、糸や針を買いに行くときも、私はついて行った。店の主人は、いつも黒い服を着た、陰気な感じの中年の女性で、ユダヤ人だという。大家さんもそうだが、つまり、ユダヤ人はベルリン市内に溶けこんで暮していたのである。
私がヒトラーに興味を抱くのは、どうしてあれほどユダヤ人を排斥し、いじめたか、ということである。日本でも、関東大震災の折、在日朝鮮人をひどい目に遭わせた。が、それは一過性に過ぎない。
ヒトラーの場合、まず宗教が背景にありそうだ。すくなくとも、口実にはなるだろう。
日本人は宗教の受け入れに寛容だが、ヨーロッパ人は、そうはいかない。日本人は神式で結婚式を挙げ、人が亡くなれば仏式で葬儀をする。神様も仏教も、有難い対象で片づけてしまう。
ベルリンの人たちは、日曜日には必ず、教会へ行く。父は学生時代、銀座教会で洗礼を受け、一応、クリスチャンだが、日曜ごとに教会へ行くことはない。
キリスト教徒とユダヤ教徒。そこには、日本人にはちょっと理解不能の溝が、あるのかも知れない。
ヒトラーが勢力を増してきたある日、父は六歳の私を連れて、ヒトラーの邸の前に行った。その日は、ヒトラーの誕生日だった。邸の二階のバルコニーに、ヒトラーが姿を現すと、バルコニーの下に集まった群衆が何事か叫んで手を振る。それに対して、ヒトラーが手を振り返す。たいそうなさわぎだった。
私の見たところ、群衆の大半は、十七、八歳から二十代前半の、若い女性だった。金髪で色白、ふくよかな女の子たちで、美しいというより、素朴で無邪気といった印象だった。
なぜ父は、そんなところへ私を連れて行ったのだろうか。
銀行勤めの父のもとには、新しいニュースがどんどん入る。ヒトラーの台頭によって、第一次大戦後の疲弊したドイツに、なにか変化が起こる、そう感じて、当のヒトラーがどんな男なのか、自分の眼で見たかったのではないか。男一人より幼い女の子を連れていれば無難に見える。ついでに私に、歴史に残る人物を見せてやろう、そんなところか。
幼い私の印象では、ヒトラーはごく普通の男性で、なぜ女の子たちがキャアキャアさわぐのか、わけがわからなかった。
実は母もヒトラーを見ている。カイザーホーフといったか、ベルリンのホテルで、日本人の夫人たちのお茶の会があった。ホールにいると、大階段を、お供を連れたヒトラーが降りてきた。
私が大人になったあと、その話を聞き、「どんな人だった?」と尋ねた。母はいつも冷静な人で、その時も、「小さい人だったわ」と答えただけだった。それが印象のすべてらしい。
九十三歳になる私は、最近、ユダヤ人関係の本を選んで読んでいる。たとえばサーシャ・バッチャーニの『月下の犯罪』(伊東信宏訳、講談社)、深緑野分氏の『ベルリンは晴れているか』(筑摩書房)、クリストファー・R・ブラウニングの『普通の人びと』(谷喬夫訳、筑摩書房)等。
しかし、読めば読むほど、わからなくなってくる。
私がベルリンで体験したように、ユダヤ人は市民に溶け込んでいた。いや、私にはそう見えた。
私の住むマンションの前には、道路一つ隔てて公園がある。冬には池が氷って、スケートができる。小山があり、橇ですべり下りて遊ぶ。私は同年輩の金髪の男の子と仲よくなり、よくいっしょに遊んだ。ほかにも友だちができたが、ドイツ人かユダヤ人かで差別する、などといった経験は、一度もない。
日本人にはわからないだけで、ひそかな差別は、あったのだろうか。
佐江衆一氏の『野望の屍』を読むと、ヒトラーがいかにたくみに権力を握っていくかが、よくわかる。
しかし、それは一方で、喜んで彼を受け入れていくドイツ民族がいたためである。誕生日にバルコニーで手を振るヒトラーと、熱狂する女性たち、その光景を思い出すと、当時のドイツ人たちの心情が、どうであったか、よく理解できるように思われる。
私の父は、ヒトラーの、そしてナチスの危険なことを、よく知っていた。むろん、口には出さなかったが。
1933(昭和8)年に、父が横浜の本店勤務になり、私どもは照国丸で帰国した。偶然、渡欧の時の伏見丸と同じ大矢船長で、私を見て「大きくなったね」と云って下さった。
その後、父は中国の天津・上海・営口などを経て横浜本店に転勤した。1941(昭和16)年のこと。
横浜に上陸すると、ホテルニューグランドに二、三日滞在した。たまたま訪日中の「ヒトラー・ユーゲント」の少年たちと、泊まり合わせた。彼らと廊下ですれちがうとき、声をかけたかったが、きまりが悪く、黙って通り過ぎた。彼等は帰国後、どんな運命を辿っただろうか。
ヒトラーは公式には、生涯、独身を通した。誕生日のあのさわぎを見れば、その意義もわかる。
いったい、ヒトラーとは、どんな男だったのだろうか。のちにチャップリンが演じているが、ほんとうに、チャップリンと一脈、通じたところがあるような気がする。本人は大まじめだが、はたから見れば、ちょっと滑稽な男。
そんな男とユダヤ人の関係が、私にはどうしてもわからない。あのアウシュヴィッツの悲劇、あれほどのことが、どうして起こったのか。
おそらく日本人であるかぎり、まず、理解することはできないのではないか。そう思いながら、今日もあれこれ、読んでいる。
(あんざい・あつこ 作家)
波 2021年5月号より
単行本刊行時掲載
遺作の重み、そして敬意
佐江衆一さんの遺作(『野望の屍』)を一読して深い感慨を覚えた。ああ作家として書きたかったテーマは、この点にあったのか、というように思える。昭和9年生まれ、太平洋戦争の始まった時は小学校(当時は国民学校と言ったが)の二年生であり、終戦時は六年生である。戦時下には東京からの疎開を体験している。世代論を持ち出すわけではないが、佐江さんの世代は少年期の戦時下体験が心理的な影になっている。
大体がこの世代の作家はあの戦争に巡り合わせたが故の作品を書く。佐江さんもこの10年余前から、満州開拓団を書いた『昭和質店の客』や回天隊員を描いた『兄よ、蒼き海に眠れ』などを発表している。そしてこの『野望の屍』で、歴史の潮流を戦争時代に生きた少年の決着と覚悟で書かれたように思う。私たちはこういう指導者の作った時代に生かされたのだとの確認である。むろんこれを批判するとか恨みで書くというのではなく、ひとりの庶民がどのようにこの時代を見つめるか、といった姿勢を崩さずに書かれている。そのことが逆にこの作品に深みを与えていて、読者に改めて自分の生きている時代の確認を迫っているとも言える。
舞台は1923年(大正12年)のミュンヘンのビヤホールから始まる。ナチ党の党首ヒトラーが取り巻きと聴衆の中央に座る。国家主義者のワイマール体制批判に耳を傾けながら、演説が佳境に入ると、ヒトラーは拳銃を天井に向けて撃ち、驚く聴衆を尻目に壇上に登る。そして、激烈な演説を始める。「共産主義者とユダヤ人どもがのさばるワイマール共和国政府を我々の一撃で倒す」というのだ。この出だしは、ヒトラーが登場するミュンヘン一揆の前夜祭のような演説会だが、佐江さんはこの場面にナチ党が持つ、あらゆる特徴を含めて書いているので、第一次世界大戦後のドイツの社会的混乱が全て盛り込まれている。
つまり暴力と反ユダヤ、戦勝国への憎悪、そして何より復讐の心理である。
続いてその頃にドイツに駐在して、第一次世界大戦そのものを研究、分析する日本陸軍の中堅将校の代表的人物である石原莞爾を語っていく。この頃には石原よりも4、5歳上の永田鉄山、小畑敏四郎、岡村寧次、東條英機らがいて、やはり国家総力戦の研究をしている。しかしそういう将校とは別に、ドイツ社会の惨憺たる状況を正確に受け止める感性知性をもつ石原の存在に佐江さんは着目したのであろう。
加えて石原は日蓮宗の国柱会の信仰員として、日々の生活を律している。国柱会の創始者である田中智学の上野公園での演説が、ドイツの荒廃状況を見る石原に想起されてくる。「父親、夫、兄弟、息子を大戦でなくし、国破れたドイツ人を、われわれ大和民族の日本人がベルサイユ条約で裁きうるや!」。石原の心底に「日蓮宗信者の軍人」という像が浮かんでくる。
石原はドイツの著名な軍人や歴史学者に教えを乞い、その過程でヒトラーという一兵士が、「ドイツ民族純血の“
むろん本書はヒトラーと石原莞爾の動きを精密に追っているわけではない。ただしドイツは確かにヒトラーとその周辺の指導者により、野望が着々と形を作っていき、やがて滅びる歴史だが、日本はむしろ石原を疎外する形で軍事主導体制が崩壊していく。佐江さんは日本の軍事総体が主語となって崩壊する様を描きながら、この国の無責任体制が浮き彫りになるような形でまとめていく。そのことに気がつくと、本書に託した佐江さんの思いは、極めて重いというべきであろう。最後のページで、アジア各地で戦死した日本軍の兵士たちは、屍と化してなお「太平洋の彼方の祖国を見つめつづけている」と書く。そういう何百万の人々が、「今なお(この国の)明日を縛っている」という語が、この書のモチーフだということにもなろうか。
あえてもう一点、本書の読み方を私なりに提示しておきたい。私見では、いずれ歴史的には第一次世界大戦と第二次世界大戦は連結していて、20世紀の「1914年から1945年までの戦争」と言われるだろう。第一次世界大戦の終結から第二次世界大戦の始まりまでの21年間は戦間期と言われるが、実は「平和」が煙草を吸って一服していたにすぎない。次の戦争の準備期間だったのである。
この間の人物の動きを直視し、作品化したことに、佐江さんの遺作の重みがあると、私は受け止めた。そのことに敬意を表したい。
(ほさか・まさやす 作家)
波 2021年2月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
佐江衆一
サエ・シュウイチ
(1934-2020)1934年、東京生まれ。1960年、短篇「背」で作家デビュー。1990年『北の海明け』で新田次郎文学賞受賞。1995年、『黄落』でドゥマゴ文学賞受賞。自身の老老介護を赤裸々に描いてベストセラーに。1996年『江戸職人綺譚』で中山義秀文学賞受賞。著書に『横浜ストリートライフ』『わが屍は野に捨てよ――一遍遊行』『長きこの夜』『動かぬが勝』のほか、『昭和質店の客』『兄よ、蒼き海に眠れ』『エンディング・パラダイス』の昭和戦争三部作など。古武道技術師範。『野望の屍』は最後の作品として取り組んだ渾身の史伝である。2020年10月逝去。享年86。