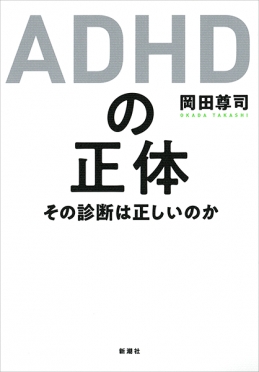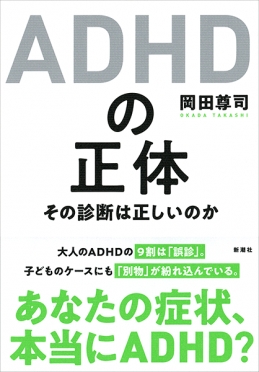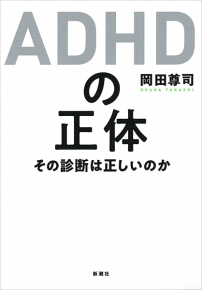
ADHDの正体―その診断は正しいのか―
1,485円(税込)
発売日:2020/04/15
- 書籍
- 電子書籍あり
その症状、ADHDではありません。「誤診」乱発はなぜ起こる?
大人のADHDの9割は「誤診」。子どものケースにも見分けのつきにくい「別物」が多数紛れ込んでいる。安易な診断と投薬は、むしろ症状を悪化させかねない。セカンドオピニオンを求め来院する人たちを診察し続ける精神科医の著者が、診療実績と世界各国の研究報告を踏まえ、最先端の実情から対策と予防法まで徹底解説。
書誌情報
| 読み仮名 | エーディーエイチディーノショウタイソノシンダンハタダシイノカ |
|---|---|
| 装幀 | 新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-339382-5 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | 心理学、家庭医学・健康 |
| 定価 | 1,485円 |
| 電子書籍 価格 | 1,485円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2020/04/24 |
書評
その症状、本当に「大人のADHD」ですか
数年前から、著名人が「自分は発達障害だった」とカミングアウトするようになった。インターネット上でも自己紹介の一環のように、自身を発達障害だと語る人が目につく。実際、精神科でそのように診断される人は増えている。発達障害は子ども特有のもの、というのは昔の話だ。大人になってからの診断で、ようやくわかったという感じである。そうした大人の発達障害には、注意欠如や落ち着きのなさが特徴のADHDや、コミュニケーションが取りづらくなりがちなASD(アスペルガー症候群とも言われていた)がある。その両方を備えていることもある。
こうした世相と呼応するように、本書の第一章に興味深い症例が出てくる。64歳の男性Uさん。子どもの頃の成績は優秀だったが友だちはほとんどいなかった。テレビ業界に入ってからは目覚ましい成果も上げていたものの、ずっと生きづらさを抱え、50代で精神科を受診し、抗うつ剤を飲む日々となった。60歳で退職し無気力な日々を過ごしていたが、大人の発達障害を扱ったテレビ番組を見て、自分はこれではないかと思い至った。診断を受けたところ大人の発達障害とわかり、SSRI(抗うつ剤)に加え、コンサータが処方された。しかし、症状が改善した実感はない。
この症例は本書の問題提起を象徴的に示している。そもそも「大人の発達障害」や「大人のADHD」とは何か。近年そういう診断を受ける人が増えている背景には、どういう事情があるのか。診断・投薬を受けても、なぜ症状が改善されないのか。そのコンサータっていうお薬は何?
本書はこうした「大人の発達障害」、特に「大人のADHD」が近年増えてきた実態について、最先端の研究成果を含む医学資料の読み直しと臨床経験を基に、その仕組みや背景を、正直、ここまでするかというほどに根気よく追究している。
そもそも「大人のADHD」と診断されている実態は何か。著者が打ち出す仮説は世界の常識を一変させてしまう。「大人のADHD」は、本来子どもが診断対象であった発達障害の延長で起きる症例ではなく、別の原因による症状かもしれない、というのだ。著者はこれを仮に「疑似ADHD」として考察を深化させる。
なるほどと私は思う。先の64歳のUさんの生きづらさや診断への希求は、まさに63歳の私に重なるからだ。現状、「大人のADHD」と診断されている事例には、著者の言う「疑似ADHD」が多く含まれているのではないか。その疑念と追究は、私のような読者には衝撃的ですらあった。
「大人のADHD」という診断と投薬によって、現在の症状が改善されるなら、それでいい。それなら診断と投薬はその人を支えている。しかし、「生きづらさ」を抱えつつも、コンサータなどの投薬が効かないし、症例が改善されていないという問題を抱えている人には、本書の提言は重要な意味を持つだろう。
誤解なきように付記すれば、本書は発達障害の診断のもとになる精神疾患の国際的な基準「DSM-5」を否定するものではない。現状ADHDと診断されている実態には次の4種類があるのではないかと考察しているのである。
(1)発達障害による本来のADHD
(2)本来のADHDが環境要因で悪化している
(3)愛着障害など養育要因から疑似ADHDとなっている
(4)養育要因以外の理由で疑似ADHDとなっている
こうした精密な考察から見えてくるのは、生きづらさを実感している人それぞれの経験や環境要因を精査する必要性であろう。「あなたは大人のADHDです。このお薬で改善されます」といった明快な答えが得られないとしても、投薬の再検討により副作用を減らすこともできるし、真の問題改善の端緒が得られるかもしれない。
また本書はこうした「大人のADHD」の問題に加え、発達障害と診断された子どもにかかわる大人のあり方についても十分な提言を行っている。発達障害の子どもを抱える親や教師にも、多くの示唆が得られるだろう。
例えば、発達障害の子どもの学童期には、押さえつけ型の教育をしても反発だけが大きくなる。問題点に目を向けるより、まず理解者となり、精神的な安全基地となることが大切である。また、親として否定的な態度にとらわれているときには、自分自身の親との関係を見直すことで事態を客観的に扱えるようになる。
発達障害や生きづらさに安易な答えはない。著者は「地道な内省とかかわりの先にこそ、根治への道は続いている」という。本書は強い励ましになるだろう。
(ファイナルベント ブロガー)
波 2020年5月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
岡田尊司
オカダ・タカシ
岡田クリニック院長。精神科医。1960年香川県に生まれる。東京大学文学部哲学科に学ぶも、象牙の塔にこもることに疑問を抱き、医学を志す。京都大学医学部で学んだ後、同大学院精神医学教室などで研究に従事しながら、京都医療少年院、京都府立洛南病院などに勤務。2013年に岡田クリニック(大阪府枚方市)を開院したのは、生きづらさを感じながら日々を過ごしている人が気軽に相談できる身近な「安全基地」になりたいとの思いからだった。『脳内汚染』(文藝春秋)、『愛着障害』(光文社新書)、『人間アレルギー』(新潮社)など多くの著作を通じても、人々の悩みや不安に向き合っている。