
アメリカ最後の実験
1,650円(税込)
発売日:2016/01/29
- 書籍
ここではないどこか、誰も書いたことがない世界を書きたい――気鋭の作家の新感覚小説!
失踪した音楽家の父を捜すため、西海岸の難関音楽学校を受験する脩(シュウ)。そこで遭遇する連鎖殺人――「アメリカ最初の殺人」とは? ピアニストの脩が体感する〈音楽の神秘〉。才能に、理想に、家族に、愛に――傷ついた者たちが荒野の果てで掴むものは――西海岸の風をまとって、音楽が響き渡る……著者新境地のサスペンス長編。
第二章 千年のつくりもの
第三章 虚無への供物
第四章 ソドムの真ん中の清教徒(ピューリタン)
第五章 ロメロゾンビのいない夜
第六章 最終試験
第七章 ルート66
書誌情報
| 読み仮名 | アメリカサイゴノジッケン |
|---|---|
| 雑誌から生まれた本 | yom yomから生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 256ページ |
| ISBN | 978-4-10-339811-0 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | ミステリー・サスペンス・ハードボイルド |
| 定価 | 1,650円 |
書評
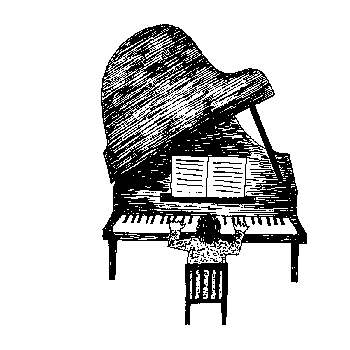
音楽とアメリカと謎――多面的な野心作
宮内悠介の新作の主題が音楽であると聞いた時、わずかに不安を覚えたことは告白しておくべきだろう。
音楽を主題にした小説にはいいものが少ない――もちろんそれは個人的な見解であるが、少なからぬ数の読者が賛同してくれるのではないかと思う。
面白いものになるのが難しい理由は、書き手があまりに主題を愛しすぎるせいである。書き手のその愛はしばしば信仰に近づく。迷いのない信仰に基づく作品が、小説として面白くないのはまあ当然だろう。「ストーンズがおれに生き方を教えてくれた」などの意識で書かれた小説の面白さが限定的であることはかなり明白である。
音楽小説が興味深いものになるのは、音楽そのものではなく、それに関連するオブセッションを描いた時だろう。そしてほっとしたことに『アメリカ最後の実験』もまたそのような方向で書かれた作品だった。ジャズって素晴らしいな、といったものではなかったのである。
中心人物は日本人の若いピアノ奏者脩で、脩がアメリカの音楽学校「グレッグ音楽院」の難易度がきわめて高い入学試験を受けるというのが、メインのストーリーである。
脩が入学試験を受けようと考えたのは、音楽的な野心からではない。脩は母親と自分を棄てるようにしてアメリカに渡った、やはりピアノ奏者である父親に会おうと考えた。父親はグレッグ音楽院で学んだ後、音楽の活動をしていたが、行方知れずになっていて、音楽院を受験すれば父親が自分に目を向けるはずだという思いが動機だった。
試験は長丁場で、同じ立場のプレイヤーとの交情も読みどころになっている。マフィアのボスの息子で、有りあまる才能を見せる少年ザカリー、スキンヘッドで巨躯だが温厚なマッシモ、暗い思想を持ったヒスパニック系のリロイ。
そして実技の二次試験の際に試験場で思わぬことが起こる。建物内のミーティングルームで人が殺されるのである。さらにホワイトボードに以下の文字があった。
〈The First Experiment of America〉
その事件はべつの事件を呼ぶ。アメリカ第二の実験、アメリカ第三の実験が各地で起こる。いずれも殺人で、インターネットにその動画が溢れる。このあたりの気味の悪さはひじょうに魅力的で、予言的な印象を与える。
ストーリーは入学試験と実験を軸に進む。しかし同時に一貫して漂うのは音楽論的なアトモスフィアである。音楽とは何か、あるいは音楽を認識する意識とは何か、という問題に関する考察が処々に現れ、それらは作品に現代文学的なニュアンスを加味している。また謎があるという点で、この長篇は哲学的なミステリーとも形容できる。第三章の章題「虚無への供物」でも分かるように。
そして本作にはもうひとつ大きなモティーフがある。北アメリカである。
伝記的なことに触れるのは少しばかり躊躇われるが、十二歳の時まで著者はアメリカ在住だったらしく、かの国にたいする複雑な思いが見え隠れしているようでもある。
そして本書を読んでいるあいだ、わたしはわたし自身の「アメリカ最初の実験」を思い浮かべていた。
北アメリカに移住した者たちはインディアンたちをほぼ壊滅状態に追いこんだわけであるが、さすがに寝覚めが悪かったのか、その行いの正当性を証するものを欲した。それが「
脩の父親が使っていたシンセサイザー「パンドラ」の存在は興味深い。パンドラはピアノでは出せないブルースの音程「ブルーノート」を、トーンホイールなどの操作なしで発音することができる。鍵盤情報をパンドラ自身がリアルタイムで判断して、第三音を微細に補正するのである。もちろん脩の演奏するパンドラを実際に聴くことはできないが、かれの弾いた「イッツ・ア・スモールワールド」は、音程面ではきわめて野蛮で官能的だったはずである。
宮内悠介が音楽的異物を描くにあたって技術や音色ではなく音程に注目したことはおそらく妥当であろう。何より音程こそが音楽における貨幣であり言語なのだ。
(にしざき・けん 作家、翻訳家、音楽家)
波 2016年2月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
音楽・アメリカ・荒野、そして家族
――この小説は、音楽が一つの大切なキーワードですが、人生最初に意識した音楽体験はどんなものでしたか?
一、二歳のころ、大竹伸朗氏が当時結成したノイズバンド「JUKE/19」の音楽を家族がかけていて、それを好んで聴いていたとのことです。してみると、私の音楽体験はノイズからはじまったということになります。これを人生にカウントしていいものか、迷うところではありますが(笑)。
――それではこれまでの人生最強の音楽体験は?
高校のころに入ったクラブです。まさにいま新たな音楽が生まれつつあり、それに立ち会っているのだという確かな肌触りがありました。「出尽くしている」というシニカルな観点からすれば、それは錯覚であるのですが、こうした錯覚こそが、あらゆる誕生の礎でもあるのだと信じます。
――書くことと音楽にはどのような相関があると思いますか。この小説の基本のモチベーションはどんなことだったのでしょうか?
先のクラブなのですが、実を申しますと、上手く乗って踊ることができず、友人に笑われました。ただ、このとき乗れなかったことの疎外感によってこそ、文章を書く資格を得られたような感も、ないではありません。
――現代の電子音楽に対して、大切なアイテムとしてパンドラという謎の楽器が登場しますが、作者としてはどんな形状、音色をイメージしていますか。
一言で言えば、アナログとデジタルの境界を突破し、境界を無化する楽器です。比喩的に言えば、それは電子が生み出すアコースティックであり、紙に書かれた電子書籍でもあります。かつて、電子楽器の開発に携わっていたことがありまして、〈パンドラ〉はその際に着想を得ました。
――もう一つの要素である西海岸のイメージはどんなご経験に根ざして、広がっていったのでしょうか?
四歳のときに家族の都合でアメリカへ渡ったのですが、最初に降り立ったのがサンフランシスコでした。憶えているのは、居候先の家族が街頭でTシャツを売っていたことや、買ってきたココナッツが割れずに石で叩き割ったこと、海へ延びる長い桟橋を見て、あれはどこへつづいているのだろうと幼心に考えたことなどです。
――ご自身のアメリカ体験とこの作品に出てくるアメリカに重なるところがあるとしたら、どんなところでしょうか。
主人公である脩は、アウェーである海外で知略を働かせ、音楽をゲームと割り切り、難関の音楽学校を受験するピアニストです。ある種のダークヒーローであるのですが、慣れない海外で戸惑い、差別を受け、思うように言葉も話せなかった私がなりたかった、もう一人の自分でもあります。
――これまでの作品とこの小説で、創作について変化(進化、深化)してきたことがありましたら、教えてください。あるいは意識して変えていることなどはありますか。
いま、お答えするにあたって昔のメモを見たところ、「音楽版『グラップラー刃牙』」とありました(笑)。と言いますのも、『アメリカ最後の実験』は私にとって、はじめての連載作品となります。ですから、これまでよりも引きや物語性を重視し、読む側も書く側も、先へ先へと進めるような展開を目指しました。テーマ面では前作『エクソダス症候群』と対をなすところもありますが、まったく別個の作品としてお楽しみいただければと考えています。
――今後の作品について、どんなご予定がありますか。
次は〈疑似科学シリーズ〉と銘打って連載をしていた短編集が、講談社から刊行される予定です。ほかにも、たまっている原稿が多数ありますので、今年を収穫の時期にできましたらと……。
――読者にお伝えしたいことがありましたら、どうぞ。
今作は音楽のほかに、もう一つテーマがありまして、それは家族や疑似家族、そしていわゆる機能不全家族です。『アメリカ最後の実験』にはさまざまな家族の形が登場しますが、さらにそれを包括するものとして、アメリカという一つの国家を、巨大な疑似家族に見立ててもいます。
今回、「才能に、理想に、家族に、愛に――傷ついた者たちが荒野の果てで掴むものは」というキャッチをつけていただきました。やや面映ゆくもあるのですが、まさに才能や理想、家族や愛をときに追い求め、ときに縛られ、焦がれ、あるいは傷ついた人たちへ、なんらかの未来像を示すことができれば、作者としてそれに勝る喜びはありません。
(みやうち・ゆうすけ 作家)
波 2016年2月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
宮内悠介
ミヤウチ・ユウスケ
1979(昭和54)年東京生れ。1992(平成4)年までニューヨーク在住、早稲田大学第一文学部卒。在学中はワセダミステリクラブに所属。2012年の単行本デビュー作『盤上の夜』は直木賞候補となり、日本SF大賞を受賞。2013年、『ヨハネスブルグの天使たち』も直木賞候補となり、日本SF大賞特別賞を受賞した。同年に「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」を受賞。2016年、『アメリカ最後の実験』が山本周五郎賞候補になる。2017年、『彼女がエスパーだったころ』で吉川英治文学新人賞、前年芥川賞候補となった『カブールの園』で三島由紀夫賞を受賞した。同年、『あとは野となれ大和撫子』は直木賞候補に、「ディレイ・エフェクト」は芥川賞候補に選ばれた。エンタメ、純文学の双方からその才能を注目される作家の一人である。

































