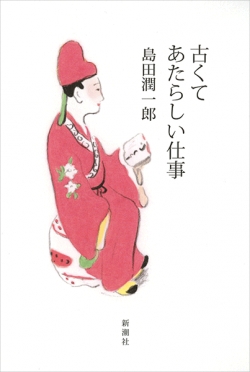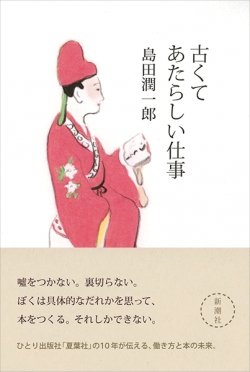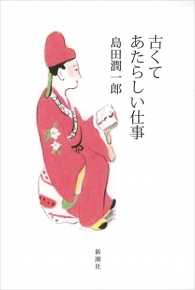
古くてあたらしい仕事
2,200円(税込)
発売日:2019/11/27
- 書籍
嘘をつかない。裏切らない。ぼくは具体的なだれかを思って、本をつくる。それしかできない。
転職活動で50社連続不採用、従兄の死をきっかけに33歳でひとり出版社を起業した。編集未経験から手探りの本づくり、苦手な営業をとおして肌で触れた書店の現場。たったひとりで全部やる、小さな仕事だからできること。大量生産・大量消費以前のやりかたを現代に蘇らせる「夏葉社」の10年が伝える、これからの働き方と本の未来。
書誌情報
| 読み仮名 | フルクテアタラシイシゴト |
|---|---|
| 装幀 | 南伸坊/装幀 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-352961-3 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 2,200円 |
書評
誠実に仕事をすることはまだ可能だ
年に三冊、二五〇〇部の本を作れば、ぼくと家族は暮らせますよ、という話を島田さんから直接うかがった時に、とても感動したことをよく覚えている。わたしとしては訊きにくい話題だったのだけれども、島田さんはあっさりと答えてくれた。事業の話は、ネットで語られていることはもちろん、対面でもあまりに個人の固有の生き方や方法論の話でありすぎて、他の人への応用が利きにくいのかなと思い始めていた矢先のことだった。要するに模倣しにくくて、普遍性を探しにくい。事業主個人のエネルギーの物語に収束してしまうことが多い。それはそれでおもしろければいい(というか事実ならおもしろくさえなくてもいい)かもしれないけれども、わたしはどこかで、もっと自分やほかの同年代の人たちに当てはめて考えやすい具体的な話を探していた。そこに気負いなく具体例を提示してくれたのが島田さんだった。
この本でも、島田さんはとても具体的に、自分はどういう来し方の人間で、なぜ出版社をやろうと思い立ち、どういうふうに運営しているか、ということを語ってくれる。たとえば、島田さんが夏葉社を設立するきっかけになったのは、島田さんと年の近い従兄を亡くした叔父さんと叔母さんに、ヘンリー・スコット・ホランドという神学者の詩を一冊の本に仕立てて贈ってあげたかったからだという。島田さんは、叔父さんや叔母さんと同じような境遇の人にも本が届いたらと思い、始めは友人の編集者にそれを頼んでいたのだが、なかなかうまく進まないので、自分でやろうと考えて夏葉社を造ったそうだ。
島田さんが起業すると同時に作った事業計画書の「事業目的」は、以下のようなものだ。「何度も読み返される、定番といわれるような本を、一冊々々妥協せずにつくることによって、長期的な利益を確保する。そのために、会社を応援してくれる本屋さんを全国に一〇〇店舗開拓し、それらの店を重点的に営業していく」。感心するのは、この開拓する「一〇〇店舗」という数字に、ちゃんとした根拠があることだった。島田さんは三〇歳の時に一年ほど教科書の会社にいて営業をしていたのだが、その時に担当していた高校がそのぐらいだったという。そしてその店舗を、北海道から沖縄まで自分の足で回り、きちんとした人間関係を築いて、その上で本を売ってもらう。どの書店を回るかについては、ある出版社のホームページにあがっている書店リストを参考にしたことまで、島田さんは語っている。
自分の仕事を静かに解体し、その意味や意図について一つ一つ明快に説明してくれる島田さんの言葉に、わたしはいつのまにかとても勇気づけられていた。こんなに地に足を着けて出版社の経営のような難しい仕事をして、それを誠実に語ってくれる島田さんのようなパーソナリティの人がしっかりやっていけるのなら、自分もまだやれるかもしれない。
他の人がちゃんと生きているなら、自分もなんとか身を正して生きていけそうな気がすると思うようなことはある。でもそう思うには「ちゃんとしている」ことに普遍性がなければいけない。「この自分だからこそできた」という目配せは、その普遍性を濁らせる。一方で、驕らない、自分のエネルギーに依存しない、そして細部を明確にする島田さんの仕事の語り方には、誰もがそれぞれの人生に応用できるのではと思えるような強い普遍性がある。この本は、必ず誰かの心をしっかりと支えるはずだ。あとがきで島田さんが語っている息子さんへの「学校に行き、落ち込んでいるクラスメートがいたら、その人のそばにいてほしい。会社に行き、なにかに思い悩んでいる人がいたら、その人を食事に誘ってあげてほしい。そういう大人になってほしい」という言葉は、そのままこの本の在り方を示している。本書は、落ち込んでいる時にそばにいてくれて、仕事で悩んでいる時に「まあごはんでも行こうよ」と言ってくれるような本だ。
本を薦める時に、あまり対象を限定した物言いをすべきではないと思うのだけれども、この本は例外的に、1978年生まれのわたしや、1976年生まれの島田さん自身と年の近い人に是非読んでほしいと思う。本書は、ロスジェネとか氷河期と勝手に名付けられた、社会の上の階層にいる心の冷たいおじいさんやおじさんたちの過失によって作り出された一つの世代の苦しみに伴走する。たとえ時代に損なわれるようなことがあったとしても、自分たちは誠実であることができるし、地道な努力を重ねながら、やりたいことだってできるということを、この本は信頼させてくれるはずだ。
(つむら・きくこ 作家)
波 2019年12月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

本がもたらしてくれるもの
ひとり出版社・夏葉社をはじめて10周年を迎えた島田潤一郎さん。新著『古くてあたらしい仕事』に描かれたのは転職活動がうまくいかず苦悩した日々や大切なひとのための一冊の本づくり、そして今日にいたるまで。誰かを蹴落とすのではなく、自分のできることに力を尽くすその姿が多くの人の心を動かしています。夏葉社の本の愛読者で、初の新聞連載にして第三作となる長編小説『人間』を刊行された又吉直樹さんと創作と本をめぐってお話しいただきました。
どうしても書きたかったこと
又吉『古くてあたらしい仕事』すごく面白かったです。体温を感じられる文章で、これはどうしても伝えたかったんだろうなというのを感じました。
島田 本当ですか。ありがとうございます。おかげさまで夏葉社をはじめて、十年になりました。又吉さん、デビューは何年ですか。
又吉 僕は2000年デビューなので、ちょうど二十年目です。
島田 二十周年ですか、すごい。おめでとうございます。続けていると、自分のスタイルのようなものができていくわけですよね。又吉さんのお仕事を見ていると、それを壊しながら進んでいるように感じます。
又吉 最初は何もわからない状態で芸人をやりはじめたので、はたして自分は芸人なのか、という違和感がずっとありました。十年位経つと、自然とお客さんにも芸風が浸透して、「又吉らしいな」と劇場で笑ってもらえるようになったのが、2010年にテレビに出始めたら、まったく通用しなくて、またすべてが崩れ落ちていって(笑)。
島田 確かに、テレビに出始めた頃の又吉さんはそういうイメージがありました。いまより青白かったというか。
又吉 メイク室で誰に頼んだらいいのかわからないから、ノーメイクで出ていた時期があったんです。それで、顔色悪い、顔色悪いって言われて(笑)。
島田 又吉さんが書かれる小説も一作目、二作目、三作目と経験が積み重なっていくことでどんどん掘り下げられて、どこまで潜るんだろうって、今回『人間』を読んで感じました。これまで芸人の又吉さんと作家の又吉さんを分けて考えていたけれど、こうした大きな小説になったことではじめて又吉さんが目指しているものが見えて、すごい感動しました。
又吉 三作目だからこういう書き方になって、また次は全然違うかもしれないですけど、登場人物と自分の距離みたいなことをどうしても僕は言われやすいので。それは僕を芸人と知っている人が本を手にとってくれるからで、ひとまずそれを完全に受け入れようと思いました。
島田 又吉さん自身ともとれる影島と主人公の対話の場面はスリリングですごい迫力がありました。同時にこれはどこにたどり着くのだろうと読み進めていくと、3章で沖縄に舞台が移って、お父さんとのくだりが始まるんです。影島との対話の重みみたいなものと、お父さまのあの感じが、人間としては同じ価値で描かれている。それが『人間』のすごいところなんだと思いました。
又吉 ああ、うれしいです。沖縄は書けてよかったところで、実は書くのが怖いところでもあったんで。自分でもこれは何なんやろ、読んだ人きっと戸惑うやろうな、と思いながら。でも、書きたかったんです。
島田 あそこがあってよかったです。
又吉 意外とみんな戸惑わずに読んでくれているみたいで、小説の途中で一回、僕のこと嫌いになりそうになったけど、最後まで読んでよかったなんて感想もありました。
他では味わえない豊かな時間
島田 僕、本や小説のすばらしいところは扱う時間が長いところだと思っていて。読みながらいろんなことを考えるし、そういうメディアは他にない気がするんです。映画も二時間観ながらいろいろ考えるけれど、本はもっと長く物語に入り込みながら自分の人生を考えることができる。だから、僕はこういう長い小説がとくに好きなんです。他では味わえない豊かな時間を与えてくれるから。
又吉 僕が小説を好きな理由もそういうところです。島田さんが本の中で引用されていた「本屋は勝者のための空間ではなく、敗者のための空間なんじゃないかと思っている」という山下賢二さん(京都・ホホホ座店主)の言葉が、滅茶苦茶よくわかるんです。二十代半ばくらいの頃、僕も毎日書店を何軒も回っていて、小説の棚をずっと見ていたから。なんかしんどい夜に、自動販売機が息継ぎする場所で、古本屋が宿みたいな感じでした(笑)。
島田 この間、あるドキュメンタリーで、末期ガンのミュージシャンが「もう本とか買わないんですか」と聞かれて、「本はものを買うのと同時に、コンサートのチケットと一緒で、未来の時間を買っている。だから、僕はもう本は買わない」と答えていたんです。僕は本をものとして愛しているけれど、それだけでなく本を買うときに、未来の本を読む時間そのものを買っていて、例えば、いま仕事が忙しいけれど、終わったらこの本を読もうと思うことが、生きる希望のように思えることってやっぱりあると思うから。
又吉 本当にそうですよね。しかも読んでいる時間は仮に一時間だったとしても、そこから得ている時間は一時間どころではなかったりする。自分の人生の時間は有限で変化しないけれど、本を読むことでその時間は膨らんでいくから、実は延命装置になっているじゃないかという気もします。
島田 ああ、そうかもしれない。その時間が蓄積されて、僕はいま四十三歳ですけど、もしかしたら頭や心のなかは五十歳くらいになっているのかもしれなくて。それが何か直接役に立つのかはわからないけれど、その七年分位の時間の厚みが緩衝材みたいになって、すごい人生の役に立っているように感じます。
又吉 あと、感情移入して小説を読んでいて、その主人公が人を殺めてしまったとき、それは実人生ではあってはいけないことだけど、どこか自分が体験したかのように感じることってあるわけで。そう考えると、本って、やっぱりすごいですよね。
島田 僕の母は元気ですけど、小説の中ではもう何回も母の死を疑似体験していて、そうしたことが生きるうえで支えになってくれるから。
小さな舞台だからできること
島田 僕もしんどかった二十代、本にお世話になったから恩返しをしたい気持ちがあるんです。ただ僕は出版社なので、作家の感覚というのはまた違うのかなと思うんですけど。
又吉 好きな本をテレビで紹介していた頃は、僕も島田さんの感覚と近かったと思うんですけど、自分で小説を書きはじめたら、こんなにも自由な表現方法はないなって。あまりに自由度が高過ぎて、やめられないんじゃないかなって思うくらいです。
島田 それはすごい(笑)。
又吉 島田さんが出版社をはじめた理由と似ていて、僕もあらゆる選択肢の中から芸人になったのではなく、他に何もできなくて唯一できるかもと思えたのが、お笑いを中心とした表現なんです。ただ、自分の中に本当はこんな感覚もあるけど、お笑いに特化すると、この部分は出しづらいなと思うこともあって、それをかろうじてエッセイでフォローしていたのが、小説を書いたら、小説はすべてを含むんだと気づいたんです。これまで取材を受けたときに僕は、「お笑いの中に小説がある」と答えてきたんですけど、それは同時に逆でもあった。だから僕にとっては、書かなあかんから書くのではなくて、書かざるを得ない感じなんです。
島田 僕の場合は、完全にものとして本が先にあって、百二十八ページのハードカバーの本をつくろう、というように本のかたちがまずある。そこから作家。あと僕は基本二千五百部で考えているんですね。本にも書きましたが、誰もやらない仕事をやらなきゃという思いが強くある。他のひとがやっていることをしてもしょうがないから。ただ今の出版業界はどうしても売り上げ先行になりやすいから、テレビでいうと確実に視聴率のとれるものばかりになってしまう。でも二千五百部なら、ある程度自由にできる。
又吉 それは僕が小さい劇場でライブを続ける理由と一緒ですね。いきなりゴールデン番組でネタをやれと言われても、イチかバチかのネタはできない。でも、二、三百人くらいの、もしかしたら大失敗しかねないことを理解してくれる人や、むしろそれを期待している人たちの前で、新しいことをどんどんやって、そこで鍛えたネタをさらに大きな舞台に持っていきたい。小さなところで成立したものなら、大きなところでも伝わるはずだってどこかで思っていて。実際には伝わらないことも多いんですけど(笑)。でも、たまに伝わるときがあるんです。イケた、みたいなときが。
島田 お笑いはもっと自由で、なんでもできるんだと。
又吉 僕はあたらしいものだけが面白いとは思わないんですけど、あたらしさは間違いなく魅力のひとつじゃないですか。だから、そこを使わないのはもったいなすぎるなって。
島田 本当ですよね。そのバランスがいつも迷うところで。
又吉 二千五百部って、僕の感覚からしたらすごいですよ。劇場に二千五百人集めようと思ったら、何日公演せなあかんのって。しかも本は無料じゃないんで。だからいろいろ言われるけれど、やっぱり読者はいて、まったく絶滅してないんです。
島田 ああ、そうですよね。その言葉を聞けただけ,でも、よかったです。
百人いたら百人みんな違う社会に
又吉 あたらしい小さな書店が各地にできていて、それが希望だと本の中で書かれていましたよね。僕もそういうのをやってみたいんです。小さな書店の奥にバーカウンターがあって、さらに朗読とかコントができる小さな舞台があったらいいなって(笑)。
島田 それは人気出そうですね。
又吉 僕自身テレビに出て、話題にしてもらっているから、一見違うように見られると思うんですけど、たぶん大事やと思っていることは島田さんの感覚とかなり近いように思います。
島田 本当ですか。
又吉 小さい書店はどんな本を置いているか棚を見ながら、店主と対話するような面白さがありますよね。その一方で、大型書店は品揃えがよくて、欲しいものを買えるよさがある。お笑いも本来、劇場に週何回か出て生きていく芸人がいてよかったはずなのに、いつもテレビに出ている芸人以外は売れていないと言われるような、一つの価値基準に嵌められるのがすごく嫌で、あらゆる表現や、あらゆる本のあり方が許されるようであったらいいのになって思うんです。
島田 本当にそうですよね。
又吉 島田さん、一年でも長くこの仕事を続けていけたらって本の中で書かれていましたよね。
島田 自分が十年後どうなっていたいか全然わからないんですけど、できるだけ長く続けたいのと、あと、世の中がもう少しよくなってほしいなと思っています。スピードがどんどん速くなって、わかりやすい言葉ばかりが流通する世の中でなく、みんなもう少し立ち止まって考えて自分の言葉を持つことができたら、やっぱり違う個性になっていくわけだから。百人いたら百人みんな違う社会になるといいなって。そのために、本のもつ力は大きいような気がするんです。
(またよし・なおき 芸人・作家)
(しまだ・じゅんいちろう 編集者)
波 2020年2月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
島田潤一郎
シマダ・ジュンイチロウ
1976(昭和51)年、高知県生れ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。大学卒業後、アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが挫折。2009(平成21)年9月に33歳で夏葉社を起業。ひとり出版社のさきがけとなり、2019(令和元)年に10周年を迎えた。著書に『あしたから出版社』『90年代の若者たち』『電車のなかで本を読む』などがある。