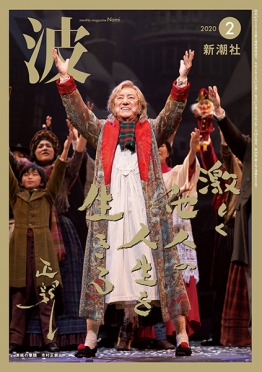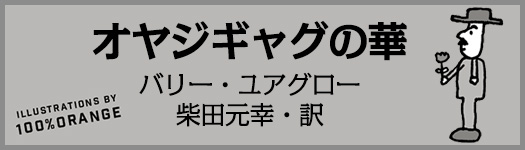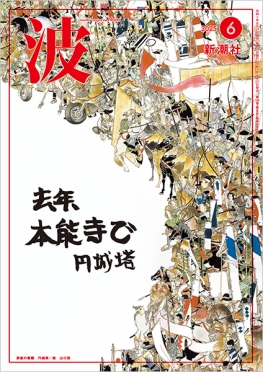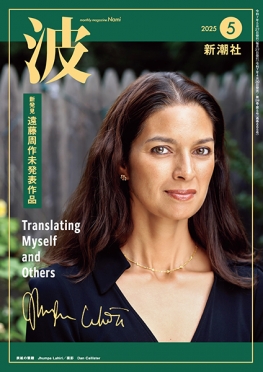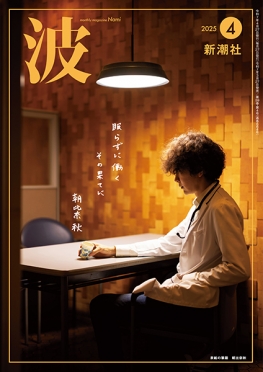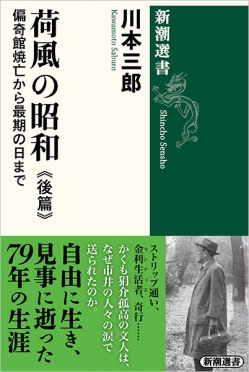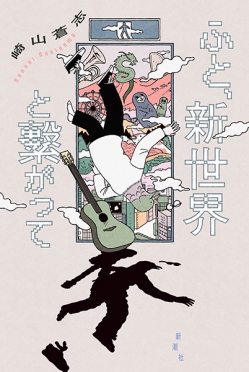今月の表紙は、市村正親さん。
波 2020年2月号
(毎月27日発売)
| 発売日 | 2020/01/28 |
|---|---|
| JANコード | 4910068230201 |
| 定価 | 100円(税込) |
阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第29回
【追悼 坪内祐三さん】
重松 清/ゆっくりと別れたかったよ。
【今野 敏『清明―隠蔽捜査8―』刊行記念】
[インタビュー]今野 敏/「隠蔽捜査」はこうして生まれた
【古市憲寿『奈落』刊行記念】
[マンガ]東村アキコ/古市憲寿氏の『奈落』を読みました……
市村正親『役者ほど素敵な商売はない』
草笛光子/役者としての人生を無駄なく生きている
シーグリッド・ヌーネス、村松 潔/訳『友だち』(新潮クレスト・ブックス)
江國香織/言葉があるが故の哀しみ
伴田良輔、今村規子、山岸吉郎、河西見佳『懐かしいお菓子―武井武雄の『日本郷土菓子図譜』を味わう―』
平松洋子/思わず指を伸ばしたくなる
瀬戸晴海『マトリ―厚労省麻薬取締官―』(新潮新書)
池上 彰/「マトリ」が赤裸々に明かす薬物犯罪史
木内 昇『
鏡 リュウジ/「なぜ女性は占い好き?」と訊かれたら
村木美涼『箱とキツネと、パイナップル』
村木美涼/両親の本棚―新潮ミステリー大賞優秀賞受賞作『箱とキツネと、パイナップル』を書くまで―
入江敦彦『京都でお買いもん―御つくりおきの楽しみ―』
千 宗屋/「ご縁」という御つくりおき
宇野維正、田中宗一郎『2010s』
西寺郷太/ポップ・カルチャーをめぐる甘美な
西尾幹二『歴史の真贋』
片山杜秀/神話で虚無を超えて行け!
ドミニク・チェン『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために―』
伊藤亜紗/風景とともにある知
【島田潤一郎『古くてあたらしい仕事』刊行記念】
[対談]又吉直樹×島田潤一郎/本がもたらしてくれるもの
【芸術新潮2019年12月号「これだけは見ておきたい2020年美術展ベスト25」発売記念】
[対談]山下裕二×成相 肇/美術展ゆく年くる年 2019年のベスト&2020年はこれが来る!
【特集 落語入門 2020】
南沢奈央、イラスト・黒田硫黄/今日も寄席に行きたくなって 第2回
[対談]北村 薫×柳家喬太郎/「落語の本質」って何でしょう!?
【今月の新潮文庫】
藤井太洋『ワン・モア・ヌーク』
大森 望/新国立競技場で核爆発? 日本の現実を暴き出す
【私の好きな新潮文庫】
階戸瑠李/背中を押してくれる物語
白石一文『ここは私たちのいない場所』
窪 美澄『晴天の迷いクジラ』
道尾秀介『ノエル―a story of stories―』
【コラム】
三枝昂之・小澤 實/掌のうた
[新潮新書]
笹山敬輔『興行師列伝―愛と裏切りの近代芸能史―』
笹山敬輔/日本「興行」噺
[とんぼの本]
とんぼの本編集室だより
【連載】
ブレイディみかこ/ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 第26回
バリー・ユアグロー 柴田元幸 訳/オヤジギャグの華 第10回
永田和宏/あなたと出会って、それから…… 第2回
瀧井朝世/サイン、コサイン、偏愛レビュー 第119回
小松 貴/にっぽん怪虫記 第2回
会田弘継/「内なる日本」をたどって 第8回
川本三郎/荷風の昭和 第21回
編輯後記 新潮社の新刊案内 編集長から
立ち読み
編集長から
今月の表紙は、市村正親さん。
◎佐藤優さんの新潮講座を受講するため(33頁広告参照)、正月休みに『カラマーゾフの兄弟』を読みました。高校生の頃、ヴォネガットの『スローターハウス5』で「人生について知っておくべきことは、すべて『カラマーゾフ』に書かれている。でも、それだけではもう足りないんだ」(大意)という殺し文句に出会い、思わず手に取って(飛ばし読みして)から久々の再読。
◎当時は一体何を読んでいたんだろと呆れるくらい、夢中になれる面白い小説です(今更こんなことを書くのは莫迦みたいでしょう)。気がついたのは最近の小説にも『カラ兄』の残響が聴こえることで、例えば五木寛之さんの『親鸞』の聖人の死はゾシマ長老を踏まえているでしょうし、大審問官の問答は筒井康隆さんの『モナドの領域』にこだましているし、生きたまま皮を剥かれる捕虜の
◎石原慎太郎さんと坂本忠雄さんの対話集『昔は面白かったな―回想の文壇交友録―』でも回想されていた、石原・江藤淳・大江健三郎・開高健各氏の伝説的座談会がありますが、そこでの大江さんの発言。「この前僕は、十何回目かにドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読んだ。江藤さんにしても石原さんにしても、俺はアリョーシャとして、俺はドミートリイとして、俺はイワンとしてというふうに読んだことを覚えているでしょう。今度読んで僕がどう思ったかというと、あっ、俺はフョードルの側から読んでいるということだね。フョードルは、五十七歳だぜ。大体僕らの年齢ね」。これもまた、一冊の本が決して一冊では終らない好例ですね。
▽次号の刊行は二月二十七日です。
お知らせ
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。
創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。
創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。
現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。
これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。