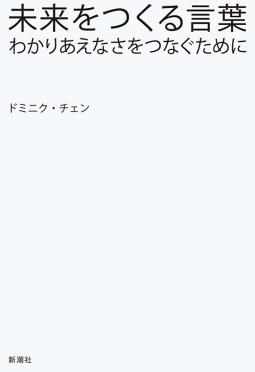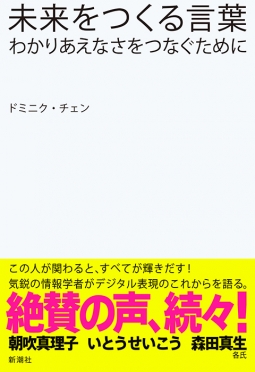未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために―
1,980円(税込)
発売日:2020/01/22
- 書籍
この人が関わると物事が輝く! 気鋭の情報学者がデジタル表現の未来を語る。
ぬか床をロボットにしたらどうなる? 人気作家の執筆をライブで共に味わう方法は? 遺言を書くこの切なさは画面に現れるのか? 湧き上がる気持ちやほとばしる感情をデジタルで表現する達人――その思考と実践は、分断を「翻訳」してつなぎ、多様な人が共に在る場をつくっていく。ふくよかな未来への手引となる一冊。
言葉の環世界
サピア=ウォーフ仮説
言語が身体化される時
翻訳の不可能性
漢字とアルファベットの混交
言語の意識と無意識の言語
自然言語のハイブリッド
文学としてのゲーム世界
「バグ」の幻惑
コンピュータの「デバッグ」
身体的な「バグ」との遭遇
吃音とともに
不可視の表現
哲学「
パリからの「強制送還」
プトトン先生との出会い
非言語の表現世界へ
世界を編集する
描かれた手でもうひとつの手を描く
「自分だけのパターン」が
それぞれの環世界言語をつくる
クリエイティブ・コモンズの運動
こどもの世界の学び方
見知らぬ人々がケアを交わす場
親しみを醸成し、持続させる場
「場を作る方法」を作る
デジタルな筆跡を辿る
生命の時間を刻む
関係のプロクロニズム
ナヴェンの祝祭に見えるもの
自然の本質へ近づくこと
関係性の言語
機械の情報と生命の情報
フィードバックが循環する
言語的なサイボーグ
生命のプロセスへ
使用するテクノロジーで知能が左右される
「計算」から「縁起」へ
ありえたかもしれない生命
「野生」のシステム
開かれた進化
「個」から「共」への軌跡
共生の論理
微生物との共生
共のリアリティに向かう
相手の視線を自分の中に住まわせる
言葉の喪失と獲得
関係性のなかの能力
関係性の環世界を描く
非生物学的関係の環世界
共話と対話
「私」の濃淡がゆらぐ
言葉の
弔いと祝いがつながる
世界そのものとの共話
遺言に学ぶこと
祈りを遺すということ
重なり合う「最期の言葉」
無言の声に聴き入る
「共に在る」という感覚
共在と共話
果てしない
終わらない贈り物
未来をつくる言葉
書誌情報
| 読み仮名 | ミライヲツクルコトバワカリアエナサヲツナグタメニ |
|---|---|
| 装幀 | GRAPH=北川一成と吉本雅俊/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 考える人から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-353111-1 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | 人文・思想・宗教 |
| 定価 | 1,980円 |
書評
風景とともにある知
子供が生まれたら、死ぬのが怖くなくなった。そう口にする人に何人も出会ったことがある。筆者自身もそうだ。出産の翌日に母子同室が許され、生まれたばかりの我が子を自分の体のとなりに横たえた。その瞬間、脳裏に浮かんだのは自分自身の葬式の鮮明なイメージだった。そして不思議なことに、底知れぬ安堵感に包まれたのである。
子供の誕生によって自らの死が「予祝」される。本書の出発点にあるのは、この不思議な、そしてこの上なく甘美な感覚だ。父となったチェン氏は、娘の誕生とともに、自分の全存在が風景へと融けこむ感覚に襲われたと言う。そしてあらゆる言葉が喪われた。
思うにこの風景への融けこみは、一種の記憶喪失体験だったのではないだろうか。子という次の世代にバトンが渡ることによって、世界は全く別様に見え、自分という存在をつくる原理が根本から組み変わってしまう。だからこそ、すっかり書き換わった景色のなかで、チェン氏は記憶をとりもどそうとするかのように、自らの過去を辿り直すのだ。
フランス国籍のアジア人として東京で生まれ、在日フランス人の学校に通った記憶。パリで過ごした不安定な高校時代、哲学の授業で経験した、明確な論理構造をもとに議論を構築する安心感。アメリカの大学でデザインと芸術を学び、自分だけのスタイルを獲得するなかで確信した、世界を語る言語としての表現の力。
だが本書は、複雑なハイブリディティを宿した一人の人間の半生をつづった単なる伝記ではない。善く生きる術を教えてくれるのが哲学書なら、本書はまさにその仲間だ。情報技術によって接続が加速すればするほど互いの分かり合えなさが増大していく時代のなかで、いかにその分裂を架橋していくか。本書は伝記でありながら、同時に言語をめぐる、人と人のインターフェイスをめぐる、きらめくようなヒントがたくさんつまった哲学書でもあるのだ。
人は、飛行機や車を使ってこの世界を地理的に移動していくことができる。だが同時に、科学や政治、文学やアートなど世界を認識するさまざまな方法のあいだを移動していくこともできる。本書が面白いのは、この二種類の移動が連動していることだ。チェン氏が東京からパリへ、あるいはパリからロサンゼルスに移動する。するとそのたびに彼は、世界の新しい見方へと移動していく。当たり前のことだけど、どんな知も文脈によって持つ意味は異なる。知が抽象化されず、土地を、人を、風景を伴っている。本書で描かれる、そのことがまず感動的だ。
特に私が好きなのは、終盤で描かれるモンゴルへの旅と「共在」をめぐるエピソードだ。チェン氏と妻は、モンゴルで結婚式を挙げようとする。おそらくは行き当たりばったりのこの提案に、現地の人たちが乗っかる。滞在先の家長が父親役を演じ、馬に乗って娘を娶る許可を取りに行くという儀式まで行った。
帰り際、チェン氏は父役だった男性の兄から、「馬をあげよう」という申し出を受ける。戸惑っていると、「あげる」というのは「持って帰れ」という意味ではないと言う。「この馬はここにいて、自分たちが世話をする。だが、君たちがここを訪れるときにはいつでも乗っていい」。つまりその申し出は、物質的な贈与ではなく、記憶のなかでどこまでも継続する関係を贈る、そういった類の贈与だったのだ。
チェン氏は、これを文化人類学者の木村大治のいう「共在感覚」と結びつける。木村は現コンゴの農耕民族ボンガンド族の調査を通じて、彼らが壁の向こうにいて顔が見えない人とも「一緒にいる」という感覚をもっていることを明らかにした。彼らは隣の家から聞こえてくる会話にも反応するし、常に一緒にいるのだから自宅から約一五〇メートル以内に住んでいる人とは会ってもあいさつをしない。
モンゴルで贈られた馬は、まさにチェン氏夫妻が東京に帰ってからもなお、モンゴルの人々や動物、景色と「共に在る」ことを可能にしてくれるものだ。そして子を持つというのも、実は同じことだろう。どんなに物理的に離れていても、その距離を含みこんで、私たちは共に在る。
(いとう・あさ 美学者)
波 2020年2月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

未来をつくる言葉を語ろう
『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために―』の著者、ドミニク・チェンに届いた一通のメール。その感想の先を語り合おうと、京都在住の森田が、東京のドミニクの自宅を1月に訪ねた――。
どこかで連帯している感覚
ドミニク 今日は遠路はるばるお越しいただいて、本当にありがとうございます。僕の本についての感想メールに大いに刺激されて、ぜひ会って続きを話したかったんです。森田さんとは何度も話してますが、こうやって対談が活字になるのは初めてですね。そういえば、僕たちはいつ知り合ったんでしたっけ。
森田 ドミニクさんのことを初めて知ったのは、ドミニクさんが日本支部を設立したクリエイティブ・コモンズのイベントで、2006年くらいのことです。現在スマートニュースのCEOをされている鈴木健さんの「サルガッソー」というベンチャー企業で僕は一時期働いており、出張先のシリコンバレーで、クリエイティブ・コモンズの創立者であるローレンス・レッシグ(アメリカの法学者。専門はサイバー法学)の前で、健さんが考案した貨幣システム「PICSY」などについて発表しました。それが2007年頃でしたかね。
ドミニク 「PICSY」の思想とクリエイティブ・コモンズの考え方が共鳴していたからこそのお付き合いですね。
インターネットやコンピューターによって計算され、可視化されて、人々が新しい気付きをもつ――クリエイティブ・コモンズではあらゆる創作の連鎖を、「PICSY」では生活の基底である経済を更新するから、文化と経済で意識がつながっていました。それで、2008年に僕はパートナーの遠藤拓己さんと自分たちの会社「ディヴィデュアル」をつくって。
森田 そのときに訪問させてもらいましたね。
ドミニク そうそう! 森田さんが偉大な数学者グロタンディークの話を1時間半くらい嵐のようにしゃべり倒して……
森田 一方的にしゃべって帰ってきた。またやっちゃってましたか(笑)。
ドミニク 森田さんはそうこなくっちゃ(笑)。卒業して「独立研究者」を名乗るようになって、京都で拠点を構えたのが……?
森田 2010年の3月に卒業し、所属がなくなったのが2010年4月からですが、現在のような講演活動を各地で始めたのは、武術家の甲野善紀先生と立ち上げた「この日の学校」という講演会シリーズがきっかけで、2009年9月からです。
ドミニク そうか、ちょうど10年経つわけですね。10周年、おめでとうございます。僕の方は10年の節目で、会社をスマートニュースに鈴木健さんが誘ってくれました。共同創業者二人はフルタイムでスマニューで働いていますが、そのタイミングで僕自身は大学の研究者に軸足を移しました。今もデジタル・ウェルビーイングの講座をスマートニュースの社員の方たちと一緒に実施したり、「スマートニュースのアプリは、どのように人類を幸せにできるのか」という問いと向き合っています。
森田 緩やかなネットワークを介して、ドミニクさんとは実際に会っていなくても、出会って以来いつもどこかで連帯しているような感覚があります。
ドミニク まさに同じです。特に会社時代は事業に専念していたので他の活動はあまり行えていませんでしたが、いまはフリーランスに戻り、ってフリーランスではなくて、大学教員という名のサラリーマンなんですが(笑)、それでもかなり自由度が上がって。最近は森田さんとトークでご一緒する機会も増えました。
【ここでドミニクさんの飼い猫が登場】
森田 猫ちゃんは何という名前ですか。
ドミニク ムウです。正式名が「麦」で、略して「ムウ」。男の子です。

森田 スタイルがいい。
【何やらヌカボット(ぬか床ロボット)が音声を発している】
あれ、ヌカボットの声がキッチンから。ヌカボットさん、どんな言葉に反応するんですか。
ドミニク いまのは独り言でしたね。発酵の調子を聞いたりできます。ちょっと聞いてみますね。
おーい、ヌカ。
ヌカ なあに。
ドミニク あなたは誰ですか?
ヌカ 僕はドミニクと一緒に住んでいる、ぬか床微生物の集合体だよ。
ドミニク 元気ですか。
ヌカ ちょっとデータ見るから待ってて。
【数秒経過】
いま、僕は発酵が少し足らない感じ。あと1週間は捨て漬けを続けてね。でも全体的に酸化傾向にあるので、いい感じ。ちょっと塩分が高めかも。
ドミニク 数日前にぬかを作り変えたので、まだこれからという状態ですね。
『未来をつくる言葉』を森田真生が読んで
読後、いまとても豊かな気持ちになっています。第1章のタイトルが「混じり合う言葉」となっていますが、まるでコラージュのようにいろいろな思考がドミニクさんという場において混じり合い、発酵していき、ついに娘さんの登場によって、(テッド・チャンの世界のように)過去と未来が交雑していく。
自分の世界が侵されていく不快感ではなく、複数の世界が縁起し合う喜びを感じながら、まるでタイプトレースで見ているかのように、ドミニクさんという人物の「成り立ちのパターン」を知るにしたがい、自然と読者は著者の思考過程と同期していく……。リニアなロジックの流れではなく、書き手と読み手が気づけば相互に照らしあう関係へと導かれていく。
まさに「『計算』から『縁起』へ」ですね。それを、ドミニクさんの文体と生き方そのものが体現しているのだと感じました。全体を読み終わった途端から、新しい思考が走り出すような本です。
ドミニク 森田さんから頂いたこのメールを読んだ時、本の中で無意識に表現したかったことを言語化して頂いたように感じ、うれしくて飛び上がってしまいました。
森田 本を書く方法論が、ドミニクさんの生き方とリンクしていました。
子ども時代から始まって、コラージュのように、人生の過程で集めてきたいろんな思考のパーツを並べながら、独自のパターンが顕れてくる。それが、ただのコラージュの並列ではなくだんだん発酵してまざり合い、娘さんの存在の登場とともに、未来と過去がまざり合っていく。南方熊楠は「雑」と書いて「
テッド・チャン的な時間の円環を彷彿させながら、過去と未来がまざり、複数の思考がまざり、言語がまざり……リニアな計算でも単純な二項対立でもなく、まさに縁起するようにして次々と思考が立ち上がっていく。自分が考えているのか、ドミニクさんの考えを読んでいるのかさえもわからなくなってくるような感じで、読み終わると豊かな気持ちになっていた。
新しい思考が動きだして、読み終わったというよりは、むしろ考え始めている感覚。読ませていただいてありがとうございましたという気持ちになりました。
『未来をつくる言葉』というタイトルには、自力の制御や支配とは違う仕方で、未来を開いていこうという広がりを感じます。こういう理念やメッセージですよ、2100年はこうなってほしいと思うのでこうしましょう、そういう計画的な未来のつくり方ではなく、異質な他者と付き合い、波長を合わせながら共存していくなかで、いままで見たこともない風景がおのずから生成してくる。そういう予感に満ちた一冊でした。
ドミニク ほんとうに、うれしいです。
【興奮して猫のムウを撫でる。ムウは去っていった】
森田 発酵は制御できるものではないけれど、なにか違うもの、おいしいものが出てくる期待感があります。そんな気持ちで読みました。面白いこと、楽しいこと、豊かなことが始まっていきそうだと思えるけれど、それはドミニクさんによって強制させられているとか、著者によって計画した未来を押し付けられているということではない。積極的な人間の自由意思よりも、「おのずからつくられていくもの」の場が提示されているような気がしたんです。
共話ってなんだ?
ドミニク ありがとうございます。いまの森田さんの言葉を聞いていて、そうか、自分の本はそのように読まれ得るのかと、打ち震えました。雑ざるという言葉でいうと、この本で重要なテーマのひとつが「共在感覚」です。この言葉を知ったのは、福岡の糸島で森田さんと散歩した時に教えてもらったのでした。
そのときに、安田登さんから伺った能楽における「共話」の話をして、タイプトレース(タイピングを記録して再生するソフトウェア)を使った実験について紹介したら、森田さんから文化人類学者、木村大治先生が研究した「共在感覚」について教えてもらった。東京に帰ってすぐさま『共在感覚』を図書館で借りて、貪るように読みました。
森田 そうでしたか。
ドミニク コンゴのボンガンドと呼ばれる人たちが、100メートル越しでも会話ができるとか、別々の家に住んでいても一緒にいると感じて生活をしているとか、その「一緒にいる」感覚を持つのに、現代人とはだいぶ違うやり方をしている。木村先生の言葉を借りれば、共在感覚を時に延ばしたり、時に遮断する。柔軟に調整するんですね。そして、彼らは時に対話ではなく、共話でコミュニケーションを取ります。この共在や共話という概念にドライブされるかたちで、僕は今回の本を書き進めました。
近代は、科学、社会契約、そして社会システムを、対話モデルに基づいて築き上げました。対話とは、話者同士が異なる個人であるという前提に立って、互いの差異を浮き彫りにする方法です。対して、共話では自分と他者がまざり合います。それは不快な侵入ではなく、もっと心地よくて、自分自身が他者によって開かれていって、プラスアルファされていくもの。
共話を日常で使いこなしている文化がアフリカにあると知った後に、調べていくと日本文化の中でも共話があることがわかりました。能楽のような伝統芸能の世界にもあるし、言語学の研究においても論じられています。
フランスと日本という二つの文化の中で育った人間として、対話と共話の違いにはコミュニケーションの本質が隠れていると思ったんです。それで、対話というものが主流である現代社会において、共話というテクニックをもっと積極的に捉えられれば、そこから新たな、より良いコミュニケーションの方法や実践が生まれてくると考えています。
共話は、結論を急がない、むしろ脱線に次ぐ脱線にこそ醍醐味があります。それは、即効性のある問題解決を目的としない会話ですが、永い時間の中で互いの思考と関係性を滋養する効能があります。例えば、「結論を出す」「計画をする」という発想を、発酵的に、つまりより長期的な時間の中で考えてみる。ただ放置しているわけでもなく、かといってすべてを計画するわけでもなく、その中間のどこかに、当たりをつけるように互いに付き合う。この流れによって、わたしたちが個人として意識しているアイデンティティがもっと雑ざり合ったり、生きる時間感覚も変わってくる。
今日はそのあたりを森田さんがどう考えるのか、あらためて伺えればと思っています。
「hold still」 の瞬間
森田 積極的に制御するのでもなく放置するのでもない、という観点で、昨年読んだリチャード・パワーズの『オーバーストーリー』(木原善彦訳、新潮社)はとても面白い本です。樹木が主役で、キーワードになるのが「still」という言葉なんです。
ドミニク おお、木が主人公なんですか?
森田 正確に言うと、木「も」主人公というか、人間が主で樹木は環境や背景だという、図と地を分けるような構図とは違う物語の描き方をしているところが、この本の面白いところです。
そして本書のなかで、樹木のあり方を象徴しているのがstillという言葉です。
stillという言葉にはいくつものニュアンスがこめられていて、第一には「じっとしていること」、「静止していること」、「静かである」こと。
また、stillには逆接の意味もあります。“I don’t know why I’m doing this, but still…”、「何の目的、何の意味があるかわからないけど、それでも」というときのように、「それでも/にもかかわらず」という逆接です。
さらに、「まだ/いまなお」と、持続、継続を意味することもあります。“He’s still speaking.”、「あいつまだしゃべってるぞ」と。
こうした複数のニュアンスを孕んだstillという言葉が、この小説の通奏低音になっている。それは、樹木の在り方そのものでもある。木々は静かにその場でじっとしているようで、それでも、まだなお、と生長を続ける。気付けば樹木は陸上の至るところにまで進出し、あらゆる生命活動を支える大気すら作り出している。最初に樹木が人間たちに“A thing can travel everywhere, just by holding still.”と語り掛けるんです。ものは、ただその場にじっとしているだけで、至るところに行くことができる。
この小説でstillがどこに出てくるのかを原書で一度リストアップしてみたことがあるんですが、そのとき、「hold still」という表現が何度も出てくることに気づきました。hold stillというのは、「じっとする」とか「凍り付く」とか、そういう意味ですよね。この小説には8組の人物が出てくるんですが、面白いのは、樹木だけでなく、登場する人物たちもそれぞれにhold stillしてしまう場面があることです。病気になったり、事故に遭ったり、強烈なアイディアが訪れたりなど、文脈はそれぞれに違うんですが、重要なポイントは、hold stillする瞬間に、みな自分ではないものに耳を澄ませはじめるというところです。
ドミニク なるほど。自分が動いている時は他者が入ってきづらい。他者の声を傾聴するには、いったん止まってから、ですね。
森田 そう、みなそれぞれに、人生がそれなりにスムーズに作動しているときには、「自分でないもの」の存在にはあまり開かれていない。弁護士として、研究者として、あるいは学生として、それぞれのアイデンティティがあり、それなりに自己完結した「世界」を生きている。ところが、ふとしたことがきっかけとなり、それまでの世界の順調な作動が止まり、ただじっとするしかなくなってしまう瞬間がくる。このとき、彼らに自分を超えたもの、自分ではないものの存在が訪問してくるんです。
順調な作動が停止してhold stillする。これが、必ずしもただネガティブなことではなく、さっきの言い方で言えば、自分で計画をするのともただ放置しておくのとも違うモードに入っていくきっかけなんです。自分でないものたちとの共存のモードに入っていく合図が、この小説のなかではhold stillというキーワードなんじゃないかと僕は読んでいるんです。
ドミニク 面白い。hold stillするというメタファーは、生命のレベルだけではなく、社会のレベルにも当てはめられそうです。
森田 これを読んだとき、空海の『性霊集』(空海の漢詩文集で、個人全集としては日本最古と言われる)の「心境冥会して道徳
「心」と「境」、これを、ここではあえて、自分と自分ならざるもの、と解釈してみると、自分と、自分でないものとが波長を合わせ、深く調和するとき、人として生きるべき道や徳といったものが、自ずとその奥深い姿を現す。この一節を僕はいま、このように理解しています。どう生きるべきか、何が価値か、ということは、自分の心で決めることではなく、自分ではないものに指令されるのでもない。自分と、自分ではないものの波長が合い、調和しているときに、おのずから道が顕れるのだと。
ドミニク さきほどの、制御でもなく放置でもないという意識に通じると思いました。全ての存在は互いに関係している、という縁起の概念を考えた空海らしい表現ですね。
森田 『オーバーストーリー』の人物たちも、自力で道を切り開くというよりも、むしろ、hold stillする瞬間から、自分でないものへと耳を傾けるようになり、そこからそれぞれの道が開かれていく。樹木もそうして何億年も生きてきたんだと思います。
ドミニク 現代ではとかく「自立せよ」「行動しろ」「アクションを起こせ」と言いますよね。自然が「自ずから」存在してきたものだとすると、近代社会は「自ら」在ることを称揚してきた。
森田 「心境」の「心」の方に偏っているとそうなりますね。自分で計画をし、意識して変えてやろう、と、特に近代の人間はこの「心の力」に依拠してきた。一方で、それは面倒だから、お上が言う通りにしよう、与えられた規則に服従しよう、あるいはAIに任せよう、と何かに全部託してしまうのも違うと思います。「主体的、能動的」でもなく「受動的」とも違う行為のあり方を、パワーズは樹木を通して描いた。ドミニクさんの本にも、通じるものを感じます。
ドミニク ありがとうございます。森田さんの声をhold stillしながら聞いていて、自分とは違う存在であるパワーズさんの考えがすっと意識の中に移入してきたように感じました(笑)。僕の本は、子どもの誕生のことから書き出しましたが、その瞬間にはまさに、hold stillしかないものですね。森田さんもお子さんとのことをよく書いている。
森田 そう思います。
ドミニク この本は、「ドミニクさんは色々な研究や表現の活動をしていますが、この10年のうねりをひとつにまとめてください」という依頼で書き始めたのですが、10年を振り返った時に、最大のhold stillは子どもが生まれたことでした。子どもが生まれると、もうてんやわんやです。生まれた直後からいつ退院するのかに始まって、おしめを替えて家事をこなしているだけで日々が過ぎていく。だから、子どもが一人歩きするようになるくらいまでの記憶は曖昧なんです。もしかしたら、その期間、僕はずっとhold stillしていたのかもしれない。自分以外の存在である娘の成長に、自分のリソースの大半を割いている間、僕は個としての自分から解放されていたように感じます。そのプロセスを、自分自身で思い出すために記憶の中に飛び込もう、と書き始めました。
そうしたら、思い出そうとする行為自体が、いま自分でやっている活動にフィードバックし始めて、子どもに向けて遺言を書くことにつながっていった。子どもが生まれた瞬間に自分が死ぬことがもう大丈夫だと思った――と後から掘り起こせた。それはまさに、いま森田さんが言ったhold stillの時間でしたね。
それまでは、「来年はこういうことをやるぞ」「こういう活動を頑張るぞ」と自分が主体的に物事を決めて人生を生きてきたのが、自分でそれ以上なにもせずとも、決まっていった。「自ずから」生まれる時間を生きるというのは、この本の一つの大きなテーマになってます。
閉じこもれない時代に
ドミニク 生と同時に、死について考えるのもテーマになりました。悲しみを乗り越える、という話ではなく、子どもが生まれ出てきたあの瞬間に見えた、死んでも大丈夫、自分の死が予め祝福されたのだという感覚を自分自身が思い起こすために、「Last Words / TypeTrace」という作品をdividual inc.(遠藤拓己とのアートユニット)として「あいちトリエンナーレ2019」に出展しました。
森田 そうでしたね。

ドミニク 10分以内に誰か一人に向けて遺言を書くというテーマ(#10分遺言)で募集したところ、展示期間中に2300人以上の方が遺言を書いてくださりました。集まったテキストをタイプトレースで再生していると、実に多様な関係性が背景に見えてきました。それでも、大きな共通項が浮き彫りになってきたんです。
自分自身がまず娘に書いてみた時、10分は本当に一瞬で、字数にしたら1000字もないくらい。なのに、その10分間は書き手にとてつもない密度をもたらすことがわかりました。この行間から「おのずと出てきてしまうもの」は在る種の「祈り」なのではないか、そう感じました。結局、テキストを寄せていただいた2300人のほとんどに共通するのが、「相手の人に、自分がいなくなった世界でも、幸せな世界を生きてほしい」という祈りでした。そのことがタイプトレースで再生される時間の隙間から感じ取れたんです。
遺言って、実際に書いてみると悲観的な内容にならないんですね。自分がもういない世界に向けて何かを書くのは、考えてみたらとても不思議な行為です。他方で、公園で子どもたちと遊ぶ親御さんたちを見ていたら、何気なく交わす所作や言葉の一つ一つが遺言なのではないかとも思いました。普段は意識していない「自分がいなくなった後の世界」に、一回意識を置いてみて、改めて現在に戻ってくること。遺言という行為を経ると世界の感じ方が変わるんです。
森田 そうでしょうね。
ドミニク 森田さんの言葉でいえば、生き方が変わる、自らをhold stillさせるための行為なんだなと思います。いまの自分を、一回宙づりにし、未来の時間に飛ばして、もう一度戻ってくる、それを10分間だけの文章を書く作業がもたらしてくれるんです。
「10分遺言」は、一つの提案ですが、むしろ、非日常的な行為をあえて日常に取り込むことの可能性についてずっと考えるきっかけになっています。
森田 現在に没入している子供と一緒にいると、僕はつい、自分も現在に没入してしまいます。ただ、同時に、「現在に閉じこもる」なんて無理だ、とも、最近は冷静になる余裕もできてきました(笑)。現在だけに引きこもれないという自覚は、いまの時代は特に切実ですよね。自分の今の振る舞いが、自分が滅びた後にどういう帰結をもたらすかを考えることは、人間がこれほど大きな影響を環境に及ぼしているいま、すべての人の責任だと思います。
「自分」と「環境」を切り離して、物事を「図」と「地」に分けられると考える発想自体がいまは機能不全を起こしています。
いまこうしていても、太陽からのニュートリノが何兆個も僕の全身を通過していて、小指の先に日本の人口以上のバクテリアたちがいるなんて知ってしまったら、自分の中には閉じられませんよね(笑)。僕のなかには僕でないものがおびただしく侵入してきているし、僕のいまの行動は、僕の知らない過去に突き動かされ、遠い未来にはみ出している。時間的にも、空間的にも、自分は一つの尺度に閉じこもれない。そう自覚し続けることを、環境哲学者としてアメリカで活躍しているティモシー・モートンはecological awareness(エコロジカルな自覚)と言っています。
ドミニク これからは、未来に一度、自分の意識を置いてみるプラクティスが、ある種の倫理的な態度として、不可欠になるのかもしれないですね。
(もりた・まさお 独立研究者)
(ドミニク・チェン 情報学者)
波 2020年6月号より
単行本刊行時掲載
関連コンテンツ
イベント/書店情報
著者プロフィール
ドミニク・チェン
Chen,Dominique
1981年生まれ。フランス国籍、日仏英のトリリンガル。博士(学際情報学)。NTT InterCommunication Center[ICC]研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、2022年8月現在は早稲田大学文化構想学部教授。人と微生物が会話できるぬか床発酵ロボット『Nukabot』の研究開発、不特定多数の遺言の執筆プロセスを集めたインスタレーション『Last Words/TypeTrace』の制作を行いながら、テクノロジーと人間、そして自然存在の関係性を研究している。