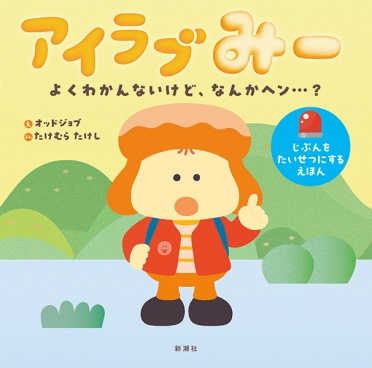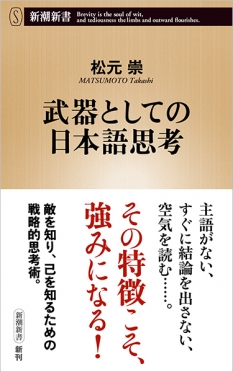最後の山
2,420円(税込)
発売日:2025/08/27
- 書籍
- 電子書籍あり
8000m超の14座そのすべてに写真家として世界で初めて登頂した記録。
23歳でエベレストを登頂して以来20年余。世界で最も高く危険な山々への挑戦はついに「最後の山」シシャパンマへ。人間を拒む「デスゾーン」でぼくが見たのは、偉大で過酷な自然の力と、我々はなぜ山に登るのかという問いへの答えだった──中判カメラを携え、人類の限界を超えようとする仲間たちと共に登った生の軌跡。
プロローグ
第一章 新世代シェルパ ガッシャブルムII峰+ダウラギリ
第二章 間違ったルート カンチェンジュンガ
第三章 執念の山 K2+ブロードピーク
第四章 真の頂上とは マナスル
第五章 悲痛な報せ アンナプルナ
第六章 楽園と地獄 ナンガパルバット+ガッシャブルムI峰
第七章 白い闇 チョオユー
第八章 二つの雪崩 シシャパンマ
第九章 生還者
第十章 最後の山 シシャパンマふたたび
エピローグ
書誌情報
| 読み仮名 | サイゴノヤマ |
|---|---|
| 装幀 | yukino kayahara/カバーイラスト、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 272ページ |
| ISBN | 978-4-10-353692-5 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | 文学・評論、ノンフィクション |
| 定価 | 2,420円 |
| 電子書籍 価格 | 2,420円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/09/19 |
書評
青春の残り香
世界には八千メートルを超える山が十四ある。
その山のすべてに登るということが、登山の歴史において何らかの意味を持つという時期はすでに過ぎている。
世界で初めてその十四座に登ったのはイタリアのラインホルト・メスナー、女性で最初に登り切ったのはスペインのエドゥルネ・パサバン、日本で最初の十四座サミッターになったのは竹内洋岳、という具合だ。
だから、当然のことながら、石川直樹が八千メートル峰のすべてに登ろうと思い決めたのも、なんらかの記録のためではなかった。
エベレスト、マナスル、ローツェ、マカルー、ガッシャブルムII峰、ダウラギリ、カンチェンジュンガ、K2、ブロードピーク、二度目のマナスルと登っていくうちに、十四座のすべてに登ってみたいという思いが強くなっていったのだという。
その理由として、この『最後の山』においては、二つのことが述べられている。
ひとつは、ヒマラヤ登山において永くサポート役を務めてきたシェルパたちのあいだに、自らのための登山をするという新しいムーブメントが生まれ、その主役のひとりであるミンマGという人物と巡り合ったことで、彼らと行動を共にすることへの喜びを覚えるようになったからだという。
もうひとつは、GPSやドローンなどの精度が上がることにより、これまで頂上と思われていた地点とは別の頂上が出現するようになって、その「真の頂」というものへの強い関心が生まれたからであるという。
しかし、私には、そうした理由以上に、すべきことは自らが見つけなければならないフリーランサーの石川にとって、それが久しぶりに心を熱くさせてくれる「すべきこと」と映ったのではないかと思えてならない。すべきことが現れて、気持が高ぶった。
その高ぶりに身を任せた石川は、アンナプルナ、ナンガパルバット、ガッシャブルムI峰、チョオユーと、一年で一気に四座に登り、ついにはシシャパンマを残すだけになる。
だが、このシシャパンマが、石川にとっては難峰となる。
頂上にあと二百メートルと近づきながら、ヒマラヤの登山史の中でも、そう多くない悲劇的な連続遭難を眼前にすることとなり、撤退を余儀なくされる。
それでも、その翌年、ふたたび、彼にとっての「最後の山」であるシシャパンマに向かうことになる……。
石川は、年齢的には四十代の半ばを過ぎているし、すでに多くの著作を持っている。しかし、この『最後の山』には、一人称に「ぼく」が使われているからというだけが理由ではない、不思議な初々しさがある。青春の残り香のようなものが漂っている気がするのだ。
何故か。
それは、その底に自分は何者なのかという問いを秘めているからだと思われる。
自分は登山家なのか。いや、違う。少なくとも、山野井泰史のような尖鋭なアルパイン・クライマーではない。
冒険家なのか。たぶん、違う。未知の土地や新しい体験を求めてはいるが、そのために人生のすべてを費やして突き進んでいるわけではない。
紀行作家なのか。結果として何冊かの本は出しているが、書くために旅をしたり、山に登ったりしているわけではない。
写真家なのか。確かに、常に撮る者でありつづけているが、そう言い切れるかどうか、わからない……。
そうした思いの揺らぎのようなものが、次々と八千メートル峰を登らせながら、自らを確固たる存在として描くことをためらわせている。
もちろん、それは欠点ではなく、私にはむしろ美質であると感じられてならない。
自らを過剰に誇らないだけでなく、ミンマG以外にも、ザイル・パートナーとしてのシェルパたちを、友人として柔らかな筆遣いで描くことができているのもそうしたところからなのだろうと思われるからだ。
しかし。
十四の八千メートル峰の「真の頂」に立ったいま、石川にひとつの覚悟に近いものが生まれたように思われる。
《ヒマラヤでの経験は決して折れることのない太く頑丈な杖のようなもので、それを片手にぼくは歩き続ける。その杖を頼りに、願わくは死ぬまでずっと歩き続けたいと思っている》
それがどこに続く道かわからないまま、石川直樹は前に進んでいくことになるのだろう。杖を持った手と反対の手には、やはりカメラを握りつつ。
(さわき・こうたろう 作家)
波 2025年9月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
最初の山
最初に登った山は奥多摩の本仁田山だった。男子校の中学に通っていた頃で、仲が良かったクラスの不良グループの友人たちと一緒に登った。不良が登山、というのもおかしな話だが、山に行けば、親からも先生からも遠く離れてタバコも吸えたしお酒も飲めた。夜更かしをして、延々とくだらない話を続けることもできた。家を出る口実としても都合がよかった。テントを担いで山に行く、と言えば親は外泊を許してくれた。ぼくたちは、家庭や学校から自由になろうとして、なぜか山へ向かったのだった。
あの頃は何も登山道具を持っていなかったから、ありあわせのもので登っていた。当時、流行っていたエアジョーダンというバスケットボールシューズを履いてぼくは登山をしていた。シカゴ・ブルズのスター選手だったマイケル・ジョーダン選手のシルエットがロゴマークになったシリーズで、くるぶしまで靴高があり、今でいうミドルカットタイプのスニーカーだった。
ぼくはサッカーに夢中で、バスケットボールのルールもおぼつかないのに、当時の流行に乗って、親にねだって手に入れたのだった。バスケットボールシューズだから靴底は平坦で、登山には向かない。山の下りでは、案の定つるつると滑って苦労させられた。
雨が降ると、愛用のエアジョーダンは見る見るうちに水が滲みこみ、足を濡らした。指先の冷えをどうにかしようと、苦肉の策としてスーパーマーケットでもらえる白いビニール袋を靴下の上に履き、その上から靴を履いた。多少の冷えは和らいだが、靴の中のビニールが滑り、登山中ずっと不快だった。そのことだけは今も記憶に残っている。
奥多摩の日帰り登山や奥秩父での縦走、河口湖の湖畔でキャンプなどをしていた日々が、ぼくの山の原風景である。友人たちはタバコを吸ったり酒を飲んだりしていたが、ぼくはどちらにも興味がなかった。タバコは二回ほど吸ってみたが、うまく吸えず、何がいいのかさっぱりわからなかった。ビールや焼酎も飲んではみたが、まったく美味いと思わなかった。無論、どんな人も最初はそういう体験から喫煙や飲酒にハマっていくのだろうが、ぼくはそのあたりはどういうわけか頑なで、現在に至るまでタバコにも酒にも興味がない。酒は付き合い程度に飲むが、自分から欲して飲んだことは一度もない。
山登りを始めた前後、ぼくは一人旅もするようになった。中学二年の冬休みに、東京の家を出て四国の高知に向かった。武田鉄矢作・小山ゆう画の『お~い!竜馬』というマンガを読みふけり、坂本龍馬の故郷である高知県にどうしても行ってみたくなって、電車を乗り継いで四国を目指した。
海外への最初の一人旅は、高校二年の夏休みに敢行したインド・ネパールの旅だった。喧騒のインドを脱出し、『深夜特急』よろしく深夜バスで国境を越えてネパールのカトマンズに入り、その後、数日間のトレッキングを体験した。ランタン地方に行って初めて万年雪をかぶったヒマラヤの山々を眺め、それが今に続くヒマラヤ登山のきっかけになっている。
あの頃のぼくには自由への憧れがあった。決められた時間に学校に行き、ときに𠮟られながら勉強を強要され、有無を言わせず教師が敷いたレールの上を進まされることに、強く反発していた。が、今から考えると、十代で山に行きインドにさえ行けた日々は、自分で思っていたよりずっとずっと自由だったのかもしれない。
十代でのほぼすべての体験は、はじめてのことばかりだった。キャンプも登山も酒もタバコも旅もインドも、すべて初めての体験だった。
過去の自分を振り返ったとき、あるいはヒマラヤの8000メートル峰14座への旅を振り返ってその出発点は何だったのだろうと考えたとき、一つの強烈な出来事が起点になったというより、自由を欲した十代のぼくのあらゆる初体験の積み重ねが今の自分を形作っているという当たり前の結論に行き着く。
子どもなりに自由を希求するようになったその根っこには小学生の頃に読んだ冒険や探検の本があり、それらの本を手に取るきっかけは自分の性格だったのかもしれず、その性格が両親や生活環境に少なからず培われたものだとすれば、自分が生まれ、常にいまを生きている、ただそのことが、それのみが原点ということにならないだろうか。
『最後の山』という本を書き上げてヒマラヤへの長い旅に区切りをつけたところだが、無論そこからはじまる新たな旅がある。また一つ一つ小さな体験を積み重ね、生きている日々の最後の最後まで、すなわち死ぬまでいくつもの旅を繰り返していくだろう。そう考えると、ぼくはこの世界に生まれたその日から、ずっと自由だったのかもしれない。
(いしかわ・なおき 写真家/作家)
波 2025年9月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
石川直樹
イシカワ・ナオキ
1977年、東京生れ。写真家。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら作品を発表し続けている。2008年『NEW DIMENSION』、『POLAR』で日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞写真賞を受賞、2011年『CORONA』で土門拳賞、2020年『EVEREST』、『まれびと』で日本写真協会賞作家賞を受賞。他に『最後の冒険家』(2008年、開高健ノンフィクション賞受賞)、『地上に星座をつくる』など著書多数。