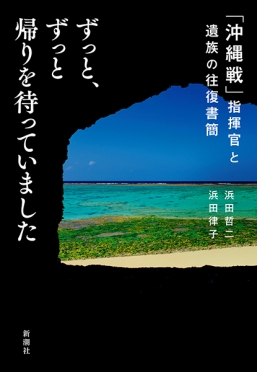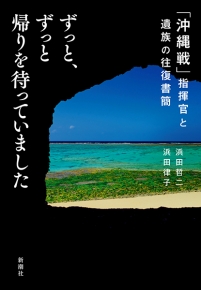
ずっと、ずっと帰りを待っていました―「沖縄戦」指揮官と遺族の往復書簡―
1,760円(税込)
発売日:2024/02/15
- 書籍
- 電子書籍あり
戦没兵士は、私の最愛の人でした――手紙が浮き彫りにする感動の人間ドラマ。
沖縄戦で、米軍から陣地奪還を果たした大隊があった。奮戦むなしく兵士の9割は戦死。終戦直後から24歳の指揮官・伊東孝一は部下の遺族に充てて「詫び状」を送り続ける。時は流れ、伊東から「遺族からの返信」の束を託されたジャーナリスト夫婦が、“送り主”へ手紙を返還するなかで目撃したのは――。不朽の発掘実話。
後藤豊 准尉(享年三三)
田中幸八 上等兵(享年三一、推定)
山崎松男 上等兵(享年二二、推定)
吉岡力 伍長(享年二四)
奥谷勇 一等兵(生年月日は不明)
横山貞男 一等兵(享年三四)
中村石太郎 軍曹(享年三五)
小早川秀雄 伍長(生年月日は不明)
太田宅次郎 上等兵(享年三四)
今村勝 上等兵(享年三三)
倉田貫一 中尉(享年三八)
黒川勝雄 一等兵(享年二一)
野勢勝蔵 上等兵(生年月日は不明)
高田鉄太郎 上等兵(生年月日は不明)
鈴木良作 上等兵(享年三六)
重田三郎 主計中尉(享年二三、推定)
松倉秀郎 上等兵(享年三五、推定)
鈴木喜代治 上等兵(享年二六、推定)
長内大太郎 上等兵(生年月日は不明)
工藤國雄 中尉(享年二九)
佐々木高喜 軍曹(享年二四)
阿子島基 一等兵(享年二二)
金岩外吉 上等兵(享年二一)
多原春雄 伍長(享年二五、推定)
木川英明 上等兵(生年月日は不明)
書誌情報
| 読み仮名 | ズットズットカエリヲマッテイマシタオキナワセンシキカントイゾクノオウフクショカン |
|---|---|
| 装幀 | petesphotography/カバー写真、iStock/カバー写真、Getty Images/カバー写真、浜田哲二/表紙写真、新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 272ページ |
| ISBN | 978-4-10-355551-3 |
| C-CODE | 0036 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 定価 | 1,760円 |
| 電子書籍 価格 | 1,760円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2024/02/15 |
書評
手榴弾の安全ピンを抜いた、私の母
沖縄戦を戦った陸軍第24師団(通称「山部隊」)の歩兵第32連隊・第1大隊を率いた伊東孝一大隊長(最終階級は陸軍大尉、1920年9月28日~2020年2月19日)と隊員、戦死した兵士の遺族たちの物語だ。当時24歳で伊東氏は1000人もの部下を率いたが、その約9割が戦死した。戦争直後、伊東氏は戦死した部下の遺族に宛てておよそ600通の手紙を書く。遺族からの返信が伊東氏のもとに356通残されていた。取材で伊東氏を知った浜田夫妻の情理ある説得に応じ、伊東氏は手紙を2人に託すことにした。伊東氏から預かった手紙を差出人に返還することを浜田夫妻は決め、その作業を行うNPO法人「みらいを紡ぐボランティア」を組織した。本書はこの手紙を返還する活動を通してみたユニークな沖縄戦記だ。
評者の母親は、昭和高等女学校2年生だった1944年10月、偶然が重なり、陸軍第62師団(通称「石部隊」)の軍属になった。14歳の軍属は異例だった。本書でも説明されているが、沖縄戦では「石部隊」が当初、米軍と戦いほぼ戦力を失った。母は前田高地(ハクソーリッジ)の戦いで奇跡的に生き残った。〈軍司令部から、敢闘してきた第一線の第62師団が、独力では対抗できないほど戦力が低下し〉たので伊東大隊が支援に向かった。母の部隊と伊東大隊はすぐ隣で戦ったのだ。
第62師団も第24師団もその後、転進(撤退)し、首里攻防戦を経て南部の摩文仁への結集を命じられた。そこから反転攻勢の機会を掴むというのだ。しかし、摩文仁で日本軍は壊滅状態に陥り、1945年6月23日、沖縄戦の最高指導部である陸軍第32軍の牛島満軍司令官と長勇参謀長が自決し、日本軍は組織的抵抗ができなくなる。ただし、司令部の残党は、「各部隊は現陣地を死守し、最後の一兵まで敵に出血を強要せよ」という命令を出した。そのため伊東大隊の悲劇は続いた。
〈ただ生き延びるだけの日々の中、壕口で歩哨をしていた兵が突然、叫び声を上げながら小銃を発射する。/「敵が来た、敵が来た! 後ろにいる、寝台の下からも来た!」/大声で喚き立てるので、とっさに敵が侵入してきたかと身構えた。/だが、何も起きていない。日々の恐怖が嵩じて精神が錯乱したのだ。小銃と手榴弾を取り上げて、壕の奥へ追いやる。肌身離さず持っていた自決用の手榴弾は返してくれ、と申し出るが、聞き入れられない。時には正気で、時には狂っているのだ。/この沖縄の戦場は、忍耐強い日本兵をも錯乱させるほど、激しくつらい戦いであった。我が大隊の将兵たちは日が経つにつれ、一歩また一歩と地獄への道を歩み始めていた〉。
評者の母はおそらく、1945年7月末か8月初めに米軍の捕虜になった。ガマ(自然洞窟を使った天然壕)に潜んでいるところを米兵に見つかった。母は手榴弾の安全ピンを抜いて、自決の準備をしたところを、隣にいた「山部隊」の伍長に「死ぬのは捕虜になってからでもできる」と言われて手を挙げた。
実は2023年、あるジャーナリストが、珍しい名字であったこの伍長の人定をした。ただし、この人は自らの主導で捕虜になったことは秘匿し、沖縄戦について別の物語を語っていた。遺族はこの人のその物語に固執しているので、心の平穏を乱してはいけないと思い、評者はこの問題に関する調査を打ち切った。沖縄戦に参加した人々にはそれぞれの物語があるのだ。本書に記された戦没者の遺族もそれぞれの物語を持っており、事実よりも物語を尊重することが鎮魂に繋がると評者は考えている。
評者には、糸満市照屋で戦死した多原春雄伍長(戦死日は1945年3~4月、あるいは6月という証言がある。享年25、推定)のエピソードが最も興味深かった。春雄氏の母・多原サヨさんの書いた手紙がサヨさんの孫の妻・多原良子氏に戻る。〈「ババちゃんの書いた手紙で、春雄叔父さんのことを知ることができるなんて……」/思わず涙ぐむ良子さん〉。応接間にはアイヌ関連の書物、民族衣装、装飾品がある。〈「実は私はアイヌ民族なのです」〉。
評者は多原良子氏と面識があり、アイヌ差別、沖縄差別について踏み込んで話したこともある。ある政治家のアイヌ民族等に対する差別表現に関連し、多原良子氏が人権救済の申し立てをし、それが2023年9月に新聞やテレビで報じられた。多原良子氏は、2023年2月に義理の叔父が死亡した地を訪れ慰霊をした。詳しくは本書を読んでほしいが、そこには沖縄、日本、アイヌを貫く人間の物語がある。伊東氏の手記、隊員の手紙、取材により伝えられる遺族の声から、人間は信頼できる存在なのであるというメッセージが伝わってくる。
(さとう・まさる 作家/元外務省主任分析官)
波 2024年3月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
浜田哲二
ハマダ・テツジ
1962年、高知県出身。元朝日新聞社カメラマン。2010年に会社を早期退職後、青森県の世界自然遺産・白神山地の麓にある深浦町へ移住し、フリーランスで活動中。沖縄県で20年以上、戦没者の遺骨収集と遺留品や遺族の手紙返還を続けている。公益社団法人日本写真家協会(JPS)会員。
浜田律子
ハマダ・リツコ
1964年、岡山県出身。元読売新聞大阪本社記者。1993年、結婚を機に退職後、主婦業と並行してフリーランスで環境雑誌などに原稿を執筆。夫・哲二と共に沖縄県で遺骨収集と遺留品や遺族の手紙返還を続けている。