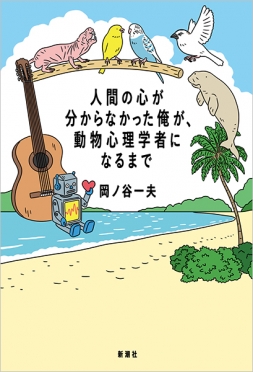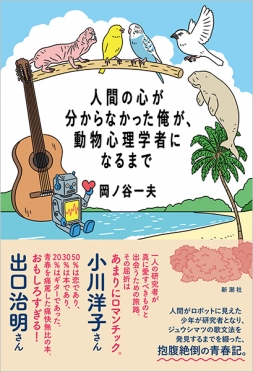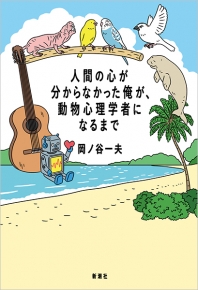
人間の心が分からなかった俺が、動物心理学者になるまで
1,980円(税込)
発売日:2025/09/18
- 書籍
- 電子書籍あり
恋愛、ギター、時々研究。研究者に至る遥かな道程を綴った抱腹絶倒の青春記。
小学生のとき、ある日突然人間がロボットに見えた。それは治ったが、以来、人との距離の取り方が下手なままだ。研究への想い止まず日本を飛び出し、アメリカの大学院に留学したものの、苦労の連続。日本に帰って来てもそれは変わらず、ポスドク地獄の果て、わらしべ長者のごとく、俺は少しずつ研究者への道を歩み始めた。
まえがき
一 少年時代
二 高校から浪人へ
三 大学教養部
四 大学研究室
五 留学
六 帰ってきた異邦人
七 さえずり研究事始め
八 ポスドク蟻地獄
九 そして大学教員になる
一〇 歌文法の発見
あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | ニンゲンノココロガワカラナカッタオレガドウブツシンリガクシャニナルマデ |
|---|---|
| 装幀 | 芦野公平/装画、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 考える人から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-356451-5 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | エッセー・随筆、ノンフィクション |
| 定価 | 1,980円 |
| 電子書籍 価格 | 1,980円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/09/18 |
書評
リラックスにストイック
著者の岡ノ谷一夫先生とは、約十年前、読売新聞本社で初めてお会いした。著者も私も、紙面に定期的に書評を書く“読書委員”のメンバーだったのだ。
読書委員は大学教授の方が多く、当時二十代半ばだった私はひどく緊張していた。何の専門性もない自分に引け目を感じまくっていたからだ。ただその中で、話し相手を塵ほども緊張させない人の存在に気がついた。著者である。
偉い人ほど偉ぶらない──そんな通説に触れるたび、私は著者を思い出す。会議室は常に著者を中心とした笑い声で溢れており、その場にいる皆が著者を好いていることは明白だった。その道の権威になるまでには間違いなくストイックさが必要だろうが、それをユーモアで覆い隠し、場をリラックスさせる在り方に、私は大変感銘を受けた。
本書は題名の通り、著者が動物心理学者になるまでの道程が描かれている。その内容は大きく三つに分けられる。
第一幕は、著者の幼少期から慶応大学を卒業するまで。読書に目覚め、逆さ語にハマり、周囲の人たちがロボットに見えるという理由で入院し、浪人を経て慶大生活を終えるまでの、いわば人生の序章だ。著者曰く変人揃いの研究室での日々はそれだけで極上の青春記なのだが、ここからが本番というところが本書の特異な部分だ。
第二幕は、米メリーランド大学への留学期。独特な教員達、脳に似ているという理由で同僚のトムとクルミの標本を染色した日のこと、好きな小説のシーンに重ねて想い人にビートを届けたら翌日その人がスープを作って著者を自宅へ招いたこと……どこを切り取っても往年の名作映画のようなジンともキュンともなるエピソードばかりだ。それにしても、ChatGPTはおろかインターネットもない時代、著者は録音した講義を繰り返し聞くことで何とか英語力を向上させたという。そして、おそらく星の数ほどあるだろうそのような苦労話は、本書では殆ど語られない。全てをユーモアで包んで差し出してくれる著者だが、帰国の要因の一つとなったエピソードからは、物事の本質を鋭く捉え深く咀嚼する人格が窺える。この感性を抱えたままユーモアを貫く姿からは、ある種の矜持を感じられる。
最後は、帰国してから千葉大学の教員になるまで。ここではまず日本社会で生活資金を稼ぎながら研究を続ける難しさを思い知らされる。やがて著者は千葉大学にて自身の研究室を発足させ、教育者としても実績を積んでいく。
全編を通して印象的なのはやはり、冒頭でも触れた、ストイックとリラックスが見事に両立している著者の在り方だ。まずストイックの面から私なりに言語化したい。
本書で著者は様々な環境に身を置くが、どの時点でも名誉欲や出世欲とはかけ離れた純粋な興味関心に司られているように見える。社会や他者からの評価が、著者の行動原理を変えることがないのだ。ストイックは禁欲的・自己抑制的と訳されることが多いが、著者はきっと何かを禁じたり抑制したりすることなくその状態に居座っているのだと思う。きっとそのほうが自然なのだろう。そんな姿は、名誉欲や出世欲をニンジンとしてひた走るニンゲンを多く見かける今、非常に稀有だし、とても眩しい。
そしてリラックス。こちらをどこから感じたかというと、度々差し込まれる“警備員コスナー”的な小ボケ──ではなく(それもあるが)、著者の人間関係の築き方だ。
著者は自分の得意分野、不得意分野を明確に把握しており、前者では人を助け、後者では即誰かに手伝いを頼む。そのとき、頼る相手の年齢、性別、国籍は一切関係ない。
私の場合、ここで寧ろ変にストイックになり、一人で何とかする方法を探ってしまう。誰かを頼るとは自分の弱点を晒す行為であり、無意識的にそれを避けるべく、ぎゅっと全身を力ませてしまうのだ。一方、著者はそんなときこそ弛緩している。自分はこれが苦手だから助けてね、何かの時には助けるからね、こんな具合に。著者の研究室には常に学生がたむろしていたというが、それは著者本人どころか著者の生み出す空間そのものがリラックスしていたからだろう。そもそも弱さを開示できる、リラックスできる人間関係があって初めて、人は目標に対してストイックでいられるのかもしれない。読書委員の会議室で著者の周りに常に人が集まっていた理由が、今ならわかる気がする。
作中、著者は何度か“動物行動と脳神経系の対応を調べたところで何がわかるのか”等といった批判を受ける。私は研究の世界に明るくないが、きっと小説の何倍も実利が問われる場なのだろう。人は、果たしたことから価値を測る。資本主義社会である以上仕方ないかもしれないが、では同時にその人が果たさなかったことにも目を向けたい。学生たちの卒論を英文原著論文として投稿しなかったこと、立ち消えた研究を他の学生に回さなかったこと、自分の発見をもってして「鳥は言葉を話している!」などと喧伝しなかったこと──著者がしなかったことを並べてみると、ここにこそ、著者が自らは語ろうとしない、けれど著者を著者たらしめている美学が潜んでいる気がするのだ。
読後、もうすっかり大人のくせに、自分もこんな大人になりたいと心から思った。続編にも期待しています。
(あさい・りょう 作家)
波 2025年10月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
岡ノ谷一夫
オカノヤ・カズオ
1959年生まれ。動物心理学者。慶應義塾大学文学部卒業後、米国メリーランド大学大学院で博士号取得。2010年より東京大学大学院総合文化研究科教授。2022年4月より帝京大学先端総合研究機構教授。動物の音声コミュニケーションから言語や心の起源を探る研究で知られる。著書に、『さえずり言語起源論』(岩波書店)、『言葉はなぜ生まれたのか』(文藝春秋)、『「つながり」の進化生物学』(朝日出版社)、『脳に心が読めるか?』(青土社)などがある。