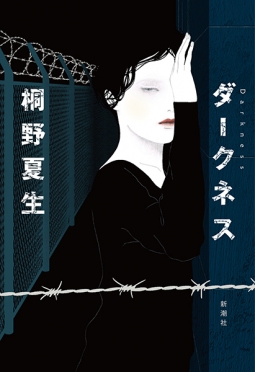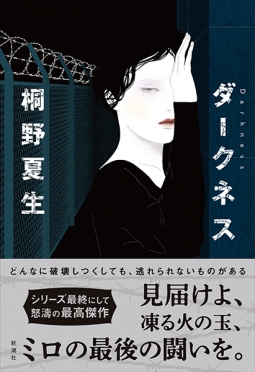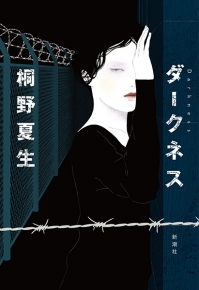
ダークネス
2,750円(税込)
発売日:2025/07/30
- 書籍
- 電子書籍あり
見届けよ、ミロの最後の闘いを。シリーズ最終にして怒涛の最高傑作。
私の愛した男たちは皆行ってしまった。私の魂を受け止めてくれる相手はもうどこにもいない──衝撃作『ダーク』から20年、村野ミロは生きていた。そして息子のハルオは「悪」を知る旅に出るが……。息子を守るため、凍る火の玉、ミロの最後の闘いが始まる。圧倒的迫力で描く、著者渾身のエンタテインメントの結末は。
第一章 山道で遭遇するもの
第二章 四十歳になったら死のうと思っていた
第三章 ミロには似合わないこと
第四章 ハルオ、荒野に放たれる
第五章 ミロもまた、荒野へ
第六章 ハルオ、悪を旅する
第七章 ミロのダークサイド
書誌情報
| 読み仮名 | ダークネス |
|---|---|
| 装幀 | 四宮愛/装画、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 504ページ |
| ISBN | 978-4-10-466705-5 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文芸作品 |
| 定価 | 2,750円 |
| 電子書籍 価格 | 2,750円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/07/30 |
書評
ミロのダークナイト
1993年、江戸川乱歩賞を受賞した桐野夏生のデビュー作『顔に降りかかる雨』とともに「村野ミロ」は誕生した。以後、『天使に見捨てられた夜』(1994年)、『水の眠り灰の夢』(1995年/ミロの義父・村野善三の若き日を描いたスピンアウト的長編)、『ローズガーデン』(2000年/短編集)とミロは活躍を続け、その間に作者の桐野も『OUT』(1997年)や『柔らかな頰』(1999年/直木賞)など代表作を積み上げながら作品世界を押し広げていった。だが、2002年に発表された『ダーク』でミロの運命は激動する。クールな女探偵村野ミロは人格さえ一変したかのごとき情念に塗れたダークヒロインとなり、読者を震撼させた。
『ダークネス』は『ダーク』から実に二十三年を経たまさかの続編であり、村野ミロシリーズの最新作である。
まさかの、と述べたのは、『ダーク』があまりにも壮絶な、そしてこれ以上ないと思えるほどに見事な「シリーズ完結編」然としていたからだ。あれから長い時間が過ぎた。だがミロと同じく、自分の意志ではどうにもならない獰猛な運命に導かれるように、桐野は筆を執った。
現実と同様、『ダークネス』では『ダーク』から二十年が経っている。前作でミロが産んだハルオは二十歳になり、母親と同じ那覇で暮らしながら医師を目指して地元の大学に通っている。ミロはハルオの実の父親の兄で、強大な富と力を持つヤクザである山岸と、ミロが自分の愛する男、村野善三を殺したと信じて恨みを募らせている盲目の女性、久恵に見つからぬように最大限の注意を払いながら、ハルオと二人、那覇でひっそりと生きている。そんな折、やはり前作でミロのために二人を殺害して有罪となったジンホの釈放の日が近づき、ミロはジンホのいる刑務所がある大阪に通いつつ、来たるべきジンホとの生活を心待ちにしている。だが、ハルオがアルバイトをしていたゴルフ場での或る出来事がきっかけで、母と息子の運命は再び狂い始める。
このように『ダークネス』は『ダーク』の物語を引き継いでいるのだが、そこには二十年という時間が挟まっており、赤子だったハルオが青年になったように、あのミロも今や還暦を迎えている。さすがに残りの人生を心穏やかに過ごしたい。息子の将来を楽しみに見守りながら、愛する男と日本か韓国で睦まじく過ごしたい。だがそうはいかない。私はこの文章ですでに何度も「運命」の二文字を書いた。そう、桐野夏生の小説はすべてが運命譚である。運命とは「自分の意志ではどうにもならない」、けっして逃れられないという意味だ。だからミロは最後の闘いに挑まなければならない。これが最後だ、今度こそ最後なのだと自分に言い聞かせて、運命に追いつかれる前に走り出さなくてはならない。
本作にはもうひとりの主人公がいる。それはもちろんハルオだ。彼はミロの運命が齎した子である。ハルオは持って生まれた自分の運命に責任はない。だが彼は、否応なしに運命に絡め取られていく。小説はミロの一人称で書かれた章と、ハルオを視点人物とする章が交錯しながら進んでゆく。ハルオの大学の同級生で那覇の大病院の娘である由惟をはじめ、新たな登場人物もすこぶる魅力的だ。
運命に落とし前をつけること。本作でミロがすることになる(それは「せざるを得なくなる」ということなのだが、もはや能動と受動の違いに意味はない)のは、そしてミロシリーズの「まさか」の続編である本作を書いた桐野夏生の動機もまた、要するに「落とし前」である。語りは、筆致は、ますますスピーディーで、苛烈な熱を帯びていく。ほんとうに凄い小説だ。ほんとうに凄いヒロインであり、ほんとうに凄い作家だ。ここには『ダーク』と『ダークネス』の間に書かれた桐野作品の数々が雪崩を打って流れ込んでいる。その意味で、これは単なる続編とは違う。村野ミロは年を取ったのではなく、自らの物語=運命を何度も生き直してきたのだ。
そして運命の夜がやってくる。ダークナイト。急激にギアチェンジして一気に加速するかのような、鮮やかで俊敏な、驚くべきラストシーン。私は呆気にとられ、深く激しく戦慄した。だが、それでも、再び朝はやってくる。本作が教える真実、それは、ミロの運命に終わりはない、ということだ。
(ささき・あつし 批評家)
波 2025年8月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

ミロは孤独を恐れない
1993年、桐野夏生氏の『顔に降りかかる雨』で誕生した女探偵・村野ミロは、衝撃作『ダーク』を最後に、読者の前から姿を消した。そして20年後、『ダークネス』で再び現れたミロについて、桐野氏と小川哲氏が語り尽くす。
ミロシリーズを破壊した『ダーク』
桐野 お会いするのは初めてですね。
小川 はい、でも『噓と正典』が2020年に直木賞候補になったとき、受賞はしなかったんですが、桐野さんが推してくださったと後で聞いて嬉しかったです。それで、桐野さんにはご縁があると勝手に思っていて。
桐野 すごい作家さんが現れたと思いました。『ユートロニカのこちら側』なども、書く快楽がほとばしってる感じで、ものすごい才能を感じました。そういう作品が好きなんです。
小川 僕自身も書く時に、自分が楽しむのをすごく大事にしてますね。で、今回『ダークネス』を読ませていただきました。「サスペンス小説です」と言われてゲラを渡されたんですが、確かに逃亡小説ではあるけれど、サスペンスというより、エンタメを超えた、人が生きること、しがらみの中で生きることが大きく浮かび上がってくる作品と思いました。桐野さんの中で、デビュー作(『顔に降りかかる雨』)から『ダークネス』まで、最初から全体の構想はあったんですか。
桐野 確か小川さんも何かの対談で、全く構想しないでお書きになるとおっしゃってましたけど、私も全く構想はしないんです。ただ、デビュー作だけは乱歩賞の応募だったし、当時脚本の勉強をしていたので、ちょっと箱書きみたいなものは作ったんですけど、もう2作目からは自由に書くようになりました。自由に書いた方が何が出てくるか分からないので、自分でも面白いんです。ミロシリーズは確かに探偵物ですけど、私はただ、30歳ぐらいの女性が東京で一人で生きるという、そういう物語を書こうと思っていました。『天使に見捨てられた夜』の時も、ミロが犯人とおぼしき男と寝たりするんだけど、編集者から怒られてね。「男性読者が幻滅するので、こういうことしないでください」と(笑)。でも、若い女の人だったら、何もわからない相手の男でも、魅力的だったらそういうこともあるんじゃないか、そこはリアルにやらせてほしいということで、以後強引にやってきました。最後の方では、ミロというシリーズものに縛られている自分にうんざりしちゃって。それでミロ自体を、もう壊してしまおうと思ってめちゃくちゃにやったのが『ダーク』なんですよね。
小川 『ダーク』では、いろんな登場人物がしがらみと愛によって、どんどん身を滅ぼしていく。僕が読んでて一番思ったのは、作者自身が、シリーズものを書くことに、自分が作り上げた登場人物や自分が築き上げたシリーズの読者に対するしがらみを感じているのかな、と。僕がシリーズものを書くのが嫌なのは、やっぱりそこなんですよね。
桐野 そうなんです。縛られますね。
小川 読者が期待しているものも、なんとなく見えてきちゃったり、そういうことが多分嫌だったんだろうなと思って。僕自身も、小説を書き始めたのは、そういうしがらみと無縁で生きていきたかったというのもあります。社会で普通に働いて生きていくと、しがらみだらけなんで。なので、登場人物たちに共感しつつも、その背後にいる桐野さんがすごいしがらみに苦しんでるのかな、と思いました。
桐野 しがらみという、うまい言葉でおっしゃったけれども、自分が築き上げた小説世界に自分がとらわれていく。それがすごく嫌で。私も自由に書きたいと思っていましたが、結局、築き上げてしまったものが、やっぱり自分を損なっていくという感じが、どうしてもあって辛かったです。だったらいっそのこと、ミロもめちゃくちゃにしてやれと思って『ダーク』を書き出したら、これがまた気持ちが良くて(笑)。ミロにとんでもないことをさせました。
小川 確かに、ミロは自分自身でこのシリーズ自体を破壊するようなこともしてるし。でもこの『ダーク』という小説で、ミロによる破壊行為自体が成立したのは、僕はやっぱり、ミロの宿敵たる邪悪な女、久恵の存在のおかげだと思っているんです。久恵というキャラクターを生み出すことができたからこそ、その後の『ダークネス』も生まれたのだと思いました。
桐野 おっしゃる通りです。ミロだけじゃ破壊できないものがあるんです。多分ミロがどんなに転落しようが堕落しようが、やっぱりそれはミロなんですよね。ミロの世界の物語になってしまうから、やっぱり久恵という人物が出てきたことによって、物語世界の完全な破壊が行われたと思っています。久恵を描くのも結構、快楽があってね。だからミロの転落と同時に、久恵がアナーキーに壊れてますよね。それを書くのも楽しかったんです。
マイノリティの存在
小川 先日、山本周五郎賞の選考会があって、そこである選考委員が、最近の小説はマイノリティを聖人として扱いすぎていて、マイノリティだからいい人とか、マイノリティだからこんな特殊なことができるみたいに書くのが納得いかない、マイノリティだって、いろんな人がいるでしょ、というようなことをおっしゃっていた。一方僕は、とはいえ、マイノリティの存在自体を書くことがまず大事な時期もあると思うんですね。今まで無視されてきた存在を、どういう書き方であれ、小説に出すことに意味がある。今、過渡期だから、その方のおっしゃることも分かるけど、そういう存在を出すこと自体が完全に普通になっているかどうか、まだ分からない、みたいなことを選考会で言ったんです。そして『ダーク』を読んだら、20年以上も前に桐野さんが、視覚にハンディキャップを持つ久恵を、すごく生々しく書いていました。
桐野 先日「ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング」を見たのですが、女性たち、それもラテン系の女性やトランスジェンダーも出るし、みんないろんなマイノリティが結構、いい役なんです。だから、確かにおっしゃるように、そういう傾向なんだろうとも思うんですけれども、マイノリティにも実はいろんな人がいるわけです。久恵の目が見えないということが、私はむしろ色っぽいなと思ったんですよね。盲目であることが、むしろ色気になるから、逆にこの人はその意味ではすごく強いんじゃないかと思って、だからこそ聖人にできないという気がしました。確かに『ダーク』に登場するのはマイノリティの人ばかりなんですよね。目の見えない人に、ゲイの男性に、韓国人、在日台湾人、そして女性。だから本当に、マイノリティのかたまりの話をずっと書いてたんだなと思って、今回自分でも驚きました。
『ダークネス』は中上健次だ
小川 そして『ダークネス』です。僕はこの作品を読んで、大学で中上健次の研究をしたんですけど、中上を思い出しました。
桐野 それは光栄です。
小川 中上の『岬』とか『枯木灘』って、血のしがらみの中で、主人公が、自分の人生や自分自身が縛られていくことを感じながら、その鬱屈が溜まっていって爆発する小説ではあるんですけど、血のしがらみって、『ダークネス』でもずっとテーマになっているんですね。例えば親を、自分の母あるいは父を否定することは、自分の半分に返ってくるわけですよね。その血の流れとして、逆に親も自分の子供を否定しようとすると、自分の遺伝子が返ってくる。やっぱり、他者とのしがらみよりも、親子はもっと複雑な愛憎がいりまじることになって、中上はそれを書き続けた人ではあったんです。究極的な、この逃れられない血のしがらみを、『ダークネス』は、なるほどこう扱うんだ、と思いました。それは、この20年間で、『ダーク』から『ダークネス』の間に、桐野さんの中に何かあったんですかね。
桐野 『ダーク』を描いた時に、私もこれでミロシリーズはおしまいと思ったんですが、ハルオという子どもを生み出してしまったので、じゃあ20年後ぐらいに、ハルオの物語を書こうかなと思ったんです。だけどハルオは、すごく苦しい状況じゃないですか、親を否定すれば自分の否定にもなるし、肯定もできない。その作用反作用はものすごく厳しい人物なわけだから、むしろ、ハルオってどういう人間になるんだろう、それによってミロはどう変わるだろう、みたいなことを書くことになった。本当に小説って、一つの世界を作ってるわけだから、一度壊してやれと思ったけれども、なかなかしたたかで、その小説からまた復讐されるということはあるんだな、とは思いましたね。
小川 『ダーク』で、ミロの母親をめぐって、村善とミロが対立する構造が、今回はミロを中心に、ハルオとジンホで対立する構造に入れ替わっていて、ミロ自体は変わらないんだけど、母親としてのミロには、やっぱりすごく揺らぎがあったりするというところが、この『ダークネス』でまたミロに新しい一面を与えているような気がしましたね。
桐野 私も母親ですけれど、そのあたりは簡単には書けない。血縁は割り切ることができない。本当に難しい問題だと思います。
小川 桐野さんはキャリアを築いてきても、未だにすごく原稿書かれてるじゃないですか。30年くらい書き続けられるのって、何かあるんですかね、コツとか。
桐野 気がつくといつの間にか40冊くらい書いていますね。割と好きなんですよね、小説書くのが。いろんなことを考えてるのが、面白いんです。書く作業は辛いんだけれども、書き出してからある一瞬、すごく乗る時があって、そのハイな気持ちをまだ得たいっていう気持ちが強くあります。
小川 今回の『ダークネス』でも書いている間に、そういう瞬間がやっぱり何度もあったから、まだ書きたい?
桐野 若干ね(笑)。小川さんは、これからまだまだずいぶん長い作家人生があって、羨ましいです。
小川 いやでも、どうやって書き続けるかっていうのは、難しい問題というか、書き続けられている人ってそんなに数が多くないから。
桐野 自分に対する好奇心じゃないですかね。
血のしがらみ
小川 『ダークネス』を執筆しようとした段階で、ミロとジンホがどうなるかというのは、まだ見えてなかったんですか。
桐野 全然見えてなかったです。多分変質はしてるだろうなと思っていましたが、その変質を、どうやって描こうかと迷ってはいました。
小川 じゃあ、ハルオとミロの関係性も、作品を描きながら見つけていったという感じですか。
桐野 そうですね。ハルオはいずれ離れていくであろう、という発想はありました。そうするとまた、ミロとジンホの問題になるから、二人はどうするんだろうと考える。
小川 『ダークネス』では、親子とかあるいはきょうだいとか、そういう血のつながりが全面に出てくる。
桐野 血縁だけは本当に、どうしようもないですもんね。
小川 自分の出自を知ったハルオは、それは絶対に混乱しますよね。でもそれがハルオに、「じゃあ血のつながりって何なんだろう」と、考え直すきっかけになって、そこが面白かったですね。
例えば自分の父親の嫌なところとかを見つけた時って、怒りと同時に怖さみたいなものを抱くわけです。遺伝子のせいで、自分にもその要素があるんじゃないかという。だから、僕もそういう嫌な面を自分が持っているんじゃないかという恐れみたいなものは、あったかもしれない。
桐野 それは普通の他者との関わりでは、ないことですよね。
小川 由惟という女性が出てきますが、作中で一番まともな人物だったかもしれないですね。ハルオに向ける愛の眼差しが、異性愛のものから、親類への愛情に変わっていくあたりは、『ダーク』では愛情がメインだったものが、『ダークネス』では血のつながりが全面に出てきたことを、由惟が体現した感じがしました。
いろんな親子が登場しますが、普通の核家族は一つも出てこない。どの親子も、何か欠損がある状態で書かれています。
桐野 確かに、普通の家族は出てこないですね。すごくシンプルなんですけど、結局みんな一人で生きていく、という話なんですよね。私は常にそうなんです。
小川 それぞれが、自分の弱いところから、誰かに頼ったり依存したりするんだけど、結局はやっぱり自分一人で生きていくしかないんだなってなっていくところが、すごくグッとくるところでありますね。登場人物たちが、孤独を恐れていないというか、孤独を受け入れているというかね。
そして終盤、久恵という強烈なキャラクターと、自分は一緒だということを、ミロが発見して愕然とする。
桐野 あれは私もちょっと、自分で書いてびっくりしました。久恵って、改めて、必要な人物だったんですね。ミロは私で、実は久恵でもあるのです。
小川 久恵が『ダーク』と『ダークネス』の間の、20年間を埋めてるわけですよね。『ダークネス』は、桐野さんが一度『ダーク』で破壊したミロシリーズの更地に、また一から、ハルオという芽を育てて、もう一回花を咲かせた、という作品であると思います。
桐野 ありがとうございます。
(きりの・なつお 作家)
(おがわ・さとし 作家)
波 2025年8月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
桐野夏生
キリノ・ナツオ
1951年金沢市生まれ。1993年『顔に降りかかる雨』で江戸川乱歩賞、1998年『OUT』で日本推理作家協会賞、1999年『柔らかな頰』で直木賞、2003年『グロテスク』で泉鏡花文学賞、2004年『残虐記』で柴田錬三郎賞、2005年『魂萌え!』で婦人公論文芸賞、2008年『東京島』で谷崎潤一郎賞、2009年『女神記』で紫式部文学賞、2011年『ナニカアル』で読売文学賞、2023年『燕は戻ってこない』で毎日芸術賞と吉川英治文学賞を受賞など、主な文学賞を総なめにする。ほかにも『ポリティコン』『ハピネス』『バラカ』『日没』など著書多数。2015年、紫綬褒章を受章。2021年早稲田大学坪内逍遙大賞、2024年日本芸術院賞を受賞。2021年より日本ペンクラブ会長。