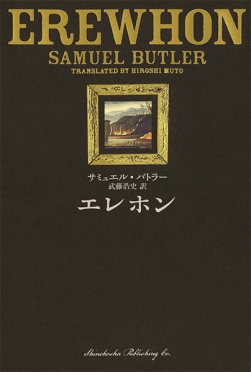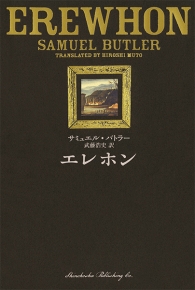
エレホン
2,420円(税込)
発売日:2020/07/30
- 書籍
- 電子書籍あり
一五〇年前に描かれた「理想郷」に、私たちはいま辿り着こうとしている――。
羊飼いの青年が迷い込んだ謎の国「エレホン」。人びとはみな優しく、健康的で美しく――。でも、それには“しかるべき理由”があった。自己責任、優生思想、経済至上主義、そしてシンギュラリティ……。社会の幸福とはいったい何なのか? ディストピア小説の源流とされる幻の長篇が、現代人の心の底に潜む宿痾をあぶり出す。
第二章 羊毛小屋
第三章 川を遡る
第四章 峠
第五章 川まで下りて、大山脈へ
第六章 エレホンに到着
第七章 第一印象
第八章 監獄
第九章 都へ
第一〇章 エレホン的世論
第一一章 エレホン国の裁判をいくつか
第一二章 不平の徒
第一三章 エレホンの人たちは死をどう観るのか
第一四章 マハイナ
第一五章 音楽銀行
第一六章 アロウィーナ
第一七章 イドグルンとイドグルン教徒
第一八章 出生告白書
第一九章 未生者の世界
第二〇章 彼らは何を言いたいのか
第二一章 屁理屈大学
第二二章 屁理屈大学(続)
第二三章 機械の書
第二四章 機械の書(続)
第二五章 機械の書(結)
第二六章 動物の権利に関する或るエレホン国預言者の考え
第二七章 植物の権利に関する或るエレホン国哲学者の考え
第二八章 脱出
第二九章 結
書誌情報
| 読み仮名 | エレホン |
|---|---|
| 装幀 | “St.Jerome Reading in a Landscape” by Giovanni Bellini National Gallery, London/表紙、(C)Universal History Archive/表紙、Getty Images/表紙、新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 320ページ |
| ISBN | 978-4-10-507151-6 |
| C-CODE | 0097 |
| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |
| 定価 | 2,420円 |
| 電子書籍 価格 | 2,420円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2021/01/01 |
書評
世界が無意味化する前に
私は『エレホン』を読み終えて、ただただ、びっくりしている。そしてなんだか、うろたえている。
一五〇年まえにイギリスで出版されたディストピア小説の嚆矢とされる本作は、何度か邦訳されたようだが、知らずに来てしまった。二一世紀になって二〇年を経過したいま、この新訳ではじめて読んでみて、地球的規模でくり返し起こる大規模な自然災害、気候変動、そして目下のコロナパンデミックの渦中にある世界のもとで、この小説は果して読者をどこへ連れて行くのだろうかと不安になりもする。せめて二〇世紀のうちに読んで、心の準備をしておけばよかったと思う。
この壮大で細密な小説の世界に足を踏みいれてみると、冒頭から延々と大自然のありさまが見事な描写力で描かれ、キリスト教の布教とあわせて羊の放牧で大儲けをたくらもうとする主人公のイギリス人青年は、さんざんな目にあいながら奥地の大山脈を越え、やがて他者の侵入を拒むようにひっそりとひらくエレホン国にたどり着く。このとても長い導入部はいくらか読者をくたびれさせるかもしれない。が、それゆえにエレホン国の秘境感をたっぷりと演出し、絵描きでもあった作者サミュエル・バトラーの観察眼の豊かさと科学的思考力のおかげで、私などはアンドレ・ジッドの『コンゴ紀行』やリヴィングストーンの冒険譚を読むような思いで堪能させてもらった。
主人公のエレホン見聞録はそこからはじまるのだが、この小国は数百年もまえに一九世紀イギリスと同レベルの高度な産業文明に達していながら、ことごとく機械を破壊し、懐中時計さえとりあげて彼を獄にいれてしまう。金髪と青い目をしているおかげで彼は良家に救われるのだが、進歩を敵視、科学は禁止、機械文明を徹底的に排斥するエレホンにはさらに奇妙な制度がいくつもあって、七〇歳以前に病気や身体的不具合になった者は裁判をうけ、公衆の侮蔑にさらされる。熱帯病や肺結核は極刑に付されかねず、家族や友だちを失う不幸や破産などの不幸、つまり他者に不快感を与えるような出来事に見舞われた者も犯罪者とされ処罰をうける。ところが、放火や強盗や詐欺行為など道徳心の欠如から起こる犯罪については、病院に収容され公費で手厚い矯正のための治療をうけるのだ。
主人公をひきとった金持ちの家の主人にしても、横領が発覚して、パンと牛乳だけの食事と鞭打ちの加療をうけるのみですまされていた。彼の娘の友人は病弱さをカモフラージュするためにアルコール中毒を装い、道徳心の欠如を強調して生きている。妻と死別した男の裁判(死別の悲しみさえ罪とされるのだ)を傍聴した主人公は、被告人が妻など愛したことはなく、その証拠に多額の保険金をかけて死後実際にうけとっていると弁明するのを聞き、判事から、その不幸の罪にたいして自然は厳罰を与えると言い渡されるのを見た。なんという倒錯。主人公は思う。
この国はなにもかも倒錯しているのだ。神の実在を説く公式宗教があるいっぽうで、イドグルンという女神を国民は信じている。経済をまわしているのは一般の銀行だが、それとは別に「音楽銀行」なる国の銀行があって、それぞれ違う貨幣を扱っている。この「音楽銀行」のシステムもまた、主人公には到底理解できるものではなかった。利子はなく、配当は三万年に一度ボーナスとして、というもの。ようするに、なんの価値も生み出さない銀行なのである。しかしながら国民は壮麗な大理石の神殿のような建物におさまるこの銀行を絶対に安全なものとして信じており、主人公はここに神と宗教の空洞化を感知する。
そもそもこの国では、生まれてくる子供は親や世間を煩わせるだけの厄介な存在として位置づけられ、出生後にかける迷惑行為についてはいっさいの責任を自分が負うという内容の出生告白書を出生時に書くこと(代理人が代筆)が義務付けられている。生まれること自体を罪とみなす国に、どんな価値があるだろうか。
産業革命以降、世界随一の工業生産国となったヴィクトリア女王時代のイギリスの三大権威は、宗教、親、機械であった。バトラーはこの小説で徹底的な風刺を試みているのであるが、それは人間の自然にたいする徹底した資源化、植民地支配による人間と自然の資源化、対立するはずのキリスト教と資本主義の無理やりの融合化、そして機械文明によって生じた人間性の喪失が、世界の無意味化へとつながっていくプロセスを描き出しているのだ。白眉は第二三章から第二五章の「機械の書」である。これを読むと、私たちの二一世紀がすでに過去の残骸であるかのように思えてくる。
手遅れとは言うまい。心ある人は今のうちに読んでほしい。風刺でも予言でもない。二一世紀の痛切な現実である。
(たかやま・ふみひこ 作家)
波 2020年8月号より
単行本刊行時掲載
綺麗に解釈できない。だから、なぜなら……。
読んでいると、頭がねじれてくる本だ。だから、読んだことのある誰かと話をしたくなる。実際、私も読み終わってすぐに、この本の担当編集者氏に話をしたいともちかけてしまった。もちろんZoomで。感想戦は盛り上がった。私たちは違ったところにひっかかっていたから、解釈が違って面白かった。そして、なにより、飛沫を共有することなく、道徳的に話ができたので、深い満足感があった。まるでエレホン国の住民のように。
最初にこの本の全体を紹介しておこう。これは冒険小説だ。『ガリバー旅行記』のように、主人公は未知の国へとさまよいこみ、そして帰ってくる。それ自体はありふれたプロットかもしれない。だけど、この本の真の魅力は、この未知の国エレホンの独特で精緻な設定にある。
エレホンは美しい。住民は皆美男美女で、礼儀正しい。自然は美しく、街は清潔だ。それはユートピアのように見える。だけど、その美しさはあらゆる価値の反転によって成り立っている。たとえば、機械の全面廃棄を行った「機械の書」、まるで死にゆく宗教のような「音楽銀行」などなど、価値の反転は精緻なディテールをもって描かれている。
なかでも、心理士を生業としている私にとって面白かったのは、エレホンでは犯罪が医学的問題になり、病気は道徳的問題とされていることだ。殺人や横領を犯しても、刑罰を受けることはなく、矯正師と呼ばれる専門家の治療を受ければいいのだけど、結核になれば牢屋に投獄されてしまうのだ。だから、体調を崩した女性は道徳的非難を浴びないようにアルコール嗜癖を装う。
ここには「自己責任」の反転がある。エレホンでは不幸ほどの悪徳はない。不治の病、遺族、犯罪被害者は死刑に値するほど悪しきことだ。だけど、私たちの社会で自己責任が問われてしまうような犯罪は、「運が悪かったのね」で済まされる。
著者であるバトラーは、自分が生きていた19世紀末イギリス社会の反転をエレホンとして描いた。だから、『鏡の国のアリス』のようにアベコベを楽しめばいい、普通に考えればそうだ。だけど、ここで頭がねじれてくる。なぜなら、エレホンは21世紀の私たちの社会にとってはただのアベコベではないからだ。いや、むしろ、それは写し絵だ。
たとえば、犯罪は現代においては医学的問題に変わりつつある。違法薬物使用に必要なのが治療であることは現代のメンタルヘルスケアの常識になりつつあるし、虐待や犯罪の背景には貧困があることも社会的な合意を獲得しつつある。だから、犯罪や道徳性の欠如を「自己責任」と言って切り捨てないエレホンは、私たちの社会のお手本に見える。エレホンの矯正師が、私にはとても他人には思えない。
同じように、病気が道徳的問題とされるのも、コロナウィルスの感染が激しい社会的非難の対象となった現代を彷彿とさせる。それだけではない、肥満や癌など健康上の問題は、食、運動、喫煙などの習慣による自己責任とされ、道徳の文脈に組み入れられている。現代社会のもっとも残酷な部分をエレホンは体現している。
エレホンはユートピアなのか、ディストピアなのか。それは私たちの社会の反転した姿なのか、それともただありのままを映した姿なのか。その両方なのだ。ある部分は反転で、ある部分はありのままの姿なのが、エレホンだ。ここで読者の頭がねじれてしまう。綺麗に解釈ができない。だから、話をしたくなる。それが『エレホン』という小説だ。
そして、わかった。編集者氏とZoomで話してわかった。エレホンはねじれた鏡なのだ。それはデコボコで、しかも不規則に歪んでいる。だから、像は乱反射する。つまり、読者がどこに立っているのかによって、エレホンはユートピアに見えたり、ディストピアに見えたりする。
だけど、よくよく考えてみると、エレホンがねじれた鏡であるのは、私たちの社会もねじれているからだ。今、私たちの社会には優しいところもあれば、残酷なところもある。その社会は私たちの人生を支えてくれてもいるし、それを押しつぶしてもいる。私たちの社会がユートピアでもありながら、ディストピアでもあるから、エレホンもその両方を兼ね備えている。19世紀末から21世紀の間に、社会ははち切れそうなほどにねじれていったのだ。
エレホンには機械がないからZoomがない。コロナウィルスに襲われたらどうするのだろう。機械という悪をとるのか、病気という悪をとるのか。二つの悪の狭間で、何をすれば善になるのかわからない。私たちの社会がエレホン的であるとは、そういうことだと思う。
(とうはた・かいと 臨床心理学者)
波 2020年8月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
サミュエル・バトラー
Butler,Samuel
(1835-1902)19世紀後半に活躍した英国の作家。父は英国国教会の牧師、同名の祖父も名門パブリックスクールの名校長で聖職者。ケンブリッジ大学を卒業するも、父にならって聖職者になる道を拒み、当時の新興植民地ニュージーランドに入植、牧羊業で財を成し、帰国。絵画、作曲を学ぶも、文筆の道へ。ダーウィン『種の起源』に衝撃を受けつつ、彼の理論に異を唱え、進化論と宗教性の融合を試みる。小説の代表作として、『エレホン』の他に、19世紀イギリス社会・家庭の抑圧性を暴いてヴァージニア・ウルフらの喝采を浴びた『万人の道(The Way of All Flesh)』(1903)がある。
武藤浩史
ムトウ・ヒロシ
(1958-)英文学者。慶應義塾大学教授。英国ウォリック大学大学院博士課程(Ph.D.)。著書に『「ドラキュラ」からブンガク』(2006)、『「チャタレー夫人の恋人」と身体知』(2010)、『ビートルズは音楽を超える』(2013)。訳書に『D.H. ロレンス幻視譚集』(2015)、D.H.ロレンス『息子と恋人』(2016、小野寺健と共訳)など。