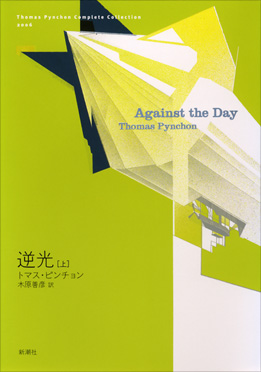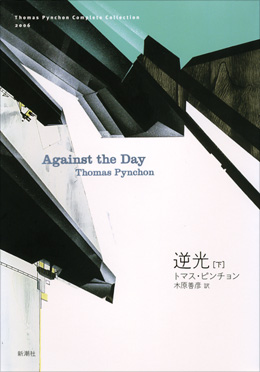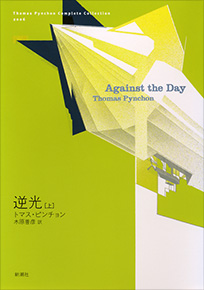
逆光(上)
4,840円(税込)
発売日:2010/09/30
- 書籍
これがあのピンチョン!? 時空を超えた感動に誘う世界沸騰の巨篇がついに刊行。
フロンティア消滅直後の19世紀末アメリカ。謎の飛行船〈不都号〉を駆る「偶然の仲間」が探し求めるは……砂漠都市シャンバラ! 地球空洞説に未確認生物、探偵に奇術師が跋扈する冒険と博覧会の時代が戦争の世紀を切り拓くとき――超弩級作家が紡ぐある一族の運命、出会いと別れ。原書2006年刊、『重力の虹』を嗣ぐ傑作。
第二部 氷州石
第三部 分身
書誌情報
| 読み仮名 | ギャッコウ1 |
|---|---|
| シリーズ名 | 全集・著作集 |
| 全集双書名 | トマス・ピンチョン全小説 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 864ページ |
| ISBN | 978-4-10-537204-0 |
| C-CODE | 0097 |
| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |
| 定価 | 4,840円 |
書評
波 2010年10月号より (詐欺のような)美しい結末へ
物語は一八九三年のシカゴ万博から始まる。最初に登場するのは、〈不都号〉(Inconvenience)なる飛行船に乗り組む〈偶然の仲間〉五人組。彼らの冒険は、少年向けのヒーロー小説シリーズとなり、世界中で人気を集めているらしい。
ふむふむと思いつつページをめくると、もう一匹の乗組員、しゃべる犬のパグナックスが登場。読書好きなんだそうで、いきなりヘンリー・ジェイムズ読んでます(しゃべる球電やしゃべる巨大砂蚤も本書には登場するので、このくらいで驚いてはいけません)。その後、〈不都号〉は、ニコラ・テスラの無線送電実験の影響を調べるため、南極点から地球内部に入り、空洞を抜けて北極に出現。ロシアのライバル飛行船とベニス上空で交戦したかと思えば、タイムトラベラーの誘惑を逃れるためハーモニカ楽団に偽装(なぜに?)。内陸アジアでは潜砂フリゲート艦〈サクソール号〉に乗り込み、伝説の砂漠都市、シャンバラを探求する……。
ヴェルヌかドイルもかくやというこの冒険物語と並行するもう一本の軸が、トラヴァース一家の物語。銀鉱山で働く父ウェブの裏の顔は、線路や鉄橋を爆破する無政府主義テロリスト〈珪藻土キッド〉。だが彼は、テスラの研究にも出資している大富豪スカーズデールが雇った殺し屋によって殺されてしまう。以降は、残された四人の子供たちの人生と復讐の物語が複雑怪奇にからみあいながら進んでゆく。中心になるのは、父の仇とも知らずスカーズデールから学費の援助を受けてイェール大学に通い、数学を勉強してベクトル主義者となった末っ子のキットで――とか説明しているとキリがない。
“脱線に次ぐ脱線、錯綜する人間関係、時間と空間を超え展開する物語。(中略)あらゆる知識、あらゆる断片、あらゆるアイディアとガラクタをかきあつめ、あらゆる境界線を破壊するパラノイア的想像力が生みだした文学史上最高最大、究極のスーパーフィクション”という、国書刊行会版『重力の虹I』カバー裏の惹句は、そのまま本書にもあてはまる。しかもこちらは、誰が主役かもわからない群像劇。冒険小説、西部劇、伝奇、SF、歴史、スパイ、ロマンス、オカルト、戦争活劇、コメディ、官能……とあらゆるジャンルを横断しつつ、ピンチョンは“9・11以後”を映した奇怪な迷宮を建設する。同時代の日本の小説で言えば、奥泉光『神器』と舞城王太郎『ディスコ探偵水曜日』と古川日出男『聖家族』を混ぜて三倍に煮詰めた感じ? 『重力の虹』よりはずっと読みやすいものの、話の道すじを見失いがちなこと(物語の行き当たりばったりぶり)にかけてはひけをとらない。登場人物を五分の一に、分量を三分の一にするくらいでちょうどいいかも。とはいえ、ピンチョンの場合、無駄な細部の饒舌にこそ読書の快楽があるから始末に負えない。たとえば、“急角度に削られた斜面に挟まれた谷を埋めるように、失敗したタイムマシン――〈クロノクリプス〉〈アシモフ型世紀横断機〉〈時間変性機Q98〉――が、使える部品をすべて外された状態で、捨てられていた”とか、“森の模様がプリントされた風呂敷をカウガールのバンダナのように三角折りにして巻き、ビール割りのウィスキーを驚異的なペースでぐいぐい飲”む美貌の天才数学者、釣鐘ウメキ嬢とか。
対策としては、お気に入りの人物を見つけて道しるべにすること。わたしのお薦めは、オカルト的秘密結社TWITの庇護下にあるヤシュミーン。セックスのあいだもゼータ関数が頭から離れない数学おたくのレズビアン美女です。
ちなみに、それでも最後には(詐欺のような)美しい結末が待っているのでご安心を。健闘を祈る。
関連コンテンツ
著者プロフィール
トマス・ピンチョン
Pynchon,Thomas
1963年『V.』でデビュー、26歳でフォークナー賞に輝く。第2作『競売ナンバー49の叫び』(1966)は、カルト的な人気を博すとともに、ポストモダン小説の代表作としての評価を確立、長大な第3作『重力の虹』(1973)は、メルヴィルの『白鯨』やジョイスの『ユリシーズ』に比肩する、英語圏文学の高峰として語られる。1990年、17年に及ぶ沈黙を破って『ヴァインランド』を発表してからも、奇抜な設定と濃密な構成によって文明に挑戦し人間を問い直すような大作・快作を次々と生み出してきた。『メイスン&ディクスン』(1997)、『逆光』(2006)、『LAヴァイス』(2009)、そして『ブリーディング・エッジ』(2013)と、刊行のたび世界的注目を浴びている。
木原善彦
キハラ・ヨシヒコ
1967年生まれ。大阪大学教授。訳書にトマス・ピンチョン『逆光』、リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』、アリ・スミス『両方になる』『夏』、オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』、ジョン・ケネディ・トゥール『愚か者同盟』、ジャネット・ウィンターソン『フランキスシュタイン』など。ウィリアム・ギャディス『JR』の翻訳で日本翻訳大賞を受賞。著書に『実験する小説たち――物語るとは別の仕方で』『アイロニーはなぜ伝わるのか?』など。