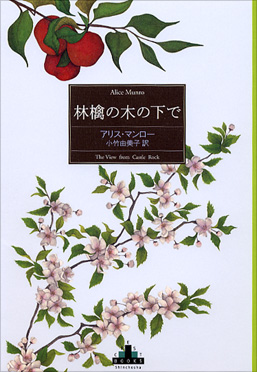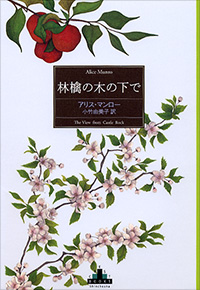
林檎の木の下で
2,640円(税込)
発売日:2007/03/30
- 書籍
三百年の時を貫いて描かれる短篇の女王マンローの芳醇な最新作品集。
17世紀、エディンバラの寒村に暮らしていた遠い祖先。やがて19世紀前半、一家三代でカナダへ。語り部と物書きの血が脈々と流れるマンロー一族の来し方を、三世紀に亙る物語として辿りなおす。実直な父、世故に長けた母、階級の違う婚家、新しい夫との穏やかな暮らし……人生のすべてが凝縮されたような自伝的短篇集。
キャッスル・ロックからの眺め
イリノイ
モリス郡区の原野
生活のために働く
林檎の木の下で
雇われさん
チケット
家
なんのために知りたいのか?
書誌情報
| 読み仮名 | リンゴノキノシタデ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 432ページ |
| ISBN | 978-4-10-590058-8 |
| C-CODE | 0397 |
| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |
| 定価 | 2,640円 |
書評
波 2007年4月号より ここに「わたし」は、なぜ在るか アリス・マンロー『林檎の木の下で』
神話の神や邪悪な妖精たちが、まだ土地に息づいていた十八世紀・スコットランド。「わたし」の祖先は、石ころだらけの農場に住んでいた。次の世紀、今度は老人、子供を含む次世代の一行が、リースの港から船にのって、新しい土地、カナダへと入植する。
舞台が「わたし」の幼年時代へと移るころ、「わたし」=マンローの、父母、そして祖父母たちが、ようやく視野に入ってくる。たくましく陽気な女たち(もっとも、このヨメと姑は仲が悪い)、寡黙な父と祖父。彼ら異性の一族を描くとき、マンローの筆には心なしか、温かみが加わる。
農夫であった祖父は、「勤勉で規則正しくひっそりと」生き、毎日、薪をきちんと積み上げた後、つまり仕事をすっかり片付けてから、本を読むという人だった。そのうえ、「彼らは必ずしも稼げるだけの金を稼ごうとはしていなかった」。生活を楽にするためにより多くの金を稼ぎ、少しの間も惜しんで働こうとするのは、みっともないと思われていたのかもしれないとある。目からうろこの労働観だ。
その祖父の一人息子であった著者の父は、いくつかの仕事を経た晩年に、小説を書きだす。そのときの描写がいい。
「書いてみて驚いたんだ、と父は言った。自分にこんなことができるんだ、ということに驚き、それがとても楽しめることに驚いたのだ。まるでその道に父の未来があるかのように。」ここには人間が変容する、輝く瞬間が書きとめられている。
「チケット」は、嫁に行く前の「わたし」が、祖母、祖母の妹、チャーリーおばさんと心通わす物語だが、苦い結末が予感される結婚に、影のように重ねられるのは、若かりし頃の祖母の恋、別の相手(祖父)と結婚した顛末。「わたし」は祖母に聞く。「『こわいと思ったことはなかったの? あのほら――』あるひとりの人間とともに人生を生きることをとわたしは言いたかったのだ。」
ここを読んだとき、何かが私の心の深部から、汲みだされたという感じがした。「わたし」は続きを結局言わなかった。けれど、その沈黙のなかに、祖母も祖母の妹も、そのこわさを通ってきた者であるということが、はっと明らかになる。その啓示の光は三人を結びつけ、さらには読者をも、引き寄せて射抜く。
日頃、私たちが持つ大方の感情は、ほとんどが行き場もなく、時間という、唯一の処方箋によって葬られていく。けれども、アリス・マンローの小説を読んでいると、葬られたはずのそれらは、なくなったのではなく、生きていくための合理性によって、ほんのちょっと、脇にどけられただけだったと気づくのである。
日常のなかの当たり前のこと、ごく見慣れた風景のなかから、マンローは、その始末されたはずの感情を、あっと思うような速度であらわにする。その一瞬は、いつも深いところから、ふわっと一気に浮上する。ふわっと一気に、と感じるのは、私たちが、普段、ソレに蓋をして生きているせいだろう。
蓋をはずす一行が、どこに潜んでいるか。それはわからない。読んでしまうまでは。それにたぶん、読む人ごとに違うのだろう。読書とは一体にそういうものだが、マンローを読むとき、読者は今に至るまでの自分を総動員することになる。させられるのでなく、自然、そうなる。
短評
- ▼Koike Masayo 小池昌代
-
19世紀初頭、スコットランドを出てカナダヘと入植し、貧しくも逞しく生きた著者の血族。土地の温もり、休息なき労働、誇り高い知性、慎ましさと野心。記憶と想像力が紡ぎだした人物は、魅力的であろうと、むごく野卑であろうと、あまりに生々しく生きているので、読んでいると血が騒ぎ、自分の家族あるいは自分自身が、そこに透けて見え、たじろぐのだ。あらゆる「わたし」を、「今ここ」に運び、やがて彼方へと押しやる力。わたしたちの血の内に、深く沈められた感情が、一つ一つ目覚めていく。なんてデリケイトで野性的な物語。
- ▼The Windsor Star ウィンザー・スター
-
驚くべき本だ。まるで自分の家族の歴史をひもといているかのようであり、色彩と洞察にあふれ、懐古趣味ではとうてい語りえない豊かさに満ちている。
- ▼The Atlantic Monthly アトランティック・マンスリー
-
あらゆる点でマンローの愛読者の期待にかなう、ずっしり読み応えのある見事な作品。さらに本書だけが当てはまるまったく新しいジャンルを創出している。
- ▼The Ottawa Citizen オタワ・シチズン
-
一篇一篇が非のうちどころなく精巧に仕上げられた珠玉の作であり、事実以上の力を持つ真実を描きだしている。
- ▼Books in Canada ブックス・イン・カナダ
-
マンローは、読者の生き方を変えうる稀有な作家のひとりである。
著者プロフィール
アリス・マンロー
Munro,Alice
(1931-2024)1931年、カナダ・オンタリオ州の田舎町に生まれる。書店経営を経て、1968年、初の短篇集 Dance of the Happy Shades(『ピアノ・レッスン』)がカナダでもっとも権威ある「総督文学賞」を受賞。以後、三度の総督文学賞、W・H・スミス賞、ペン・マラマッド賞、全米批評家協会賞ほか多くの賞を受賞。おもな作品に『イラクサ』『林檎の木の下で』『小説のように』『ディア・ライフ』『善き女の愛』『ジュリエット』など。チェーホフの正統な後継者、「短篇小説の女王」と賞され、2005年にはタイム誌の「世界でもっとも影響力のある100人」に選出。2009年、国際ブッカー賞受賞。2013年、カナダ初のノーベル文学賞受賞。
小竹由美子
コタケ・ユミコ
1954年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。訳書にマギー・オファーレル『ハムネット』『ルクレツィアの肖像』、アリス・マンロー『イラクサ』『林檎の木の下で』『小説のように』『ディア・ライフ』『善き女の愛』『ジュリエット』『ピアノ・レッスン』、ジョン・アーヴィング『神秘大通り』、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』、ジュリー・オオツカ『あのころ、天皇は神だった』『屋根裏の仏さま』(共訳)、ディーマ・アルザヤット『マナートの娘たち』ほか多数。