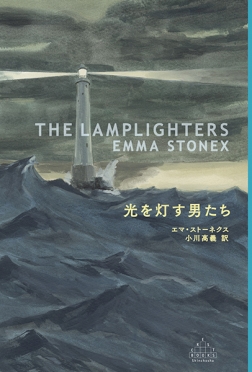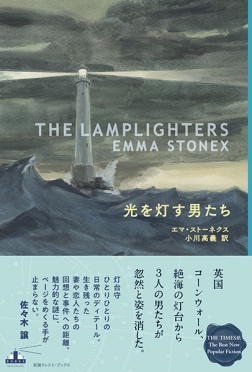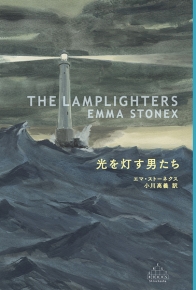
光を灯す男たち
2,640円(税込)
発売日:2022/08/25
- 書籍
絶海の灯台から3人の男たちが消えた! 実在の事件を元にした傑作文芸ミステリ。
1972年末、英国コーンウォールの灯台から3人の灯台守が忽然と姿を消した。灯台は内側から施錠、食事も手つかずのままであった。8週間の任務、狭いベッド、夫婦の距離……。孤絶したコミュニティの中で、灯台守とその妻たちに何が起きていたのか? 誰もが光として抱えてきた思いが、20年前の未解決事件の謎を解き明かす。
書誌情報
| 読み仮名 | ヒカリヲトモスオトコタチ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |
| 装幀 | Naoki Ando/イラストレーション、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 384ページ |
| ISBN | 978-4-10-590183-7 |
| C-CODE | 0397 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 2,640円 |
書評
伝統の灯台奇譚に新しい解決
本書には、モデルとなった事件がある。イギリスではかなり有名なもののようであるし、最初にこの事件のことを書いても、ネタをばらすなと作者は怒るまい。読者の楽しみを奪うことにもならないだろう。
また、たぶん欧米では、これまで多くの表現者たちがこの事件の解釈に挑み続けてきたのではないか。それほどまでにこの奇譚は好奇心をそそるし、クリエーターの想像力を刺激する。そこにいまひとつ、豊かで魅力的な解釈が加わったのだ。本書『光を灯す男たち』だ。
現実のその事件は、スコットランド沖フラナン諸島の中のアイリーン・モア島で1900年に起こった。ただし本書は、場所も時代も、アイリーン・モア灯台事件とは違えてある。
本作は、1972年、イギリス南西部ランズエンド岬沖の岩礁上の灯台で起こった、という設定だ。ネットで灯台のあるロングシップス島の写真を見ると、なるほど著者がここを舞台とした理由もわかる。灯台が建っているのは、「島」と呼べるほどの大きさもない(つまり灯台の外にも隠れ場所などない)岩礁なのだ。
アイリーン・モア灯台事件は、最近映画にもなっていた。2018年のイギリス映画「バニシング」だ。監督はクリストファー・ニーホルム。本作は刊行されたのが2021年だが、当然ながら、「解釈」はその映画ともまったく違うものとなっている。
それにしても、新年に近い冬のある日、北の海の岩礁の上に建つ灯台から、灯台守の男三人が消えた。内側からロックされた扉。日常生活が継続していた様子。事故や犯罪の痕跡はない。
何が起こった? なぜ彼らは消えた?
これ以上はないと思えるほどに極限的な密室空間、読書欲をそそる謎。しかも灯台は、分銅の重みでレンズを回転させるクラシカルな機械式だ。その構造や動き方を想像するだけでも、謎に「アナログ的な深み」が加わる。無機的な事故などではないという確信が深まっていく。
事件から二十年経った1992年まで男たちは見つからず、何があったのか解明されなかった。1992年になって、残された妻たち、若い見習い灯台守の恋人だった女性のもとに、小説家が接触してくる。事件について聞かせてほしいと。事件についての彼の執着も、謎として物語を駆動させている。
小説家の接触が、凍結されていた事件をもう一度融解させてゆく。生き残った妻や恋人の回想。彼女たちの事件への距離。思い入れの濃淡。
当事者たちが過去と二十年後を行き来して語ることで、読者は最初想像もできなかった方向から、事件の様相を見るようになるのだ。
やがて三人称で、消えた男ひとりひとりの、灯台守としての生活が、またその事件前後の緊張感漂う日常と、ほかの灯台守との関係が記述されていく。
それは客観性のある描写なのか? それとも作中の小説家が提示する、新しい仮説なのか。
読者は記述の仕掛けまでも探しつつ、このサスペンスフルな物語を読み進めることになる。
作者が、アイリーン・モア灯台事件をそのまま小説化するのではなく、わざわざ1972年の事件として書いた理由も、読書を進めるうちに、沖の海霧が薄れてゆくように見えてくる。
作者は、十九世紀の英国労働者階級の男たちの物語ではなく、現代人が遭遇した事件として、設定する必要があったのだ。ただし、記憶の凍結が融解され、その解釈が仮説として受け入れられるだけの時間が経っていることも要件であった。
息苦しさを感じつつ最後の一ページまでを読んで、読者はようやく自分が北海の岩礁上の灯台から外に出たことを意識する。設定こそ密室もの本格ミステリーそのものであるが、読後、自分はまぎれもなく現代を生きる読者にとっての「恐怖」の物語を読んだのだと理解する。
そして書を閉じるとき、読者はいまいちど、その灯台が何の象徴であったのかと、荒れる海に規則的に光を回転させる灯台の姿を思うのだ。
(ささき・じょう 作家)
波 2022年9月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
暗い孤立の時代に灯台守が照らす道。

絶海の灯台から三人の男が忽然と消えた――。実在の事件をモデルに、灯台守とその妻たちに起きた人間模様を解き明かす話題作で、第二のデビューを飾ったストーネクス。編集者から小説家に転身した彼女が、なぜ灯台の世界を描いたのかを語る。
翻訳:小川高義
もし灯台守になったらどうだろう。遠くに離れ、ほとんど隠れ住むと言ってもよさそうだ。そんな職業について、以前の私が思い浮かべたのは、せいぜいカモメが風に舞い飛んで、髭面の海の男がパイプをくわえている、というようなものだった。そんなロマンチックな灯台イメージを持つ人は多いだろう。だが深く知るようになるほどに、実態はまるで違うとわかった。いや、まるで違っていた、と言うべきかもしれない(有人で管理される灯台は、もう消滅したのだから)。
陸地にある灯台、たとえば赤い縞が目立つポートランドビル灯台や、陸続きのランドウィン島に指貫のような形で立っている灯台は、沿岸に愛すべき立ち姿を見せていて、もちろん魅力はあるのだが、とくに私が心を惹かれるのは、沖合の岩礁にある灯台だ。まさかこんなところにと思うような海の中から、堂々たる塔が立ち上がっている。ベルロック灯台、ビショップ灯台、ロングシップス灯台――。かの有名なエディストーン灯台は、プリマスの南沖にあって、その岩礁では四代目の塔が、ほぼ二百年におよぶ努力の結果として立っている。その隣に土台だけ残っているのは、スミートンが設計した三代目の痕跡だ。これを見ただけでも、水は建造物を支えてくれないという当たり前のことがよくわかる。
岩礁の塔は、遠くから見れば、水平線上の幻影だ。ランズエンド岬に立って、ロングシップス灯台を見るとしよう。さほど遠くない。わずか一カイリの距離である。もっと沖へ、ぼんやりした遠くまで目を凝らすと、晴れた日なら、うっすらとマッチ棒のようなものが見えるかもしれない。その名も恐ろしいウルフロック灯台。八カイリの沖にあって、岩礁を吹き抜ける風の唸りが、ウルフという名の由来になっている。現在のイギリスでは、灯台はすべて自動で管理されていて、最後の一基も1998年に電化された。その昔は、三人の男が常駐することになっていた。島流しのような職場で、一度行けば二カ月は帰らない交替勤務である。
海の真ん中で、ほかの二人しかいない。部屋は広がらず、縦方向に積み上がる。二歩も踏み出せば突き当たって、もう行き場がない。狭苦しく、薄暗く、汗とタバコと焦げたベーコンの匂いが立ち込める。荒天時にはシャッターを閉じる。窓は二重になっているが、波しぶきが八十五フィートも飛んでくることがある。茶を飲んでいると、その高さの窓ガラスを波がたたく。嵐の最中には、塔の全体が電流を浴びたように揺らぐ。岩が基底部にぎしぎしと迫って、これで倒れないのだから奇跡かと思えた。
執筆の下調べにとりかかった私は、じつは灯台のことを何一つわかっていなかった。子供の頃に、陸の灯台を見たことは何度かあったのだが、たぶん当時はつまらないとでも言っていたのだろう。灯台の魅力に気づいたのは、二十代になってからのことだ。最近、どうして灯台好きになったのかという質問を受けた。それで記憶をたどろうとしているが、行き着くのはワイト島にあった祖母の家かもしれない。階段の窓から、灰色のソレント海峡や、本土側に見えるフォーリー発電所の煙突をながめていた。あるいは学期の中休みに、ノーフォークの泊まれる風車へ行ったせいだろうか。部屋が丸くて、ぐるぐる上がって回廊へ出ると、白い格子形の羽根が、空への梯子のようにきらめいていた。
海図のない水域に漕ぎ出して、ますます深みにはまることになった。灯台守と言われた人たちが、どうやって生きていたのか知りたくなった。どうしてこの仕事について、どれだけの代償があって、ずっと続けていられたのか――。当事者による証言を、できるだけ読んでみた。回想、自伝、また名著と言うべきトニー・パーカーの『灯台』に収録された聞き書きの記録。
そういう生活が好きだから灯台守になった人もいる。いや、好きどころか、必要としたのでもある。海と仲良く暮らして、空模様を読めた。絵を描いて、本を読んで、ボトルシップを作って気晴らしができた。そんな人にしてみれば、灯台は文句なしの孤独、平和、静穏をもたらす。その一瞬に集中して生きる(いまの言葉だとマインドフルネスかもしれない)には好都合だろう。灯台は通りかかる船の安全をはかるだけではなく、勤務する人の安全な居場所にもなっていた。それで淋しくなかったのだろうか。むしろ逆だ。陸地にいると、舵を失った船のようになった。八週間たつと家に帰って、通常の生活に入り込まねばならない。また普通の男になる。夫になり父になる。陸の生活はペースが速すぎる。落ち着かない。むやみに広い。灯台にいれば領域の固定された狭さに安んじていられる。しばらく灯台にいて、陸に帰ったらどうなるか。ついに船を下りたと思えば、脚がふらついて、地面が当てにならない。そんな気分にもなるだろう。
一方で、帰りたくてたまらなかった人もいる。沿岸の灯台か、それなりに大きな島の灯台なら、どうということもなく務まるが、岩礁の灯台だけは苦手である。そこまで特殊な任地だと、隔離されたようで精神がおかしくなる、ということで異動願いが出された例もある。もし私だったらどっちだろうと考えた。一人でいることは好きだ。あまり退屈はしない。海に出て平気かもしれない。それも灯台に魅力を覚えた一因だろうが――さて、どうにか頑張れたとして、僧院のような生活を喜べるだろうか。2021年現在、私たちはみな何らかの形で孤立することに慣らされた。私が考えたいのは、そんな孤立状態をあえて選ぶのだとしたら、その人は、何から、何に向かって、逃げようとするのか、ということ。
調べていくうちにわかってきた。灯台守になる人が、内気、弱気ということはない。ものごとを現実的に考えて、何でも綿密に処理する。それでいて何世紀にもおよぶ伝説につきまとわれる職務でもあったはず。私が気になるのは、ある灯台に補佐として勤めていた男の話だ。塔の入口まで下りて魚を釣っているうちにいなくなった。あっさりと、ただ消えた。波は静かで、鳥の群れが回って、空は青く、まったく異常はない。この世から一人だけかき消えたようなもの。
もう一つ、スモールズ灯台での事件がある。1801年のこと、ある灯台守が死んでしまった。その相棒は、殺人を疑われることを恐れつつ、補給船が来るまで何週間も遺体と過ごすことになった。おぞましい事件を再発させまいと、〈トリニティ・ハウス〉(水先案内協会)は管理上の改善策として、各灯台の駐在員を二名から三名に増やした。そして、さらに、これぞ灯台にまつわる伝説の決定版というべき謎がある。もはや神話の域に近い。1900年に、アウター・ヘブリディーズ諸島のアイリーン・モア島で、一度に三人の灯台守が失踪した。どんな運命に見舞われたのか、いまなお真相は不明である。そのことが私の小説にとってのインスピレーションになった。
だが灯台守の生き方だけに興味を惹かれたのではない。それぞれの妻にも人生があった。夫の職務に合わせて生きることを迫られた女たち、と言うこともできよう。あてがわれた住宅に暮らして、任地が変われば国中のどこへでも移るしかない。しかしパイオニアだったと言えなくもない。灯台守の女房は、思い通りに家庭を切り盛りした。夫が留守なら、妻が一家の主である。年間のかなりの部分でシングルマザーになっていて、何につけ自分の流儀で決められる。もちろん、さびしい無限の海を見てばかりの、厳しい暮らしではあったろう。私が作家になろうとしたとき、生まれた娘は六カ月になっていた。赤ん坊を抱えて、眠れずに困り果てた長い夜に、遠い灯台を見る心境がわかるような気がした。あっちに夫がいると思いながら、手が届くわけではない。海とは、すなわち距離である。そんなことを思った。現実の距離でもあるし、心の距離でもある。うっかり油断すると、難しい時期に夫婦を隔てる海になる。そういう妻たちの物語に、深い共感を持てると思った。
2018年の夏、デヴォン州のブルポイント灯台へ行ってみた。灯台守の住宅を改装したコテージに、一人で三泊したのだった。曲がりくねる細い道を下って、ぎりぎりまで海に近づいた岬の突端に、住宅がならんでいた。小説家としては、一日ずっと海を見ていると思えばロマンチックな気分だが、しばらく見ていたら、ただ広いだけで無感動な海が、解放感よりも圧迫感をもたらしてきた。それまでの調査で、もう私にもわかっていた。有人の灯台は、浴室の置物からイメージするような灯台とはわけが違う。人間の努力と忍耐が折り重なった貴重な歴史を守ろうとしながら、実地に関わる人々にとっては、光にも闇にもなるものだった。
去年(2020年)から今年にかけて、ある意味で、私たちはみな灯台守になったのではないかと思えてきた。誰もが自分の塔にいるしかない。わずかでも一緒にいる人がいれば幸運だ。ちらりと遠くに陸地が見えて、再出発の望みもありそうな気がする。いまの生活で知っておいてよいことを、灯台がしっかり教えてくれる。だから私は灯台が好きだ。もし距離があったら越えるがよい。離れるよりは近づくのがよい。暗闇は照らすこともできる。伸ばしてくれそうな手があれば、さびしさは薄らぐ。
Emma Stonex
1983年、英国ノーサンプトンシャー生まれ。大手出版社の編集者を経て小説家となり、いくつかのペンネームでこれまでに9作のエンターテインメント小説を出版。初めての文芸作品となる本作は、英大手出版社Picadorの編集者に絶賛されて出版前から話題となり、発売早々サンデータイムズ紙などでベストセラーにランキングされた。
“How lighthouse keepers show us the way in dark, isolated times”
First Published on The Observer, Mar. 13,2021.
(エマ・ストーネクス)
「新潮クレスト・ブックス 2022-2023」小冊子より
単行本刊行時掲載
短評
- ▼Sasaki Joh 佐々木譲
-
イギリスの、灯台をめぐるあの奇譚がモデルだろう。でもあちらは1900年の事件。こちらは1972年という設定。この時代の差に意味はあるのか? またこれはモデルとなった事件の新しい解釈の提示なのか? それともまったく違う視点から叙述された、別の種類の物語なのか? 魅力的な謎に、ページをめくる手が止まらない。灯台守ひとりひとりの日常のディテール。生き残った妻や恋人たちの回想と事件への距離。小説家の執念の理由。読後、読者はいまいちど、その灯台が何の象徴であったのかと、荒れる海に規則的に光を回転させる灯台の姿を思うのだ。
- ▼The Guardian ガーディアン紙
-
ゴースト・ストーリーと、見事な捜査心理学とがひとつになった作品。しかも文章は素晴らしく洗練されている。シャーリイ・ジャクスンの作品やサラ・ウォーターズの傑作『半身』と同様、いわゆる超常現象と呼ばれるような、検証不可能で、語られることもなく、目には見えない、抑圧と虚構に蝕まれた世界が、ストーネクスの手にかかると、恐ろしいほど具体的になってくるのだ。
- ▼Kate Riordan ケイト・リオーダン
-
思慮深く、美しく、静かに破滅的な調べをもつこの作品は、他の小説にはないやり方で、読者の心を揺さぶる。最後のページを読んでから何週間も経つのだが、いまだに胸が痛む。
- ▼Emylia Hall エミリア・ホール
-
これまで読んだ本の中で最も不思議な本のひとつ。文章はまばゆいばかりに素晴らしく、謎解きはユニークで魅力的。そして何よりも、優しさと人間らしさと気品に溢れている。
著者プロフィール
エマ・ストーネクス
Stonex,Emma
1983年、英国ノーサンプトンシャー生まれ。出版社ヴィラゴ・プレスの編集者を経て小説家となり、3つのペンネームで9作のエンターテインメント小説を刊行。初めて本名で発表した『光を灯す男たち』は、英大手出版社Picadorの編集者に絶賛されて出版前から話題となり、2021年の発売早々、タイムズ紙などのベストセラー書ランキングに入った。
小川高義
オガワ・タカヨシ
1956年横浜生まれ。東大大学院修士課程修了。翻訳家。ホーソーン『緋文字』、ヘミングウェイ『老人と海』、ジェイムズ『ねじの回転』、ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『見知らぬ場所』『低地』、トム・ハンクス『変わったタイプ』、『ここから世界が始まる トルーマン・カポーティ初期短篇集』、エリザベス・ストラウト『ああ、ウィリアム!』など訳書多数。著書に『翻訳の秘密』がある。