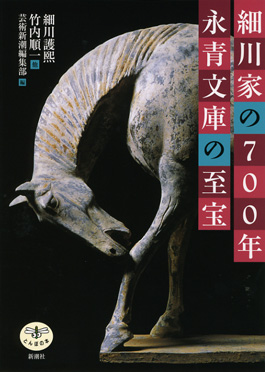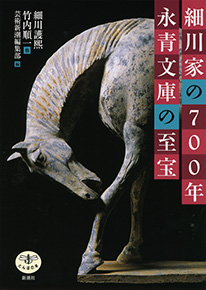
細川家の700年 永青文庫の至宝
1,540円(税込)
発売日:2008/10/24
- 書籍
中世から現代まで、波乱万丈のファミリーの美と闘いの歴史を、永青文庫所蔵の名品でたどる。
足利幕府の名宰相・頼之、乱世の達人・歌人幽斎と茶人三斎、悲劇の女性・ガラシャ、肥後の鳳凰・重賢から、近代屈指の大コレクター・護立侯爵、そして元首相にして陶芸家の護熙まで、細川家の人々はまことに多士済々。山あり谷ありの700年を生き抜いたファミリーの“遺伝子”と“遺産”に迫る! 築城400年の熊本城も特別撮影!!




【グラフ】
細川家の700年
城から城へ 細川家の中世 小和田哲男
歌に遊び、茶に憩う 乱世の達人・幽斎と三斎
茶の湯vs.世界基準
細川家の茶道具・やきもの20選 竹内順一
女たちの細川家
細川家240年の居城 甦った熊本城
財政難もなんのその 肥後国主200年の夢
〈往復書簡3000通〉細川家、情報戦を制す 山本博文
◆対談◆
「殿様」の思い出 護立コレクションをめぐって 細川護熙/佐久間幸子
永青文庫の過去、現在、未来 奥田尚良
◆コラム◆
武蔵はともだち
第一八代当主細川護熙 晴耕雨読の日々
古書コレクター垂涎 コルディエ文庫と坦堂文庫
細川家略系図 中世篇
細川家略系図 近世・近代篇
書誌情報
| 読み仮名 | ホソカワケノナナヒャクネンエイセイブンコノシホウ |
|---|---|
| シリーズ名 | とんぼの本 |
| 雑誌から生まれた本 | 芸術新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | A5判 |
| 頁数 | 128ページ |
| ISBN | 978-4-10-602180-0 |
| C-CODE | 0371 |
| ジャンル | 芸術一般 |
| 定価 | 1,540円 |
担当編集者のひとこと
細川家の700年 永青文庫の至宝
国宝8点、重要文化財31点、総蔵品数は90,000点! 永青文庫は収蔵品の質も量も、日本を代表する美術館のひとつです。しかし、実際にこの美術館を訪ねたことがある人は、意外と少ないのではないでしょうか。 永青文庫は目白台の丘の上、シイノキや松の古木が鬱蒼と茂る森の中にあります。このあたり一帯は、もともと細川家の下屋敷があったところで、永青文庫理事長の細川護熙さんによると、そこには「孔雀が放し飼いにされていた」こともあるそうです。現在、展示室が設けられている建物は、昭和初期の建造で、もともと細川家の「家政所」として使われていたもの。昭和25(1950)年、護熙氏の祖父に当たる細川護立侯爵が、細川家が700年にわたって蒐集してきた武器や武具、茶道具、そして稀代のコレクターとして知られる護立侯が蒐めた古書画、陶磁器、彫刻、近代書画などの美術品を管理する財団法人としてここに「永青文庫」を設立し、昭和47(1972)年からは一般公開もされるようになりました。
その展示スペースは決して広いとはいえませんが、折に触れ、テーマを変えて所蔵品の展覧会が開催されています。美術品の展示だけでなく、護立侯が幾多の美術品を披露したであろう2階の応接間もそのまま開放されており、往時に思いを馳せることができます。
本書は、この永青文庫が所蔵する名品の数々を紹介しながら、その母体である細川家700年の歴史を辿るものです。室町幕府の管領として頭角を現してきた細川家は、戦国時代には文武に秀でた名将・藤孝(幽斎)、忠興(三斎)を輩出し、また忠興の夫人であったガラシャの悲話も語り継がれてきました。江戸時代、肥後54万石の大名として君臨した歴代の殿様たちの活躍も、あまり知られてはいませんが、とてもユニーク。
そういえば、今年は築城400年を記念して熊本城に本丸御殿が復元され、話題を呼びました。白木の香もすがすがしい、その本丸御殿の内部も撮影してきました。隣接する熊本県立美術館には「永青文庫展示室」が常設され、目白台の本館とあわせて名品が鑑賞できます。
中世から現代まで、波瀾万丈の700年を生き抜いたファミリーの“遺伝子”と“遺産”をたっぷりとお楽しみください。
2008/05/23
著者プロフィール
細川護煕
ホソカワ・モリヒロ
1938年、東京都生まれ。朝日新聞記者を経て、衆参議員、熊本県知事、日本新党代表、内閣総理大臣を歴任。政界引退後、神奈川県湯河原の「不東庵」にて作陶、書、水墨、茶杓作り、漆芸などを手がける。財団法人永青文庫理事長。著書に『不東庵日常』(小学館)、作品集『晴耕雨読』(新潮社)、『ことばを旅する』(文藝春秋)など。
竹内順一
タケウチ・ジュンイチ
1941年、神奈川県生まれ。1966年、東京芸術大学美術学部卒業(工芸史専攻)。五島美術館学芸部長、東京芸術大学大学美術館館長を経て、2007年より永青文庫の館長。専門は茶道美術史、陶磁史、美術館学。著書に『織部』(中央公論社『日本陶磁全集』第16巻)、『美術館へ行こう(やきものと触れあう 日本)』(共著 新潮社)などがある。