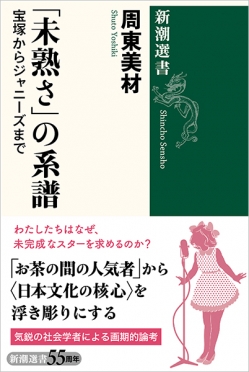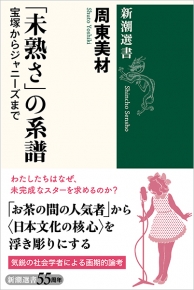
「未熟さ」の系譜―宝塚からジャニーズまで―
1,705円(税込)
発売日:2022/05/25
- 書籍
- 電子書籍あり
わたしたちはなぜ、未完成なスターを求めるのか?
若さや親しみやすさで人気を得るアイドル、ジュニアから養成されるジャニーズ、音楽学校入試が毎年報じられる宝塚歌劇団……成長途上ゆえのアマチュア性が愛好される芸能様式は、いかに成立したのか。近代家族とメディアが生んだ「お茶の間の人気者」から日本文化の核心を浮き彫りにする、気鋭の社会学者による画期的論考。
初出・関連研究一覧
書誌情報
| 読み仮名 | ミジュクサノケイフタカラヅカカラジャニーズマデ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮選書 |
| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 288ページ |
| ISBN | 978-4-10-603879-2 |
| C-CODE | 0373 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 定価 | 1,705円 |
| 電子書籍 価格 | 1,705円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2022/05/25 |
書評
「未熟さ」と「成熟」のあいだで思案する
プロデューサー・秋元康自身が述べたとされる「K-POPはプロ野球、AKBは高校野球」という比喩は、現在では一種の紋切型になっている。プロの高度な技術を堪能するのではなく、技量において未完成な少年少女が、苦難に立ち向かい奮闘し、時には失敗しながら成長してゆく過程を、手に汗握って見守り、応援する、というあり方が日本のアイドル文化の特徴だというわけだ。こうした認識は日本国内に留まらないようで、実際、数年前に中国のアイドル文化における日本の影響について研究したい、という中国人留学生から、日本の影響下にあるアイドル類型として「育成系」という括りがあることを教えられた。
本書『「未熟さ」の系譜―宝塚からジャニーズまで―』は、現代の「アイドル」に至る「未熟さ」への偏愛のあり方が、どのような歴史的条件のもとで成立し、産業化され、メディアを通じて拡散し、意味づけられたのか、を扱う。その射程は広く、1920年代の童謡、宝塚少女歌劇から、1960年代の渡辺プロダクション、ジャニーズ、グループ・サウンズを経て、1970年代以降の「アイドル」のあり方を決定したテレビ番組、「スター誕生!」に至る。単に類似の事例を年代記的に並べるだけではなく、それが日本の近代(化)とどのような関係を結んでいるのかに深く分け入る。新中間層の形成と、「女、子ども」の空間としての「家庭」。そうしたイメージを喚起しまた体現するその時々の新興メディア(雑誌、レコード、舞台、なによりテレビ)と産業。そして、「未熟さ」を体現する「日本」に対する、優越した鑑としての「西洋」とりわけ「アメリカ」。個々の章での、目配りの利いた資料渉猟に基づく明晰な論述は、学術的な精密さと一般的な読みやすさを高い次元で両立させている。その上での終章での理論的な総括のスケールの大きさと分析の切れ味は抜群だ。
本書の歴史社会学としての精度の高さは、前著『童謡の近代』を引き継ぐものだが、グループ・サウンズを論じる章では、著者が独自に行なった元ザ・タイガースの瞳みのるのインタヴューが大きく参照されているのが興味深い。十分な資料的裏付けを伴った当事者の証言は、論述の説得力を大いに高めている。ザ・タイガース解散後、高校教師に転じた瞳は、近代日本の音楽教育史にも大きな関心を持っており、同志的な信頼関係がうかがわれる。この二人の本格的対談を読んでみたい、と思った。
さて、同業者による書評のお約束として、いくつかの疑問点を提示しておこう。まずは、日本における「未熟さ」愛好が、近代に特有の現象なのか、それとも、それ以前から潜在してきた傾向が、近代化の過程で変化したものなのか、ということ。本書の卓抜な表現を借りれば、「子ども」は「異文化受容の緩衝装置の役割を担ってきた」という。西洋文化輸入の実験と教育の草刈り場としての「子ども」というわけだ。この指摘には膝を打ったが、一方で、娘義太夫や女剣劇など、本書で強調する(想像上の「西洋」を模範とした)「家族」像から逸脱する、ある種土着的な「未熟さ」への愛好の系譜も存在してきたように思える。少なくとも美空ひばり、こまどり姉妹、藤圭子あたりまではそうした系譜を描けるだろう。
もうひとつは、本書の射程は「1920年代から1960年代まで」という一連の時代なのか、それとも「1920年代と1960年代」という大きな社会変化を伴う2つの時代なのか、ということだ。比喩的に言えば、「未熟さの系譜」をなだらかな平野または丘としてイメージするのか、2つの山の隆起に挟まれた地形と考えるのか、となるだろうか。もちろんこれはポピュラー音楽という一領域に留まる議論ではなく、また連続と断絶の間の振幅自体が興味深いところであり、今後のさらなる議論が楽しみだ。
私自身の素朴な読後感としては、まず、自分は「未熟さ」への愛着をほとんど持たない無粋者であることを改めて自覚した。それでも、近代日本の「未熟さ」の鑑として想像的に設定された「西洋」の規範的な(本書でも指摘される軍事的男性性に加え、人種主義や帝国主義と共犯関係にある)「成熟」の側につくことは断固拒否したいと思った。本書の明晰な記述によって、「未熟さ」がほとんど「必然的」に思えてしまうため、その桎梏からは抜け出せないのか、と嘆息してしまった。「どうすりゃいいのさ思案橋」という、「未熟さ」からは程遠い昔の歌の文句をふと思い出したりした。
一方で本書には、「未熟さ」を相対化し、別の視点から読み替えるヒントも記されている。たとえば、戦前の少女歌劇の「男装の麗人」、水の江瀧子の人工的な「男らしさ」が、ジャニーズの兄貴分である「タフガイ」石原裕次郎へと引き継がれた、とする指摘は、「未熟さ」の系譜が、「家庭」の性的規範を超えて越境し逸脱してゆく可能性を示しているだろう。ジェンダーの人工性、上演性という観点からも興味深い。
多様な事例と、一貫した理論と、さらなる発展可能性を兼ね備えた、ポピュラー文化史の重要な成果といえる。
(わじま・ゆうすけ 音楽学者)
波 2022年6月号より
インタビュー/対談/エッセイ
ジャニーズとふたつの東京オリンピックのあいだ
拙著『「未熟さ」の系譜―宝塚からジャニーズまで―』を刊行したのは2022年5月。そのときには、ジャニーズ事務所(現・SMILE-UP.)という最大手の芸能集団が危機に陥るとは想像していなかった。ジャニー喜多川の性暴力とその隠蔽が白日の下に晒され、後継の東山紀之に「人類史上最も愚かな事件」と言わしめるに至った。その暴力は、後述するような米軍の占領・駐留という経験とも深く関わっていると私は考えている。
拙著が考察しているのは、なぜ日本の芸能界では、完成された技芸や官能的な魅力より、成長途上の「未完成なスター」が愛好される傾向があるのかという点である。その考察対象のひとつがジャニーズだった。
ジャニーズタレントの活躍は、幼いころからの日常の景色として馴染みはあった。私自身の記憶の中で特に印象的だったグループは、KinKi Kidsだ。1994年にドラマ「人間・失格~たとえばぼくが死んだら」に出演する彼らは、まだ正式なデビュー前だというのに、爆発的な人気を博し、中学のクラスの女の子たちが口々に話題にしていた。私にとっては初めての同世代の同性アイドルだった。華があって眩しく、ミステリアスでもあった。
そのころから、ジャニーズ事務所は、破竹の勢いで成長し、やがて国民的なアイドル集団の座に君臨していった。1993年の「琉球の風」の東山紀之以降、大河ドラマの主演を香取慎吾、滝沢秀明、岡田准一、松本潤が務めた。1995年の「24時間テレビ「愛は地球を救う」」ではSMAPがパーソナリティーとなり、また、同年の阪神・淡路大震災を機にJ-FRIENDSが結成された。1997年には中居正広が「NHK紅白歌合戦」の司会に就任、その後には嵐が続いた。
その快進撃と歩みをともにしたメディアは、もちろんテレビだった。しかし、ジャニーズ事務所が国民的なタレント集団へと上り詰めたとき、テレビ全盛の時代は曲がり角を迎えようとしていた。1990年代半ば以降といえば、「Microsoft Windows 95」が発売され、パソコンやインターネットが生活に入り込み、テレビの影響力は日増しに相対化されていくことになったのである。インターネット広告費は年々増加し、ジャニー喜多川が死去した2019年にはテレビ広告費を抜いた。
しかも、この1990年代半ばという時期は、ジャニーズ事務所の歴史から見ればちょうど中間の時期に位置する。最初のグループ「ジャニーズ」がレコードデビューしたのは、その30年前の1964年のことだった。彼らは未熟でアマチュア性が強調され、「未完のジャニーズ」などと評された。この年は東京オリンピックの開催年でもあり、特に女子バレーボールの「東洋の魔女」の活躍によって記憶されている。他方、ジャニー喜多川とメリー喜多川という強力な創業家が死去したのが2019年と2021年、2度目の東京オリンピックのときだった。ジャニー喜多川は2013年、オリンピックに向けた新グループ結成を発表、グループ名も「Twenty・Twenty」とした。だが当初の計画は実現せず、それどころか、2023年には事務所の看板そのものが消滅してしまう。
つまり、ジャニーズ事務所は、ふたつの東京オリンピックに挟まれるかたちで成立し、終焉を迎えたのであり、その中間の1990年代半ばの時点で、全盛期を過ぎつつあったテレビと結びつくことで、国民的なアイドル集団へと転換していったのだ。そして、私がテレビでKinKi Kidsを見ていたのも、まさにその転換の時期だったわけである。
ジャニーズ事務所の創始と東京オリンピックの関係は、単なる偶然ではない。ジャニー喜多川は、ロサンゼルス生まれの日系2世であり、戦後は日本で暮らした。生活の拠点となっていたのは、東京・原宿の米軍住宅地区「ワシントン・ハイツ」だ。彼はここで暮らしながら、アメリカ大使館に勤務し、日本の自衛隊の創設・指導に関与した米国機関MAAGJの一員として働いていた。ワシントン・ハイツは1964年のオリンピックを機に日本へと返還されて選手村へと作り変えられ、現在は代々木公園となっている。
代々木公園に隣接するランドマーク・国立代々木競技場は東京オリンピックの際に建設され、バレーボールの国際大会の試合会場にもなってきた。そして、1995年のV6から2011年のSexy Zoneまで、多くの新人タレントたちが、バレーボールのスペシャル・サポーターとして、この体育館からデビューしていった。そのパフォーマンスは、東京オリンピックの記憶に依拠しながら、ジャニーズの歴史的な誕生の地に再来する演出でもあったのだ。
2023年、ジャニーズ事務所のひとつのサイクルが閉じることになった。その終わりが2度目の東京オリンピックに重なることは、拙著執筆時には気づかなかった歴史の見え方である。それは、単にジャニーズ事務所の個別事情に留まらず、占領から高度経済成長期に確立した日本のメディアの来し方を問うものであり、そうした歴史の徹底的な反省なくして未来を構想することはできないだろう。
(しゅうとう・よしき 学習院大学教授)
著者プロフィール
周東美材
シュウトウ・ヨシキ
1980年、群馬県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、東京大学大学院学際情報学府修了、博士(社会情報学)。専攻は社会学、音楽学。東京大学大学院特任助教、日本体育大学准教授を経て大東文化大学社会学部准教授。著書に『童謡の近代』(岩波現代全書、第46回日本童謡賞・特別賞、第40回日本児童文学学会奨励賞)、『カワイイ文化とテクノロジーの隠れた関係』(共著、東京電機大学出版局、2016年日本感性工学会出版賞)など。