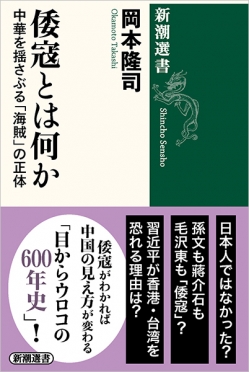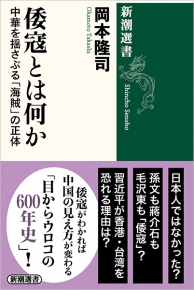
倭寇とは何か―中華を揺さぶる「海賊」の正体―
1,760円(税込)
発売日:2025/02/19
- 書籍
- 電子書籍あり
倭寇が中国の歴史を動かしてきた──驚きの「倭寇史観」!
日本史学は「倭寇は日本人主体ではない」と立証した。それでは、彼らは何者だったのか。グローバルな視座から東アジアの長期的な構造をとらえなおし、倭寇が収束したとされる17世紀以降も次々と「海賊」が現れ、今なお「中華」の秩序を揺さぶり続けている状況を解き明かす。世界史の見方が大きく変わる、岡本史学の決定版!
はじめに
第1章 「倭寇」をみなおしてみる
1 経過と言説
「倭寇」という語句/ことばと事実/矛盾/「倭寇」のはじまり/「倭寇」の命名
2 研究の進展
概念の理解/潮流の変化/「倭人」の世界/「倭人」と「倭寇」のあいだ
3 契機と過程
「前期倭寇」と「後期倭寇」/前・後を分かつもの/政権の体質/後期倭寇へ/関心の所在
4 「倭寇的状況」をこえて
王直という典型/「倭寇国の王」/「倭寇的状況」/「倭寇」の収束?/「倭人」のゆくえ/「華人の貿易ネットワーク」
第2章 「互市」の時代
1 鄭成功
事例として/「和藤内」/鄭氏政権の興起/海禁の復活と鄭氏の敗亡/「倭人」の限界
2 「倭寇」から「互市」へ
海禁解除/「華夷同体」/海関の設置/海関の制度的位置/制度構造/「互市」のはじまり――日中貿易の帰趨とデフレの脱却
3 「倭寇」「互市」から「夷務」へ
康煕から乾隆へ/日本から西洋へ/近世から近代へ/光と翳/「夷務」
第3章 近代史という「倭寇」
1 アヘン戦争と「条約体制」
アヘン貿易/「自由貿易」/「互市」の転変/「華夷同体」の転化/「条約港」/立場がかわると/「延長」
2 「洋務」の展開
移民と内憂外患/李鴻章と「洋務」/明治日本・森有礼からみると/「洋務」の群像/小康のしくみ
3 世紀末にあたって
日清戦争の位置/均衡の喪失と李鴻章/「瓜分」という「華夷同体」/義和団事変の含意
第4章 革命とは「倭寇」?
1 変法
見取り図/変法の位置づけ/康有為という「華夷同体」/政変/世紀交の転換/梁啓超という「華夷同体」
2 孫文と「革命」
「中華」から「中国」へ/「革命」という概念/革命家/生涯/是非/争奪
3 「革命」の進展
三民主義と「革命」/「革命」の概念と現実/「革命の父」「国父」/転換と逝去
4 孫文という「倭寇」
遺言と生涯/「専政君主主義」/歴史的慣性と「華夷同体」/「五族共和」/やはり「倭寇」
第5章 「倭寇」相剋の現代中国
1 国民政府の時代
蒋介石と国民政府/転身/三つ巴/「合作」から内戦へ/「倭寇」の再現?
2 中華人民共和国
対外危機/国内統合/文化大革命/毛沢東からトウ小平へ
3 香港の履歴と運命
「改革開放」の意味/習近平の登場と香港問題/「雨傘革命」から国家安全維持法へ/「一国二制度」の帰趨/香港という「倭寇」
4 現代と「倭寇」
両岸三地/あらためて、「倭寇」とは何か/その本質は/なれの果て
おわりに
参考文献
書誌情報
| 読み仮名 | ワコウトハナニカチュウカヲユサブルカイゾクノショウタイ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮選書 |
| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-603922-5 |
| C-CODE | 0322 |
| ジャンル | 歴史読み物、歴史・地理・旅行記、世界史 |
| 定価 | 1,760円 |
| 電子書籍 価格 | 1,760円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/02/19 |
書評
グローバルな視点から見た「倭寇」の正体
「倭寇」が14―16世紀の海賊だということは、学校の歴史でも習うことだ。前期倭寇は主として「日本人」からなる集団で、朝鮮半島を含む黄海沿海部で活動したのに対して、後期倭寇は東シナ海を中心に猖獗を極め、彼らは華人も多い多(無)国籍的な集団だったということも、少し勉強した人たちは知っているだろう。だが、その人たちの実像となると、なかなかイメージがわかない。
海洋では国家が暴力の行使を独占するのは陸上よりずっと難しい。現代でも武装集団に出くわしたからといって、警察を呼べばすぐに来てくれることは期待できないから、沿岸国の監視が行き届かない一部の海域で海賊は出没しており、船舶の乗員を人質にして交渉の上で身代金を獲得する半ば近代的なビジネスになったりしているくらいだ。
だからかつて貿易を生業とする人々にとっては、集団で武装して自分の身は自分で守るというのは、生き残りのための常識にすぎなかった。とりわけ倭寇が活発化した室町時代の日本のように中央政権が弱体な場合は、略奪をする集団も増えるのは事実だろうが、海賊行為と民間貿易の区別は現実には截然としないことも多い。
その民間貿易だが、モンゴル人は商業を振興したので元時代には東アジアでも大いに発展した。しかし、漢人による「正統王朝」である明王朝は一挙に閉鎖的かつ差別的な華夷秩序へと内閉し、貿易も朝貢貿易に限定し民間貿易を禁止する「海禁政策」を採用した。今日観光名所になっている万里の長城は、明時代に改修強化されたものだが、海にも万里の長城をつくろうというのが、明の公式の政策だったのである。
しかし実際に明朝政権がこういった観念的原理を中国社会の末端にまで強制できたかどうかは、まったく別の話だ。国際貿易はすでに中国の経済生活の重要な部分に成長しており、これはまったく非現実的だった。貿易を生業とする華人の中には、倭人との間で脱国家的な「華夷同体」が形成されていて、彼らは実態に合わない中央の制度を無視できる時には無視し、あるいは役人を買収したりして折り合いをつけたりしただろうが、時には武力をもって反抗するようにもなった。これが「倭寇」だというのである。つまり「倭寇」というのは、あくまで中国の王朝側の用語法にすぎず、ハリウッドの映画に出てくるような髑髏の旗をなびかせて商船を襲う、冒険的略奪に特化した集団を連想したのではその正体を見誤る。
さて、ここまでなら普通の歴史の話だが、著者の真骨頂はこれからだ。「倭寇」は17世紀に入ると収束したとされるが、実は「倭寇」は中国を動かし続けてきたと著者は分析する。考えてみれば、中国史とは、歴史上の「倭寇」が登場したころからずっと、「中華思想」にもとづいて国家を一元支配しようとする王朝勢力と、海外勢力と結びつき時には反乱の主体にもなる「華夷同体」という脱国家的な勢力との間のせめぎあいではなかったのか、というのが著者の見立てだ。欧米と組んで政権を取ろうとした蒋介石も、ソ連と組んだ毛沢東もそう見れば「倭寇」なのではないか。権力闘争に勝利して自身が「皇帝」になった毛沢東は、今度は自力更生という中央の建前を無理やり強行して、大躍進計画や文化大革命という大惨事を引き起こした。それに対してトウ小平らの「走資派」や「実務派」たちは、欧米や日本と組んで、外資や技術を導入し大成功を収めたが、どうやらこれで話は終わりではない。欧米に逃げ出したがる富豪たちや欧米と組んで自治を求めるチベットの亡命政権、取るに足らない少数派だがイスラム教を信仰するウイグル人、さらには欧米流の民主主義という危険思想にかぶれた香港の若者たちが、中央にとっては皆倭寇なのだ。確かに香港の一国二制度を露骨に反故にして、「台湾統一」という建前を強引に推し進める習近平の姿を見ると、いつか来た道のように見える。
私のような国際政治学者は、国家という確乎たる実体があることを前提に、世界を見てしまう癖がある。ちょうど経済学者が市場が正常に機能することを前提に経済を見るようなものだろうか。だが、中国の内部には常に強い遠心力が潜在している。あれほど巨大なのに、外部の勢力と組んで自分たちの権力を脅かす「倭寇」「漢奸」「買辦」を、中央政府が病的なほど恐れるのは、そう考えると了解できる。
だとするとこれは中国に固有の力学ではなく、巨大帝国一般に当てはまるかもしれない。例えば中国以上に人口が多い上に民族構成が中国よりもいっそう多様なインドはどうなのだろうか? もし中国に固有なものがあるとすると、それは何なのだろうか? 無理難題なのは承知の上だが、一国史を超えてグローバルな歴史像をキャンバス一杯に描いてくれる著者に刺激されて、こんなことを尋ねてみたいという気持ちがしてくる。
(たどころ・まさゆき 国際政治学者)
著者プロフィール
岡本隆司
オカモト・タカシ
1965年、京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科東洋史学博士後期課程満期退学。博士(文学)。宮崎大学助教授、京都府立大学教授を経て、2025年2月現在、早稲田大学教授。専攻は東洋史・近代アジア史。著書に『近代中国と海関』(大平正芳記念賞受賞)、『属国と自主のあいだ』(サントリー学芸賞受賞)、『中国の誕生』(樫山純三賞、アジア・太平洋賞特別賞受賞)、『世界史とつなげて学ぶ 中国全史』、『悪党たちの中華帝国』など多数。