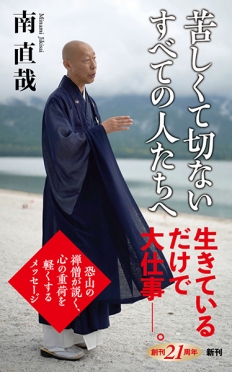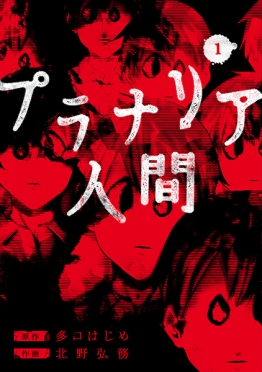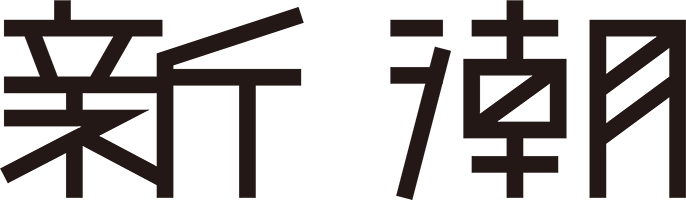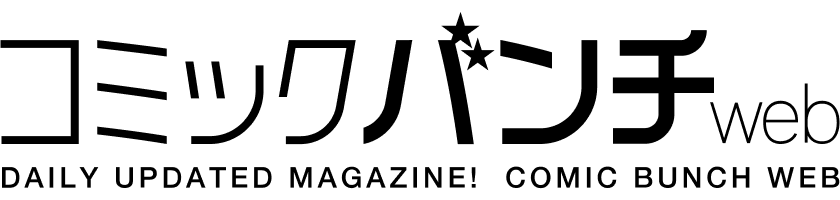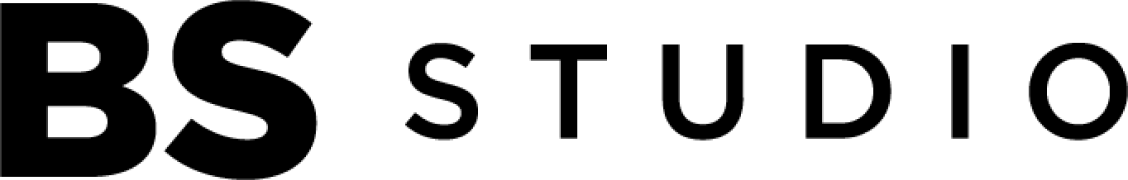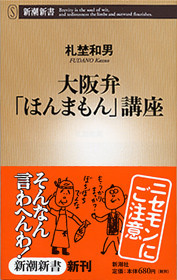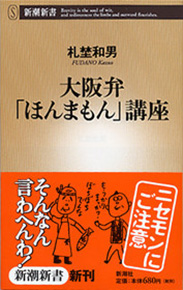
大阪弁「ほんまもん」講座
748円(税込)
発売日:2006/03/20
- 新書
- 電子書籍あり
ニセモンにご注意。「もうかりまっか?」「ぼちぼちでんな」そんなん言わへんわ!
本当はことばの宝石箱なのに、ニセモンが出回っています――。「もうかりまっか」誰が言うてんのやろ。「がめつい」こんな造語はエエ迷惑。「ど根性」誤用の典型。「こてこて」本来は薄味の文化です。「まったり」大阪では主に味の意味。「きしょい」ことばのブラックホールや。……ホンマモンをこよなく愛し、ニセモンの横行氾濫を憂い悲しむ。大阪の人間まで唸ってしまう〈正調大阪ことば指南〉。
目次
おいでやす
I 「にせもん」編
第1章「もうかりまっか」――誰が言うてんのやろ
第2章「がめつい」――こんな造語はエエ迷惑
第3章「おけいはん」――「はん」には法則があります
第4章「どキレイ」「どうまい」――いくらCMコピーでも殺生な
第5章「こてこて」――本来は薄味の文化です
第6章「きしょい」――ことばのブラックホールや
第7章「めっちゃ」――もともとこんな言い方しまへんで
第8章「まったり」――大阪では主に味の意味
II 「ほんまもん」編
第1章「わけとくなはれ」も「おあいそなしで」も――謙虚な気持ちで
第2章「おはようおかえり」と「よろしゅうおあがり」――祈りや感謝をこめて
第3章「今日耳日曜」――平和主義は日頃から
第4章「雨風食堂」で「血みどろ」――遊び心でシャレのめす
第5章「ぼちぼち行こか」――一語多様の世界
第6章「あいぼれ」で「みょおと」に――恋や愛にもふさわしく
第7章「レイコ」に「フレッシュ」――意外にハイカラ
第8章「ごまめ」は「かいらし」――子供に温かい眼差し
ほ な
書誌情報
| 読み仮名 | オオサカベンホンマモンコウザ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-610160-1 |
| C-CODE | 0281 |
| 整理番号 | 160 |
| ジャンル | 言語学、政治・社会 |
| 定価 | 748円 |
| 電子書籍 価格 | 660円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2012/02/24 |
インタビュー/対談/エッセイ
波 2006年4月号より 方言はあかんのン? 札埜和男『大阪弁「ほんまもん」講座』
大阪方言の「あかん」は「埒あかぬ」から生まれたという。私のような大阪人にとっては、「だめだ」と言われるより、どこか救われたような気持ちになることばだ。牧村史陽『大阪ことば事典』は「大阪では、これを『アカン』と軽くすかしてしまうところに、何ともいえぬやわらかい味がにじみ出す」としている。
十年ほど前の話だが、福島県出身の職場の同僚から「東北の人間からすると、『あかん』は冷たく感じる」と言われたことがあった。「だめだ」の方が優しく聞こえるのだそうだ。ことばの感覚にはこうも違いがあるのかと驚いたものである。
ただ、少しは事情が変わってきているようで、福島県の高校生を対象とした調査(半沢康「東北地方における関西方言の受容実態」)によれば、「あかん(・いかん)」の使用率は二四%という回答結果になっている(陣内正敬他編『関西方言の広がりとコミュニケーションの行方』和泉書院、二○○五年)。「あかん」の柔らかいイメージが東北にも少しは伝わるようになったのかもしれない。
もっとも、常に「やわらかい味がにじみ出す」とは限らない。研究者というもう一足の草鞋を履く私の目下の研究テーマは「法廷における方言の役割」である。先日知人から借りた公判資料の中にこんな使われ方があった。「全部撤去して地盤改良せなあかんというような意見を出されているわけですか」。前後の文脈からすると、この場合は相手方を強く批判する役割を果たしている。
研究を進めるうちに、法廷からは方言が締め出される方向にあることが明らかになってきた。最高裁が音声認識装置の導入を検討しているのはその一例だろう。法廷でのやりとりの忠実な記録に大きな貢献を果たしてきた速記官の養成は中止するという。「きついなまりや方言については、(中略)裁判官は標準語に直してもらうことで初めて心証を取るわけですから、そういう意味では方言がどういう意味だったかは、ほとんどの場合それほど重要なことではないわけであります」(二○○四年三月十八日参議院での最高裁の答弁)。
二○○九年五月までにスタートする裁判員制度のキャッチフレーズは「私の視点、私の感覚、私の言葉で参加します」だが、答弁を聞く限りでは「私」を「裁判官」に直した方がぴったりくる。「方言の時代」などと方言がもてはやされる風潮にあるが、おめでたい話ばかりではないのだ。
環境権を巡る裁判の嚆矢となった「豊前環境権裁判」のリーダーで作家の故松下竜一氏は次のように訴えている。「暮らしのなかから生まれたことばにこそ耳を傾けていただきたい」(『豊前環境権裁判』日本評論社、一九八○年)。
今回上梓した『大阪弁「ほんまもん」講座』にも同様の想いが込められている。
十年ほど前の話だが、福島県出身の職場の同僚から「東北の人間からすると、『あかん』は冷たく感じる」と言われたことがあった。「だめだ」の方が優しく聞こえるのだそうだ。ことばの感覚にはこうも違いがあるのかと驚いたものである。
ただ、少しは事情が変わってきているようで、福島県の高校生を対象とした調査(半沢康「東北地方における関西方言の受容実態」)によれば、「あかん(・いかん)」の使用率は二四%という回答結果になっている(陣内正敬他編『関西方言の広がりとコミュニケーションの行方』和泉書院、二○○五年)。「あかん」の柔らかいイメージが東北にも少しは伝わるようになったのかもしれない。
もっとも、常に「やわらかい味がにじみ出す」とは限らない。研究者というもう一足の草鞋を履く私の目下の研究テーマは「法廷における方言の役割」である。先日知人から借りた公判資料の中にこんな使われ方があった。「全部撤去して地盤改良せなあかんというような意見を出されているわけですか」。前後の文脈からすると、この場合は相手方を強く批判する役割を果たしている。
研究を進めるうちに、法廷からは方言が締め出される方向にあることが明らかになってきた。最高裁が音声認識装置の導入を検討しているのはその一例だろう。法廷でのやりとりの忠実な記録に大きな貢献を果たしてきた速記官の養成は中止するという。「きついなまりや方言については、(中略)裁判官は標準語に直してもらうことで初めて心証を取るわけですから、そういう意味では方言がどういう意味だったかは、ほとんどの場合それほど重要なことではないわけであります」(二○○四年三月十八日参議院での最高裁の答弁)。
二○○九年五月までにスタートする裁判員制度のキャッチフレーズは「私の視点、私の感覚、私の言葉で参加します」だが、答弁を聞く限りでは「私」を「裁判官」に直した方がぴったりくる。「方言の時代」などと方言がもてはやされる風潮にあるが、おめでたい話ばかりではないのだ。
環境権を巡る裁判の嚆矢となった「豊前環境権裁判」のリーダーで作家の故松下竜一氏は次のように訴えている。「暮らしのなかから生まれたことばにこそ耳を傾けていただきたい」(『豊前環境権裁判』日本評論社、一九八○年)。
今回上梓した『大阪弁「ほんまもん」講座』にも同様の想いが込められている。
(ふだの・かずお 高等学校国語科教諭)
蘊蓄倉庫
「ドまんなか」の不思議
「ドあほ」とか「ドぎつい」など、大阪弁の「ド」は否定的な言葉に付く接頭語。単に意味を強調する接頭語ではありません。「どキレイ」なんてCMコピーがありましたが、ひどい誤用。肯定的な言葉に付けることは本来ありえないのです。では、野球で使われる「ドまんなか」も誤用でしょうか。『大阪弁「ほんまもん」講座』の著者・札埜和男氏は大胆な仮説を立て、この問題を考察しています。ピッチャーは「まんなか」に投げてはいけない。これがヒントです。詳しくは同書で。
「ドあほ」とか「ドぎつい」など、大阪弁の「ド」は否定的な言葉に付く接頭語。単に意味を強調する接頭語ではありません。「どキレイ」なんてCMコピーがありましたが、ひどい誤用。肯定的な言葉に付けることは本来ありえないのです。では、野球で使われる「ドまんなか」も誤用でしょうか。『大阪弁「ほんまもん」講座』の著者・札埜和男氏は大胆な仮説を立て、この問題を考察しています。ピッチャーは「まんなか」に投げてはいけない。これがヒントです。詳しくは同書で。
掲載:2006年3月24日
著者プロフィール
札埜和男
フダノ・カズオ
1962(昭和37)年大阪府交野市生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。関西大学大学院総合情報学研究科修士課程修了。関西学院大学大学院社会学研究科博士課程満期退学。社会言語学専攻。京都府立八幡高等学校国語科教諭。日本笑い学会理事。著書に『大阪弁看板考』など。
この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。
感想を送る