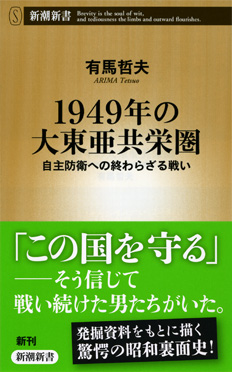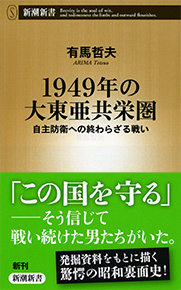
1949年の大東亜共栄圏―自主防衛への終わらざる戦い―
858円(税込)
発売日:2014/06/16
- 新書
「この国を守る」――そう信じて戦い続けた男たちがいた。【発掘資料をもとに描く驚愕の昭和裏面史!】
一九四九年、中国・山西省でまだ日本兵たちは戦っていた。彼らだけではない。帰国した大本営参謀、軍人や児玉誉士夫らは、「理想」の実現を諦めずに戦い続けていたのである。ある者はアメリカと手を結んで反共活動に身を捧げ、ある者は日本軍復活のために奔走し、ある者は政界工作に突き進んだ。その活動はいつしか、東アジア全体へと波及していく。CIA文書など発掘資料をふんだんに使いながら描く、戦後の裏面史。
いち早く帰国した指揮官は、更に大きな作戦に着手する。
石原莞爾の理想を実現すべく、再び彼は工作に乗り出した。
総理大臣を目指す宇垣一成の下に大本営参謀たちが集結する。
自らの潤沢な資金を背景に天皇制保持のための戦いを開始した。
その動きは壮大な反共のための参謀団、義勇軍へとつながっていく。
再軍備が現実化する一方で、吉田茂は旧軍人たちの力を殺いでいった。
大本営参謀たちのこの構想をアメリカは認めなかった。
しかし、政治家たちの思惑はもはや別のところにあった。
あとがき
注釈/参考・引用文献
書誌情報
| 読み仮名 | センキュウヒャクヨンジュウキュウネンノダイトウアキョウエイケンジシュボウエイヘノオワラザルタタカイ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮45から生まれた本 |
| 発行形態 | 新書 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 256ページ |
| ISBN | 978-4-10-610573-9 |
| C-CODE | 0221 |
| 整理番号 | 573 |
| ジャンル | 日本史 |
| 定価 | 858円 |
蘊蓄倉庫
「憲法9条のおかげで日本は戦争をしなかった」というような話をよく耳にしますが、実際には1949年になっても中国で戦闘行為に参加していた日本人は沢山いました。山西省では、「特務団」として元日本軍人たちが中国共産党と戦っていたのです。
『1949年の大東亜共栄圏』では、戦後なおも戦い続けていた元軍人や政商らの動きを追った昭和の裏面史です。彼らを動かしていたのは、「この国を守る」という強い使命感です。
それを正しいと思うか、おかしいと思うか。ご一読の上、ご判断ください。
担当編集者のひとこと
軍人たちは戦後も戦い続けていた
このところ「集団的自衛権」についての報道が増え、国会やメディアにおいても、よく議論されています。
その是非については、色々な考え方があると思うのですが、ちょっと気になるのは「戦後、平和憲法になってから、海外で武力行使をしていないことが日本の誇りだ」という主張です。当然、こういう主張は「行使容認反対派」の方に多く見られます。
何が気になるかといえば、「海外で武力行使をしていない」という点です。
本書『1949年の大東亜共栄圏』は、タイトル通り、1949年頃の日本について描いたものです。
当時、日本人が何をしていたか。
たとえば、ある元日本軍人だちは中国の山西省で「特務団」として、中国共産党と戦闘を行っていました。特務団には、敗戦直後は1万5000人もいたのが、1949年には1600人ほどになっていたそうです。それでも大変な人数の日本人兵士が、異国の地で戦っていたのです。この場合の「戦い」は比喩ではなくて、本当に武器を使って戦闘行為を繰り広げていました。
他にも、元軍人たちは、中国共産党と戦っていた中国国民党のために軍事アドバイスをするグループを結成し、現地で指導を行っています。このグループは白団と呼ばれ、1960年代まで活動をしていました。
こういう行為が良いか悪いかについてはまた議論が分かれるところでしょうが、事実として戦後も海外で何らかの戦闘にかかわっていた日本人は多くいたのです。
せっかく平和になったのに、何でそんなことをしていたのか。
疑問に思われる方は、ぜひ本書をお読みください。
平和というものは一筋縄ではいかないということがよくわかります。
2014/06/25
著者プロフィール
有馬哲夫
アリマ・テツオ
1953(昭和28)年生まれ。早稲田大学社会科学総合学術院教授(公文書研究)。早稲田大学第一文学部卒業。東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得。2016年オックスフォード大学客員教授。著書に『原発・正力・CIA』『日本人はなぜ自虐的になったのか』など。