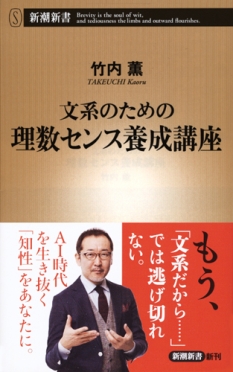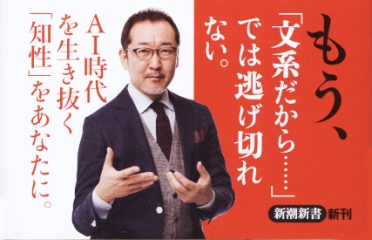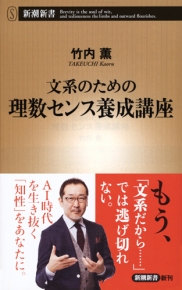
文系のための理数センス養成講座
836円(税込)
発売日:2017/02/17
- 新書
- 電子書籍あり
もう、「文系だから……」では逃げ切れない。AI時代を生き抜く「知性」をあなたに。
あなたが心の底で求めていたのは、数学や科学の「知識」ではなく、「知恵」そのものだったのではないか。「理系と文系は、そもそもどこが違うのか?」を入り口に、「論理的思考」の本質や「科学観」の育て方など、あなたの「理数センス」をサイエンス界の名ガイドが徹底的に磨き上げる。AI時代と最先端テクノロジーの捉え方や、研究不正といった科学のウラの顔の疑い方まで、現代を生き抜くための教養を一冊に凝縮。
書誌情報
| 読み仮名 | ブンケイノタメノリスウセンスヨウセイコウザ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 雑誌から生まれた本 | 週刊新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-610705-4 |
| C-CODE | 0240 |
| 整理番号 | 705 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 定価 | 836円 |
| 電子書籍 価格 | 836円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2017/02/24 |
インタビュー/対談/エッセイ
文系? 理系? それは幻想だ!
文系・理系という分類はナンセンスだ。
そもそも複雑な物事を無理矢理「二分」するのは愚かなこと。政治家がテレビ番組で「YES」と「NO」の札のどちらかを挙げろと言われて怒るのも当然だ。
私は海外生活が長く、幼少時は父親の転勤でニューヨークに連れて行かれ、25歳から32歳までは極寒のモントリオールに「島流し」になっていた。足かけ10年、海外にいたわけだが、「あなたは理系? それとも文系?」という質問には、アメリカでもカナダでもついぞ出くわしたことがない。
それもそのはず。理系と文系なんてェ「区別」は、明治時代に日本で作られた代物であり、きわめてローカルかつ時代遅れのルールなのだ。
実は、同じようなローカルな区別に血液型がある。「B型だといい加減でA型だと几帳面」などという非科学的な性格分類は噴飯物だが、海外で「あなたの血液型は?」なんてェ質問したら、「おまえはオレの主治医なのか? なぜそんな個人情報を知ろうとする!」と、少しおかしな人に分類されてしまうだろう。
脱線したので話をもとに戻すが、明治時代にいきなり出現したのが、理系・文系という二分法。そんなものは共同幻想にすぎないと、一蹴するのはカンタンだが、実際に日本社会が「あなたは理系? それとも文系?」というマインドになっていることは事実である。
そこで、日本に蔓延る「文系マインド」に楔を打ち込んで粉砕してしまおう! と意気込んで、週刊新潮の連載「もう一度ゼロからサイエンス」は始まった。私には珍しく、最初から新書で出版することを念頭に、昨年末まで約2年、毎週せっせと原稿を書きためていたのだ。
その結果できあがったのが『文系のための理数センス養成講座』である。驚くべきことに、現在連載中の「科学探偵タケウチに訊く!」を含めて10年近くも週刊新潮でコラムをやらせてもらっているのに、竹内薫著の新潮新書は、なんと、これが初めてである。空気みたいなもので、そこにある(いる)のがあたりまえで、編集部の誰も私の存在に気づかなくなっていたらしい(おいおい)。
さて、そんなこんなでようやく世に出ることになった本書であるが、もしも本屋さんで手に取っていただけるようであれば、一つだけ留意事項をお伝えしておきたいのです(いきなり丁寧語……)。62頁の真理値から84頁の帰納法までの「論理」の解説は、少し難しいなあ、ともし感じたら、遠慮なくいったん飛ばして、最後まで本を読んだ後にまた戻ってきて、あらためてこの23頁分をじっくり噛みしめていただきたい。この部分は本書の肝なのだが、その分、人によってはそれなりにハードルが高い箇所なのですね。
それでは、本屋さんにゴー! ということでお願いいたします。
(たけうち・かおる サイエンス作家)
波 2017年3月号より
薀蓄倉庫
なぜコンピュータは0と1で動くのか?
『文系のための理数センス養成講座』は、サイエンス界の名案内人である著者が、
教科書とはまったく違うアプローチで、あなたの眠れるセンスを呼び覚まします。さて、今や文系だからといって、たとえばパソコンを使えない人などほぼいません。コンピュータが0と1の2進法で動いていることも、皆さん先刻ご承知でしょう。
でも、なぜ2進法なのか、どうして日常的な10進法ではいけないのか、と聞かれたら、あなたは答えられるでしょうか?
昔、数学の授業で、「命題」だとか「真」とか「偽」とか、そんな用語に悩まされた記憶がおありになると思いますが、じつは、あの命題に対する真と偽に、コンピュータは0と1を対応させていたのです。
論理学の世界では、この0と1を「真理値」と呼んでいるのですが、つまり、真と偽に
0と1を対応させることで、コンピュータはスーパー哲学者さながらに論理的に複雑な思考をいくらでも行うことができるのです。
というようなことが、もっと分かりやすく、初歩の初歩から書かれている本書を是非ご一読ください。
掲載:2017年2月24日
担当編集者のひとこと
AI時代の到来に、文系でも知っておくべきこと
テレビでも新聞でも、AI、IoT、クラウド、インダストリー4.0と、最新テクノロジーの威力とその未来を喧伝する言葉があふれ、どうやらこれまでとは全く違う時代が来そうだ、ということはひしひしと感じるのですが、いったいどこまでそれらに関心を持つべきなのか? どう対応すべきなのか? さっぱり分からないので、そこは理系の人たちに任せておけばいいんじゃないの? というところへ落ち着いてしまうのが、私を含めた文系人間の実態なのかもしれません。
でも、竹内さんによれば、「文系だからといって、もう逃げられませんよ」とのこと。
であれば、新時代に我々はどう備えるべきなのでしょうか。
すべての核になるのは「論理的思考」で、これがますます重要になると竹内さんは話します。たしかに、日常的にも論理的思考という言葉自体はキーワードとしてよく耳にします。でも実際にそれを学ぼうとすると、それこそ理系のための本ばかり……。
そこで生まれたのが『文系のための理数センス養成講座』なのです。
文系の私たちにも、けっして論理性がないわけではないそうで(よかった!)、ただその本質をきちんと理解していないため、せっかくの理数センスが埋もれているのだとか。この眠れるセンスを磨き上げるため、数式を使うことなく、基礎から実感的に、論理的思考、科学的思考の作法を、竹内さんが指導してくれます。
そして、この論理的思考の基礎を理解できたら、次に、科学とはどんなもので、これからどのように発展していくのか、といった科学観も手に入れよう、という欲張った構成。さらには、STAP事件などを事例にして、「科学をどう疑うべきか」という問題にも取り組みます。
現役のビジネスパースンを中心読者に想定している本書ですが、就活を前にした大学生の皆さんや、学び直しを考えている方々、そして理系の人々にだって、本当におススメです。
2017/02/24
著者プロフィール
竹内薫
タケウチ・カオル
1960(昭和35)年東京都生まれ。サイエンス作家。理学博士。東京大学教養学部、同理学部を卒業。カナダ・マギル大学大学院博士課程修了(高エネルギー物理学専攻)。科学や数学の案内人として活躍。主な著書に『99・9%は仮説』『数学×思考=ざっくりと』など。